最大のクラスターは病院や介護施設。今すぐ職員・患者全員に検査を実施すべきだ
2020年05月12日
緊急対談「中島岳志×保坂展人」(前編)では、新型コロナウイルスのPCR検査が制限されてきた実態を自治体側から検証した。後編では、感染拡大を招いた主要因である「院内感染」を防ぐにはどうしたらよいのか、ひたすら国民に努力を強いる「外出自粛」は本当に有効な対策なのか、中島岳志・東工大教授が保坂展人・東京都世田谷区長とともに考える。(論座編集部)
中島 PCR検査の拡大の他、現状での課題として認識されているのはどんなことでしょうか。
保坂 まず、検査後に陽性となった方や感染の疑いがある方の入院先調整に関する問題があります。本来、空きベッドを探して入院先を調整するのは医療を所管する都の役割なのですが、とても追いついていないのが現状です。
昼間はまだなんとかなっていても、夜中に容態が急に悪化し、コロナウイルス罹患の疑いが出た発熱の方がいた場合などは「入院先を決めるのは保健所だから」と、保健所の責任者の携帯に電話が掛かってきます。夜中ですから、どこのベッドが空いているかもすぐには分からない。それで責任者は、病院リストを見ながら一件ずつ、夜通し電話をかけていく……という延々とした作業がつい最近まで行われています。
しかし、ここで手間取って入院先に運べず、医療につながるべき人がつながれないと、命を救えないということにもなりかねません。医療機関同士のネットワークを作り、それぞれの空きベッド状況がすぐに分かるようにしておく必要があると思います。今、その支援を国と厚生労働省に要請しているところです。
また、検査で陽性反応が出たけれど症状がない、あるいは軽い人について、厚生労働省は4月24日の記者会見で、当初の「自宅療養も選択肢」という方針を取り下げ、「ホテルなど施設での療養を原則とする」と発表しました。一人暮らしの方が自宅療養するのは症状急変の時に危険ですし、買い物などで外出する必要も出てきてしまう。また、家族がいる場合は家庭内での感染拡大も懸念されますから、施設療養を基本としたこと自体はよかったと思います。
しかし、実際には在宅療養からの切り替えはなかなか進んでいません。
重症者の入院を促進するとともに、陽性反応が出たけれど症状が軽い人、目立った症状のない人は、自治体が用意したホテルなどの施設で療養してもらう。そこで医療スタッフがしっかりと健康観察し、悪化した場合はすぐに治療に結びつける。この循環を作ることで、軽症者の重症化を防ぎ、医療現場の病床不足をバックアップすることにもなると思うのですが、そこがうまくいっていないように思います。
 保坂転人・世田谷区長
保坂転人・世田谷区長中島 自宅療養からの切り替えがうまく進まないというのは、なぜなのでしょうか。
保坂 東京都の場合は、都が受け入れ体制を整えるのに時間がかかったということがあると思います。
療養先となるホテルの部屋を確保するだけではなく、十分な医療スタッフを配置する必要がありますし、同意をとったうえで自宅まで迎えに行き、病院から移る場合には退院の手続きといったさまざまな実務が発生します。それについて、実際の現場との歯車が噛み合っていなかったということだと思います。
中島 しかし本来なら、そうした問題は2月から3月にかけて、まだ感染拡大が深刻でなかった時期に準備しておくべきだったはずです。そうならなかった、つまりは都政が3月の段階で非常に対応に遅れを取った理由については、しっかりと検証しておく必要があると思います。
まだ東京オリンピックの延期が決定していなかったことも影響しているのではと言われていますが、現場ではどう感じられましたか。
保坂 少なくとも、オリンピックの延期決定直後から都の対応が急に進み始めたのは事実です。ただ、その際に発信されたメッセージも、PCR検査を拡大するよりは、都民に行動制限を呼びかけるという方向でした。
国の対応もそうですね。最近になって専門家会議などが「十分な検査ができていない」と口にするようにはなってきましたが、「検査の幅を広げたら陽性者数が増えて医療崩壊を招くから、検査数は絞ってクラスターを追う」という当初の方針が、明確に否定されたわけではありません。
中島 最初にも少し触れましたが、自宅療養から施設療養への切り替えの話も含め、方針を大きく転換する際には、責任ある人たちが、以前の方針は間違っていたから、あるいは状況が変わったから「こういう理由で、ここから方針を転換した」と明確に表明することが重要です。
しかし、政府は感染拡大の初期段階からいくつかの対応ミスをしてきたにもかかわらず、そのことをはっきりと認めようとしてきませんでした。いわゆる「4日間ルール」を撤回したときのように、「そういう意味ではなかった」などと言って後出しじゃんけんをしようとしさえする。これは非常に大きな問題だと思います。
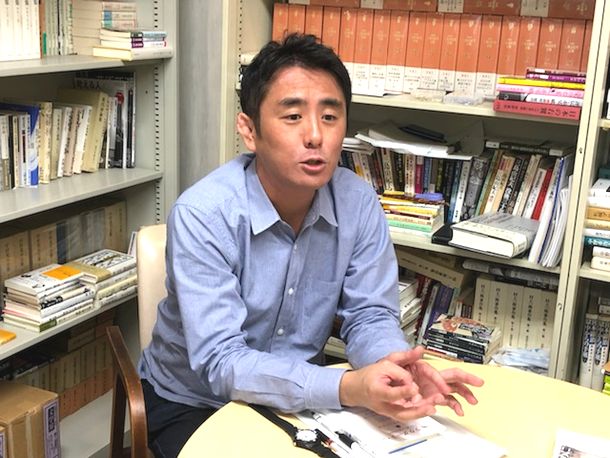 中島岳志・東工大教授
中島岳志・東工大教授保坂 私は、政府が当初進めていた、PCR検査を絞り込むともにクラスターをつぶすという戦略は、現実には市中感染の拡大と病院クラスターの発生という形で裏目に出たと考えています。
台東区の永寿総合病院では、患者と医療スタッフあわせて200人以上が感染し、40人が亡くなりました。そこから患者さんが転院した病院にも感染が拡大し、感染症の指定医療機関として高度な医療機能を有する都立墨東病院でさえ院内感染が起こったことが報じられています。世田谷区内でも院内感染は複数発生しています。
中島 高齢者施設や障害者施設での集団感染も伝えられていますね。
保坂 今後、国や都は戦略的に方向性を是正し、そうした集団感染の防止に特化して人や予算をつぎ込んでいくべきだと思います。
行動を制限して「人との接触を8割減らせば感染拡大はとどめられる」というかけ声の効果は、施設内感染には及びません。いくら人と人との接触を減らしたとしても、医療機関や施設での院内感染があれば、そこを拠点にして感染は広がっていく。病院や施設は地域の人が絶対に出入りする場所だし、職員も地域で生活しているわけですから、当然です。
しかし、国も都も、その部分の対策をどうしていくのかということが現状ではなかなか見えない。このままでは外出制限をいくらしても安心はできないと思います。
 「8割削減」を唱える北大の西浦博教授
「8割削減」を唱える北大の西浦博教授国や都が手が回らないのなら、住民から一番近い基礎自治体がやるしかありませんから、区でも院内感染防止のためのチームを立ち上げて動かしていこうと考えています。
先日、東大先端科学技術研究センター(以下、先端研)の児玉龍彦先生をはじめとする専門家の方々にお話をうかがう機会があったのですが、そこでも一番「なるほど」と思ったのは、院内感染に関するお話でした。
中島 どのようなお話だったのですか。
保坂 院内感染においては、コロナウイルス陽性だと分かっている人から感染が広がるケースだけではないそうです。陽性とわかっている場合、スタッフはしっかりと防御しているからですね。そうではなく、けがなどで他の科を訪れた人が、自覚症状はないけれど実は感染していた、医療スタッフが病院外で感染したといった、さまざまなルートから病院の中に入ってくるのだといいます。
そこで、そうしたケースを防ぐために、職員はもちろん受診する患者さん全員に抗体検査や簡易PCR検査を行うといったことが、世界各国で進んでいるそうです。先端研でも高性能の定量的な抗体検査機器を入手したので、しっかりとした戦略的な検査を導入し、院内感染・施設内感染を徹底防止することが急務だとお話しいただきました。
ひたすら「国民の努力」を求めるだけの呼びかけより合理的で有効な対策だと思います。いくら国民が行動規制などに協力しても、院内感染の危険性は変わらない。医療に資源や感染防止のシステムが導入されない限り、防止はできないんですよね。
院内感染が起こると、医師や看護師も罹患したり、周囲の医療スタッフも濃厚接触者として身動きが取れなくなったりして、病院機能にも支障が出ます。事実、一部の病院では救急受け入れを停止したり、外来を閉鎖したりといったことがすでに起こっていますよね。もちろん、コロナ対応自体にも大きな影響が出ますから、その意味でも絶対に防がなくてはならないんだ、ともお聞きしました。
私も含め、自治体の首長は感染症の専門医でもなんでもない人が圧倒的多数ですから、専門家──それも、国や自治体の方針に異を唱えない人だけではなく、客観的で合理的な視点を持った方からの助言をいただくことは、非常に大事だと考えています。
中島 日本では当初からのクラスター対策にこだわるあまり、PCR検査が十分にできていないだけでなく、実はもっとも大切なクラスター対策であるはずの院内感染対策が進んでいないというのは、非常に重要なご指摘ですね。医療現場での、マスクやフェイスシールド、防護衣などの不足も解消されていません。
保坂 世田谷区でも、緊急事態宣言前の4月6日の時点ですでにほとんどの病院で「足りない、もうすぐ尽きる」という悲鳴のような声が上がっていました。
4月10日には厚生労働省が、本来使い捨てであるはずの医療用マスク「N95」について、「使い捨てにせず、減菌して2回まで再利用するように」という事務連絡を出しましたし、医療崩壊は多くの人が想像するシナリオとは異なる形で進んでいるのかもしれません。
しかし、ちょっと不思議に思うことがあります。世田谷区の「区長へのメール」には1日100本以上が寄せられるのですが、その中に、マスクなどの医療装備提供の申し出がかなりの数、あるんですよ。1週間で十数件くらいは来るでしょうか。
寄付の申し出もありますが、海外も含めた業者や輸入商社からの「この値段で提供できます」という連絡もたくさんあります。そういった情報を医療機関に回すことで、かなりの数を確保してもらうことができましたし、区でも、マスクや消毒液などを購入しました。
区の単位でさえこれだけ情報提供が来ているのに、なぜ国の単位で手配することができないのか。いったいどうなっているんだろう、と疑問に思います。
医療現場に最低限の器具や装備を届けるというのは、行政の非常に基礎的な役割だと思うのですが、国も都も残念ながらそれを果たせていないのがこれまでの現状ではないでしょうか。
中島 国の施策では、各家庭2枚の「布マスク」配布も批判を集めましたね。
 ソウル郊外の高陽市でのドライブスルー方式検査=同市提供
ソウル郊外の高陽市でのドライブスルー方式検査=同市提供
保坂 先行して配布が始まった妊婦さん向けのマスクには、虫や汚れが付着していたり、変色していたりする不良品が1割も含まれていたというので配布が停止されましたね。衛生用品としてありえないというだけではなく、検品を担ったのが保健所だったということで、ただでさえ疲弊している保健所に、さらに余計な仕事を押しつけることにもなってしまいました。
先日、2020年度の補正予算が発表されましたよね。布マスク配布にかかるとされる費用466億円のうち233億円が計上された一方で、検査体制にはわずか49億円でPCR検査や院内感染防止のための費用は決して十分とはいえません。
また、これは杉並区の田中良区長も言っているのですが、コロナの治療に本格的に取り組んでいる病院ほど、実は収益が大きく減ってしまうんです。感染を恐れて他の病気やけがで受診する患者さんが激減しますし、コロナ陽性やその疑いがある患者さんに個室に入ってもらった場合、その個室料金も病院負担となります。
もちろん、院内感染などが起きて、さらに評判を落とすリスクもあります。すでに、前年比で収入が半分以下になったという病院もあるようです。
最前線で闘っている病院が疲弊して、最終的に破綻することのないよう、国のサポートが絶対に必要です。そのための思いきった補助も、補正予算の中には組み込むべきだったと思います。
中島 さて、日本では5月4日に緊急事態宣言の延長が発表されました。
一方、日本とそれほど変わらない時期に感染拡大が始まった韓国では、1日あたりの感染者が10人以下に減っているということで、行動規制緩和が始まっています。韓国や、やはり感染終息の兆しがあるといわれる中国に日本はなぜ学べなかったのか、と思わずにいられません。
ある研究者の方が、「日本には、感染症対策をリードしてきたのは自分たちのほうだという自負がある。途上国援助の現場などではずっと、日本の医療従事者が韓国の人たちに教える立場にあったので、彼らから学ぶという姿勢そのものがない」という話をされていましたが、保坂さんはどう感じられますか。
保坂 韓国の対応は日本とはまったく逆で、ドライブスルー方式などで「徹底的に検査数を増やす」ところに力が注がれていました。その結果、一時的に陽性者数がどんどん増加しましたが、一方で徹底した院内感染対策などの仕組みをしっかりと構築し、保養センター等で隔離もしっかり行って、感染拡大を抑えていったわけです。
 新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、緊急事態宣言の延長について説明する安倍晋三首相(右)。左は専門家会議の尾身茂副座長、中央は加藤勝信厚労相=2020年5月4日
新型コロナウイルス感染症対策本部の会合で、緊急事態宣言の延長について説明する安倍晋三首相(右)。左は専門家会議の尾身茂副座長、中央は加藤勝信厚労相=2020年5月4日にもかかわらず日本は、ドライブスルー検査については「まったく評価に値しない」との態度で、そこから学ぼうという姿勢をまったく見せませんでした。そこには、「中国や韓国から何が学べるというのか」という、ある種の「上から目線」があったように思います。
4月半ばになってようやく、厚労省が「ドライブスルー方式の検査も認める」という事務連絡を出しましたが、ここでも「いつどのように方針が変わったのか」は明確にされないままです。
本来なら、ある程度ウイルスの抑え込みが成功したように見える中国や韓国には、積み重ねられた知見があるわけですから、むしろ厚労省から技官を派遣するくらいのことをやるべきだと思います。どういうふうに制圧したのか、医療崩壊をどう防いだのか、出口に向かう時にクラスターなどをどう抑えるのか、学ぶことはたくさんあるはずです。
私も少し前に、朴元淳ソウル市長とメールでやりとりをしたのですが、「韓国ではこういう対応をしてきました。何か必要な情報があればどんどん公開します」とおっしゃっていました。人間が生きるか死ぬかという根底的な問題を突きつけてくる感染症との戦いには、イデオロギーを超えて立ち向かわなくてはならない、そのために知見を共有するという姿勢があるのだと思います。
対して日本はどうでしょうか。国としてのメンツや気位にこだわって、「命を守る」という最優先すべきことがそうなっていないのではという気がします。
中島 ありがとうございます。最初にお話ししたような痛ましいニュースもありますが、それを隠したり誤魔化したりするのでなく、失われた命を無駄にしない、そこから改善点を模索していくというのが、何よりも政治に求められる姿勢だと思います。
厳しい道のりですが、今後も基礎自治体にこそできる取り組みを重ねていっていただければと思います。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください