【11】ナショナリズム ドイツとは何か/ベルリン② 現代史凝縮の地
2020年07月30日
 1945年7~8月にポツダム会談が行われた会議場=2月、ドイツ・ポツダムのツェツィーリエンホフ宮殿、藤田撮影
1945年7~8月にポツダム会談が行われた会議場=2月、ドイツ・ポツダムのツェツィーリエンホフ宮殿、藤田撮影ドイツのナショナリズムを探る旅でベルリンに入り、取材の2日目。近郊のポツダムを2月14日午前に訪れた。ドイツと、そして日本の戦後に甚大な影響を与えた、1945年7~8月の米英ソ首脳会談があった場所だ。
近代国家や国民というまとまりは、人間社会が生み出した秩序だ。それを侵そうとした国家がいかに厳しい報いを受け、自身のまとまりをも根底から揺るがされるのか。ナショナリズムの因果を現代史に赤裸々に刻んだ会談の地を、見ておきたかった。
今回は日本と相似である敗戦国ドイツの側ではなく、ポツダム会談の主役である戦勝国の側に回って考える。ドイツが破壊した欧州秩序の再構築をめぐり、戦勝国もまた揺れていた。
ポツダムは、ベルリン州をすっぽり囲むブランデンブルク州の州都だ。プロイセン王国以来の首都ベルリンに座したかつての王室の離宮や庭園の数々がある古都で、世界遺産に指定されている。
ドイツ鉄道のベルリン中央駅から、ローカル線で30分と少しでポツダム駅。冷たい小雨の中、見学の生徒たちとハーフェル川に架かる橋を渡り、市街へと歩いていく。
 ドイツ・ポツダム市街へ向かう見学の生徒たち=2月、藤田撮影
ドイツ・ポツダム市街へ向かう見学の生徒たち=2月、藤田撮影路線バスに乗って石畳の町並みを抜け、10数分で煉瓦造りの門と塀に囲まれた庭園に着く。ポツダム会談の場となったツェツィーリエンホフ宮殿だ。
この宮殿もドイツの歴史を映す。第一次大戦敗北により帝政が終わった頃にできた最後の宮殿で、皇太子が住み続けた。ドイツ史の継承者として「第三帝国」を掲げたヒトラーも何度か訪問。そして敗戦後、第二次大戦末期にベルリンへ反攻したソ連軍に接収された。
住宅街と隣り合う庭園の脇にある、寂れた門から入る。木立を抜けると茶褐色の山荘風の宮殿が現れた。今はポツダム会議の史料館になっており、中庭の芝生に大きな星形の刈り込みが見えた。ソ連軍接収当時の名残だ。
 ポツダム会談が行われたツェツィーリエンホフ宮殿=2月、ドイツ・ポツダム。藤田撮影
ポツダム会談が行われたツェツィーリエンホフ宮殿=2月、ドイツ・ポツダム。藤田撮影
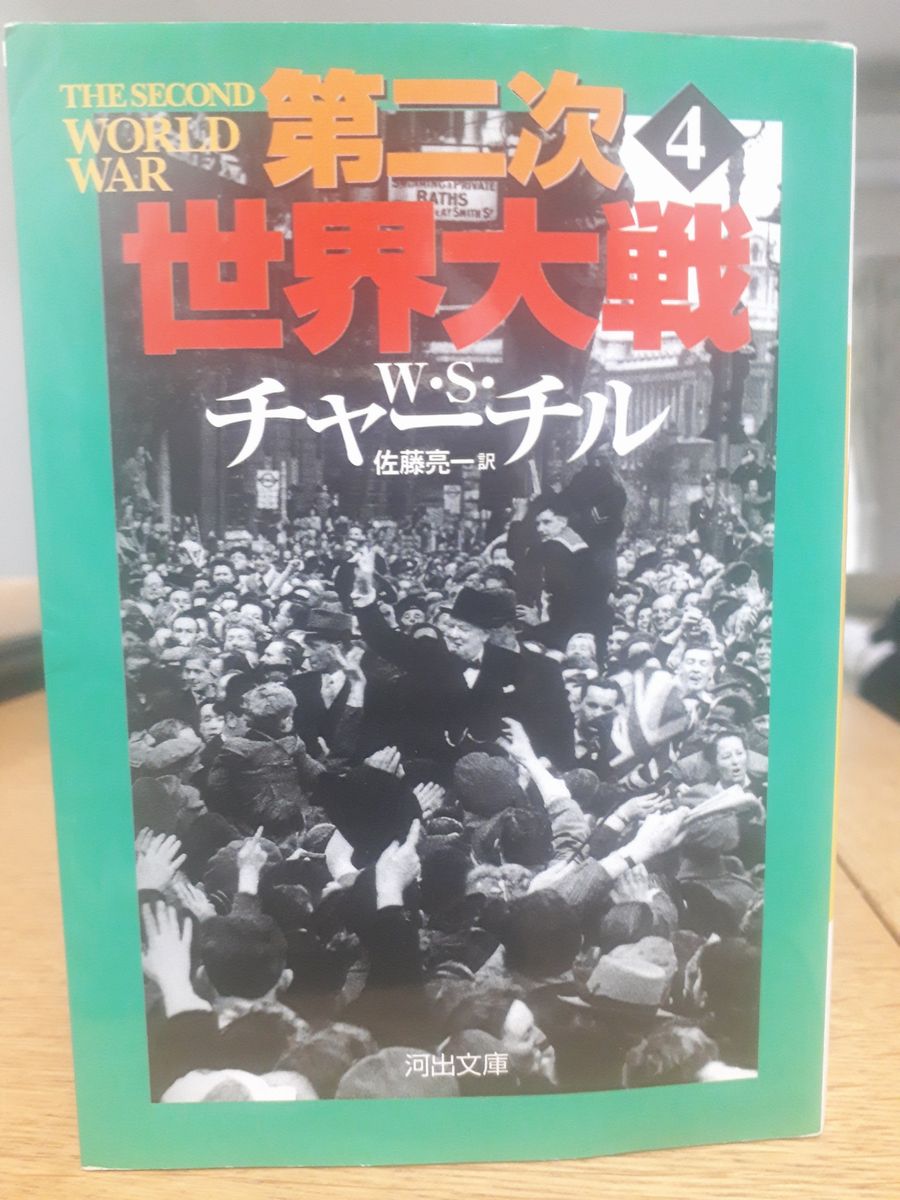 チャーチル回顧録「第二次世界大戦」。1957年、河出文庫
チャーチル回顧録「第二次世界大戦」。1957年、河出文庫チャーチルの回顧録も頼りに振り返っていく。米大統領トルーマンに宛てた電報に、翌年の演説で有名になる「鉄のカーテン」に似た言葉がすでに記されていた。
ソ連は東からポーランドを越えてベルリンを陥落させ、さらに欧州中央へ勢力を広げようとしている。それなのに米国は戦力を欧州から太平洋の対日戦へと移している――。チャーチルは懸念を示し強調した。
ヨーロッパ中央部へこのぼう大なモスクワ進出が行われるとき(中略)、カーテンがふたたびおろされるでしょう。かくて数百マイルに及ぶ広大な帯状のロシア占領地域が、我々をポーランドから隔離することになるでしょう。(チャーチル回顧録「第二次世界大戦」 1957年、河出文庫)
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください