米国も神経質になるコロナ危機対応などでの優位性の原点
2020年10月19日
資本主義陣営にとって、中国を理解することは容易ではない。
たとえば、2年ほど前からの米中関係悪化で改めて浮き彫りになった共産主義の政治形態について、中国では昔から一貫していたにもかかわらず、あまり触れられてこなかったように筆者には思える。また、中国の国営企業は生産性が低いということは、実は理由があるからそうなっているのに、発想としてはなかなか浮かんでこない。これは、長年にわたる研究や付き合い、取引をしているのとは裏腹に、中国を見ることに慣れていないからだろう。
そこで本稿では、共産主義国である中国経済に注目し、共産主義国としてどのような運営が行われてきたか、中国外の学者から指摘される不良債権問題などの懸念をどう乗り切ろうとしているかについて述べたい。これは2019年3月7日公開の論座の拙稿「日本からは見えにくい中国経済の本質」のもう少し基礎的な部分について、体系だって見るものである。
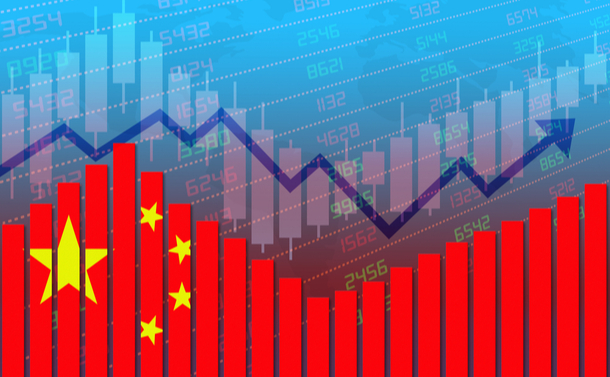 Ronnie Chua/shutterstock.com
Ronnie Chua/shutterstock.com世界経済がコロナで停滞し、先進主要国の2020年第2四半期の実質GDP前年比が軒並み二桁のマイナスとなった中、新型コロナの発信源と欧米が非難する中国は、第1四半期ここそマイナス6.8%と前年割れしたものの、第二四半期はプラス3.2%と唯一プラスを記録。上半期を通してプラス1.6%まで回復してきた。
主たる背景は、2020年4月14日公開の論座の拙稿「新型コロナは外交手段? マスク輸出と内需拡大で経済復興を始めた中国」をご覧いただきたい。
コロナへの初期対応において、発生源だった武漢ほかを徹底的に閉鎖・隔離してノーマル化を図ったことの効果は大きかった。もちろん、自由を束縛するその強引さに疑問を抱く声は海外から上がったが、経済活動が世界に先駆けて動き出したのは紛れもない事実である。
中国で注目すべきは、エコノミストなどから市場開放の遅れなど様々な批判を受けながらも、また成長率の振れを伴いながらも、経済が長らく成長トレンドを続けてきたことだろう。
実質GDP成長率の年平均をみると、計画経済が始まった1953年から改革・開放の開始年である1978年までの25年間にプラス5.8%、その後の25年間でプラス9.6%だった。さらに世界が礼賛する2002年からの10年間は、平均プラス10.7%の高度成長を達成し、2012年以降は徐々に成長率を下げながらも、6年間の平均がプラス7.2%。その後、昨年までの2年間も低下したとは言え、それぞれプラス6.5%とプラス6.1%だった。
まとめると、中国経済は一時的にマイナス成長の時もあったが、計画経済開始から67年間、年平均8%の経済成長率を達成したのである。
マクロ経済学の視点からすると、中国にも景気循環が当てはまるはずだが、中国におけるマイナス成長や低成長時は景気循環によるものというよりは、その時々の政策の影響だと考えた方が理解し易い。
中国を形容する時に使われる「経済が資本主義に移行していない」という批判は、むしろ、国民生活の向上のかかわる国家による積極的な介入が、資本主義のなせるわざとは異なる結果に繋がっていると考えるべきではないのだろうか。
日本や米国などの西側先進国では、ソ連の崩壊によってマルクス経済学は死んだように扱われている印象を受ける。これに対し、中国政府で働く学者や官僚、中国の大学の研究者には、今もマルクス理論を社会思想や経済学と結びつけて研究する人が少なくない。
先月、スタンフォード大学のZOOM会議に出席したところ、ソ連が失敗し、ベネズエラでも駄目だったのに、なぜ米国の若者は社会主義を好きなのか、という話題が出た。その時の答えを一言で表現すれば、「夢があるから」ということだった。
北欧型やフランス型の社会主義もあり得るわけだが、呼び名や中身が多少違っても、実現が可能な理想の形だと考える若者が多いのかもしれない。
米国では、共産主義を宗教の一つだと考える学者も出てきている。確かに、今回の大統領選挙におけるバイデン候補の健闘は、民主社会主義者を標榜するサンダース上院議員たちを抜きにしては考えられないが、その熱狂ぶりはまさしく一種の宗教のような感じがする。
つまり、イデオロギーとしての共産主義が残っている以上、経済学としてのマルクス理論が死んでも、それに代わるものが出てくるのは必然で、今も昔もその信奉者は少なくないのだ。
 pskamn/shutterstock.com
pskamn/shutterstock.com筆者はマルクス理論の信奉者ではない。しかし中国共産党の中や中国の大学でこれを研究する人達の経済の現状に対する分析と、熱心な説明を聞くと、資本主義とは異なる道を目指してきた国が、今後もこのやり方で成長を続けることは決して不自然ではないと感じる。
このところの米国の対中政策の転換は、「関与戦略」(Engagement Strategy)を続ければ、いずれは中国も自由主義や資本主義、民主主義になるとの期待が外れたことによる。
しかし、1972年のニクソン米大統領の訪中以降、米中の往来が増え、中国研究者も増えたにもかかわらず、米国が見込み違いをした原因は、ニクソン大統領が形容した「フランケンシュタイン」をそのまま放置したこと、そしてその中国が米国を騙(だま)したことだと言われても、あまりに短絡的な気がする。
むしろ、資本主義の良さや強みを取り込みながら、ソ連のマルクス理論による共産主義の失敗を修正し、中国なりの経済理論を作り上げてきたためだと理解しないと、今後の経済外交などにおいて失敗をするのではないかと、個人的には懸念する。
米国(またはその他の資本主義国)の失敗は、こうした動きを、中国が資本主義経済に移行しようとしていると誤解したことだろう。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください