政策研究大学院大学の座長らが求めるインド太平洋構想の具体化
2020年10月23日
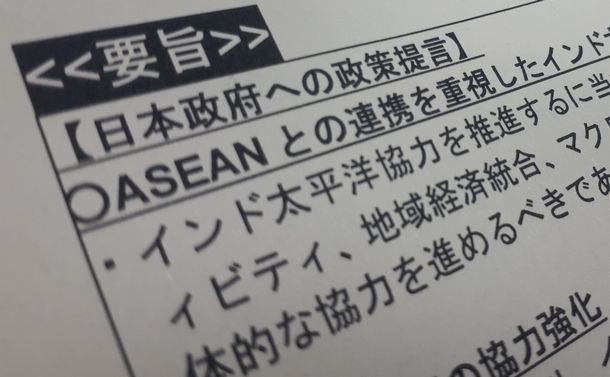 今回の提言文書の表紙より
今回の提言文書の表紙より米中対立が深まる中、日本はどうすべきか。始動した菅義偉内閣に向け、最近まとめられた提言がある。国立大学法人の政策研究大学院大学(GRIPS)を中心に産学官の関係者で練られたものだ。そこには、政府がなかなか語らない「中国の台頭をどう捉え、対処すべきか」が記されている。菅内閣の外交・安全保障政策の指針となりうるその中身を紹介する。
10月下旬に政府に提出される予定のこの提言は、GRIPSの田中明彦学長を座長とする「インド太平洋協力研究会」が作成。メンバーには他の大学やシンクタンク、経団連や東京商工会議所からも名を連ね、外務省や防衛省、経済産業省、財務省の官僚もオブザーバー参加している。
基本的には、安倍晋三内閣が2016年に打ち出した構想「自由で開かれたインド太平洋」(Free and Open Indo-Pacific=FOIP)を後押しする内容だ。しかし、「自由で開かれ、法の支配が貫徹されて初めて地域の平和と繁栄が実現する」(菅首相)という理念は語られても、諸政策を体系的に実現するための「国家戦略は存在しない」と提言は辛辣だ。
筆者はこの指摘に同意する。それは、日本が米豪印と連携して進めるこの構想の根幹として、「中国の台頭をどう捉え、対処すべきか」が詰まっていなければならないのに、政府内の議論を映す首相の言葉が、そうした大局観を国民に示すところまで熟していないからだ。
政府の説明不足を、この提言は補っている。まず、FOIPが単なる地政学的な勢力圏争いでなく、米国、中国それぞれに代表される国家理念のせめぎ合いであり、日本は米国側にいるということだ。提言から概要を示す。
米国は冷戦終結後、中国の経済発展が政治制度の民主化につながることを期待し関与政策をとってきたが、必ずしも成功していない。中国は国力拡大に伴い、特に習近平政権以降、香港や新疆ウイグル自治区などで共産党による抑圧的な統治を強化し、国有企業の優遇・強化など「国進民退」の動きもみられる。対外政策面では「韜光養晦」(力を隠し蓄える)から「奮発有為」(奮発し実行する)に転じ、米国に新型大国関係の構築を提案し、一帯一路構想を通じてアジアから欧州、アフリカに至る地域で経済・安全保障面で覇権を拡大しようとしている。朝日新聞社
中国は「豊かで安全な生活」を目指すモデルを新興国の発展モデルとしてアジア、アフリカの新興国に広げようとしているが、自由や民主主義を欠いた発展モデルが国家及び国際社会の持続的な安定と繁栄の達成を導くのか疑わしい。民主主義や基本的人権などの価値観を共有する日本と欧米が連携し、「豊かで自由で安全な生活」を目指してインド太平洋地域の安定と繁栄を実現する必要がある。改革・開放志向でグローバル化の利益を得てきた中国が権威主義、覇権主義を強めることは自身のためにもならないという理解を促さねばならない。
提言はさらに、今年のコロナウイルスの感染拡大が米国、中国を揺るがした結果、インド太平洋地域への脅威が増していると指摘する。
中国は情報公開の不透明さにより世界へコロナの拡散を引き起こしたが、国家統制社会モデルにより国内のコロナ禍を収束させ、「健康シルクロード」を標榜し、各国にマスクなど医療物資を供給する「マスク外交」で先行。また、豪州牛肉の輸入制限、インドとの国境紛争、東シナ海への公船侵入、南シナ海での行政区設置など「戦狼外交」と呼ばれる対決姿勢を前面に出している。
米国はコロナ禍への対策が遅れ、人種問題を含む経済・社会格差の問題に直面し、自国第一主義・孤立主義的な外交を続ける中、米中競争関係の根源は中国の統治体制にあるという認識を明確にしている。米中体制間競争の側面がより先鋭化し、国際秩序が揺らいでいる。中国の挑発行為は続いており、コロナ禍による米国の混乱に乗じ覇権主義的行動を激化させる傾向がみられる。
では、日本はどうすべきか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください