すべてを自生化する必要はない、問題は自生化の範囲だ
2020年11月09日
ロシア語で書かれた文献のなかには、ときどき興味深いものがある。そうした記事や論文に触発されて、深く考えなければならないことがある。ここでは、「主権争いに備えよう!」というタイトルのロシア語雑誌『エクスペルト』に掲載された記事(2020年9月21日付)を紹介しながら、デジタル分野でのサプライチェーンの分断(デカップリング)の問題について考察してみたい。
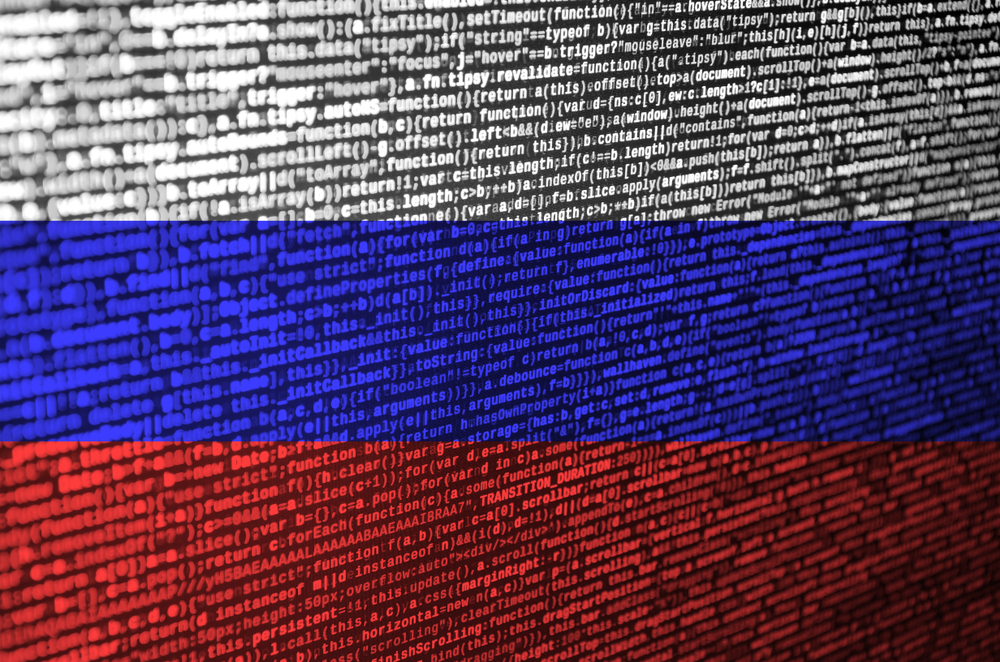 Shutterstock.com
Shutterstock.comこの記事の冒頭、「ソヴィエトのチップは世界最大である」という話が紹介されている。半導体チップをなかなか極小化できずにいたソ連の技術を揶揄する笑い話だが、こんな結果になったのは、ソ連が原料から製品までのすべてを自国製にこだわっていたからであった。米ソの冷戦下で、「産業のコメ」とも呼ばれていた集積回路などを外国に依存すれば、制裁などで自国に甚大な被害をもたらしかねないため、ソ連は半導体の自国製造に腐心したわけである。
もちろん、こんなやり方ではコスト負担がかさみ、最先端の技術に追いつくことが難しくなる。国際分業を前提に、安価で優れた製品を輸入して利用すれば、より大きな便益をより低コストで享受できる。
にもかかわらず、ドナルド・トランプ大統領の登場後、米中対立が深まるなかで、とくにデジタル分野での対中警戒感が強まり、これまでの国際分業に黄色信号がともるようになっている。暗号システム、情報技術(IT)システム、ネットワーク、末端コミュニケーション装置にバックドアのような脆弱性をもたせるように仕組む戦術があり、それを実践している米国政府は、中国政府が同じようなことをできるだけの技術力をもっている現状に大きな危惧をいだいている。
この危惧が強迫観念にまで至ると、かつてのソ連のように、「デジタル分野のハードもソフトもすべて自国製でなければならない」と言い出しかねない。少なくとも軍製品だけは「メイド・イン・アメリカ」を義務づけるかもしれない。
拙稿「中国の「ネット・ナショナリズム」にどう対抗すべきなのか」でも紹介したように、トランプ大統領は中国のTikTokやWeChatを目の敵にして、それらによる米国の企業や個人の情報データの違法取得を防止しようとしている。これ以前にも、2018年に商務省は虚偽の申告を理由にZTE(中興通訊)への輸出特恵の拒否を決めた。
さらに商務省は、2019年、ファーウェイ(華為)への米国製チップの米企業による販売を禁止し、2020年5月には、内外の企業がファーウェイのカスタムメイド・プロセッサーを製造するために米国製チップ製造装置を利用することを禁止する規則を追加した。加えて、連邦通信委員会は同年6月、ファーウェイとZTEを国家安全保障上の脅威に指定した。
他方で、できるだけ重要な部品は米国内で製造させようとする動きも
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください