2021年01月13日
新型コロナウイルス感染症(COVID-19)向けワクチンをいち早く開発し、国内だけでなく海外向けにも輸出することで、外国との関係強化につなげようとする外交、すなわち、「ワクチン外交」がいま世界中で展開されている。いわば、ワクチン外交を通じて、国家の覇権を拡大しようする地政学上の新たな競争が繰り広げられているのだ。そこで、その実態について考察してみたい。
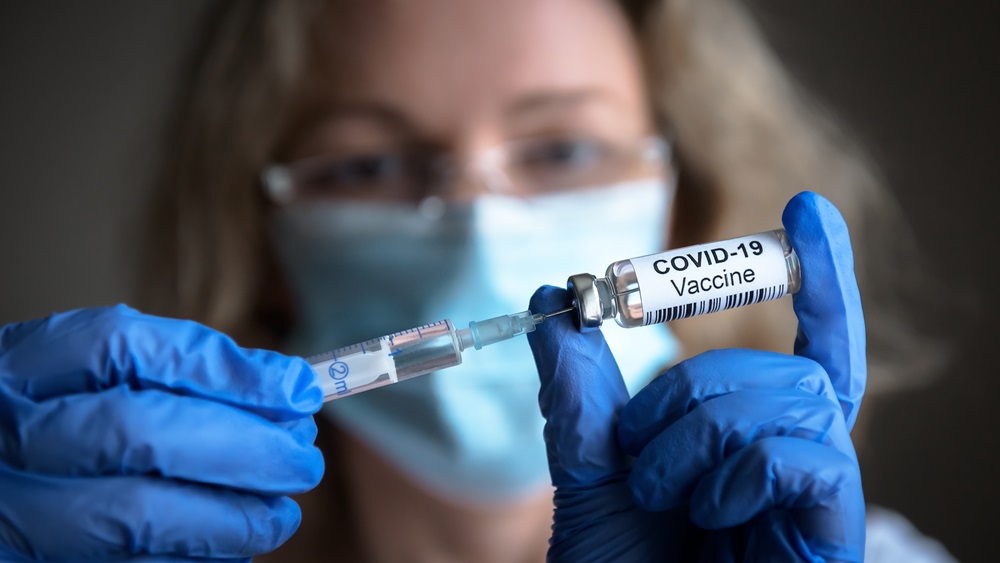 Shutterstock.com
Shutterstock.comワクチン外交がどのように行われているかを示す、わかりやすい事例がウクライナをめぐるものだ。「ニューヨーク・タイムズ電子版」(2021年1月9日付)の「ワクチン地政学でのウクライナ人の健康を賭けた大勝負」という記事がウクライナにおけるワクチン外交と覇権争奪について興味深い状況を伝えている。
2014年春のウクライナ危機の表面化、その後のロシアによるクリミア併合などによって、ウクライナ政府は反ロシアの立場からプーチン大統領の率いるロシアと激しく対立してきた。ゆえに、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)ワクチンもロシア製のものではなく、米国などの民主国家で開発されたものを輸入して国内で使用するというのが既定路線であった。
ところが、2020年12月8日、トランプ大統領は「米政府COVID-19ワクチンへのアクセスを確保するための行政命令」に署名し、「米国で開発され、または、米国政府が調達したCOVID-19ワクチン(米政府COVID-19ワクチン)に米国人が優先的にアクセスできるようにしなければならない」とした。この行政命令の結果、当時、ファイザー・バイオンテック製ワクチンなど、欧米のワクチンメーカーと協議中だったウクライナ政府は早期のワクチン輸入が絶望的な状況に追い込まれてしまう。
これに対して、ロシアは「スプートニクV」と呼ばれるワクチンを世界に先駆けて承認し、ロシア国内だけでなく、隣国のベラルーシ、さらに、アルゼンチンでも同ワクチンがすでに承認されている(「表 SARS-CoV-2向けワクチンの開発・輸出状況」を参照)。さらに、同ワクチンの輸出や各国でのライセンス生産がすでに決まっているとの情報もある。
具体的には、2021年1月6日現在で、インド(1億回分、インド国内生産で合意)、韓国(1億5000万回分を国内生産で合意)、ブラジル(5000万回分)、ウズベキスタン(3500万回分)、エジプト(2500万回分)、ネパール(2500万回分)、アルゼンチン(1000万回分)、ベネズエラ(1000万回分)、ボリビア(520万回分)、カザフスタン(200万回分, 国内生産で合意)などである。
このため、ウクライナにはロシアからのワクチン輸入の可能性が残されていることになる。だが、ウクライナ政府が選択したのは、中国製ワクチンであった。記事によれば、「12月下旬、ウクライナは中国のサプライヤーであるシノバック・バイオテックとの交渉を急ぎ、大晦日には2月初旬の納品をめざして190万回分の注文を発表した」のだ。
しかし、ウクライナ国内では、ロシア側による情報戦が仕掛けられている。親ロシア派のテレビ局などは、ウクライナのゼレンスキー大統領を、「敵から薬をもらうことを頑なに拒んだ結果、ウクライナ人を死なせてしまった」と非難しているのだ。
さらに、ウクライナ東部のハリコフを拠点とするバイオレックが2020年12月30日、ウクライナ保健省と同省国家専門家センターにスプートニクVの医薬品登録申請を行ったことが大々的に報道され、政府に対応を求める動きもある。加えて、ロシア側(ロシア直接投資基金)は昨年12月、アストラゼネカ・オックスフォード大学製ワクチンとスプートニクVとの混合ワクチンの試験を行うと発表し、ウクライナでの試験も準備しているとされる。
ロシア側は、アストラゼネカ・オックスフォード製ワクチンと組んだ実験が可能となるほど国際的に信用度が高まりつつあるスプートニクVの承認申請をウクライナ政府が拒絶すれば、「国民の命を軽視している」との政府批判を巻き起こしてゼレンスキー政権を揺さぶることができると、もくろんでいるようにみえる。なお、スプートニクVの評判については、「ニューヨーク・タイムズ電子版」(2021年1月8日付)に掲載され
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください