連載・失敗だらけの役人人生③ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓
2021年03月11日
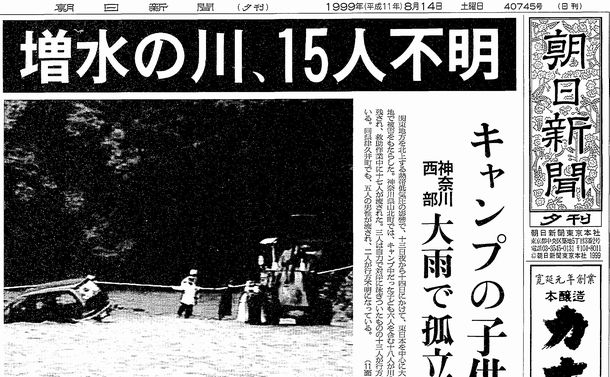 神奈川県内での水難事故を伝える1999年8月14日の朝日新聞夕刊1面
神奈川県内での水難事故を伝える1999年8月14日の朝日新聞夕刊1面2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。
1999年(平成11年)の7月に防衛庁で運用局運用課長を拝命し、部員時代以来ほぼ10年ぶりで再び運用課に勤務することとなりました。自分では「昔取った杵柄」で土地勘はそこそこ持っているつもりだったのですが、10年の間に内外情勢は激変し、自衛隊の行動も大きく変化していました。
国内では1995年(平成7年)に阪神淡路大震災と地下鉄サリン事件を相次いで経験し、国民の間に危機管理意識が醸成されるとともに、自衛隊の組織力・行動力に対する信頼感と期待感が高まりました。国際社会ではベルリンの壁の崩壊から10年が経ち、湾岸戦争や北朝鮮によるミサイル開発、不審船事件などを通じて、冷戦終結直後に高まった平和への期待感がしぼみ、国際情勢の流動化が明らかとなっていました。国際社会の安定化に寄与するため、自衛隊が国連PKOなどの形で海外に派遣されて活動する機会も拡大しつつありました。
こうした中で入庁18年目にして初めて課長ポストに補職された私は、与えられた責任の重さを意識しつつも大いに高揚していました。しかし、就任直後から立て続けに発生した様々な事案のため高揚感はあっという間にどこかへ消え去り、相次いで発生する各種の事案に無我夢中で対処する毎日となりました。
課長に任ぜられてひと月も経たない8月14日の土曜日、神奈川県足柄上郡玄倉川(くろくらがわ)の中州でキャンプ中の一行が増水した川の水に流されて13名の犠牲者を出すという玄倉川水難事故が発生しました。前日から降り出した大雨のため玄倉川が増水し、上流のダムでやむを得ず放水を開始したところ、当局の再三の警告にもかかわらず中州にとどまっていた行楽客の一行が増水した川の中に取り残されたという事案でした。
 玄倉川水難事故で神奈川県警のゴムボートで救出された女の子=1999年8月15日、神奈川県山北町。朝日新聞社
玄倉川水難事故で神奈川県警のゴムボートで救出された女の子=1999年8月15日、神奈川県山北町。朝日新聞社現場にはテレビ局のクルーが駆けつけ、一行が力尽きて流されるまでの一部始終の映像がテレビで放映されました。一行の中には、テントの支柱につかまって濁流に抗しながらヘリでの救出を求めて指を空に向けてくるくると回す者もいました。雨雲でほとんど視界が効かないという当日の悪天候の下では自衛隊のヘリを飛ばすことはできず、休日出勤したオフィスで私はその映像を居心地の悪い気分で観ていました。
このテレビ報道が大きな反響を呼んだこともあり、後日、警察庁の警備課長などと一緒に内閣官房長官(野中広務氏=編集部注)に呼ばれ、自衛隊や消防、警察などの対応について厳しく追及されることとなりました。なぜヘリを飛ばさなかったのか、基地から飛んで行けないなら現場近くまで車で運んで飛ばせば良かったではないか、農薬散布ヘリなどはそうやっているのに自衛隊や警察はなぜ出来ないのか、などと問い詰められました。さらに、ヘリが無理なら水陸両用車は使えなかったのか、戦車は川を渡れるのではないか、とまで問われて叱責されました。
 野中広務官房長官=1998年。朝日新聞社
野中広務官房長官=1998年。朝日新聞社もちろん、ヘリの運航基準や戦車の性能などについて説明はしたのですが、官房長官は最後まで得心が行かない様子でした。その時は正直「なぜそんな無理を言うのか」と思いましたが、後になってから、官房長官が問いたかったのは戦車を使わなかった理由などではなく、本当に先入観なしにあらゆる手段を検討したのかという点だったのではないかと気がつきました。確かに、私自身もヘリ以外の選択肢は思い浮かばず、「結果を出すために使えるものはすべて使う」というアプローチが出来ていたとは言えませんでした。
災害救助を含め、危機管理は結果が全てです。政治家は選挙民から常に具体的な結果を求められるため、結果を出すことに対して極めて敏感です。これに比べて防衛庁を含め中央官庁の役人は直接の現場を持っておらず、現場で求められる結果をイメージしにくい立場にあります。このため、ともすれば役人は結果よりも制度や手続き、手順を重視する傾向に陥りがちだと言えます。さらに、冷戦時代の防衛庁の主要課題は「自衛隊の運用」よりも「防衛力整備」だったため、なおさら「実動によって結果を出す」という意識が乏しかったように思います。
ところが、阪神淡路大震災や地下鉄サリン事件への対応、さらにはPKOや国際緊急援助活動など自衛隊の実動の機会が増え、「防衛力整備から自衛隊の運用へ」「存在する自衛隊から働く自衛隊へ」という変化が進みました。玄倉川水難事故はそうした変化のさなかに発生した事案であり、官房長官からの叱責によりそれまでの自分に欠けていたものを突き付けられたように感じました。
人命がかかった場面ではプロセスは二の次で、命を救うという結果こそが最も重要です。厳しい言い方をすれば、「自分はこんなに努力した」とか「規則に従えばここまでしか出来なかった」というのは言い訳に過ぎず、求められている結果を出せなければ何もやらなかったのと一緒だということになります。
もちろん、当時の自衛隊や警察、消防の能力を客観的に考えれば、中州に取り残された人々を救出するのは極めて困難だったと言わざるを得ません。しかし、私自身はこの一件をきっかけとして、手続きや手段などの固定観念にとらわれずに「結果を出す」ということを意識するようになりました。
続いて翌9月には茨城県東海村において東海村JCO臨界事故が発生しました。これは、核燃料加工施設で安全基準を守らずにバケツを使って作業していたところ、誤って核分裂連鎖反応を起こしてしまったという前代未間の臨界事故でした。我が国で初めての臨界事故に直面し、自衛隊は臨界を止めることも出来るのではないかと期待されて対応を求められました。
確かに、地下鉄サリン事件において活躍した自衛隊の化学防護部隊は、残留核物質や化学物質から乗員を防護出来る気密性の高い化学防護車や汚染された人員・装備を洗い流す除染装備などを保有していました。しかし、これらは全て核兵器や化学兵器などが使用された後の汚染された環境下で安全に行動するための装備で、現に臨界反応が起きていて放射線がどんどん放出されているような場所へ安全に接近できるようなノウハウや装備は皆無でした。
 1999年9月、日本初の臨界事故が起きたJCOの施設=茨城県東海村。朝日新聞社ヘリから
1999年9月、日本初の臨界事故が起きたJCOの施設=茨城県東海村。朝日新聞社ヘリからこのため最終的には、事業者自身が臨界を止める作業を実施し、自衛隊は東海村周辺で放射線検知や住民の除染活動などに従事することになりました。核兵器や化学兵器を保有していないのですからこれは当然の結果でしたが、これを機に特殊災害への備えの重要性が認識され、放射線が放出されている環境下で自衛隊はどのような行動をすべきかについても検討が開始されました。
核防護や化学防護と言っただけで「すわ自衛隊は核兵器や化学兵器を保有しようとしている」と批判されるような雰囲気に慣れてきた身としては正直戸惑いも感じましたが、同時に「これはいよいよ何でもありの状況になってきたな」という強い危機感を持ちました。
私が運用課長を務めていた2年間は、トルコとインドでの大地震、東チモール独立運動の混乱などにより、国際緊急援助活動のための自衛隊派遣が続いた時期でした。当時の自衛隊はまだ海外派遣について経験が浅く、その都度手探りで対応する状態でした。私自身にとっても初めての事だらけで、様々なところで衝突したり失敗したり叱られたりを繰り返しながら、「求められている結果」を目指して走り続けることとなりました。
ちょうど東海村原子力事故が発生し陸上自衛隊の部隊が対応していた頃、海上自衛隊はトルコヘプレハブ住宅の部材を運ぶ準備に忙殺されていました。この年8月17日、トルコはM7.6の大地震に見舞われ、1万7000名を超える死者を出し、60万人が家を失いました。日本政府は、地震で住居を失ったトルコの被災民のために阪神大震災の際に仮設住宅として使われたプレハブ(通称「神戸ハウス」)を送ることを決定し、これを国際緊急援助活動として海上自衛隊の輸送艦が運ぶこととなりました。
 1999年のトルコ大地震での海上自衛隊による援助物資輸送=防衛省の動画「平成11年 防衛庁記録」より
1999年のトルコ大地震での海上自衛隊による援助物資輸送=防衛省の動画「平成11年 防衛庁記録」より輸送準備に明け暮れていたところへ、あるNGOから「備蓄している毛布をトルコの被災民へ送りたいのだが輸送手段が確保できない。ついては神戸ハウスを運ぶ海上自衛隊の輸送艦に一緒に積んで持って行ってくれないか」という依頼がありました。「トルコはこれから冬に向かい寒さが厳しくなるが、神戸ハウスに暖房はついていない。ならばせめて毛布も一緒に配って被災民に暖をとってほしい」というのがそのNGOの想いでした。
早速実行に移そうとしたところ、法令解釈担当部署から「明確な法的根拠がないのではないか」という意見が出てきたのです。法律上自衛隊が実施できる国際緊急援助活動は、救援、医療、防疫等の活動と「これらの活動に必要な人員・物資の輸送」に限られています。このケースでは、現地でプレハブを組み立てて被災者に提供することが救援活動なので、神戸ハウスの輸送は救援「活動に必要な…物資の輸送」に当たります。他方、毛布がこの場合の「活動に必要な…物資」に当然該当すると言えるか疑問だというのが法令解釈担当部署の見解でした。
私自身も以前に法令解釈を担当した経験があったので、その見解はある程度理解出来ました。自衛隊は実力組織であり、出動に関する法手続きは特に厳格に遵守する必要があります。まして海外での活動となれば、慎重な上にも慎重を期さなければなりません。当時は前年にハリケーンで被害を受けたホンジュラスヘ初めての派遣を行ったばかりで、国際緊急援助活動については未だ若葉マークの段階でした。活動経験が乏しく万事に慎重な対応をとっていた時期なので、いきおい法律も厳格に解釈していたのです。
しかし、トルコヘ毛布を運ぶことは、誰かに対して実力を行使するようなものではないし、誰かの権利を制限するような行為でもありません。むしろ、私には「輸送艦には毛布を積む十分なスペースがあるし、運べばNGOも助かるし、何よりもトルコの被災民も喜ぶだろう。誰も困らず、むしろ皆が喜ぶのだから野党からもマスコミからも批判されるはずがないし、むしろこれを実行しない方が批判される」と感じられました。
このため、毛布の輸送は輸送艦の余ったスペースを活用して行うものであり法的効果のない事実行為であるという「事実行為・余席活用論」や、毛布はプレハブ住宅で使う暖房用品であり神戸ハウスと一体のものであるという「プレハブと毛布の一体化論」などを主張し、何とか法令解釈担当部署を説得して実施に漕ぎつけました。当然、どこからも批判はされず、毛布は無事にトルコヘ届けられました。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください