不安の感染を止められない日本の政治に処方箋はあるのか?
2021年02月19日
昨年来、新型コロナウイルス感染で揺さぶられ続ける日本の社会。“切り札”とされるワクチン接種ははじまったものの、先行きは依然として不透明です。コロナ禍があらわにした政治の問題や社会の課題は何か、それを克服するためにはどうすればいいのか。「論座」でコロナと社会について連載する社会学者の西田亮介さんと、立憲主義の観点からコロナ下の日本社会のあり方について問題提起する弁護士の倉持麟太郎さんに、オンラインでぶっちゃけ対談をしていただきました。(聞き手 論座編集部・吉田貴文)
 Zoomで対談する西田亮介氏(左)と倉持麟太郎氏(画面から加工しました)
Zoomで対談する西田亮介氏(左)と倉持麟太郎氏(画面から加工しました)西田亮介(にしだ・りょうすけ)
1983年生まれ。慶応義塾大学卒。同大学院政策・メディア研究科後期博士課程単位取得退学。博士(政策・メディア)。専門は社会学。著書に『コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か』(朝日新聞出版)、『ネット選挙』(東洋経済新報社)、『メディアと自民党』(角川新書)、『マーケティング化する民主主義』(イースト新書)など。
倉持麟太郎(くらもち・りんたろう)
1983年東京生まれ。慶應義塾大学卒、中央大学法科大学院修了。2012年弁護士登録(第二東京弁護士会)。日本弁護士連合会憲法問題対策本部幹事、慶應義塾大学法科大学院非常勤講師(憲法)など多方面で活動。共著に『2015年安保 国会の内と外で』(岩波書店)、『ゴー宣〈憲法〉道場』(毎日新聞出版)など。著書に『リベラルの敵はリベラルにあり』(ちくま新書)。
――新型コロナウイルス感染拡大に対応する特別措置法と感染症法の改正案が2月初め、自民、立憲民主両党が政府提出法案から刑事罰などを除外して修正することで合意し、4日間というスピード審議で成立しました。何かと批判の多い政府のコロナ対応ですが、迅速に対応したとみるべきでしょうか。
西田 今回の特措法、感染症法の改正は「出来レース」に近い認識をもっています。過去の感染症対策、2012年の新型インフルエンザ等対策特別措置法制定の経緯、1990年代の感染症法の施行に至る過程に照らして、今回の改正の当初案は人権配慮や私権制限の面で明らかに無理筋でした。野党第1党の立憲民主党は迅速な法改正が必要だとして、与党案の部分的な修正を引き出すとあっという間に妥協しましたが、「公正性」「公平性」の議論が十分ではなかったと思います。そもそも「第3波」がくると言われながら、十分な備えをしていなかった政治の責任は重い。
――確かに、コロナの感染がやや収まっている間、再感染への備えが政治には乏しかった。年明けの2回目の緊急事態宣言もどこかバタバタしていて、1回目の経験がいかされていないように見えました。
倉持 今回も前回同様、小池百合子都知事ら地方の首長に突き上げられる形で緊急事態が宣言されました。プロセスに進歩がないことに加え、内容的にも問題が大きいと思います。緊急事態は、国や社会を守るために立憲的な縛りを一時止めるもので、明らかに「有事」です。立憲主義社会では「有事」と「平時」を区別することが不可欠ですが、そこがあいまいです。それどころかまん延防止等重点阻止という“グレーゾーン”も設けられ、「有事」と「平時」の境界線がさらに溶けた。
また、本来罰則という我々の権利制限については、代表者である国会が制定する法律である程度明確に規定すべきです。しかし、罰則の対象となる行為が実質的に政令に丸投げされており、政府のさじ加減で罰則の対象が規定できるため、予見可能性もありません。宣言発令に国会の関与がないことや宣言延長の回数制限及び解除の基準が事実上ないのも、明らかに立憲民主主義の逸脱です。
 衆院本会議で、新型コロナウイルス感染症に対応する特別措置法と感染症法の改正案が賛成多数で可決された=2021年2月1日
衆院本会議で、新型コロナウイルス感染症に対応する特別措置法と感染症法の改正案が賛成多数で可決された=2021年2月1日――患者数の拡大と社会不安の高まりに押され、政治が慌てて対応するなかで、立憲主義をなおざりにしているということでしょうか。「第1波」のときは、コロナ患者も死者も欧米と比べて少なく、「日本モデル」が成功したという声もありましたが、いまなぜ、こんな状況なのでしょうか。
 『コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か』(朝日新聞出版)
『コロナ危機の社会学 感染したのはウイルスか、不安か』(朝日新聞出版)
倉持 同感です。「日本モデル」といいますが、要は法的根拠がない自粛要請で、国家が責任主体にならず、市民社会に丸投げしたものに他なりません。業者がそれで収入を減らしても、強制力を伴う公権力の行使ではないので行政訴訟も提起できない。法的に争えない措置でここまで国民の行動変容を調達できたのは、権力側にすればコスパがよかった。
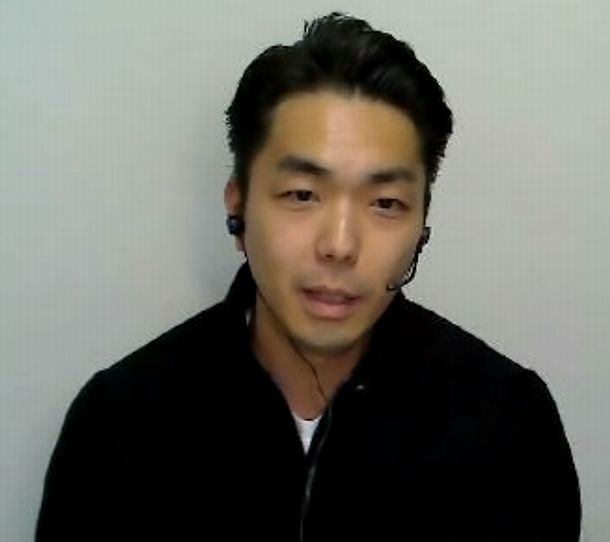 倉持麟太郎さん
倉持麟太郎さん昨年4、5月に野党の一部は議員立法で感染症法や特措法の改正案を検討していました。私も関わっていたのですが、感染者数が収まった時点で、野党は完全に葬り去ってしまった。立憲民主党が年末に出した法案より、ずっと目配りのきいた法案だったのですが……。
西田 新型インフルエンザ等対策特別措置法が定める「基本的対処方針」を通じて、政府は大きな方針を国民や国会に示すはずでしたが、昨年5月25日に更新されてから、年明けに二度目の緊急事態宣言がでるまで、対処方針は更新されませんでした。一体どういうことなのでしょうか。
1回目の緊急事態宣言が解除されてからも、コロナをめぐる状況は刻々と変わっていました。細かいデータや目標はさることながら、政府がコロナにどう対応するかという「大局観」は、もっと示されてよかったと思います。それなしに「Go To トラベル」などさまざまな施策が行われていくというのは、原理原則からすると本当におかしな話です。政府は国民や社会に説明する気も、説得する気もなかったと捉えられても仕方ありません。
――安倍首相はコロナ対応ついて世論の支持を得られず、体調も崩して8月末に突然、退陣を表明します。その間、そしてその後も「Go To」の扱いなどをめぐり、政府のコロナ対応は迷走します。
 西田亮介さん
西田亮介さん
政権に影響を与える世論には二種類あると考えています。ひとつは定量化された世論。内閣支持率、政党支持率、メディアによる世論調査が典型例です。もうひとつは、より質的なもので、著書では「可視化された民意」と書きましたが、ワイドショーの論調やSNSのランキングなど、「民意」と呼べるかどうか統計的にはかなりあやしいところもあるけれど、そのように見えてしまうもののことです。安倍政権は定量化された世論と可視化された民意の両睨みで対応しようとした。菅政権は両者を天秤にかけていたと見ています。
菅政権は定量化された世論、つまり内閣支持率が高い時は、可視化された世論は気にせず、強権的な対応をしています。日本学術会議への対応がその典型です。ところが、支持率が急落し、可視化された民意迎合に一気に傾きます。この傾向は安倍政権よりも強まっているように見えます。とても不安定です。
さらに、菅政権は自民党内“世論”にも対応しなければいけない。想起されるのが、「Go To」です。全国旅行業協会の会長であり、総裁選で真っ先に派閥としての支持を表明した二階俊博幹事長に、実質的に派閥を持たない菅首相は配慮せざるを得ません。また、観光産業、交通産業、飲食店といった地域で自民党を支えてきた経済団体にも配慮しなければならないという事情も抱えています。
 image_vulture/shutterstock.com
image_vulture/shutterstock.com倉持 今回の緊急事態宣言や特措法改正をみて思うのは、「耳を傾け過ぎる政府」が加速しているのではないかということです。象徴的なのは知事との関係。今回の特措法改正も1月9日の知事会の緊急提言が決定打になっている。菅政権は知事会の声やSNSなどの「新しい世論」に対して弱すぎる。僕は、特措法や感染症法の改正が場当たり的になってしまったのは、知事会からの要請が大きいと思っていて、「耳を傾け過ぎる」ことの弊害が出ていると思います。
日本にはこれまで、安保法制にしても、共謀罪にしても、基本的にアメリカの意向、“天の声”があったのですが、コロナ対応についてはアメリカも自国の対応に追われ、手が回らない。その結果、日本の統治機構やリーダーが、国民にこびるということでしかビジョンを示せていない。ビジョンなき場当たり的民主主義、現状を守るだけの保守政党が選挙で勝ち続けてきたなれの果てを、コロナ禍が図らずもあらわにしたと思います。
西田 日本におけるコロナ対応の最大の問題は、強権化する政治の一方で政策のオプションが枯渇しているように見えることです。現在走っている政策のほかにプランB、C、Dみたいなものが、自民党からでもいいし、野党からでもいいのですが、提示されていれば、政権のプランがうまくいかない時、他の政策を基に議論ができる。
ところが、安倍政権以来の官邸「一強」政治で、プランB、C、Dが自民党からも官僚からも出なくなってしまっているようです。野党も自分たちで大きな政策パッケージみたいなものをすっかり出さなくなってしまいました。
倉持 政策オプションは必要ですね。社会課題についての争点整理と争点形成は、基本的に政党、メディアの役割、特に野党の役割が大きいと思っていますが、スキャンダルに対して場当たり的に打ち返すばかりで、争点形成はもちろん、政府の政策にかわる提案も必ずしもできていません。
 西田亮介さん
西田亮介さん
その一方で、「生存権」や生活の保障はどうかというと、たとえば雇用調整助成金は一人1日上限1万5000円、休業中の労働者にも大雑把にいえば給与の8割が保証されます。一定額の給与がある人はいいかもしれませんが、非正規の人や手取りの少ない人はとてもやっていけません。困窮者への緊急貸付を増額すると言うけれど、こちらは貸付です。
戦後の日本社会は、人の生存権、生命を、諸外国以上に大切にしてきたと思います。例えばテロリストとは交渉しないのが国際社会の原則ですが、福田内閣下のダッカ事件では人命尊重第一のもと、テロリストに明白な妥協をしたことすらある国でした。リスクに対しては極めて防衛的な対応をする社会といっていいわけです。
そうした規範が、今回のコロナ対応では変質したように見えます。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください