官邸周辺の意向に右往左往する官僚。あるべき「政官関係」に向けた分析と提言
2021年03月28日
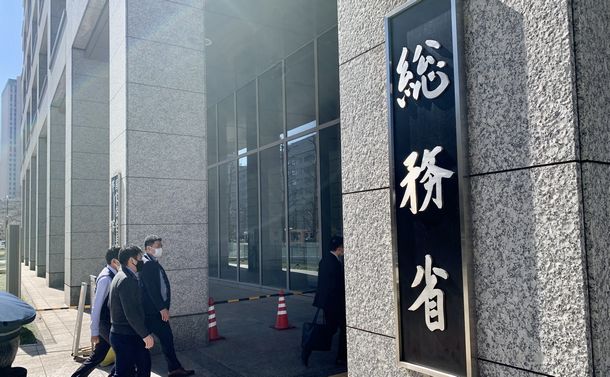 総務省の看板
総務省の看板総務省幹部の接待問題が国政の大きな問題として浮かび上がっている。
1999年に制定された国家公務員倫理法違反の法的問題として取り上げられているが、官民接待はすでに倫理法制定の数年前に、いわゆる「二信組事件」などを契機に、各省庁内では厳禁されるようになっていた。
その後、四半世紀が過ぎ、多少の緩みがあることは見聞きしているが、官僚の間では現在も、高額接待を受けることが法的問題以前に、倫理的にも組織規律的にも許されないことであることは認識されていたはずだ。さらに、接待が日常的に行われていた四半世紀前の霞ヶ関の基準で見ても、東北新社規模の企業が多数の総務省幹部クラスと頻繁に会食していたのは、非常に特異なケースとされるであろう。
しかし、国会に招致された総務官僚たちからは、国民の代表者である議員たちの前で、起きてしまったことを真摯(しんし)に反省し、事実を明らかにしようという姿勢はうかがわれない。すでにいくつかの答弁や「記憶」が事実と相違していることが判明した。真偽は不明であるものの、常識的に考えられないことを、国会で堂々と答えた者もいる。
政治の歴史の中で、議会の重要な機能の一つは、政府の監視と規律づけである。その国会の場で、官僚たちが議員の前でこうした対応をすることは、高額接待の問題を超えて、日本の統治機構のあり方として非常に深刻な問題である。
安倍晋三前政権に遡れば、いわゆる森友・加計問題の際には、さらに多くの「記憶にない」答弁に加え、公文書の破棄や改ざんまでもが判明した。こうした日本の現況は先進民主主義国家の中でも異様である。
省庁や事案をまたがってこういう異様な現象が同時期に顕れることは、偶然ではありえない。個人のモラルの問題は当然あるが、それだけでも説明しきれない。
官僚たちはとりわけ、「権力の所在」に敏感である。すでに国民もメディアも気づいているように、官僚たちの権力中枢への忖度(そんたく)が、一連の異様な行動をつなぐ要因になっている。官僚たちが国会であのような答弁を繰り返し、違法行為にさえ手を染めるのは、彼らの視線の先が国民や議員ではなく、権力の中枢を向いているからである。
国民やメディアも、権力の所在の変化を嗅ぎ取っている。20年前であれば、今回の総務官僚の接待問題やその後の国会での対応に対して、官僚への激しい怒りが沸き起こったはずだ。しかし、森友・加計事件以降、メディアの報道やSNSやニュースサイトのコメントを見ると、官僚に対して同情的なものが目立つ。この20数年で権力の中枢が官邸周辺に移り、今や官僚は、その中枢の意向に忖度し右往左往する主体性のない存在になりつつあると見られているのである。
 接待問題で参院予算委に出席する(左から)総務省の谷脇康彦・前総務審議官、吉田真人・総務審議官、秋本芳徳・前情報流通行政局長、湯本博信・前官房審議官=2021年3月8日
接待問題で参院予算委に出席する(左から)総務省の谷脇康彦・前総務審議官、吉田真人・総務審議官、秋本芳徳・前情報流通行政局長、湯本博信・前官房審議官=2021年3月8日統治機構のあり方を考えるうえで最も重要な視点の一つは、権力の集中と分散のバランスのあり方である。
古くは三権分立に始まり、権力の均衡と抑制のあり方については様々な枠組みが提案されてきた。東京財団政策研究所ではここ数年、権力の集中と分散のバランスについて、「政治のリスク分析」プロジェクトで分析を行ってきており、その一環として政官関係についての分析も行った。
民主主義国家における官僚には、「政治への応答性」が求められる一方、「政治に対する自律性」も求められる。そして両者の関係は、権力の集中と分散の問題そのものでもある。前者を重視すれば政治に権力が集中し、後者を重視すれば権力は分散する。立法府と行政府とが明確に分立している大統領制に比べ、日本の採る議院内閣制では、官僚の政治への応答性と自律性とのバランスのあり方には、とりわけ繊細な配慮が求められる。
政官関係についての議論はともすると、「政治主導か官僚主導か」といった過度に単純化、抽象化された二元論的な構図で語られることが多かった。しかし実務に適合しつつ、適切な権力の集中と分散のバランスを取るには、よりきめ細かな対応が必要となる。
本稿ではそのような視点から、今後の制度的対応のあり方について具体的に提言したい。
政官関係のあり方は、1990年代以降の日本で最も大きな政治論争の対象となった争点の一つである。
バブル崩壊後、「官僚の無謬性」の虚構は崩れ、激しい「官僚バッシング」が沸き起こった。「強すぎる」官僚の力を抑制し、いかに「官僚主導」を排し「政治主導」を実現するかが、90年代後半以降に進んだ諸改革の大きな方向性の一つだった。
一連の改革の結果、日本の政官関係は、他国との比較で見ても、政治サイドに強力かつ集権化された制度的な権力を与えることとなった。特に大きな影響力を持ったのは、閣僚人事検討会議、内閣人事局などによる幹部公務員の人事権の掌握だ。
ただ、制度だけでは政治や行政の実態は決まらない。政官関係についての現在の諸制度の原型は、90年代末の橋本龍太郎政権の頃にすでに形成されていた。閣僚人事検討会議が発足したのも橋本政権時だ。
しかし、日本でも強力な「政治主導」が実現しつつあることを多くの国民が実感するのは、2012年に誕生した第二次安倍晋三政権が誕生してからである。そこで顕わになったのは、政治――なかでも権力が集中した官邸――に「忖度」し、駆けずり回る幹部官僚たちの姿である。
最近は、「官僚主導」の問題点を指摘する主張は政界でもメディアでも少なくなった。逆に、政治、特に官邸への権力集中を問題視する論調が目立つ。しかし、90年代以降の諸改革が目指していたのは、まさに「官僚主導」を排し「政治主導」「官邸主導」を実現することである。
見方によっては、現在の状況は、一連の改革が目指していた到達点とも言えよう。改革の目的は達せられたのであろうか。あるいは行き過ぎたのであろうか。官僚の政治的応答性と自律性とのバランスが問われる局面に、今はある。
 首相官邸(奥)と公邸= 2017年1月18日、東京都千代田区(本社ヘリから)
首相官邸(奥)と公邸= 2017年1月18日、東京都千代田区(本社ヘリから)
官僚の政治的応答性と自律性のバランスについては、1940年代に官僚の「政治的説明責任」と「プロフェッショナルとしての責任」との緊張関係の問題として、ハーバード大学(当時)のカール・フリードリッヒとユニバーシティ・カレッジ・ロンドン(当時)のハーマン・ファイナーとの間で激しく論じられている。政治応答性を重視するファイナーが、階層的な制度によって政治は官僚を統制すべきだと考えたのに対して、自律性を重視するフリードリッヒは、組織的な統制ではなくプロフェッショナルとしての責任感により、官僚を内的に規律づけることの重要性を強調した。
官僚の政治応答性と自律性とはトレードオフの関係にある。前者を徹底すれば、官僚は政治に完全に従属し、政治に権力が集中する。この場合、政治家が国民全体の方向を向いていれば良いが、自らの選挙や利権や政治闘争のために官僚を使うといった事態も生じるだろう。そこでは、政治家のモラルハザードが問題になる。
一方、後者を徹底すれば、官僚に民主的なコントロールが効かなくなる。また官僚機構の中でも、各省庁や各行政機関が自律権を持つようになる。権力は分散するが、迅速かつ体系だった政策決定が困難となる。省益や私益に走る官僚も出てくるだろう。官僚のモラルハザードの問題である。
ここで必要なのは、「政か官か」の抽象的・理念的な二元論ではなく、両者の間の最適点をきめ細かに探ることである。「最適点」が両者の間にある以上、単純な二元論は必ずどちらかの方向への「行き過ぎ」や「暴走」を招くだけだ。
そういった地道な作業をするうえで有益なのは、政治学や経済学で発展した理論・実証枠組みを活用することだ。本稿では詳細には立ち入らないが、一連の研究の蓄積や歴史的な経験から示唆されるのは、政治応答性と自律性の適正なバランスは、政策分野や組織や各国の置かれた環境や歴史的経緯などによって異なってくるということだ。しかし、90年代以降の日本においてなされてきたのは、「官か民か」の単純な二元論と、周辺環境や歴史が異なる英米など他国の制度を直輸入しようという試みだった。
以下では、日本の現状や政策分野の特性を考慮しつつ、日本の政官関係についての制度改革の方向性を具体的に提案したい。
 yu_photo/shutterstock.com
yu_photo/shutterstock.com90年代以降の政治行政改革は、「官から政へ」「党から官邸へ」の権力移行を進め、多くの成果も生み出してきた。たとえば安倍政権への批判が噴出した加計問題でも、獣医学部が半世紀以上新設されなかったのはおかしく、そうした状況を打破したのが、安倍政権の官邸主導である。
ほかにも環太平洋経済連携協定(TPP)交渉などで、官邸主導の取り組みは、時代遅れの省壁を打ち壊し既得権を解放してきた。重要な政策課題に対する政策決定のスピードも向上しているように思える。これらは権力の集中のプラス面だ
しかし、一部で報じられているように、せっかく省壁の中から解放されたはずの既得権が、権力の所在に敏感な官僚の忖度などにより、新たな権力、すなわち官邸周辺に吸い寄せられ、官邸周辺の新たな利権となるのでは意味がない。財務省での文書改ざん、各省庁での文書廃棄、国会で次々と記憶を失う官僚たちなど、異様な事態が発生したことを考えると、なにをかいわんやである。
官邸主導を実現するうえで内閣人事局の影響力は絶大である。そのため一部領域では、内閣人事局の影響力を通じ、官僚の「政治への応答性」の重みが「プロフェッショナルとしての自律性」を圧倒し、幹部官僚が官邸周辺への“御用聞き”的な役回りにされている。
ではどうすればよいか。
国全体の重点政策についての官邸主導の大きな流れは捨て去るべきではない。一方で、官僚には一定の自律性を与え、彼らが無節操な忖度に走ることを防がねばならない。行政執行のプロフェッショナルとしての自己規律を守らせるようにしなければならない。この二兎を追うには、政策領域や組織に応じて、きめ細かに両者のバランスを取ることが必要だ。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください