連載・失敗だらけの役人人生⑰ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓
2021年06月17日
 甲子園球場のスタンドで、7回裏の阪神の攻撃前にジェット風船を飛ばすファン=2009年。朝日新聞社
甲子園球場のスタンドで、7回裏の阪神の攻撃前にジェット風船を飛ばすファン=2009年。朝日新聞社2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。
職業人にはP・K・Oの三要素が大切だと思っています。Pは「プロフェッショナリズム」です。Kは、責任を負う「覚悟」、逃げない「気概」、さらには喧嘩も辞さない「心意気」で、いずれにしても「K」です。最後のOは「思いやり」です。
「課題」を認識し、解決策を「検討」し、「結論」を得て望ましい結果を出すのが我々の仕事だということは既に述べました。行政のプロになるということは、担当分野に関する専門性を身につけて、この3Kの過程をきちんとこなして望ましい結果を出せるようになることです。そのために必要なことが二つあるということも既に防衛政策編で述べました。勉強して知識を身につけることと、実務の経験を積み重ねることです。
役所では、キャリアアップするにつれて、知識や経験のインプットとアウトプットの比重や内容が変化して行きます。一年生、二年生の係員の頃は、知識も経験もほぼインプット中心です。私は入庁してすぐに陸上自衛隊の防衛力整備計画の策定を補佐するポストに配置され、陸上幕僚監部(通称「陸幕」。陸上自衛隊を管理する制服組の組織=編集部注)に日参して、陸自の編成、装備、運用などのイロハから教えて頂きました。二年目の秋からは官房に勤務し、国会対応や法令・文書審査などを担当し、自衛隊関係の法律や政令の勉強に明け暮れました。
その後、主任、係長、部員(他の省庁でいえば課長補佐=編集部注)と昇任して行くにつれて、インプットと同時にそれまでに培ったものをアウトプットする場面が出てきます。この時期には法令立案の「修羅場」における内閣法制局との集中的な議論や、各幕との議論・調整、安全保障政策を巡る外務省との議論、防衛力整備に関する大蔵省との議論などを経験しました。より高度な知識のインプットと政策立案という形でのアウトプット、両方の機会が増えたという印象です。先任部員(課のナンバー2=編集部注)になると課の組織管理も担当するので、政策立案のみならず、それまでに自分が蓄えた人間関係についてのスキルもアウトプットする機会が増えました。
 1981年に黒江氏が入庁した頃、東京・六本木にあった防衛庁=防衛省の動画「昭和55年 防衛庁記録」より
1981年に黒江氏が入庁した頃、東京・六本木にあった防衛庁=防衛省の動画「昭和55年 防衛庁記録」よりさらに進んで課長になると、責任はより重くなり、部員の頃とは違った視点から様々な事を学ぶ機会を得るようになりました。この頃には、行政府内の議論・調整のみならず、法案を巡る与野党との議論・調整などに主体的に関わる場面も増えました。局の筆頭課長は、こうした仕事に加え、局全体のマネージメントを行うことも必要でした。
いわゆる中二階の審議官や地方防衛局長になるとインプットの機会も増えるはずなのですが、私が経験した国会担当審議官や防衛政策局次長は相対的にアウトプット中心だったような気がします。局長以上のポストでは、それまでに培ったプロとしての自分のスキルをもっぱらアウトプットしていました。
このようなサイクルを意識したのは、文書課長や審議官として国会対応を担当するようになった頃でした。何となく「今の自分は過去に蓄積したものをアウトプットしているだけで、新たなものをインプットする機会が乏しくなっているのではないか」と感じるようになったのです。このため、先輩に紹介された部外の勉強会に積極的に顔を出したり、防衛省の情報本部から提供される分析資料を丁寧に読んだりするようになりました。もともと休日出勤の多い職場ですが、何もない週末でもオフィスに行って一人で資料を読むことが習慣化しました。この習慣は、次官を辞するまで続きました。
私は要領の悪い人間なので、プロになるための近道はなく、基礎勉強と実務経験を地道に積み重ねるしかないと感じています。職業人としての人生を歩む人たちには、勉強する手間をいとわず、新たな経験を積むことをためらわず、プロにふさわしい専門性を身につけて、「この分野については自分が一番詳しいんだ」というくらいの自信を持って仕事に取り組めるようになってほしいと思います。
総理官邸に勤務していた頃、上司としてお仕えしていた事務担当の内閣官房副長官(各省事務次官の元締め)(古川貞二郎氏=編集部注)から「いずれ幹部になろうとする者は、自ら責任を負う覚悟を決めておかなければならない。」と言われました。
役人人生で少なくとも二回、「覚悟」を決めるきっかけがありました。一度目は、既に紹介した運用課長時代のインド国際緊急援助会議における幹部激怒事件です。修羅場で他人に助けを求めても無駄であり、自分で何とかしなければならないということを思い知りました。
二度目は、2011年(平成23年)12月、防衛政策局次長として沖縄問題を担当していた頃です。普天間移設が停滞している焦りから極端で乱暴な言辞を吐くことが多くなっていた私は、そのたびに当時の次官(中江公人氏=編集部注)からやんわりと諭されていました。その次官が年明けに退官されると聞いた時に、この先自分を諭すバランサーの役目を果たしてくれる先輩はもういない、と気が付いたのです。
 2003年、首相官邸で記者会見する古川貞二郎・内閣官房副長官=朝日新聞社
2003年、首相官邸で記者会見する古川貞二郎・内閣官房副長官=朝日新聞社当時の手帳を眺めていたところ、あるページに「スーパーサイヤ人にならねばならない」「当たり前に、常識的に、前向きに→自覚持たねばならない」という走り書きがありました。当時何を考えたのか、記憶はもう曖昧です。多分、漫画「ドラゴンボールZ」で厳しい修行の末いつもスーパーサイヤ人でいられるようになった悟空のように、常に持てる能力を100%発揮できなければならない、仕事ぶりにムラがあったり極端で非常識な事を口走ったりしないように自らを律しなければならない、と反省し自覚したのだと思います。
苦しくても自力で闘うしかないし、その結果については自分が責任をとらなければなりません。その覚悟を決めるのは、早ければ早いほど良いと思います。では、どうすれば覚悟を決められるのでしょうか。
先の内閣官房副長官は、「若いうちから自分よりも二階級上の上司が何を考えてどう判断するのかをよく見ておくことが役に立つ。二階級上の上司は、君には見えないものが見えるし、手に入らない情報にも触れられるから、君とは異なる広い見地から判断することが出来る。それをよく観察して、自分がそのポストに就くための準備をしておくということだ」とおっしゃいました。普段から意識を高く持って準備しておけば、自然に覚悟も身につくということだと思います。
仕事から「逃げない」という気概も大事です。誰しも面倒な事、難しい事に関わりたくない、逃げて楽をしたいという誘惑にかられます。しかし、逃げるのは責任の放棄だし、責任者が逃げてしまえば仕事は失敗します。周囲はそういう態度を見ています。逃げずに難問に立ち向かえば、苦しいけれども周囲から信頼され評価され、次の仕事にもつながって行きます。逃げれば悪循環、逃げずに立ち向かえば好循環に入って行くのです。私はこのことを特に官房業務から学びました。
入庁二年目に官房総務課(当時)の係員として、国会からの要求を処理する窓口業務を担当しました。国会議員から要求される資料、説明、部隊視察の希望や陳情などをそれぞれの担当部局に割り振り、成果をフィードバックする仕事です。
ところが、その頃庁内には俗に言う「消極的権限争い」、すなわち面倒な仕事は自分の担当ではないと言い張って極力引き受けないという風潮が蔓延していました。私の調整相手はみな10年以上年次が上の先任や班長で、しかも多くは「余計な仕事はしない」という強固な意思と理屈で武装していました。こういう人たちに資料作成や議員説明をお願いし引き受けてもらうのは非常に骨が折れました。
さらに、文書課の先任部員を務めた時には、答弁作成の割り振りがもめた時(通称「割り揉め」)に関係者を集めて引導を渡すという嫌な役回りも経験しました。こうした業務を通じて、仕事から逃げようとする姿勢がみっともないだけでなく、本人にとっても組織にとっても有害だということがよくわかりました。
「自分の仕事ではない」と逃げる人たちは、逃げる理由を驚く程よく考え、よく詰めています。しかし、そんな事を考えているヒマがあるなら、関係者の知恵を持ち寄って答弁を書いてしまう方がよほど組織にとっても本人にとってもプラスになります。また、逃げる理屈ばかり考えていると、やれる仕事の範囲がどんどん狭まり、そのうちに最低限必要な仕事すらやり方を忘れていきます。逆に、「自分にはその仕事すべてはやれないけれど、出来る部分で貢献しよう」と考える人は、それを積み重ねることによって出来る範囲が徐々に広がっていきます。
 東京・市谷本村町の防衛省=2021年4月、藤田撮影
東京・市谷本村町の防衛省=2021年4月、藤田撮影「逃げない気概」を身につける上でもう一つ役に立ったのは、官房が所掌しているいわゆるバスケットクローズ、すなわち「防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること」の存在でした。官房は最後の砦であり、どんな面倒な仕事からも逃げられないのです。
文書課長の時も官房長の時も、私はこの所掌事務について「他人が嫌がる仕事を引き受けるのは最高にカッコいい事なんだ」と部下を鼓舞し続けました。ただでさえ割に合わない官房業務で苦労しているところに「持ち込まれる仕事は積極的に受けろ。それが最高にカッコいいんだ」などと言われ、部下はさぞかし迷惑したと思います。
しかし、ややこしい案件で処理に困っているからこそ、官房を頼りにして相談に来るのです。野球で言えば、官房は捕手や外野手のようなところがあります。捕手が難しい投球を捕ろうとしなかったり、外野手が間を抜けそうな打球を追うのをやめてしまったりしたら、ボールはネット際やフェンス際まで転がり、失点につながってしまいます。それと同じで、官房を頼りにして相談に来ているのに、抱きつかれるのが嫌だから蹴り飛ばすというような態度で接していたら仕事は絶対にうまく行きません。
役人生活を通じて自分が何一つ逃げなかったなどと言うつもりは毛頭ありませんし、きっと逃げたこともあったのだろうと思います。でも、少なくとも「逃げるのは格好悪い」「逃げたくない」という気持ちだけは持ち続けたつもりです。
逃げないためにどうすればいいか。それは面倒くさいし、苦しいし、簡単なことではありません。でも、手始めに「出来ない理由を考えるのではなく、自分は何が出来るのかを考える」のが良いと思います。最初はちょっとだけしか出来なくても、それを積み重ねて行けば徐々に大きな仕事もこなせるようになります。そうすれば自信もつき、必ず逃げない気概を身につけることが出来ます。
自分はどちらかというと温厚な性格だと思っていますが、この連載に当たり過去を振り返っているうちに、結構先輩たちと喧嘩していたことに気づきました。この連載の冒頭で書いたように天邪鬼だった上に、生意気で跳ねっ返りでもあったのでしょう。こちらから売った記憶はありませんが、先輩から理不尽な喧嘩を売られたら迷わずに買っていました。
法規課主任時代に、立法作業の修羅場を終えてやっとの思いで法案を国会に提出した直後、ある先輩から「君らは法制局で降りてばっかりいたらしいな」と言われ、「誰がそんな事を言ってるんだ?」と言い返しながら胸ぐらをつかもうとして周囲の人に止められました。私には体育会系のDNAがあるので目上の人には99%敬語を使ってきましたが、この一件は乱暴なタメ口をきいた数少ない例でした。
大臣秘書官時代には、ある先輩課長に呼びつけられて大臣の部隊視察日程に因縁をつけられたことがありました。この時は、激しく(敬語で)反論し、無理な主張を引っ込めて頂きました。
防衛政策局長の時には、平和安全法制の案文について先輩幹部と激論を交わしました。条文を巡る議論なので必ずしも理不尽な喧嘩だった訳ではありませんが、目撃した後輩には「ゴジラ対キングギドラのようだった」と言われました。どちらがゴジラだったのかは聞き忘れました。
 ゴジラ(右)とキングギドラのフィギュア=2015年、富山県の黒部市立図書館。朝日新聞社
ゴジラ(右)とキングギドラのフィギュア=2015年、富山県の黒部市立図書館。朝日新聞社若い人たちに喧嘩を奨励するつもりはありません。しかし、冷静に考えてどうしてもおかしいと思ったら、相手が先輩でも正々堂々と(敬語で)反論すればよいと思います。独りよがりではいけませんが、正当な反論はプロフェッショナリズムの表れでもあります。もちろん、先輩風を吹かせて後輩に意味のない喧嘩を売ったりするようなことは論外ですので、十分気を付けなければなりません。
職業人たるものは、同僚や部下、家族に対して思いやりをもって接しなければなりません。同僚や部下への思いやりは職場の雰囲気を明るくし、職員の士気を向上させます。思いやりは、言葉を通じて伝わります。普段の会話では気が付きにくいことですが、人が口にする言葉には大きな力があります。適切な言葉を使えば、一人一人の士気を高め、組織全体を活性化することが出来るのです。
私が役所生活を送った昭和・平成のレトロな雰囲気の中では、今でいうパワハラまがいの指導などは日常茶飯事でした。職員が上司に「死ね」などと面罵されている場面に出くわすことも珍しくなかったし、自分がその対象になったこともありました。
※写真はイメージです
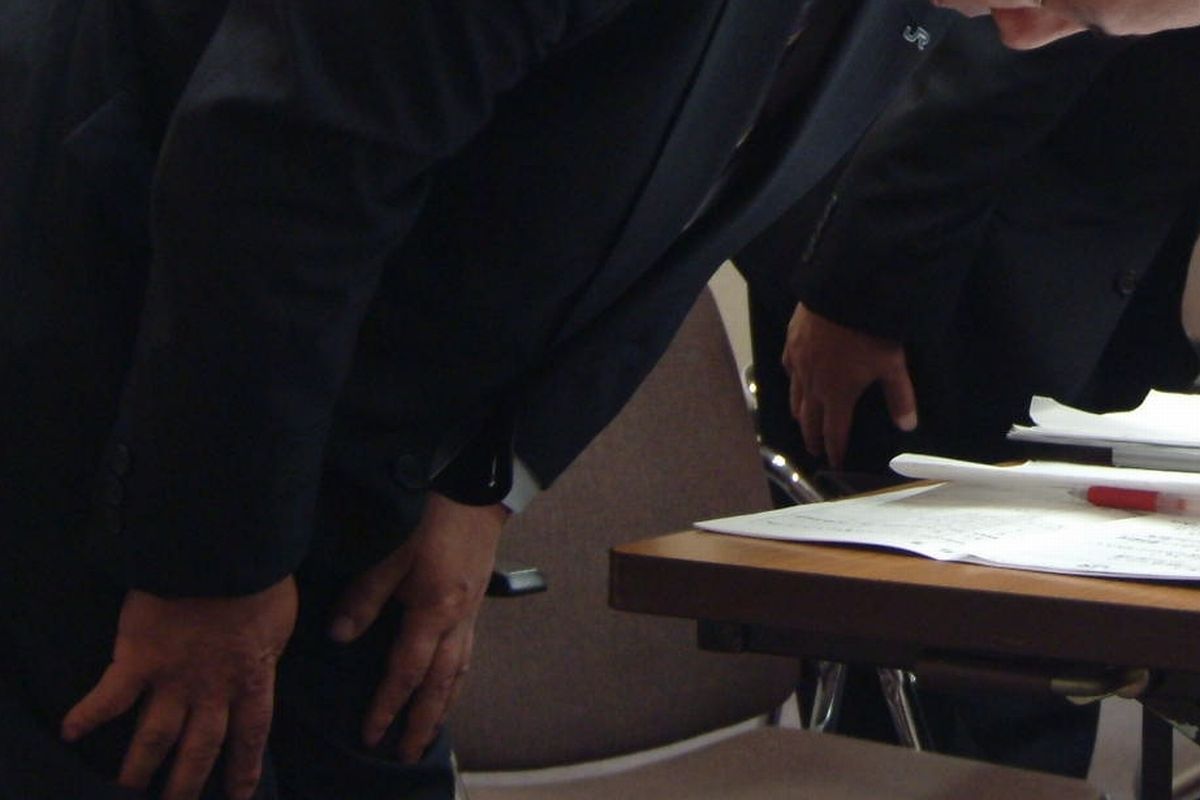 朝日新聞社
朝日新聞社特に、国会からの要求の調整窓口を担っていた二年生の頃にはずいぶん嫌な目に遭いました。要求を持って相談に行くだけで罵詈雑言を浴びせられ、挙句に「お前じゃ話にならん。上司を呼んで来いっ」と怒鳴られるような事も度々ありました。彼らは彼らで、自分の上司の局長に所掌外の答弁をさせたり部下に余計な仕事をさせたりしないために必死だったのでしょう。しかし、鈍感な私ですらそういう課に出向くのは気が重く、憂鬱で寝床から起きたくない、役所に行きたくないと思うような日もありました。
乱暴な指導が横行している職場はピリピリして雰囲気が暗く、職員は疲れ切っていました。逆に、雰囲気の明るい職場は風通しが良く、職員の士気も高くて良い仕事をしていました。実は、そうした対照的な職場の差は、ほんの些細な事なのです。上司が職員に対してほんの少し思いやりを示すだけで、思いやりを言葉にして口に出すだけで、雰囲気は大きく変わります。
防衛政策局の部員だった頃にお仕えしたある局長は、常々「自分は他の役所から来て知識が乏しいので、自分が言う事に素直に従われるとかえって不安になる。反論してくれる方が有難い。どんどん議論してくれ」とおっしゃられ、言葉通りに自由闊達に議論させて下さいました。情熱をもって仕事に当たられる一方、冗談がお好きな気さくな方で、役人生活を通じて私にとってのロールモデルでした。
また、防衛政策局次長として沖縄問題を担当した際には、取りまとめ役の内閣官房副長官(滝野欣弥氏=編集部注)にお世話になりました。民主党政権が誕生し、政治家と官僚の間合いが変化し、政府内での仕事のやり方も大きく変わって行く難しい時期でした。そんな時期に先が見えない仕事で苦しんでいた我々にとって、官僚の最高位にありながら気さくに接して下さり、苦労を分かち合って頂いたことは、大きな支えとなりました。
 2011年、民主党政権で沖縄問題を担当した滝野欣弥・内閣官房副長官(前列中央)と防衛省のメンバー。黒江氏は滝野氏の後ろ=黒江氏提供
2011年、民主党政権で沖縄問題を担当した滝野欣弥・内閣官房副長官(前列中央)と防衛省のメンバー。黒江氏は滝野氏の後ろ=黒江氏提供これから幹部になって行く若い人たちには、ぜひ部下や同僚に対する思いやりの言葉をはっきり口に出すことで組織を活性化してほしいと思います。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください