コロナ危機とその後の日本を待ち受ける深刻な課題にどう取り組むか?
2021年06月11日
コロナ禍は日本の社会が抱える課題をあらわにしました。それは、格差や貧困といった社会問題、雇用や不況などの経済問題、医療やITなど社会インフラに関わる問題、国際関係や民主主義のあり方をめぐる問題など、実に多様です。
「論座」では、こうした課題に向き合い、どうしたら解決できるのかをともに考え、行動するきっかけとなる論考を、これまで以上に力を入れて公開していきたいと考えています。その“政治版”として、自由民主党の4人の議員、林芳正さん、齋藤健さん、村井英樹さん、松川るいさんに、継続的な寄稿をお願いしました。
それに先立ち、今の政治をどう見るか、どんな課題に着目し取り組もうと考えているか、座談会で語っていただきました。コメント欄にぜひ、ご意見をお寄せください。(司会 論座編集部・吉田貴文)
林芳正(はやし・よしまさ)
1961年生まれ。東京大学卒業後、三井物産、大蔵大臣秘書官などを経て1995年参院選で初当選。当選5回。山口選挙区。大蔵政務次官、防衛大臣、農林水産大臣、文部科学大臣などを歴任。著書に『やさしい金融・財政論』、『国会議員の仕事』
齋藤健(さいとう・けん)
1959年生まれ。東京大学卒業後、通産省(現経済産業省)に入り、大臣秘書官、埼玉県副知事などを経て2009年衆院選で初当選。当選4回。千葉7区。農林水産大臣などを歴任。現在、予算委員会理事。著書に『増補 転落の歴史に何を見るか』
村井英樹(むらい・ひでき)
1980年生まれ。東京大学卒業後、財務省に入り、米ハーバード大大学院留学、同省主税局などを経て2012年の衆院選で初当選。当選3回。埼玉1区。自民党副幹事長や内閣府大臣政務官などを歴任。現在、国会対策副委員長(予算・文科担当)
松川るい(まつかわ・るい)
1971年生まれ。東京大学卒業後、外務省に入り、国際情報統括官組織首席事務官、女性参画推進室の初代室長などを経て2016年参院選で初当選。当選1回。大阪選挙区。党外交部会副部会長などを歴任。現在、防衛大臣政務官兼内閣府大臣政務官
 座談会で語る(左から)松川るいさん、齋藤健さん、林芳正さん、村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
座談会で語る(左から)松川るいさん、齋藤健さん、林芳正さん、村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館――メディアでは新型コロナの感染状況、ワクチン接種の進み具合、東京五輪の開催の可否などについてのニュースが連日、報じられています。そんななか、政府のコロナ対応をめぐり、有権者の間には不満が高まっているように見えます、秋までには衆院選もあります。与党議員として現状をどう見ているか。また、政治の課題はどこにあると考えていますか。
 齋藤健さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
齋藤健さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
まずはコロナ対策に全力をあげるしかない。ただ、その一方で、コロナ危機が去った後、さらに大きな危機がくるんじゃないかと思っています。
産業の競争力はかなり痛んでいる。財政は大変だ。少子化も止まらない。安全保障も、有事に対する備えがどれだけあるのか。これらの問題に我々は早晩、直面します。本来はコロナと平行して取り組むべきですが、その余裕がないのには忸怩(じくじ)たる思いです。
 村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
そのうえで、その先に目を向けたとき、私は政治の役割、課題が二つあると思います。一つは、危機に瀕して政治がしっかり機能するようにすること。2020年代、30年代に金融、安保、災害、新たな感染症などの危機が来たとき、政治が対応できるようにしなくてはならない。
もう一つは、政治が明るい未来像を示すこと。例えば、将来、年金をもらえないと思っている若い人は多いのですが、決してそんなことにはなりません。きちんと改革を進めれば、経済も社会保障もしっかり維持できます。皆さんに明るい見通しを持ってもらうためにも、必要な改革を一つずつ実行することが政治に求められていると思っています。
 林芳正さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
林芳正さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
対策に至るプロセスをもう少し説明をしたほうがよかったとも思います。我慢してもらうにしても、どんな理由で我慢してもらい、どうなれば解除されるかが、あまり伝わっていない。メディアの伝え方もありますが、説明が十分ではなく、どこもかしこも不満が残ることになったと思います。
コロナ後の課題は、私が言う日本の「負のお家芸」をどう克服するかです。日本は「シーズ」は結構つくっています。ヒトゲノムの解析をはじめたのは日立。3Dプリンターも日本の研究者がはじめた。タネを撒きながら、実になる前に他国の人に持っていかれ、果実を得られないという「負のお家芸」が最近目立つ。政府がお金をつけるだけではなく、お金が再投資される仕組みがあってもいいと思います。
 松川るいさん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
松川るいさん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
コロナに勝るとも劣らない日本の課題は、強大化し世界の覇権を狙う中国にどう対処するかです。強権的、高圧的で我々と異なる価値観を持つ国が、すぐ横で大きくなっている。日本としての中長期的な対中戦略を持って中国に対処していくことは、日本外交の最大の課題だと思います。
中国の問題は海と経済安保の二正面で顕著です。海については、尖閣諸島や南シナ海だけでなく、台湾有事への危機感も強く持っています。仮に台湾海峡で有事がおきれば、日本も無関係ではいられない可能性が高い。台湾と与那国は110キロしか離れていません。地図をみれば明らかですが、仮に中国が台湾を攻めようとすれば、大陸正面からだけで背後や周辺は放置ということにはならない。そこに尖閣諸島、先島諸島がある。ですから、台湾海峡で有事が起きないように中国を思いとどまらせることは、日本自身の安全保障のためにも重要です。
経済安保の問題もあります。中国はソ連と異なり、経済・技術強国であり、「超限戦」で見られるように、経済や技術を覇権獲得のために意図的に用いています。したがって、機微に触れる技術や半導体は安心できるサプライチェーンで調達するようにしないと、国の安全は保てません。
齋藤 中国の台頭が日本の危機になるという指摘は、非常に重要です。バイデン米大統領は「民主主義対専制主義」と言っていますが、そういう構図に世界が入りつつある。
「専制主義」の人たちの本音は、「今ある法と秩序は、自分たちが弱かった植民地時代に西欧諸国がつくった秩序で、従うつもりはない。自分たちは力を付けたので、新しい秩序をつくる」というところだと思います。そういう人たちが台頭してきているのです。
既存の法と秩序を守ろうとするアメリカは、このような動きを抑えようとしますが、専制主義の中国からすれば、「東シナ海や南シナ海で中国がやっていることをアメリカは批判するが、かつてアメリカがカリブ海でやったことと同じだ」と、聞く耳をもちません。そんなアメリカと中国に挟まれ、日本はどうすればいいのか。
松川 アメリカと日本は対中において、ほぼ国益が重なっていると思いますが、地政学的違いもあり、まったく同じというわけではありません。日本は中国のすぐ隣にあり、中国との平和で安定的な関係の維持は極めて重要です。アメリカは太平洋を挟んで向こうに位置し、今は民主主義と専制主義のどちらが主導権を握るかという戦いのフロントに立っていますが、引きこもることもできる。
ご指摘の通り、中国は失地回復の最中で、その最たるものが台湾です。習近平体制は極めて強固ですし、勝てない戦いは共産党体制そのものを揺るがせかねないので、そう簡単に台湾に手出しをするとは思わないし、米中のパワーバランスについては時間が中国を利すると考えているでしょうが、人口減少が進む中国にすれば、気長に待つ余裕もたぶんない。この10年間ぐらい、抑止力を高め、偶発的なものを含めて紛争が起きないようにする、そしてできれば中国の行動を変えさせることが大事になります。
バイデン米政権も紛争したいわけではない。同盟国やパートナー国と連携して強い立場をつくることで、中国の強権的行動を抑止しつつ、対中外交に取り組もうとしており、それは日本自身の対中戦略と重なります。
もうひとつ指摘しておきたいのはASEANの重要性です。日本が提唱した自由で開かれたいインド太平洋アジェンダが、米国や英仏など欧州を含む世界の戦略となっていますが、その帰趨を左右するのはASEANや太平洋諸国などの「間にいる国々」だと思います。私はASEANに関する仕事をやっていましたが、彼らは中国に支配されたくはないが、「中国に対処するために連携しよう」と言われても、中華経済圏にいる現状では、経済的な代替策なしに「そうですね」とはならない。そうした国々に「Quad」や英仏などインド太平洋戦略にコミットする国々が、積極的に投資をする、市場を提供する、援助をするといった経済的な関与策が不可欠でしょう。
――ここまでの議論で見えてきたのは、コロナ禍を通じて、日本の有事対応の脆弱さが鮮明になったということだと思います。振り返れば、平成の30年間、日本は冷戦終結後のグローバル化が進む世界に時代に対応できる政治を求めて、様々な改革を進めてきました。それは選挙制度改革や行政改革、地方分権改革、司法改革など多岐に渡りましたが、危機対応については十分ではなかったということでしょうか。令和の政治ではどういう改革が必要になると考えますか。
村井 平成の一連の改革は、一定の成果は出始めていると思います。たとえば官邸主導への転換です。55年体制では自民党の族議員と省庁の抵抗がからんで、総理が進めたい施策が進められないことがありましたが、今は総理・官邸がやろうと思ったらできる態勢は少なくとも実現しました。
 村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館そのうえで私は、令和は日本人が自信を取り戻す、取り戻すべき時代だと思っています。日本には今、様々な懸念があります。若い人たちが結婚しない、子どもを持たない。高齢者が貯金を使わない。企業がもしもに備えてお金を貯め込む。根本的な原因は、日本人の自信喪失であり、閉塞感だと思います。日本には、まだまだ優秀な人材がいますし、世界有数の技術力や製造業の基盤があり、豊富な金融資産もあります。細かな施策よりも、まずは自信を取り戻す。実現可能な明るい未来像を共有し、自信を取り戻すことで、日本企業、日本人の潜在力を発揮していくことが大切です。
松川 私も、令和の改革で大切なのは、日本がアニマルスピリッツを取り戻すことだと思います。少子高齢化で政治的リソースが若者にいかない現状を変え、若者に投資し、権限を与えて、国や社会、経済がじわじわと衰退する“ユデガエル”状態から抜け出さなくてはいけません。コロナで社会基盤の弱さが明らかになった今は、転換の好機です。例えば若い人を中心に、こんなにもダメだったIT基盤を構築するというのもありだと思います。
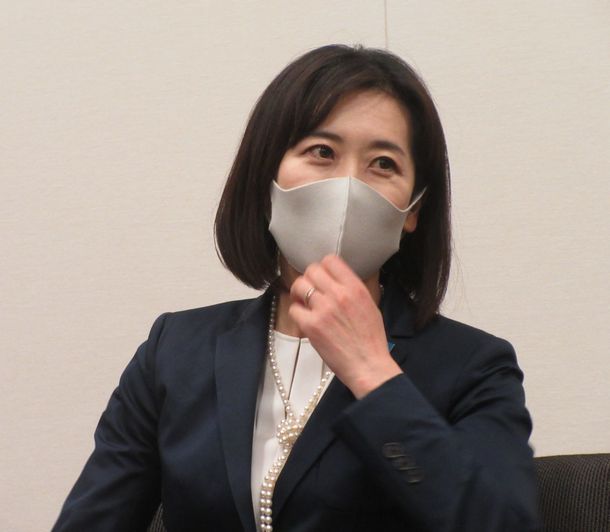 松川るいさん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
松川るいさん=2021年6月1日、衆院第一議員会館日本はどうか。かつては優秀な人材が霞ケ関で国づくりに邁進していました。ところが、1990年代の行政改革で政治主導が進み、第2次安倍晋三政権はそれをうまく活用したと思いますが、一方で官僚が積極的に知恵を出して仕事することが少なくなった気がします。やりがいが減った“ブラック”な霞が関に一流大学の学生が行かない、若くして辞めて外資系にいく、なんていうことも起きている。
政治主導は正しいと思うのですが、それではその分を政治家がカバーしているかというと、自分も含めて申しわけないですが、政治家を育てて活躍してもらうというシステムになっていません。選挙対策に大半の時間をとられ、国民の声や中長期的視点を反映した政策に取り組むのは容易ではありません。一方で、アメリカでは中長期の政策づくりを担うシンクタンク文化も日本ではいま一つです。人材をどう育てて活用していくかが、令和の大きな課題だと思います。
 齋藤健さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
齋藤健さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
プロボクサーの戸高秀樹は4回戦ボーイの時、マック・クリハラという名トレーナーに会い、見込まれて育てられ、世界チャンピオンになる。ボクシングは10キロも減量した上でなぐり合うという厳しいスポーツですが、ハングリー精神に欠けると言われながら、世界を制する日本の若者がいるんです。
この世界でナンバー1になれるなら、政治や経済、技術の世界だって、世界一になる若者はいると思うんですよ。いないのはマック・クリハラの方なんです。若い人を、上の人たちがどう引き上げて、挑戦させるか。これを意識的にやらないといけない。政治も例外ではありません(笑)。
林 明治維新や戦後は、外圧で上の人たちがいなくなり、若い人が出やすかった。外圧なしに、「時代は変わった。年配者は引っ込め」というのは、難しいかもしれません。また、昔の50歳と今の75歳は違う。今の75歳は生物学的にも能力的にも十分に働けます。
 林芳正さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
林芳正さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館平成の改革について言えば、戦後、日本は欧米という「お手本」をうまくキャッチアップしました。昭和から平成になり、すでに欧米に追いついているのに、教科書を探すメンタリティーが残った。平成には、政治改革もあったし、不良債権処理もしたけど、昭和のキャッチアップモデルを引きずったところがありました。
令和でこれがどうなるか。今の若い人たちは、かつてのような右肩上がりが当たり前の時代を生きていない。でも、それでも悲しくはないし、自分のやりたいことをする、友達や家族といるということに価値を見いだし、それを犠牲にして働いて給料を上げるという昭和モデルに価値を求めない。そこに、令和の「自信を取り戻す」のきっかけがあると思います。
――令和になり、昭和・平成モデルから新しいモデルに転換しなければならない、新しいビジネスや環境を作っていかなければならないということですが、どういう方向が考えられますか。
林 経済政策の前提として、どうしてもGDPで考えますが、4年前ぐらいから党にPT(プロジェクトチーム)をつくって「GDPが我々の実感と合わないところがある」という議論をずっとしています。
たとえば私は若い頃、2500円もするLPレコードを買っていました。今は月に1000円弱しか払わずに聞き放題で音楽を聴ける。安いお金でより多くの音楽を楽しめる。「Well being」(幸せ)は上がっているのに、GDP上は1000円しか計上されない。IT化でお金を使わずに満足するのでGDPが上がらなくなりました。
とすれば、GDPよりも「Well being」を重視したほうが合理的ではないか。OECDの「Beter life index」などの指標も取り入れ、「幸せ」の数値化、「見える化」し、それを増やすというのが令和らしいと思います。
村井 子育て世代で、さいたまでパパ友、ママ友と接している感覚でいうと、同じ収入でも、これまで体験できなかった価値やサービスが楽しめるようになったとは思います。
ただ、注意しないといけないのは、子どもの同級生の世帯で、収入が足りない低所得世帯が、なんとなく増えていると皮膚感として感じることです。聞いてみると、収入が上がらない職種、介護や警備、清掃の仕事をしていたり、フリーランス的だったりする人が多い。そして、今回のコロナ禍は、こうした層に悪影響を与えました。
こうした人たちに何らかの手当をする必要がある。特に、フリーランスの方には、雇用保険も厚生年金もありません。就労形態に中立的な社会保障が必要だと思っています。
林 低所得世帯の増加は深刻ですね。エッセンシャルワーカーのような、給料の上がらない職業に就く人への手当ては必要でしょう。ベーシック・インカム的なものとか、職業訓練をして給与のいい仕事に移ってもらうとか、やり方はいろいろあると思います。
80年代から2015年ごろまでの主要国のジニ係数の変遷を見ると、アングロサクソンの英米と、日本と、大陸系のドイツ、イタリア、フランスで、同じぐらいのところから始まっていて、アメリカ・イギリスは上昇、ドイツ・フランスはだいだい同じぐらい。日本はその間です。今後、どちらに向かうかは、注意する必要がある。
松川 コロナでは男女の賃金格差も拡大しています。3人に1人は離婚する時代なので、女性が「稼ぐ力」をもてないと、貧困のスパイラルに陥りますし、子供を持つこともできずに少子化が進んでしまう。就労形態に中立的な社会保障は多くの女性にとっても重要ですし、女性に限らず再教育の機会がもっと広く利用可能になればとも思います。女性は多様性の象徴みたいなものなので、すべての人に幸福度の高い多様なライフスタイルを可能とするためにも、女性が活躍できる仕組み作りは重要だと思います。
齋藤 マクロ経済の立て直しが不可欠でしょう。アベノミクスは成功例だったとは思うけど、では日銀はいつまで株を買い続けるのか、国債をいつまで発行し続けるのか、そこをしっかり考えないと、いつかカタストロフが来ます。くわえて、産業界の若返りをしないといけない。
私は、「道に迷わば原点に戻れ」という言葉が好きです。では、「日本の原点」とは何なのか。
日本は、アメリカのように資源があり、自分たちだけでやってはいける国ではない。食べ物も資源もエネルギーも、すべて輸入しないといけない。海外でお金を稼いて、それを国内のために使うことでしか、生きていけない国。それが原点です。そこでは、経済力、あるいは産業力といった「稼ぐ力」が最も重要です。コロナが終わった後、きちんとしたマクロ経済政策を作らないと、この国は漂流する気がしてなりません。
冒頭でも言ったように、できればこれをコロナと平行して進められないか。例えば、各省の大臣はコロナ対策に専念するが、副大臣に大物を据えて、コロナが終わった後の経済をどうするか、中長期的な視点から考えるというのも一策だと思います。経済産業省なら、大臣はコロナで苦しんでいる現在の経済をどうするかに集中するけど、副大臣は中長期的な経済の立て直しについて考えるわけです。厚労省の社会保障や財務省の財政もしかりです。
林 それはおもしろいですね。副大臣は若い人が普通はなるので、若い視点から中長期的な政策を考えるというのはいいと思います。官庁横断で考えないといけない課題が増えていますが、副大臣だと比較的自分の官庁にそれほどとらわれず、自由に現実的に考えられますしね。
松川 霞が関の「リボルビングドア」もありにすればいいと思います。経産省で培った知見を民間で活かし、お金も稼ぐ。民間で培った新しい能力を経産省や総務省に戻って活かす。そんな流動性がもっとあっていい。
 林芳正さん(左)と村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
林芳正さん(左)と村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館――コロナ対策への不満から政治への信頼が損なわれ、最近は「政治とカネ」の問題も目につきます。秋には衆議院の任期が切れる。選挙を控え、政治家として政治不信にどう向き合いますか。
村井 政治不信の原因は、「政治とカネ」やスキャンダルなど様々ありますが、最大の原因は、コロナ対応が有権者の皆さんに満足できるものでなかったことでしょう。そうだとすると、政治不信の解消は一朝一夕にはいきませんが、次の危機が来た時にしっかりと満足頂けるパフォーマンスができるよう、準備をすることしかないと思います。
危機時のガバナンスや統治のあり方はどうあるべきなのか、真正面から考えるべき時です。
伝統的に、日本人は強力な政府を嫌い、分権的な構造を好みます。織田信長のような強力なリーダーが許容されにくい社会です。デジタル化が進まない、医療の提供体制の改革が進まないのも、そうした分権構造に原因があります。しかしコロナ禍は、そうした日本の統治構造に大きな疑問を突きつけたのではないか。危機時には、もっと強力な政府が必要ではないか。政治も、与野党が一致団結する体制が必要だったのではないか。
与野党の議員のあり方も問われます。与党の政治家は個々の課題について役所に問い合わせることが多いですが、それによって役所が、対応に忙殺されることになった。野党の政治家は厚労大臣と健康局長を国会に4日間呼びつけて、ワクチンの「進捗が遅い」と質問するが、幹部が国会に貼り付けになっていて、ワクチン対策をどう進めよというのか。
未知の事態への対応については、専門家にもわからないことがあるし、いろんな意見がある。その場合、どう対応するのか。政府と地方公共団体との関係は、一般論としては民主的で分権的というのが望ましいですが、危機時には集権的に物事を判断して動かすことも必要になる。
こういった課題を、コロナ禍が落ち着いた時点で検証し、危機時など政治が求められている時に、求められている仕事をしていると思ってもらえた時に初めて、有権者の政治不信も解消すると思います。
――自民党は危機時に強い政党のはずです。今回はそこにガッカリ感がでていて……。
村井 そのガッカリ感があることは承知しています。ただ、他国との関係で、超過死亡者数がどうたったか、感染者数がどうだったか、丁寧にみていかないと、わが国の対応がどうだったかわからない。政府の対応を評価をするのはまだ、ちょっと早いと思います。
齋藤 僕が地元の人と接して感じるのは、みんな頭の中に「クエスチョンマーク」がでてきているということです。どうして日本はこんなにPCR検査はできないのだろう? ワクチンはなぜ遅れるのだろう? デジタル化はなにゆえ遅れているんだろう? といったクエスチョンがある。それが、政権への不満につながっていると感じる。
コロナ対策において、結果としてのパフォーマンスは、国際的に見ても悪くないと思っていますが、こうした疑問に一つ一つに反論できない。それが有権者、特に無党派が自民党から離れている要因だという気がしますね。
 齋藤健さん(右)と松川るいさん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
齋藤健さん(右)と松川るいさん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
松川 政治不信を払拭するには、政治家がきちんと仕事をすることに尽きると思います。ただ、政治家をめぐる環境は、必ずしも成果がすぐに出せるような仕組みになっていないように思います。
任期6年が保障されている参院議員から見ると、衆院議員の任期は短すぎます。本来の任期は4年なのに、衆院選が2~3年でおこなわれる。いつ選挙があるか分からないので、活動の多くが、特に当選回数が少ない議員だと、地元回りなどの選挙活動に費やされる。じっくりと仕事に取り組めるのでしょうか。
秘書の数も少なすぎます。国から人件費が出る秘書は政策秘書、公設第一、第二の3人。それ以上は自費。アメリカ並みとまではいわないまでも、もう少し秘書が雇えるようにしてほしいと思います。そうでないと、選挙ファーストもあいまって、有権者を満足させるような仕事は出来ないのではないでしょうか。その他いろいろな点で、人材活用としては非効率的なシステムだと感じます。
――平成の政治改革は、二大政党による「政権交代のある政治」を追求しました。実際、2009年、12年の二回、二大政党間での政権交代が実現しました、今回のコロナのような危機時において、野党は何をするべきなのでしょう。現在の野党についてどう見ますか。
林 東日本大震災の後、民主党の枝野幸男さんが自民党本部に来たことがありました。自民党本部に地方から上がってきた「要望」を政府に持って行ったのですが、枝野さんは「民主党にこれはできないので原本がほしい」と言うので、政調会長代理だった私が対応しました。枝野さんは「生まれてはじめて、自民党本部に入りました」と緊張していましたね。
当時の野党・自民党はやるべきことはやっていたと思います。コロナの今も、野党がもう少し存在感を、いい意味で発揮をして、与野党がいがみあうのではなくて、補完しあって対応できないかと思うのですが。
齋藤 3・11の時は、与野党で連立を組もうという話もありましたからね。国家的な危機ということで。
――今は大連立という話は皆無ですね。では、政権交代かというと、そういう機運は乏しい。
村井 私自身は都市部の議員として、遅かれ早かれ政権交代はありうると思っていますし、自民党もその危機感をもたなければならない。ただ、今年それが起きると大変だなと、一国民として感じています。
2009年に政権交代をはたした民主党は、与党になる準備を10年ぐらいかけて進めていました。当時、私は若手官僚でしたが、民主党に期待する声もかなりありました。今の野党には、残念ながらその準備はない。混乱は前回の比ではないと思います。
齋藤 下野した時の自民党には大変な危機感がありました。若手を抜擢(ばってき)しないといけない、派閥は壊さないといけない、派閥人事はやめようなど、全党をあげて変わろうとした。今の野党には、そういう危機感を感じません。
林 「Oposition」というのはイギリスでは与党を経験したことがあるという意味らしい。イギリスにはOpositionではない野党はいないわけで、これはとても大事なことだと思うのです。いつでも次は与党になると誰もが信じている集団が二つか三つあるというのが、政党政治なんですよ。
民主党政権が終わり、我々が政権に戻った時、民主党の人たちに「まずはお詫びと訂正からじゃないですか」と言いました。政府に入ってみたら、マニフェストは財源がなくて、実現できませんでした。間違って迷惑をかけました。しかし、次の内閣に入ったときには、同じ失敗は繰り返ません。そう言わないと、何を言っても有権者は聞いてくれないと。
民主党の一部はやりかけたのですが、党内の反対で諦めてしまった。有権者は高い授業料を払って、自民党にかわって与党になる経験を民主党に与えたんだけど、生かされませんでしたね。
松川 私の地元は大阪で、国政では野党の維新が大阪では与党なので、選挙では危機感はあります。でも、今の野党、立憲民主党や国民民主党が本気で政権をとろうとしているとは思えません。むしろ、55年体制に戻ったのではないかと感じています。日本では二大政党制はうまくいかないという認識が、民主党政権の大失敗でできてしまったんではないでしょうか。
政権能力のあるOpositionがあれば、緊張感をもった政権交代もあり得ますが、それがないので、結局、自民党の中でその機能を果たさなくてはいけない。それって、55年体制そのものではないかと思うのです。
林 宮沢喜一・元総理が、本にも書かれているのですが、日本は「一か二分の一ですから」と言ったことがあります。一が保守で、そうでない人が半分。だから、自民党がよほど失敗をして、民意がお灸を据えようとならない限り、自民党以外はなかなか勝てない。僕は平成の頃まではそうだったけど、だんだん変わってくるのではないかとも思っだけど、やはりそんなに変わらない。
齋藤 私も政権交代はないだろう、まさかコロナ危機のこの時期に、政治が混乱するような選択を有権者はしないと思ってはいますが、民意が動いているもの事実です。与党は油断なく、有権者の方々の声に真摯に向き合い、全力で取り組まないと、わかりませんよ。
 座談会を終えた(左から)松川るいさん、齋藤健さん、林芳正さん、村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館
座談会を終えた(左から)松川るいさん、齋藤健さん、林芳正さん、村井英樹さん=2021年6月1日、衆院第一議員会館有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください