失敗だらけの役人人生㉗ 元防衛事務次官・黒江哲郎が語る教訓
2021年08月26日
 2004年、イラク・サマワ近郊で移動中に周囲を警戒する陸上自衛官ら=朝日新聞社
2004年、イラク・サマワ近郊で移動中に周囲を警戒する陸上自衛官ら=朝日新聞社2017年まで防衛省で「背広組」トップの事務次官を務めた黒江哲郎さんの回顧録です。防衛問題の論考サイト「市ケ谷台論壇」での連載からの転載で、担当する藤田直央・朝日新聞編集委員の寸評も末尾にあります。
政府は2004年(平成16年)12月に、前回紹介した「安全保障と防衛力に関する懇談会」の報告書をもとに07大綱に代わる新たに「16大綱」を策定しました。この報告書の安全保障戦略を踏襲し、安全保障の二つの目標として侵略の抑止・対処と並んで「国際安全保障環境を改善し、我が国に脅威が及ばないようにすること」を掲げるとともに、目標達成の手段として07大綱に萌芽が見られた同盟政策の強化及び国際平和協力活動の拡大を明示しました。これは、国境を越えた広がりを持つ国際テロなどの脅威に対応するためには他国との協力が必要不可欠であるという考え方に立ち、自国の平和のみでなく国際社会の平和と安定をも重視する07大綱の方向性をさらに発展させたものでした。
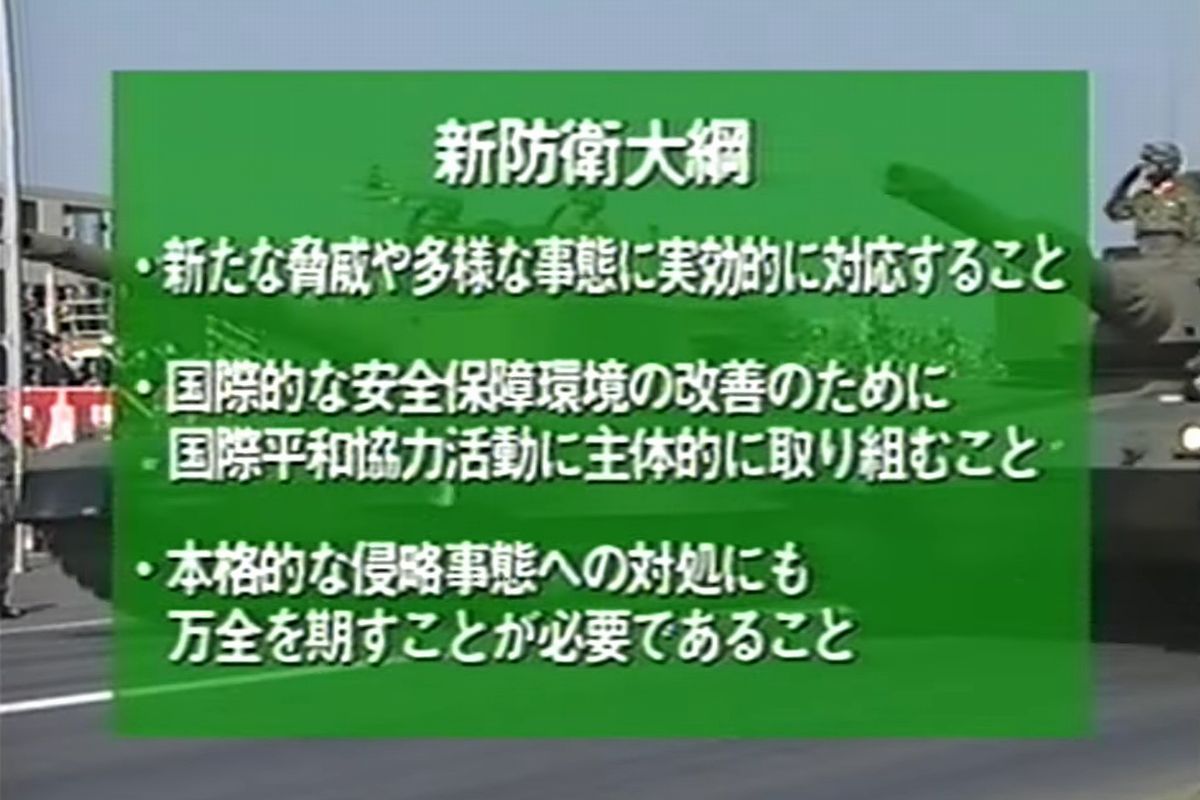 平成16年防衛庁記録より、「16大綱」の説明
平成16年防衛庁記録より、「16大綱」の説明また16大綱は、基盤的防衛力に代わるものとして、報告書を下地にしつつ「多機能で弾力的な実効性のある防衛力」を目指すこととしました。新たな国際環境の下では、中国のような地政学的な競争相手に加えて、北朝鮮に見られるような大量破壊兵器やミサイルの拡散、国際テロ活動など多様な脅威や不安定要因が出現しました。これらの脅威や不安定要因を防衛力の存在のみによって抑止することは難しく、実際に事態が発生した場合に迅速かつ柔軟に対処することを重視しなければなりません。加えて、海外活動の増加にも対応する必要がありました。冷戦時代であれば一定の防衛力が存在するだけで侵略を抑止することが可能であったのが、ポスト冷戦時代には多様な事態に自衛隊が柔軟に対応して実際に活動することが必要になったのです。
なお、16大綱は、変化を続ける国際情勢の下では防衛力の在り方について定期的に見直すことが望ましいとの考え方に基づき、情勢に重要な変化が生じた場合のみならず、5年という具体的な年限を定めて検討、修正を行うこととしました。
 平成16年防衛庁記録より、「16大綱」に盛り込まれたミサイル防衛の説明
平成16年防衛庁記録より、「16大綱」に盛り込まれたミサイル防衛の説明ところで、16大綱が閣議決定された直後に、また防衛庁から私のところへ電話がかかってきました。今度の電話は私の同期生からで、「新しい大綱、いいねえ。特に、第Ⅰ章から第Ⅲ省までは素晴らしいよ」と絶賛してくれたのです。その同期生は辛口で滅多に誉め言葉を言ったりしないタイプなので私は嬉しくなったのですが、「それに比べて第Ⅳ章はひどいな。結論だけ書いてあって考え方が書いてない」と言葉を継いだのでした。
実は、第Ⅰ章から第Ⅲ省までを書いたのは安危室の後輩の参事官で、出来の悪い第Ⅳ章の原案を書いたのは私だったのです。彼が指摘した欠点は自分でも内心気になっていたのですが、あまりに率直な論評だったので鼻白みました。それでも、全体として褒めてもらったのだからまあいいか、と気を取り直し「そうか、ありがとう」と答えて電話を切りました。
16大綱は、07大綱が先鞭をつけた「存在する自衛隊から働く自衛隊への転換」をさらに加速することとなりました。しかし、財政上の制約と16大綱が目指した「多機能性、弾力性、実効性」との間には深刻な矛盾がありました。現実問題として考えれば、個々の部隊や人員が果たし得る「多機能性、弾力性、実効性」には自ずと限界があるので、予算を削るために同じ隊員や部隊に際限なく任務を課することは出来ません。しかし、16大綱策定後の防衛力整備においては予算の抑制に重点が置かれ、結果的に部隊の負担が過大なものになって行きました。次の22大綱にも同様の問題点がありましたが、実効性のある防衛政策を行うには相応の資源配分が必要不可欠だということだと思います。
2006年(平成18年)は、私にとって官邸連絡室、安危室と5年間続いた内閣官房勤務の最後の年でしたが、様々な出来事があって忘れられない1年になりました。その一つ目は、イラク派遣の出口戦略です。
 2004年、イラク・サマワの陸上自衛隊宿営地に看板を掲げる先崎一・陸上幕僚長(中央左)と番匠幸一郎・派遣部隊長(同右)=朝日新聞社
2004年、イラク・サマワの陸上自衛隊宿営地に看板を掲げる先崎一・陸上幕僚長(中央左)と番匠幸一郎・派遣部隊長(同右)=朝日新聞社自衛隊のイラク派遣は既に2年に及び、その間は陸自の宿営地に迫撃砲弾が撃ち込まれるなどずっと緊迫した状況が続きました。官邸幹部も現地の状況には神経質になっており、派遣期間中は毎日欠かさず事務担当副長官の下に内閣官房・防衛・外務各省の関係者が集まって情勢ブリーフィングが実施されていました。
余談ですが、宿営地に迫撃砲弾が撃ち込まれる事案が発生した際、統合幕僚会議事務局(現統合幕僚監部)の幹部自衛官がブリーフィングの席に模擬の手りゅう弾や迫撃砲弾を持ってきたのには驚きました。説明にリアリティがあったのは良かったのですが、私は官邸へどうやって持ち込んだのか心配になりました。もちろん火薬は入っていませんが、それでもかなりの重量で金属探知機のある総理官邸に持ち込むのは容易ではありません。防衛庁の事務方の誰かが余程うまく官邸の警備担当に話を付けたのだと思いますが、総理官邸に手りゅう弾と迫撃砲弾が持ち込まれたのは後にも先にもこの時だけではないかと思います。
※イメージです
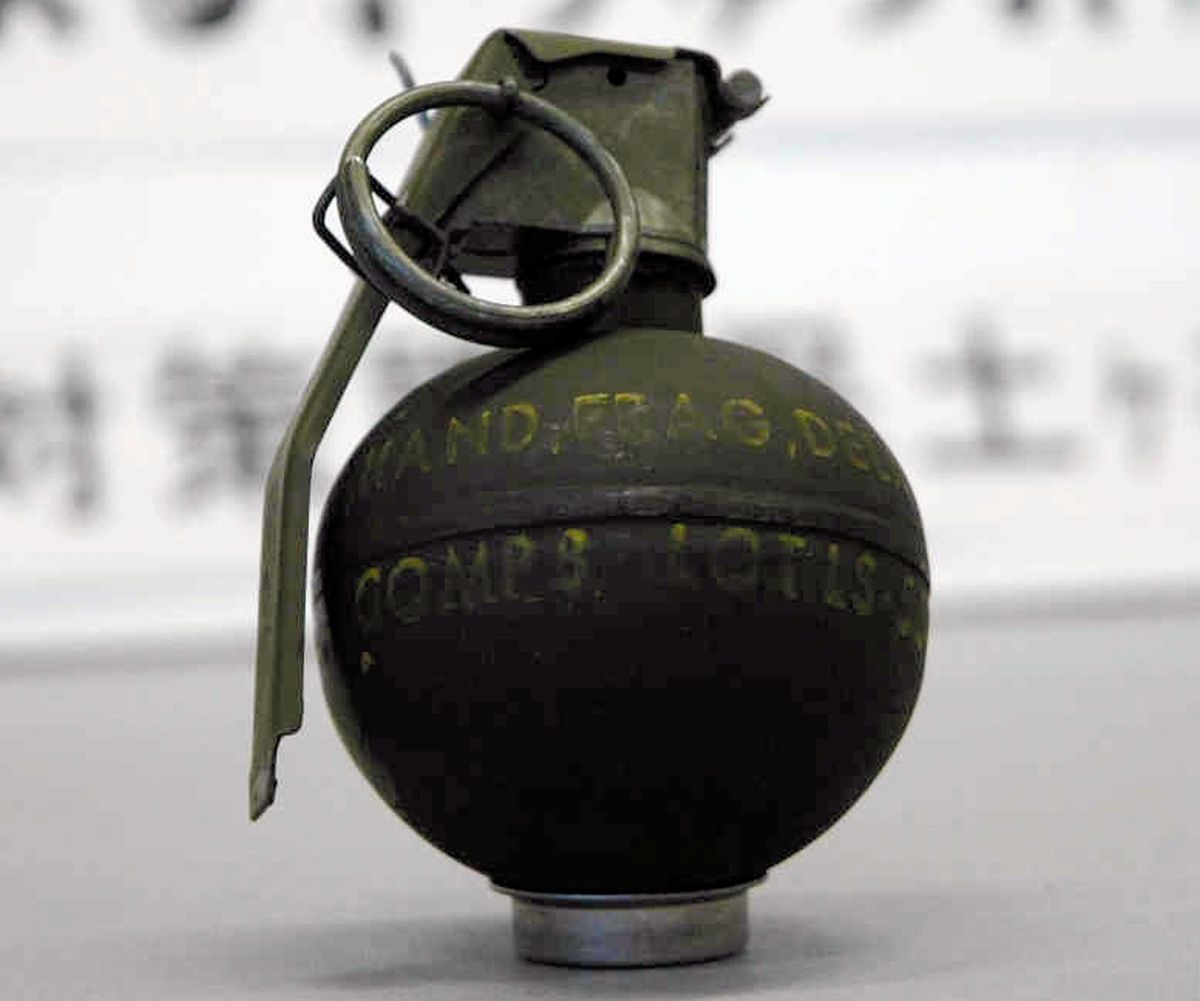 手りゅう弾。2008年に神奈川県警が暴力団幹部から押収した=朝日新聞社
手りゅう弾。2008年に神奈川県警が暴力団幹部から押収した=朝日新聞社サマーワにおける復興支援活動はテロの危険と隣り合わせの活動でしたが、陸自派遣部隊は規律正しい行動と地元住民との良好な関係の構築等を通じて一人の殉職者も出さずに任務を完遂しました。陸自によるインフラ復旧や医療、給水などの活動は、ODAや草の根無償支援などの経済援助と連携することで更に効果を高めることが出来ました。こうして派遣期間が2年になろうとする頃には、活動実績も積み上がって、インフラ復旧などもかなり進んでいました。さらに、サダムフセイン政権が倒れた後、多国籍軍を中心とする暫定統治機構がイラクの統治に当たっていたのですが、ようやく選挙や政権移譲が日程に上って来ました。
こうした様子を見ながら、いわゆる出口戦略を検討する必要性が出てきたのです。現地情勢や活動実績のほか、多国籍軍側の兵力配置なども勘案せねばならず、撤収の理由とタイミングを判断するのはかなり微妙で難しい課題でした。多国籍軍側とすれば、サマーワのあるムサンナ県のように治安権限の委譲が進んでいた地域ばかりではなかったため、一か国でも多くコミットし続けて欲しいというのが率直な考えでした。他方、この種の活動は部隊派遣国の事情を無視するわけには行かないので、様々な調整がなされました。調整過程ではイラクの別の地域への再展開も検討されました。
 朝日新聞社
朝日新聞社その頃、私は安危室の総括参事官を務めていました。再展開の候補地の一つとして当時英国軍が駐留していた南部のバスラという都市が上がり、2006年(平成18年)3月下旬に内閣官房・防衛庁・外務省の合同チームで現地調査をすることとなりました。クウェート経由の0泊4日の強行日程で、内閣官房からは私が参加しました。イラクへ行くと言うと心配されると思い、家族には「クウェートの空自部隊の視察」と称して出かけたのですが、家内には見破られていて、帰国した後に「イラクに行っていたんでしょ?」と言われました。私は気が弱いので、嘘をつくのが下手だったのだと思います。
この出張では、バスラの空港から市内の王宮に設置されていた多国籍軍本部まで移動する際に、英軍のヘリに乗せてもらいました。ヘリは、市内を流れる川沿いに猛スピードで低空飛行しました。しかも、その間中、英軍兵士がヘリのサイドドアを開け放しにして機関銃を構えているのです。高空を飛んで地上から携帯ミサイルで狙われるのを防ぐためだというのはすぐにわかりました。我々ももちろんヘルメットに防弾チョッキを着用していましたが、現地の治安状況が緊迫しているのを肌で感じさせられ、バスラ視察を終えてクウェートへ戻った時には正直ホッとしました。
※イメージです
 海賊対処行動でアデン湾に派遣された自衛艦の哨戒ヘリに搭載された、海賊への威嚇射撃などに使用する機関銃=2009年。代表撮影
海賊対処行動でアデン湾に派遣された自衛艦の哨戒ヘリに搭載された、海賊への威嚇射撃などに使用する機関銃=2009年。代表撮影クウェートからの帰路、乗り換え地のフランクフルトの空港ホテルで休憩した際、何気なくつけたBBCのTV番組がバスラでテロの犠牲となった英軍兵士のドキュメントを流していて、あっという間に現実に引き戻されました。さらに数週間後、我々が乗せてもらったのと同じルートを飛んでいた英軍ヘリが撃墜されたという報道に接することになりました。結局、陸自部隊がバスラに再展開することはありませんでした。こうした経験を通じ、海外派遣では早い段階から出口戦略を練っておくことが重要だと痛感させられました。
バスラ視察から帰国した後、4月は出口戦略の検討に費やし、5月の連休には入院中の父を見舞うため家族全員で郷里山形へ帰省しました。父の入院先の病院は山形市郊外の森林公園のそばで、病室には澄んだカッコーの声が聞こえてきました。連休が終わって東京に戻った私を待っていたのは、北朝鮮が弾道ミサイル発射の準備をしている模様だという情報でした。
当時、北朝鮮は車両搭載型の弾道ミサイルとともに、発射場から打ち上げるタイプの大型の弾道ミサイルを保有していました。後者の通称テポドンは発射場に据え付ける様子を衛星画像で確認することが可能だったため、発射の兆候を把握するのが比較的容易でした。政府内では安危室が中心となって関係省庁と協議しながら直ちに対応準備に入りました。一方で、この時期にはイラクからの撤収が具体化しつつあり、撤収に向けた段取りに関する政府・与党内での調整も並行して行われていました。細部はあらかた忘れてしまいましたが、当時の手帳を見ると北朝鮮対応とイラク撤収関連の会議日程が入り乱れ、極めて多忙な日々を過ごしていたことがうかがわれます。
 2006年、英軍ヘリに乗り込みサマワを離れる陸上自衛隊の派遣部隊=陸自提供
2006年、英軍ヘリに乗り込みサマワを離れる陸上自衛隊の派遣部隊=陸自提供そんな中、6月中旬のある日、入院中の父が逝去したとの連絡が入りました。連絡を受けた際、イラク派遣を担当していた安危室の上司の内閣審議官と一緒にイラク関連の会議へ向かっていたのですが、事情を知った審議官から「すぐ山形へ帰れ」と強く諭され、夕方の新幹線で帰郷しました。葬儀は数日後に山形市内の斎場で行われました。式が終わって会葬者をお送りする段になって、私がお仕えした防衛庁長官が参列しておられたことに気がつきました。わざわざ山形までお運び下さったお気遣いに心から感謝しつつ、先に気がついていればお席もご用意したのに、と失礼を悔やみました。いつまでたっても私はやはり気が利かない秘書官だったのでした。
数日後、父の葬儀が済んで東京へ戻った日に、イラク派遣に関する安全保障会議が開かれました。この会議で、サマーワの所在するムサンナ県の治安権限が多国籍軍からイラク側へ移譲され、治安・復興両面で自立的な復興段階に移ったことをとらえて、陸自の役割は終了したと判断され、イラク撤収が正式に決定されました。会議終了後、総理がその旨を発表しました。この決定を受けて陸自部隊は、6月下旬から7月上旬にかけてサマーワの宿営地を後にしました。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください