自ら行動しなければ政治は良くならない。民主主義の神髄に気づく契機に
2021年07月28日
国内外に課題が山積する今、政治はそうした課題にどう向き合い、解決すればいいか――。現役の国会議員が、それぞれ関心のある分野について、課題とその解決策について論じるシリーズ「国会議員、課題解決に挑む~立憲民主党編」。今回は落合貴之衆院議員の2回目の論考です。
現在の政治の閉塞状況を変えるために、被選挙権を選挙権にあわせて引き下げてはどうかという提案。「地盤」「看板」「カバン(鞄)」なしで国政に出てきた落合議員ならではの主張です。コメント欄にぜひ、ご意見をお寄せください。(論座編集部)
◇落合議員からの一言です。本稿をお読みいただく前にご覧ください!(1分30秒)
「論座」の前回の論考「政治改革の残された課題 企業団体献金全面禁止が今必要な理由」に多くのコメントをいただき、ありがとうございました。企業団体献金の実現を阻んでいるのは、世論ではなく、政治家だということも改めて認識しました。すでに法律案はでき、国会にも提出しています。実現のため、世論を喚起しながら、政治家たちをさらに説得してまいります。
さて、今回の私が論じたいのは、選挙に立候補が可能な年齢の引き下げ、つまり被選挙権の引き下げです。例えば現在、衆院議員に立候補できるのは25歳以上、参院議員だと30歳以上、都道府県知事も30歳以上、地方議員の場合は25歳以上ですが、これを一気に18歳以上にしてしまう、というものです。
暴論、と思われますか。いえいえ、そうではありません。世界的にみると、むしろ日本の現状のほうが異例なのです。なぜ、私はこれを皆さんに訴えようと考えるのか? 以下、説明をいたします。
7月4日、東京では都議会議員選挙が行われました。投票率は42.39%。過去2番目に低い投票率となりました。
都議選の記録を見ると、一番高かったのが1959年の70.13%。そこから段々と下がり、1997年には最低の40.80%を記録しました。以来50%台が3回、40%台が3回。そして、毎回、若い人ほど投票率が低いという傾向が続いています。
若者はなぜ投票に行かないのか、様々なアンケートが行われていますが、理由として、「関心がない」「面白くない」「選びたい候補者がいない」「政治家が信頼できない」などが多くあがってきます。これは若者に限った話ではない。中高年層でも、選挙に行かない理由は、同じようなものだと思います。
政治家として耳が痛いのは、「選びたい候補者がいない」「政治家が信頼できない」という声です。自分を棚に上げて恐縮ですが、実際のところ、現在、政治の世界において、議員の「いいなり手」が足りていないのは、紛れもない真実です。
衆院選が近づいています。今回は引退するベテラン議員が結構いるのですが、親族が地盤を引き継ぐケースが多い。当選すれば、いわゆる世襲議員になるわけですが、現在の国会をみても世襲議員が本当に多い。世襲議員が一概に悪いというつもりはありませんが、すべてが「いいなり手」とは言えないでしょう。
地方議会の選挙を見ても、立候補者が少なく選挙が行われず、届け出た人が全員当選という事態が、全国で頻発。「いいなり手」不足は深刻です。
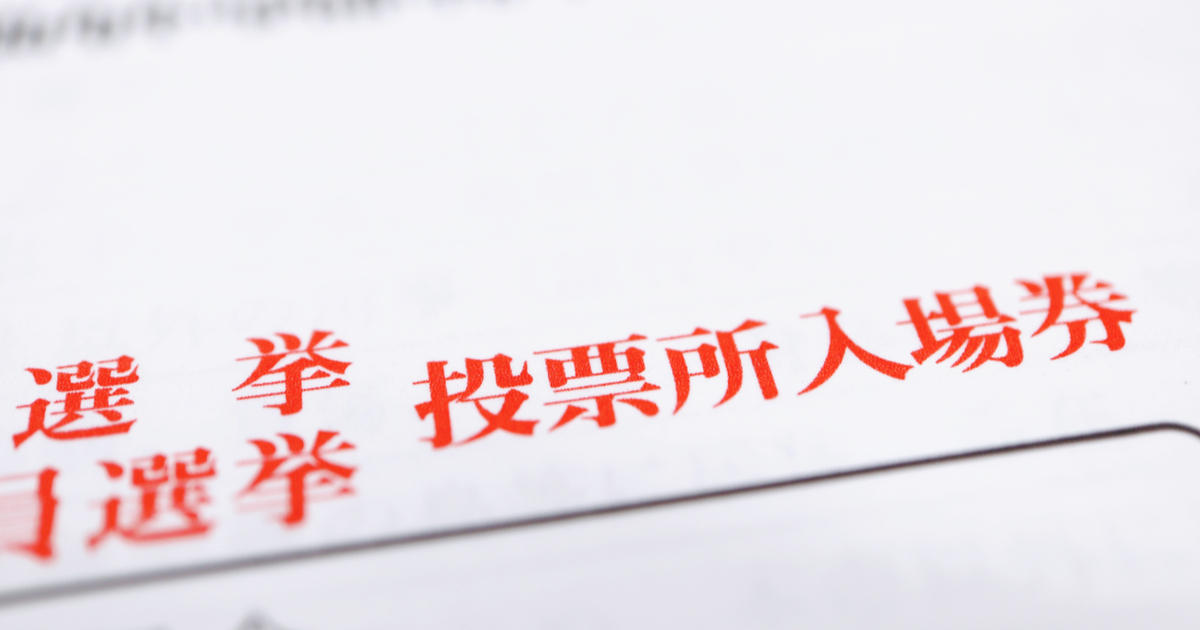 umaruchan4678/shutterstock.com
umaruchan4678/shutterstock.com民主主義のもとでは、選挙で投票するのは国民ですが、立候補するのもまた、国民、自分たちです。自分たちの中で立候補する人がいなければ、選挙という仕組みは成り立ちません。国民の誰かが、立候補して議員になり、国民の生命財産を守るという重責を担わないといけないのです。
そう考えると、選びたい候補者がいなかったり、政治家が信頼できなかったりする現状を招いた責任の一端は、実は有権者にもあるのではないか。政治がおもしろくなくて関心がもてないとすれば、自分たち有権者が政治をおもしろくしないから、おもしろくしようという人が立候補しないから、ということになります。
確かに日本では、「みんなの前では政治の話は控えよう」という“空気”が支配的です。こうした政治文化のもとでは、政治は有権者にとって遠い存在で、自分たちとは関係ない、自分たちには何も責任ないという、誤った感覚から脱することは難しいでしょう。
とはいえ、こうしたの他人任せの状態のままだと、今の政治は変わらない。「いいなり手」とは言えない政治家たちが権力をふるい、有能なリーダーが活躍する場面はなかなか出てきません。
こうした状態を変えるために私が提案したいのは、18歳から選挙に立候補できる仕組みを導入することです。
選挙には、二つの関わり方があります。ひとつは投票をして、政治家を選ぶという関わり方。もうひとつは、立候補をして政治家になるという関わり方です。
前者について言えば、わが国では、18歳になると投票できるようになります。自らの代表を選挙で選ぶことのできる「選挙権」という権利が与えられるのです。
その後、一定の年齢になると、選挙に立候補して有権者の代表になる資格ができます。「被選挙権」といわれる、これもまた国民の権利です。
ここで一定の年齢と書きました。実は、被選挙権は衆院議員や地方議員だと25歳以上、参院議員や知事では30歳にならないと与えられません。選挙権の18歳と、なぜか差があるのです。
政治という営みをつかさどる政治家には、それに相応(ふさわ)しい知識や経験、人格を持つ人が求められということかもしれませんが、なんとも腑に落ちません。選挙で投票する権利と選挙に立候補する権利は表裏一体なのだから、同時に与えられていいはずです。選挙権年齢にそろえて、非選挙権年齢も18歳にするべきです。
 Spica_pic/shutterstock.com
Spica_pic/shutterstock.comちなみに、世界の被選挙権年齢はどうなっているのでしょうか。
国会図書館の2015年12月の資料によると、調べのついた199カ国中、18歳までに被選挙権を得られる国は50か国。そのほとんどが選挙権年齢も被選挙権年齢も18歳で取得できます。
イギリスは2006年に被選挙権年齢を21歳から、フランスは2011年に23歳から、ともに18歳まで引き下げました。
その他、なじみのある先進国では、オーストラリア、オランダ、カナダ、スイス、スウェーデン、スペイン、デンマーク、ドイツ、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、ベルギー、ポルトガルなどが、被選挙権年齢が18歳です。
また、ヨーロッパにならったのか、アフリカの国にも18歳で被選挙権を与えられる国が多くあります。
日本は、国会の下院に当たる衆議院は25歳から立候補できますが、下院の被選挙権年齢が日本よりも高い26歳以上の国は、中東を中心に12か国しかありません。
このように国際的に見ても、日本の被選挙権年齢は高いのが特徴です。
なぜ、若者に立候補させないのか?
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください