「シーズ」が成果につながらない悪循環を断ち、新たな経済の方向性を示す
2021年08月10日
国内外に課題が山積する今、政治はそうした課題にどう向き合い、解決すればいいか――。現役の国会議員が、それぞれ関心のある分野について、課題とその解決策について論じるシリーズ「国会議員、課題解決に挑む~自由民主党編」。今回は林芳正参院議員の論考です。
国会議員として国政に携わるようになって四半世紀。日本をとりまく内外の情勢は大きく変わりましたが、なかでも経済の停滞ぶりは深刻で、その克服のためには、日本が依然もっている潜在能力を生かせる環境整備と、従来のGDP信奉にかわる経済の新しい方向性を示すことが必要だと林氏は主張します。詳細は以下の論考で。コメント欄にぜひ、ご意見をお寄せください。(論座編集部)
私が参院選に当選し政治家として歩み始めたのは1995年でした。当時、世界は冷戦が終焉して約5年。アメリカ、ソ連いう二大国による「米ソ対立」の緊張が解け、民主主義と自由経済が“勝利”したという「歴史の終わり」といった言説も流布していました。
日本では、90年代はじめにバブルがはじけ、さすがに「ジャパン・アズ・ナンバーワン」ではないにしても、「モノづくり」は依然健在で、トヨタやソニーが世界を席巻し、半導体でも世界の生産量の半分を日本企業が占めていました。外貨収入もふんだんにあり、経済は順調でした。
それから四半世紀が過ぎ、国際社会も日本も大きく変わりました。世界では、中国が確実に存在感を増し、経済でアメリカを凌ぐ勢いです。軍事的にも「大国化」を着実に進めており、アメリカは警戒感を強めています。
米中の“二大大国化”は、かつての米ソ対立と比べてはるかに複雑です。中国と世界との間で、ヒト、モノ、カネがかなりの勢いで動いているからです。冷戦の頃の米ソ間の1年分の貿易量が、現在の米中の貿易量の1日分というのは象徴的です。かつては「鉄のカーテン」でソ連陣営との間に壁をつくれましたが、今、中国との間に壁を作るのは無理です。
 J_UK/shutterstock.com
J_UK/shutterstock.com一方、日本を見ると、90年代半ば以降の長い経済的停滞を経て、勢いを失っているように見えます。得意の「モノづくり」で日本を引っ張る企業がでてきてないことに加え、GDPに反映されない「新しい経済の形」が生まれているにもかかわらず、「GDPの増加」にかわる目指すべき方向を見いだせず、迷走している感は否めません。
ただ、経済面でも安全保障面でも、変化のスピードは早さを増しており、いつまでも迷走しているわけにいかないのも事実です。日本は今、これまで築いてきた豊かな社会を子や孫の世代にどうやってつないでいけるかが、問われる局面にきています。
こうした局面に、どう対応すればいいのか。本稿では、経済を中心に私が重要だと考える課題と、解決のための提案について述べたいと思います。
日本の経済を立て直す鍵は、やはり「モノづくり」にあると思います。これまで培ってきた技術力をもとに、コロナ禍で出遅れが露呈したITはもとより、2050年カーボンニュートラルを見据えてグリーン産業を育成していく。なかでもグリーンについては、日本自体の温室効果ガスの排出量削減にとどまらず、排出量が多い中国、アメリカ、インドなどに技術を提供することは可能だと思います。
ここ数年、私が問題だと感じているのは、日本が「潜在能力」をいかしきれていないことです。例えば、羽のない扇風機も元々の発想は東芝だったと言います。3Dプリンターもヒトゲノム計画も、日本はにつながらない。そうしたシーズに注目した海外の資本家が大きな投資をして、花が開くという例が目立ちます。
シーズもない、潜在能力もないというのならともかく、それだけのものをもっているのに、成果につながっていないとすれば、政策や制度で後押しをする必要があります。
その第一歩として、私もかかわって6月に自民党がまとめた「経済成長の基本的考え方及び成長戦略についての提言」に、スタートアップ企業を生み出し、その規模を拡大するための環境整備に関する提言を、幾つか盛り込みました。ウイズコロナ、ポストコロナの世界において、企業のダイナミズムを復活させる狙いがあります。
日本で、後に上場企業になるような会社が数多く生まれたのは、終戦の年である1945年からの10年間でした。それ以降、こうしたブームは今に至るまで起きていません。実際、起業から10年以内で評価額が10億以上、非上場の「ユニコーン企業」は現在、日本では少数にとどまり、アメリカと中国が世界の8割を占めています。
寿命が長い会社がたくさんあるのは、決して悪いことではありません。しかし、変化のスピードが速い世界では、前例踏襲や現状維持では対応できない。旧来の会社が内部改革を進め、社内からベンチャーを出すことに加え、スタートアップ企業が終戦直後の日本のように次々と生まれるという状況になってはじめて、日本の経済は勢いを取り戻すと思います。
そのためには、スタートアップ企業が創業しやすい環境をつくる。逆に言えば、それを妨げてきた環境を改めることが必要です。
例えば、日本のIPO(新規公開株)では初値が公開価格を大きく上回っていますが、これはアメリカ、ドイツ、イギリスと比べて非常に高い水準です。スタートアップ企業がより多くの資金を調達できるよう、公開価格を初値に近づくよう引き上げることが望ましい。
そこで、自民党の成長戦略の提言には、IPO取引の公開価格設定プロセスのあり方の実態を調査し、見直しを図ることを盛り込みました。
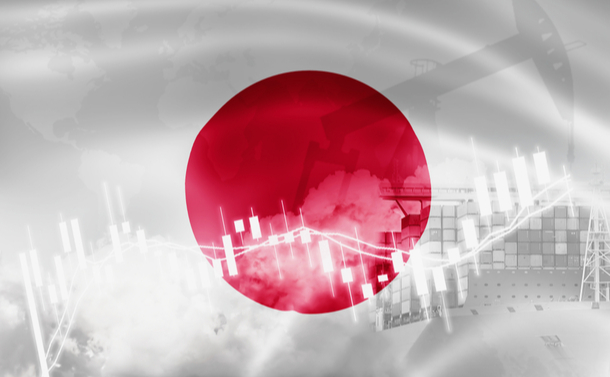 TexBr/shutterstock.com
TexBr/shutterstock.com「モノづくり」の復活とともに大切なのは、昭和型の「成長」にかわる経済の新たな方向性を定めることです。かつて池田勇人首相が「所得倍増」を掲げ、経済大国を目指して実現したように、令和の日本が目指すべき「大きな枠組み」を示したい。
日本はこれまで、ひたすらGDPを増やすこと経済の目的としてきました。しかし、成熟社会になって、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください