コロナ禍で市民社会は権力によってだけでなく自ら進んで萎縮的になっていないか
2021年08月27日
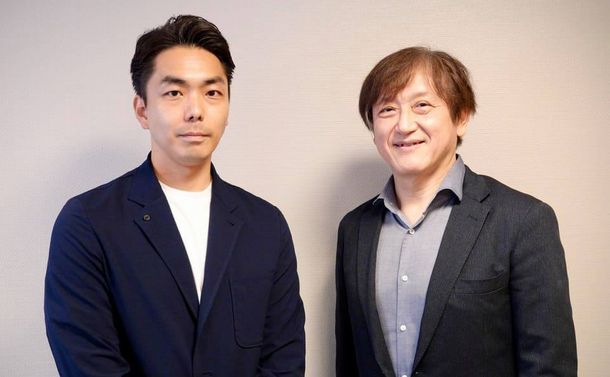 大野和士さん(右)と倉持麟太郎さん=2021年7月26日
大野和士さん(右)と倉持麟太郎さん=2021年7月26日コロナ禍の起点である2020年2月頃から約1年半が経つが、その間、新型コロナウイルス自体によってだけでなく、「コロナ対策」で様々なものが失われてきた。
だが、そうした喪失は、政府やメディアが繰りかえす「不要不急」という、定義が定かではない漠然たる言葉によってコーティング(隠蔽)され、“コロナ禍”という狂騒に飲み込まれた。我々は今一度立ち止まって「不要不急」という暴力的な言葉によって何が失われようとしているのか、我々が何を放棄しようとしているのか、厳しく問うべきではないか。
本稿では、コロナ禍における表現のあり方という「主題」をもとに、民主主義やコミュニケーションの自由とその根底にある「人間らしさ」について、変奏して考えてみたい。
この“変奏曲”の指揮をお願いしたのは、海外の数々のオーケストラや歌劇場の音楽監督を歴任し、現在東京都交響楽団(以下「都響」)やバルセロナ交響楽団の音楽監督を務めるマエストロ、大野和士氏だ。法律家と指揮者による対話は、「法の支配」と「文化芸術」をめぐり、交響した。
思い出してほしい。コロナウイルスについて、我々がほとんど何も知らなかった2020年春、2月には一斉休校が突如決定され、3月末の三連休は外出自粛要請、4月に戦後初めての緊急事態宣言が発出された。裁判所は通常事件の期日を一斉に取消し、映画館や美術館はもちろん、クラシックコンサートもすべて中止された。
そんななか、都響は同年7月、いち早く有観客でのコンサート開催を実現した。有観客実現に至るには、「自分の頭で考える」大野氏と都響の工夫があった。
都響は独自にコロナウイルスとオーケストラ演奏に関して、微粒子工学、感染症学や呼吸器科医等の専門家を集めた実証実験を行い、「東京都交響楽団演奏会再開への行程表と指針」を策定した。そこには、「お上」からの号令によらず、コロナに関する自前のスタンダードを創るという明確な哲学があった。
「こうであるべきだという結論ありきでは考えていなかったんです。事態や状態に応じてアクセプタブルにいこう、適応していこうという方針でした。この時期、ヨーロッパでもオーケストラ演奏の再開にむけて飛沫実験が行われていました。しかし、私は、直感的に全世界的に共通するようなデータがとれるわけがないと考えていました。各国で気候も違うし湿度も違う。ヨーロッパでのデータを鵜呑(うの)みにしないことがスタートでした。だからこそ自分たちで検証するしかないと考えたんです」
 対談する大野和士さん(左)=2021年7月26日
対談する大野和士さん(左)=2021年7月26日当時、ヨーロッパから、オーケストラ演奏とコロナウイルスについての情報も入り始めていたが、大野氏は、そのデータを「ばからしい」と言い切った。
「あまりにばからしい数字が来ました。2メートル離れることから始まり、それらのデータを元にするとヴァイオリン8本、コントラバス2本等々。これに基づいて演奏すると、モーツァルトの小規模なシンフォニーですら、後ろの方のホルンの音やリズムなんかよく聞こえないような状態です。演奏を成立させるのには実効的ではない数字だと考えました」
ウイルス対策をしつつ、オーケストラの核心を犠牲しない演奏を実現する。そうしたギリギリのバランスを模索する作業が不可欠なのだ。そして、これはオーケストラに限られない、生命・安全と自由との厳格なバランシングという、社会のあらゆる場面で問われるべき主題を内包している。
「演奏するときに、それぞれの奏者がどこまで寄り添い、お互いの音を聴き合えるのかというオーケストラの根本的なニーズがあります。お互いの音が聴こえる距離で、しかも衛生面も担保できる距離を模索しました。ヴァイオリンの並び方でも、少し角度をつけるとお互いが聴こえやすい、とかね。工夫すればいいんです。
お客さんに対価を求めるわけですから、それに相応しい演奏をできなければ意味がないんですよ」
コロナ禍の日本社会では、要請という名の無機質かつ暴力的な制約と、これに従った非現実的な商品やサービス提供がまかり通った。例えば、営業態様を無視した飲食店への“一律”規制、学校の教育現場での子どもたちへの非人道的な教育環境強制などだ。そして、これには権力側だけではなく、それを受けた市民社会や我々の「思考停止」が加担した側面が強い。
都響と大野氏の独自検証によるコンサート再開へのプロセスは、「0か100か」という思考停止へのカウンターケースとしても記憶されるべきであろう。
 大野和士さん=2021年7月26日
大野和士さん=2021年7月26日法律家として、少しお堅い憲法論をすれば、表現の自由は自己の考えを表明するという個人の自律の価値はもちろん、民主主義社会を構成するためにも不可欠なものとされる。しかし、コロナ禍で、我々はこの自明にも見えた自由と民主主義の関係を再定位することに迫られている。
音楽表現にとっても民主主義社会においても、生身の個人が顔を突き合わせて時間と空間を共有するという原始的な「身体性」が極めて重要である。この「身体性」をコロナ禍は奪った。3密回避、ソーシャルディスタンス、そしてリモートである。
マエストロはこのコロナ禍での身体性の欠如をどう受け止め、また、切り抜けたのか。
「去年4月に都響でもリモートで演奏をしました。そのためだけに楽団員に集まってもらって演奏をした。医者や看護師に聴いてほしい、加えて、おうちで困っている親子に聴いてほしい、という二本立てのコンセプトで行ったんです。双方がそれぞれ20万回再生され、これはこれでとてもよかったと思っています。このようにリモートは手段としては有用な面はあります。しかし、突き詰めていくと、やはり生じゃないとダメだ、というところに戻ってきたんです」
大野氏が「生じゃないとダメ」というそのロジックは、我々の民主主義社会が失おうとしているものへの視座を提供する。
「ただ、その後、緊急事態宣言が明けて、普段の10分の1程度である200人くらいのお客さんを入れて、12本のヴァイオリン等、小規模な編成でベートーベンの1番の交響曲を中心としたプログラムを演奏しました。入ってくるだけでものすごい拍手、思わず楽団員も立ったままお辞儀をしました。2000人の拍手をもってしても越えられない熱さを持った拍手でした。彼らはこの演奏会での“体験”で、音楽家としての使命をより感じてしまった。これを伝えるために、より自分を律しなければならないと生まれ変わったんです」
「演奏家は、それにふさわしい“息”をし、呼吸をして音を出す。楽器によっても息遣いが違うし、出そうとする音色によっても息遣いは違うわけです。つまり、鍛錬した肉体性というものをそこに持ち込まないと、音楽にならない。その総体としてのオーケストラなのであって、これはリモートでは伝わるべくもないことです。このことは、受け手であるその場にいたお客さんにも、身体性、肉体性を伴って伝わっていくわけです」
「再開したときの演奏会では、一人一人が、一音一音、どのように自分の楽器を鳴らすのか、いかなる音色を出すのかを今まで以上に大切に考えて演奏していたのです。流れ作業ではなく、一人一人が一つ一つの音に命与えていく過程・作業があったからこそ、返ってきた拍手が、胸にいたく刺さったのでしょう」
「この経験をした演奏家としない演奏家では、このあとの音楽家としての人生がまったく違ったものになるのだろうと思わせるには十分な経験だったのです」
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください