国際競争力が失われ、賃金が上がらない日本を救う鍵は「教育の無償化」にあり
2021年09月27日
日本も世界も課題だらけの今の世の中で、政治が果たすべきつとめは何なのか。現役の国会議員が、それぞれ関心のある分野について、課題と解決策を論じるシリーズ「国会議員、課題解決に挑む~国民民主党編」。今回は前原誠司・衆議院議員の論考です。
平成から令和への30年間は、日本にとって「凋落の30年」だったと前原氏は指摘します。日本の国際競争力は低下し、企業も勢いを失いました。なにより賃金が一向に上がりません。こうした厳しい状況から脱し、令和を繁栄の時代にするためにどうすればいいのか。政治家として30年のキャリアをもとに前原氏が挑もうとしていることは……。論考をお読みいただき、コメント欄にご意見をお寄せください。(論座編集部)
◇前原議員が論考の狙いを語っています。本稿をお読みいただく前にご覧ください。
私は平成3(1991)年に京都府議に初当選し、政治家として一歩を踏み出しました。平成5(1993)年には衆議院議員に当選、今に至ります。つまり、平成のほぼすべての期間を、政治の世界で生きてきたことになります。
平成の日本はバブルの中で始まりました。経済は好調で、国際的には「ジャパン・アズ・ナンバーワン」とも言われ、人も企業も、そして政治家も、ある種の自信をもって生き、活動していた気がします。
では、その後の平成の30年はどういう時代だったのか。改めて振り返ってみると、残念なことに、「凋落の30年」だった言わざるを得ません。
なぜ、そうなってしまったのか。どこで間違ってしまったのか。「国づくり」にかかわる政治家として、内心忸怩たる思いはぬぐえません。
ただ、令和になった今、自信を失ったままでいいはずはありません。凋落の理由を知り、取り組むべき課題を明らかにして、日本を立て直していく必要があります。「国会議員、課題解決に挑む」シリーズの一貫として、本稿では平成の日本の実態を点検したうえで、この国が抱える課題を明らかにし、今後に向けた提言をしてみたいと思います。
 TexBr/shutterstock.com
TexBr/shutterstock.com今、日本は世界でどんな国だと位置づけられているのでしょうか。
国の経済規模や豊かさを示す指標としてお馴染みのGDP(国内総生産)が、アメリカ、中国についで第3位というのは、多くの人が知っているでしょう。2位の座を中国に奪われたとはいえ、国力は依然、世界のトップクラスにいると感じているかもしれません。しかし、現実はそれほど甘いものではありません。
スイス・ローザンヌに本部をおく国際経営開発研究所(IMD)は毎年、63の国・地域について、①経済状況、②政府効率性、③ビジネス効率性、④インフラ――の四つの指標を踏まえ、国際競争力を判断しています。
それによると、日本は平成の初め、4年連続で総合トップ(1989~1992年)で、その後も96年まで上位をキープしていますが、97年に17位まで下落した後は「ベスト10」に戻ることはなく、今年はなんと31位。昨年(2020年)の34位からはやや上がったものの、全体の真ん中あたりで低迷しています。
個別の指標をみて目につくのは、ビジネス効率性が48位と低いこと。デジタル化の遅れが影響しているのでしょう。政府効率性も41位と足を引っ張っています。ビジネスや政府の効率の悪さというのは、私たちの皮膚感覚にも合致するのではないでしょうか。
平成の30年間で企業も往時の勢いを失っています。
企業の規模を示す時価総額の世界ランキングを見ると、平成元年(1989年)は日本企業がベスト10に7社、ベスト20に14社、ベスト50だと32社も入っていました。ところが、現在(2021年)はベスト10にもベスト20にも日本企業は見当たらず、ベスト50まで広げてようやくトヨタ自動車が入るだけです。
平成元年にトップだったNTTは、分割されたのでランクが下がるのは仕方ないとしても、10位以内に名を連ねていた銀行5社が、それぞれ合併で規模を大きくしているはずなのに、今や見る影もないのはどうしたことでしょうか。
日本が得意とする「モノづくり」に目を転じると、平成元年は上位だった新日鉄(15位)、日立製作所(17位)、松下電器(18位)、東芝(20位)が、今や50位にも入っていないのは寂しい限りです。かつて日本の“お家芸”とされた半導体もその面影はなく、台湾積体電路製造(TSMC)やサムスン電子にお株を奪われています。ちなみに現在、TSMCは11位、サムスン電子は12位にランキングされています。
企業にも人間と同じように「成長サイクル」があり、創業、成長、成熟、衰退といった経路をたどる場合もあるでしょう。その昔、「企業寿命30年説」が話題を呼んだこともありましたが、それにしても平成の30年間の日本企業の凋落ぶりは衝撃的といえます。
 sdecoret/shutterstock.com
sdecoret/shutterstock.com既存の企業が勢いを失うなか、それに代わる新しい企業はどれぐらい生まれているのでしょうか。今後、創業から成長へと向かう企業が一定程度あれば、いわゆる“代替わり”ということで、先行きに明るさもみえてきます。
そこで、設立から10年未満、未上場で評価額が10億ドル、将来の成長性が高いと見込まれるスタートアップ企業、いわゆる「ユニコーン企業」が日本にどれぐらいあるかをみてみました。
現在(2021年6月現在)、世界には729社のユニコーン企業がありますが、国別だとアメリカが51%を占めてトップ、中国が20%で2位。以下、インド(34社)、イギリス(29社)と続きます。日本はといえば、わずか6社で、韓国(10社)にも及びません。
このように企業の時価総額でもユニコーン企業の数でも、世界のトップ集団から滑り落ちているのが、日本の企業の偽らざる現状なのです。
それでは、私たちの生活はどうでしょうか。バブルの頃とまではいかないまでも、豊かな暮らしは送れているのか。周囲を眺めるだけでも、そうでないのは明らかですが、データもまた、日本がすでに「先進国における低賃金国」になっていることを示しています。
OECD(経済協力開発機構)の調べによると、平成3(1991)年から令和元(2019)年までの間、先進各国の名目平均年間賃金は軒並み増加しています。伸び率が最も高いスウェーデンは2.6倍、イギリス、アメリカは2.4倍、伸びが緩やかなフランスでも1.9倍。ところが、日本はずっと横ばいです。
物価のなどを考慮した生活実感に近い購買力平価ドル換算・実質平均年間賃金の推移をみても、平成2(1990)年から令和元(2019)年にかけて他国が軒並み右肩上がりなのに対し、日本はほぼ横ばいです。金額的にも3万8000ドル超にとどまり、約6万6000ドルのスイス、アメリカはいうに及ばず、ドイツ(約5万4000ドル)、イギリス(約4万7000ドル)をも大きく下回ります。
名目上も実質的にも、日本はもはや先進国中で最低レベルの低賃金国になっているというのが実情なのです。
ところで、安倍晋三首相のカムバックにあわせて、2012年末に華々しく登場した「アベノミクス」は、企業や賃金にどのような影響を与えたのでしょうか。公正を期するため、新型コロナウイルス感染拡大による影響を受ける前の2019年までを対象に見ていきます。
企業利益はアベノミクス始動前から1.7倍に増えています。これに連動する形で内部留保も着実に伸び、1.6倍を越える規模になっています。一方、設備投資は1.3倍程度で若干の増加。人件費はほぼ横ばい。名目賃金は少しあがっていますが、実質賃金はむしろマイナスです。
要するに、アベノミクスは企業を儲けさせたが、利益のほとんどは内部留保に回り、人件費や設備投資にはあまり回っていない。会社の経営は安定し、株主には恩恵があったが、企業が新たな挑戦に乗りだしたわけでも、一般の国民が幸福になったわけではない実態が透けて見えます。
 beeboys/shutterstock.com
beeboys/shutterstock.comさらに、日本の潜在成長率の推移をみると、日本が陥っている深刻な状況が、いっそう鮮明になります。
潜在成長率とは中長期的に持続可能な経済成長率。換言すれば、供給能力をどれだけ増やせるかを示す指標ですが、平成の初めは高かったのに、この30年間、多少の上下はあるものの、基本的には下落傾向で、今やゼロに近づいています。なかでも気がかりなのは全要素生産性(TFP)の低迷。すなわち、イノベーションが起きていない点です。
こうした窮状を招いた一つの要因は、教育や研究開発への投資を日本が怠ってきたことだと思います。
実際、教育への公的支出の対GDP比をみると、比較可能なOECD38カ国の中で日本は下から2番目で、平均よりもかなり低い。科学技術関係予算の推移をみても、アメリカや中国がその額を増やして競っているのに対し、日本は横ばいです。
こういうと財務省は、「教育支出の対GDP比が低いのは確かだが、日本は子どもの数も少ないので、1人あたりだとOECD平均並みである」と反論します。けれども、この主張には疑問があります。
日本と同様に少子化が進んでいる中国(2018年までの20年間の平均出生率1.63。日本は1.37)ですが、人口全体に占める在学者数の割合がOECD平均より約2割低いにもかかわらず(日本は3割強)、公的教育支出の対GDP比ではOECD平均と同じです。子どもの割合が低いことは、教育への支出が低いことの理由にはなりません。
今年度(2021年)予算と30年前の1990年度の予算の比較からも、教育や研究開発への投資の弱さが明確です。
歳出は30年前が66兆2000億円、今年が106兆6000億円で40兆円ほど増えていますが、内訳をみると、大きく増えているのは社会保障費と国の借金返済である国債費。その他は防衛費が1兆円超増えているほかは、伸びが抑えられ、文教・科学技術費は5兆1000億円から5兆4000億円と3000億円しか増えていないのです。
高齢化への対応と借金の返済に追われるばかりで、日本の将来をつくり出す教育や研究開発への投資が十分ではない。それが凋落の30年につながっているという図式が浮かびます。
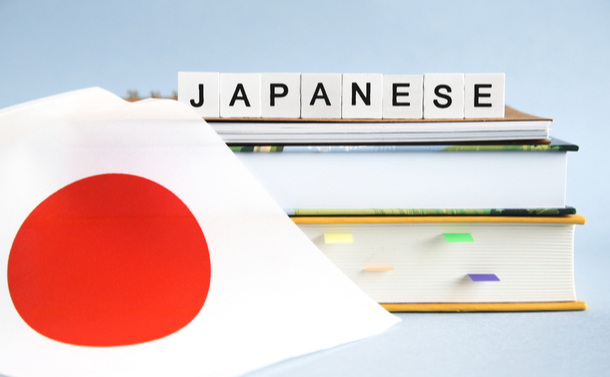 Evgeniia Primavera/shutterstock.com
Evgeniia Primavera/shutterstock.comこうした悪しき図式を克服するためにはどうすればいいのか。私は「教育の無償化」が鍵になると考えています。
具体的には、文教・科学技術費を現在の5兆4000億円の倍の10兆円に増やし、学校教育はもとより、リカレント教育も含む「全世代型教育」をすべて無償化する。まさしく、「国づくり」の基となる「人づくり」への投資です。財源は、当面は「教育国債」でまかないます。
教育の無償化は効果は大きく三つあります。「一石三鳥」といっていいでしょう。
第一に、国際競争力の回復です。無償化で教育の厚みと質を増し、イノベーションが起きる条件を整える。30年間で損なわれた競争力を取り戻すには30年間がかかるかもしれませんが、これはやらないといけません。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください