疑似政権交代、連立政権、リーダーの選び方……総裁選・衆院選から浮かぶ数々の論点
2021年10月18日
衆議院が解散され、10月31日の投開票に向けて衆院選が事実上始まりました。自民党総裁選で総裁を菅義偉氏から岸田文雄氏にかえ、支持率低下が止まらなかった菅政権から岸田政権へとバトンタッチする、いわゆる「擬似政権交代」によって衆院選を優位に進めようとする自民党の底意は、野党が求めた国会での予算委員会開催に応じず、短兵急な選挙期日を選んだ点からも明らかです。
だからこそわれわれ有権者は、与党、野党の実態や戦略、思惑を、限られた時間とはいえしっかり見極め、一票を投じる必要があります。今のような時代の変革期においては、政権を選ぶ選挙である衆院選の結果が、時の政権や政党の浮沈にとどまらず、次の時代の政治体制そのものを規定することがあるので、なおさらです。
政治について、世代も性別も様々な研究者や記者で議論する「政治衆論2021」。第2回のテーマは目前に迫る衆院選です。4年ぶりにおこなわれる「政権選択選挙」では何が問われようとしているのか。与野党はいかなる態勢で選挙に臨もうとしているのか。この9年間なかった与野党による政権交代が起きる可能性はあるのか。そもそも二大政党制による政権交代は日本の政治になじむのか――。目の前の“政局”を超え、時間軸を長くとった観点から、様々に意見を交わしました。(司会・構成 論座編集部・吉田貴文)
◇今回の議論に参加していただいた方々
御厨貴(みくりや・たかし) 東京大学名誉教授
1951年生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大教授、政策研究大学院大学教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、放送大学教授、青山学院大特任教授を経て現職。政治史学。著書に『政策の統合と権力』『馬場恒吾の面目』『権力の館を歩く』など。
松本朋子(まつもと・ともこ) 東京理科大講師
1985年生まれ。東京大学法学部卒業。2016年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。名古屋大学特任講師、ニューヨーク大学客員研究教授を経て18年から現職。専攻は実証政治学・実験政治学・政治行動論・政治史。研究成果を海外学術雑誌に掲載。
曽我豪(そが・たけし) 朝日新聞編集委員(政治担当)
1962年生まれ。東京大学法学部卒業。朝日新聞社に入り、熊本支局、西部本社社会部を経て89年に政治部。首相官邸、自民党、野党、文部省など担当。週刊朝日編集部、月刊誌「論座」副編集長、政治部長、東大客員教授などを歴任。2014年から現職。
吉川真布(よしかわ・まほ) 朝日新聞政治部記者
1991年生まれ。2015年に朝日新聞社に入り、神戸、岐阜総局を経て2019年に政治部。安倍晋三首相番を担当した後、2020年から立憲民主党など野党を担当。立憲や国民民主党の合流などを取材した。現在は主に立憲の枝野幸男代表を担当している。
野平悠一(のびら・ゆういち) 朝日新聞政治部記者
1993年生まれ。2015年に朝日新聞社に入り、山口、神戸両総局を経て政治部。安倍晋三首相番や自民党の平成研究会(竹下派)、参議院自民党などを担当。菅義偉政権の発足時から、二階俊博前幹事長が率いる志師会(二階派)を主に取材している。
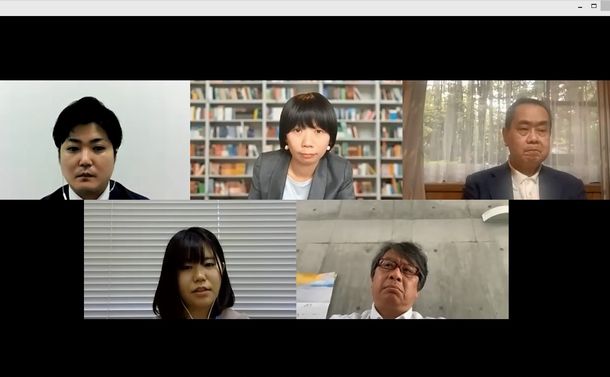 議論する5人。右上から反時計回りに、御厨貴さん、松本朋子さん、野平悠一さん、吉川真布さん、曽我豪さん(Zoomの画面から)
議論する5人。右上から反時計回りに、御厨貴さん、松本朋子さん、野平悠一さん、吉川真布さん、曽我豪さん(Zoomの画面から)――「政治衆論2021」の第2回です。今回は19日公示、31日投開票の衆院選を前に、「政権選択選挙」とされる衆院選で今回は何が問われるのか、政権交代のあり方にまで話を広げて議論したいと思います。まず松本朋子さんから「問題提起」をしていただき、前半ではこれに基づいて議論をしたいと思います。
◇松本朋子さんの問題提起◇
私からは自民党総裁選と衆院選に絡めて、二つの問題提起をさせていただきます。
まず、自民党総裁選から見えた問題です。確かに今回、総裁選のキャンペーンは大いに盛り上がりました。候補者の政策論争が連日、メディアで配信され、これほどまでに国民の参加を要求する総裁選はあっただろうかという印象をも覚えました。
しかし総裁選を終え、多くの国民は小さな虚無感を感じているのではないでしょうか。それは岸田総裁への支持不支持とは関係ありません。どんなに盛り上がっても、これは私たちの選挙ではない。最終結果を決めるのは派閥なのだということを、改めて実感したからです。
総裁を派閥が決めるのは当たり前という議論もあると思います。確かに55年体制のもと、一貫して政権を維持した自民党は、党内の派閥間の切磋琢磨を軸に政治を展開してきたわけですが、注意すべきは、往時と今とでは、派閥のあり方が異なっているということです。
1994年の選挙制度改革以前、衆議院が中選挙区だった時代、選挙区では複数の派閥の自民党議員が立候補できたので、有権者が派閥を選んで一票を投じることもできました。有権者から支持を得た派閥は勢力を伸長し、得なかった派閥は後退するという制度上の仕組みが担保され、派閥間の“疑似政権交代”であっても、選挙を通じて有権者の意思が反映されたと見ることもできました。
ところが、選挙区に自民党候補が一人しか立たない現行の小選挙区では、有権者は派閥を選べません。小選挙区のもとでは、いずれ派閥は衰退するとも言われましたが、派閥の残存が顕在化するなか、国民の声を反映する制度的基盤をもたない派閥に、有権者はどうかかわればいいのか。これは総裁選が開かれたからこそ見えた新たな課題とも考えられます。
二つ目の問題提起は政権交代についてです。小選挙区比例代表制においては、結局のところ、私たちは政党を選ぶしかないわけですが、では、選挙制度改革から幾度も議論されてきた政権交代可能な二大政党制はいつ実現するのか。そもそも、二大政党制という議論の立て方が妥当なのでしょうか。
平成時代、二大政党制への期待に応えてできた民主党は瓦解しました。民主党政権以降10年弱の度重なる野党の離合集散は、選挙目的に加え、政策の不一致も原因だったということは、専門家の研究からも得られている知見です。野党の分裂が政策的にも不可避であるということを前提に、政権交代のあり方をいま一度問い直す必要があると思います。
実は1999年以降、自民党は公明党と連立政権を組んでいます。自民党の単独政権ではありません。とすれば、野党の側も連立によって政権交代を実現することも可能なのかもしれません。その際に何が必要なのか。どんな政策を争点にすれば自民党と競えるのかという点も考えたいと思います。
――問題提起をありがとうございます。自民党の派閥は依然、力を持っている。しかし、現在の選挙制度では有権者は派閥を選ぶことはできない。その点について御厨さん、いかがですか。
御厨 今回の総裁選から想起するのは、小泉純一郎さんが当選した2001年総裁選です。党員が雪崩をうって投票した結果、小泉さんが圧勝、「私は国民に選ばれた」と言いました。しかも、当選直後に「首相公選制を考える懇談会」を立ち上げ、官邸での議論に自ら参加した。そうすることで、自分が国民から選ばれた首相であるというイメージをつくりました。
これは「ウソ」ですね。彼はあくまで党員に選ばれたわけで、国民に選ばれたわけじゃない。小泉さんにうまくやられました。それが小泉内閣の高支持率につながった。
今回の自民党総裁選も似ています。国民に開かれた議論をして選ばれたというしつらえにし、総裁が国民から選ばれたように印象づけようとした。実際には党員が選んでいるわけでそれ自体が「ウソ」ですが、今回は最終的に派閥の論理で決めたという点でも「ウソ」を重ねています。
松本さんの指摘のように、小選挙区制のもとでは、有権者が仮に自民党のこの派閥がいいと思っても、必ずしもその派閥の議員に投票できるわけではない。メディアは、「首相(総裁)公選」に擬した総裁選のそうした矛盾を指摘するべきでした。この国のリーダーの選び方として根の深い問題だと思います。
 御厨貴さん
御厨貴さん――自民党担当として総裁選を間近で見た野平さんはどう見ますか。
野平 現場で感じたのは、派閥の力が弱まっているということです。無派閥の高市早苗さんがあれだけの支持を集めたこと。これまで派閥の切り崩しにあって総裁選に出られなかった野田聖子さんが今回は出られたことなど、そう感じる理由は幾つかありますが、実際、今回、派閥が力を発揮したのは岸田派だけだったと思います。私が担当していた二階派も推す候補を一本化せず、自主投票になった。従来の総裁選とは形が変わったと感じています。
総裁選を“首相公選”に擬しているという点は、国民にそういう感じを抱かせたのは確かだと思います。ある議員が「4人の候補が訴える政策で、国民世論の8割をカバーできているのではないか」と高揚して話していました。幅はかなり広い。国民への訴求力の大きさを議員たちも実感していたようです。
ところが、岸田文雄政権が発足し、“ご祝儀”が期待された内閣支持率は、それほど上がっていません。総裁選後、有権者に虚無感が広がったという指摘があたっている気がします。
 野平悠一さん
野平悠一さん――野党は今回の総裁選をどう見ていましたか。
吉川 立憲民主党の枝野幸男代表は、総裁選は「準決勝」で衆院選が「決勝戦」と言ってきました。ただ、「準決勝」が終わった今、野党内に「決勝戦で勝負するぞ」という意気込みがあまり感じられないのも事実です。党内では、今回の衆院選ではあくまで自民党との議席差を縮めて政権を狙う野党としての存在感を印象づけ、来夏の参院選でも議席を増やし、次の衆院選で政権交代を狙うという戦略が現実的だとの声も多く聞かれます。
枝野代表は政権交代について、「アメリカのバイデンさんのような勝ち方をするんだ」とよく言います。バイデンが大統領選で勝ったのは、本人に人気があったからではなく、トランプ前大統領が不人気だったからだ。消去法でバイデンが勝利をした。日本でもそういう風に政権交代をするんだと。
皮肉なことに、枝野さんの言う消去法的な政権交代が、自民党内の“疑似政権交代”という形で起きたと見ています。岸田さんに人気があって総裁・総理になったのではなく、菅義偉さんよりはマシな人を選んだ。枝野代表が言う「バイデンさん」がすでに誕生してしまったのではなないでしょうか。
 吉川真布さん
吉川真布さん曽我 先日、総裁選のキーマンに会いましたが、彼も「今回は疑似政権交代だ」と言いました。その説明がおもしろい。私はてっきり、大宏池会と清和会の間での“政権交代”という話になると思っていたのですが、そうではなかった。彼はこう言うんです。
自民党は、経済政策ひとつとっても、“岸田流”と“河野流”のふたつがある。今回、岸田が総裁になったが、河野太郎も後詰めで残った。岸田がダメなら、河野がいる。二人とも大宏池会だ。要は、派閥の次元を超えてきている。そもそも今回、派閥の領袖で総裁選に出たのは岸田だけ。派閥の領袖であることが、次の総理を狙う条件でなくなっている。総理総裁への道が多様化している――。
派閥のイメージが変わっていまるんです。今回の総裁選でかつての派閥に近いのは岸田派だけ。古い派閥が残りつつ、同時に新しい派閥への変化も見えてきたというのが、今回の総裁選ではないかと思っています。
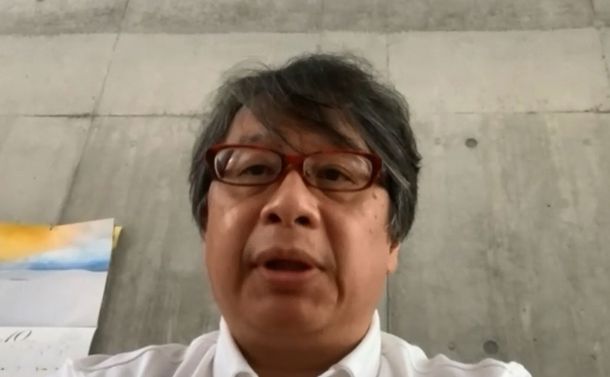 曽我豪さん
曽我豪さん――ここまでの議論について、松本さんはいかがですか。
松本 派閥の中身が少しずつ変わっているという話は興味深いです。御厨先生の“首相公選制”という指摘も腑に落ちました。
有権者が国のリーダー選びに関わろうと思えば、たとえば自民党員になるという手はありますが、党員になったところで、党員票は現状では限定的な役割しか果たせていないのです。これは自民党に限ったことではなく、立憲民主党などでも同様に抱える問題です。
しかし、他国に目を向ければ、これは当たり前のことではありません。英国で保守党が党首選の際にどうするかというと、何回か議員たちの間で選挙をしたうえで、最後は党員投票で決めます。米大統領選も党員投票で選ばれる。
衆議院選挙が小選挙区比例代表並列制である以上、リーダーの選び方は与野党ともに見直さなければいけない部分だと痛感しています。
 松本朋子さん
松本朋子さん――松本さんの二番目の問題提起である二大政党制の現状についてはどうでしょうか。平成の政治改革が目指した政権交代は、2012年以降、実現していませんが。
吉川 1年半ぐらい野党を担当していますが、政権交代のリアリティーをあまり感じません。野党第1党の立憲民主党の幹部も所属議員も政権交代への気迫が薄い。支持率低迷もありますが、2009年政権交代のトラウマから抜け出せていないのも大きいと思います。
民主党政権で、衆参のねじれのためマニフェストを実現できなかった経験から、実現が難しそうな政策には躊躇する。国民がオッと思う政策が打ち出せず、支持率も上がらず、政権交代へのリアリティ-をもてずに、野党第一党を維持することに重点を置くという「負のスパイラル」から抜け出せていません。
――今回、野党は衆院選で初めて、野党第1党と共産党などが共闘する「野党共闘」を全国の3分の2以上の小選挙区で実現しました。連携のかたちは出来つつあります。
吉川 共産党と立憲民主党による選挙協力がほぼ完成し、全国289の選挙区のうち、立憲、共産、国民民主、社民、れいわの5党の候補者が一本化される選挙区が200以上になりました。ちょっとした風向きの変化でオセロゲームのように一気に勝敗が変わるのが小選挙区制度です。一本化で将来的に政権交代がしやすい状況は作れたと思います。
ただ、野党が政策面で一致して自民党との間に有効な争点を設定できるかというと、現状では難しいと思います。今回、野党各党は衆院選の公約として、首相が否定的な消費減税を掲げています。一見、支持を集めそうですが、財源面などでの批判は強いうえ、消費減税の時期や下げ幅でも各党に違いがあります。「選択的夫婦別姓」や「同性婚」のような政策では野党の方向性が一致していますが、これが幅広い有権者にとって争点になるかは疑問です。
――数年前までは自民党の若手議員の間に「いずれ政権交代がある」という緊張感がありましたが、今の自民党はどうですか。
野平 菅政権の末期に内閣支持率が落ち込みましたが、野党の支持率が伸びていないことを根拠に、政権交代は起きないと自民党の議員たちは繰り返していました。ただ、私は7月の東京都議選で明らかになったように、本来自民党に入れていた層が自民党に投票しなくなったという状況が出てきていると思っています。そういう人たちの受け皿となる政党が出れば、票を集める可能性はあると思います。
――都議選の直後、自民党の中堅・若手の議員から衆院選が不安だという声を聞きました。そうした不安は、総裁が菅さんから岸田さんにかわって解消されるのでしょうか。
野平 岸田政権の支持率があまり高くないことに戸惑いを感じている議員は多いと思います。新しい総理・総裁を誕生させて高い支持率で衆院選に突入するという見立てがあったと思いますが、期待していたほどではなかった。。自民党は解散直前の週末に情勢調査を実施し、各派閥を通じて議員本人に結果が伝えられましたが、「厳しい」と顔をしかめる議員も少なくはありませんでした。
 上空から見た国会議事堂=2021年9月10日、東京都千代田区、朝日新聞社ヘリから
上空から見た国会議事堂=2021年9月10日、東京都千代田区、朝日新聞社ヘリから曽我 20代の若手記者の2人の話を聞きながら、政治記者になった28歳の時にあった、1989(平成元)年7月の参院選を思い出しました。この参院選では、野党第一党の社会党(当時)が大勝利をおさめ、土井たか子社会党委員長が「山が動いた」という言葉を残しています。
この結果についてメディアは、世論が自民党に「お灸を据えた」と言いましたが、55年体制下ではしばしば、こうした「お灸を据える」選挙がありました。自民党政権を代えないが、ダメな時には「お灸をすえて」反省を促す。疑似政権交代と表裏の関係にあったのは「お灸を据える」選挙でした。
平成の政治改革が目指したのは、「お灸を据える」を超える「政権交代をさせる」選挙でした。そのために小選挙区制を導入し、世論もそれに応じて、いったんは政権交代が実現した。ところが、今や世論はすっかり「お灸を据える」に戻っているような気がします。もしそうだとすれば、二大政党制とミスマッチだと思うのですが……。
御厨 立憲民主党が政権交代まで考えていないとすれば、野党があてにするのはまさに自民党に「お灸を据える」世論でしょう。与党の不祥事を叩いて一定の支持を得て、多数を占めるまではいかなくても、現状は維持する。もしそういう戦略になっているとすれば、かつての自社の二大政党制の時代に完全に戻ってしまうと思います。
 議論する5人。右上から反時計回りに、御厨貴さん、松本朋子さん、野平悠一さん、吉川真布さん、曽我豪さん(Zoomの画面から)
議論する5人。右上から反時計回りに、御厨貴さん、松本朋子さん、野平悠一さん、吉川真布さん、曽我豪さん(Zoomの画面から)――自社の二大政党制は、社会党が政権をとらないという意味で、「1か2分の1」政党制とも言われます。日本には本格的な二大政党制はなじまないのでしょうか。
 御厨貴さん
御厨貴さん御厨 ちょっと長くなりますが、日本の政党史を振り返りつつ、二大政党制について考えてみたいと思います。
政党の揺籃期だった明治時代、藩閥派の山県有朋は3党鼎立を主張しました。これに反対したのが後に“庶民宰相”となる原敬です。鼎立だと、結果的に藩閥政党にしてやられることを懸念したからです。原は二大政党制をめざして、政友会の立ち上げに参加する。
ところが、政友会に伍する野党がなかなか育たない。10年以上が過ぎ、大正になって桂太郎が政友会に対抗するべく立憲同志会をつくり、それが民政党になっていく。1925年から32年にかけての昭和初期の政党政治は、政友会と民政党という保守の二大政党が政権を担い合った時代でした。
戦時にかけて、保守ではない無産政党が生まれ、戦後、社会党になる。保守のほうは戦後、自由党に「第二の保守党」として改進党が対抗する。これが崩れたのが1955年です。社会党の右と左が合同し、政権をとるかもしれないという恐れから、絶対にまとまらなかった保守2党が合同して自由民主党となり、社会党と対峙した。日本の二大政党制は、この時点で保守の二大政党から保革の二大政党になりました。
ただ、保守と革新との間には、決定的な力の差があった。社会党は保革二大政党を高唱し、いずれは政権交代すると言うが実態が伴わない。危機をもったのはむしろ保守のほうで、池田勇人首相が高度経済を成し遂げ、自民支持層を固めていく。逆に社会党に投票する人は少なくなり、政権交代は遠ざかり、自民党に不祥事があった際、世論が「お灸を据える」ための存在になった。
こうした55年体制をチャラにして、平成の二大政党制をつくろうと考えたのが小沢一郎です。小沢の発想は、所属する竹下派が膨れあがって派閥としてもたないから、二つに分けてそれぞれを政党にしたほうがいいという発想でした。彼は「竹下A党と竹下B党で政権交代するほうが、利益配分もしやすく、国民は幸せになれる」ってはっきり言っていました。
竹下派内の権力闘争のあおりで自民党が割れ、飛び出した保守勢力を小沢が率いて新生党、新進党などをつくっては壊し、最終的に民主党の代表になって、2009年の政権交代までいくわけです。保守の二大政党制を目指し、政権交代を実現した。ところが、政権から下野した民主党は瓦解。離合集散を繰りかえすなかで、保守二大政党制から再び遠ざかっている。私が「かつての自社の二大政党制の時代に戻ってしまった」と言ったのは、そういうわけです。
 松本朋子さん
松本朋子さん
松本 自社の二大政党制は政権交代可能な二大政党制でなかったがゆえに、心の中で は自⺠党を支持している人が、「お灸を据える」目的で社会党に投票できたの でしょう。ただ、「お灸を据える」ことは「業績投票」という観点からは重要だとも思います。
インターナショナル・ソーシャル・サーベイ・プログラム(ISSP)の2016年国際世論調査によると、日本では「国会議員は選挙中の公約を守ろうと努力している」と考える人の割合が9.1%しかいない。これをただすには「お灸を据える」しかないのも事実です。政権交代を前提としなければ、政権交代は嫌だと思っている有権者が、どのみち政権交代は起きないのだから、与党以外に入れるという選択肢が再び浮上するのかもしれません。
――ここまでの議論を踏まえ、後半では目前の衆院選についてさらに深掘りをしたいと思います。まずは議論のための問題提起を御厨さんにお願いします。
◇御厨さんの問題提起◇
数ある衆院選の中でも、今回ほど燃えない選挙は珍しいと思います。岸田新政権が発足した10月4日に衆院選の日程が発表になり、10日後に解散、19日公示で31日投開票という短期決戦なのに、すでに中だるみの空気が漂っている。理由は、任期満了に伴うもので、事実上解散をしていないからだと思います。
解散は首相の専権事項で時期についてはギリギリまで分からないものです。権力行使の最たるものなので、踏み切る時にはそれなりに「大義」を考え、「演出」もこらす。一種の「劇場」がつくられるので、クビを切られた議員たちも、なんとしても勝って帰ってくるぞという高ぶった気持ちになるものです。熱量の乏しさが選挙にどんな影響を与えるのだろうかというのが、第一の問題提起です。
第二の問題提起は、この間に私が感じている自民党の変質です。
総裁選のトピックのひとつは、安倍晋三・前首相が高市早苗候補を支援したことでした。前回の政治衆論でも触れたように、安倍さんは自民党を支える保守層をつなぎとめるため今回、高市候補を担ぎ出しました。結果的に高市さんの存在感は増し、自民党の要職である政調会長になりました。
その結果、今回の衆院選の自民党の公約には、高市さんが総裁選で示した保守のイデオロギーに基づく主張や政策が多く並び、総裁になった岸田さんが掲げていた政策がなくなったり、後退したりしています。おそらく安倍さんも、高市さんがここまで伸びるとは想像しなかったと思います。
保守のイデオロギーが少数派だから、自分が引っ張らないといけないと思っていた安倍さんですが、8年近くも自身が政権を担っている間に、自民党員の中にも保守のイデオロギーが想像以上に広がっていた。憲法改正もアリ、経済安保も進めるべき、中国との関係も強硬路線でいいという風に、昔なら党内で対立した問題が、すんなり受け入れられるようになっています。
自民党全体がいわゆる「安倍シンドローム」に染まっている気がする。これって、安倍さんとしても困るのではないでしょうか。少数派の保守を代表しているからこそ、にらみも効くわけで、ここまで保守のイデオロギーが表面にでてくると、安倍さんでもコントロールできなくなる恐れがある。ましてや、岸田さんが掲げる宏池会的なリベラルな政策の実現、「岸田色」を出すことが難しくなるのではないか。国会議員が公約を守らないという議論もありましたが、守りたくても守れなくなるのではないかと思います。
こうした自民党の変質を、野党がどこまで理解しているのか。見ている限り、自民党の底流で起きていることをつかみきれず、攻めどころが絞れていない。政治を有権者に近づけ、選挙に足を運ばせるためにも、明確な争点探しが必要。もっと言えば、争点というあえて作るぐらいのことをしないとダメだと思います。
――総選挙は与党にとって一番いいタイミングに行うものですが、今回は必ずしもそうではない。選挙の空気感や「安倍」的なものの浸透というのは、自民党を取材していてどう感じますか。
野平 衆院選を菅さんのままで迎えていれば、菅政権への評価という有権者が判断しやすい材料があったと思いますが、岸田政権に代わり、岸田さんが総裁選で訴えたこと、代表質問や記者会見での岸田さんの言葉を、有権者がどう判断するのかという形になり、実態の見えにくい選挙になっているとは思います。メディアが自民党の主張を明確にし、野党の主張と比較して対立軸を示すことが、いつも以上に必要だと感じています。
安倍シンドロームは興味深い指摘です。実は総裁選の際、安倍さんからの電話で高市さんを応援した議員はたくさんいたのですが、地元で「高市さんを応援しろ」という声が大きいと言う議員も結構いました。そういう党員の空気が国会議員を動かたのも確かです。自民党が変わりつつあると、僕自身も感じています。
 野平悠一さん
野平悠一さん――熱のない選挙に野党は影響を受けますか。
吉川 争点の設定が非常に難しくなっています。枝野代表は、「岸田首相に代わっても安倍・菅政治から自民党は変われない、変わらない」と街頭演説やテレビで言っていますが、菅さんよりマシな岸田さんに変わったという空気が国民の間にあり、どこまで響くのか……
自らの立ち位置や政策について、枝野代表はこれまで「30年前なら自民党宏池会ですよ」と言ってきました。今回、宏池会の岸田首相が誕生し、自民党との違いを見せるのが難しくなった。岸田首相の「成長と分配の好循環」と枝野代表の「分配なくして成長なし」の違いをどう見せるのか、悩ましいところです。
安倍シンドロームについて言えば、枝野代表が言う「変えなくてはいけない安倍・菅政治」とは、森友・加計・桜を見る会の問題、公文書の隠蔽改ざん、アベノミクス、あるいは後手に回ったコロナ対策で、イデオロギー的なものへの言及はあまりありません。
――衆院選では具体的にどれだけの議席を狙っているのでしょうか。
野平 自民党幹部が公に言っているのは自公で過半数ですが、低めに設定された数字だと思います。現有議席からの減り幅はできるだけ少なく、現状に近いかたちでというのが本音だろうと思います。
吉川 枝野代表は公には全員当選といっていますが、党内的には「現有議席の110は最低でも維持、プラス10~30議席ぐらい増やしたい」ではないでしょうか。菅首相が退陣する前には150議席は固いと見ていましたが、そこまでは難しいという雰囲気です。
立憲民主党には、今回の衆院選で政権交代できなくても、来夏の参院選である程度議席を増やし、次の衆院選で政権交代を狙うという声があります。今回は「お灸を据える」票をとって自民党との議席差を縮め、「批判勢力としての野党を大きくさせてください」というアピールをして参院選につなげ、自民党の議会運営を苦しめるような議席をとって、その先の衆院選で政権交代を果たすと。
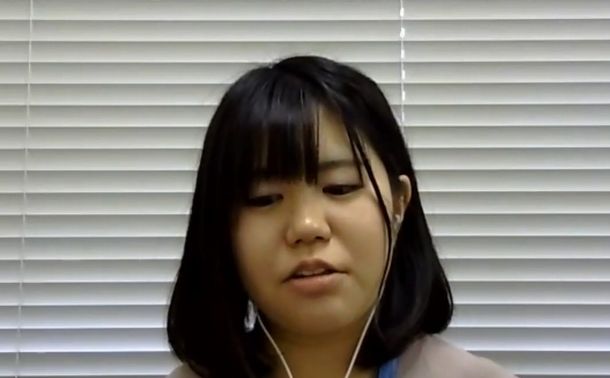 吉川真布さん
吉川真布さん――熱のない衆院選ということですが、曽我さんはどう見ますか。
曽我 選挙では、メディアが気付かないうちに、結果的に何かが選び取られることがあります。何度も言及されている55年体制がいつ選び取られたかというと、私は1960年11月の池田勇人政権での総選挙だと思っています。安保紛争で岸信介政権が倒れ、後継の池田政権が発足して4カ月後の選挙で、政権支持率は30%台しかありませんでした。
朝日新聞も含め各メディアが社会党の躍進を予想したのですが、自民党が圧勝して300議席、社会党が146議席にとどまった。社会党はそれ以降、得票率をずっと下げていきます。まさにこのとき、自社の「1か2分の1」体制、55年体制が有権者によって選び取られたと思うんです。当時はメディアも、政党もそれに気付いてはいません。
立憲民主党が、今回はそこそこでいい、来夏の参院選、そして次の衆院選で勝負するという理屈も分からないではないですが、それは、一気に政権交代までいかずにまずは橋頭堡を築くという1960年総選挙の社会党と似た発想です。私は、今回の衆院選が結果的に次の体制を選び取ってしまうのではないかという予感がしてなりません。
今回、政権交代までいかないと、安倍シンドロームの自民党の中で長期間、疑似政権交代を繰りかえす体制、55年体制的なものが、選び取られてしまうんじゃないかという気がするんです。
まだ「仮説」にすぎないのですが、メディアは意識的に、今回の衆院選ではこうしたことが選び取られる可能性があるということを、書いていかなければならないとは思っています。
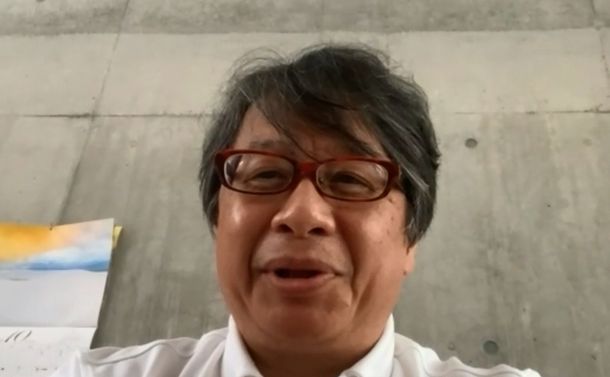 曽我豪さん
曽我豪さん――曽我さんの「仮説」について、自民党担当、野党担当として、どう考えますか。
野平 今回の衆院選は、新型コロナウイルスという未曽有の危機を迎えてから初めての衆院選です。この間、政府のコロナ対策は後手にまわったとの批判が国民の間で噴き出した一方で、受け皿となるべき野党の支持率はあがっていません。民主党政権への政権交代の経験を踏まえ、良くも悪くも自民党と付き合っていかざるを得ないという判断を国民が下すのであれば、自民党がこれから長期にわたって政権を担う体制ができつつあると見なすことができるのかもしれません。
吉川 民主党から自民党に政権交代して9年間が経るなかで、国民が不満を募らせていたことは、菅政権末期の支持率の低下からも伺えました。ただ、今回、誕生したばかりの岸田政権が信任される結果になれば、有権者は自民党に「ひどい政権運営をすると政権交代が起きるかもしれない」という緊張感よりも、「疑似政権交代をすればいい」というメッセージを与えることになると思います。
そういった意味で、政権交代のリアリティーを国民に感じさせることができていない、選択肢として弱い野党の責任は大きいと思います。
松本 先ほど吉川さんは、枝野代表が言う「変えなくてはいけない安倍・菅政治」の肝として4点を挙げられましたが、「お灸を据える」だけでなく、政権交代を夢見るならば、問題を指摘するだけでなくそれをどう変えるか明示することが必要だと思います。具体的にどういう風に変えると枝野代表は言っているのでしょうか。
くわえて「分配」についてです。この衆院選は与野党が「分配」をフィーチャーするのが特徴的だと思っています。経済が良くないときに、「分配」に言及するのは有権者の声に呼応する対応ですが、自民党と野党の分配はどこが違うのか。教えていただければと思います。
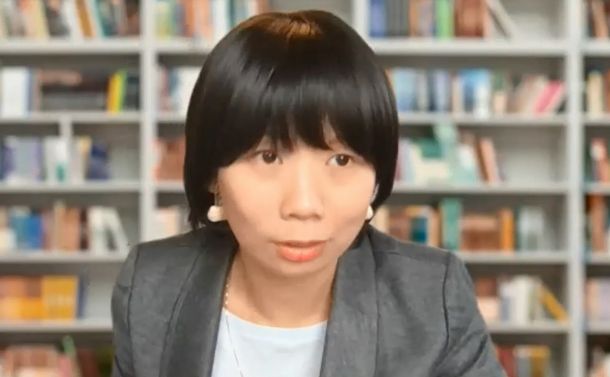 松本朋子さん
松本朋子さん吉川 森友・加計・桜を見る会については真相解明チームをつくる。今後、自分たちはきちんと説明する、情報公開する、まっとうな政治に変えていくと言っています。
アベノミクスにかわる立憲民主党の経済政策は、成長ありきで成長をした果実を分配するのではなく、最初に分配がある経済です。格差や将来不安が広がるなか、医療や介護の面でベーシックサービスを充実させることで不安を取り除き、人々が安心して消費できるようにして経済成長につなげるというのが、枝野代表の考え方です。
コロナ対策では司令塔をつくる。担当大臣が複数いた安倍・菅政権の態勢を改め、司令塔となる担当をはっきりさせる。水際対策を徹底し、補償をしっかり出したうえで休業や時短に協力してもらい、封じ込めをめざすということです。
野平 枝野代表は分配が先だということだと思いますが、岸田さんも分配と成長は両方やると。ただ、金融所得課税は、本人は意欲を見せていましたが、すぐに翻意しました。それも含めて今後、どこまで踏み込んでいけるかが問われます。この点は、衆院選に向けてというより、来年の参院選までに何ができて、何ができなかったのかというのを、よくみていく必要があります。
――14日の衆院解散を受け、日本全国で一気に選挙戦が本格化します。今回の議論を振り返って、考えるところを述べていただければと思います。
御厨 二大政党制をもっと疑ってもいいと思います。日本の政党史を振り返ると、「二」という数字に呪縛されてきました。確かに二大政党になればいいけど、なかなかならないのはどうしてか。そこで悩んでいても先に進まないので、連立も含め、色んな形の政権交代に挑んでいいと思います。
小選挙区のもとで二大政党による政権交代を実現するという筋道は頓挫したので、一から出直すことも必要でしょう。二大政党制に拘泥しないところから、より個性的でおもしろい政治家がでてくるのではないか。そこから新たな政治の可能性が広がるのではないか。そう思っています。
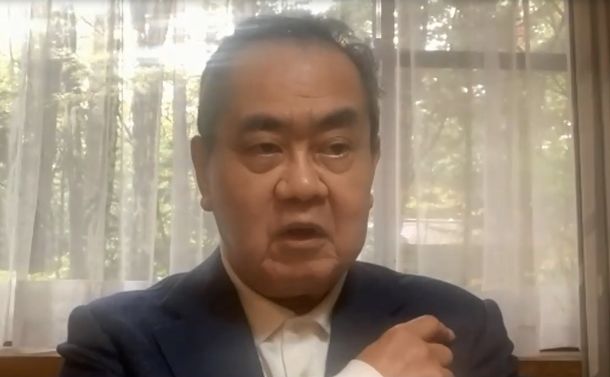 御厨貴さん
御厨貴さん吉川 旧民主党の流れをくむ政党で4年間も代表を続けていたのは枝野代表だけです。バラバラといわれる野党の求心力を保ってきたという意味はありますし、今回は選挙区調整も相当に進んで、野党としてはかなりいい態勢はつくれていると思います。
ただ、そこまでしても、今回、政権交代が起こらないとか、議席もさほど伸びなかったとなると、その先はどうすればいいのか。戦略の分岐点になる可能性はあります。野党の間で再び遠心力が働いてしまう恐れもあります。
 吉川真布さん
吉川真布さん野平 衆院選の注目点は無党派層の動きと、その結果、自民党がどれだけ議席をとれるかに尽きます。さらに24日には山口、静岡の両県で参院補選があります。参議院は衆院選に向けた前哨戦として力を入れていますが、二つとれるかどうか。衆院選とあわせてしっかり勝ちきれるかどうかが、来年の参院選をにらんだ党内の雰囲気を決めると思います。
安倍シンドロームについてですが、菅義偉政権になってから、夫婦別姓やLGBTといった安倍長期政権でフタをされてきたテーマにも光りが当たるようになったのは事実です。前進はしていないが、議論の土台にはのるようになってきた。安倍シンドロームから脱却する過渡期として捉えることもできるのかなとも感じていて、そのあたりの動きも追っていきたいと思っています。
 野平悠一さん
野平悠一さん松本 総裁選を通じて、LGBTや夫婦別姓も含めて、自民党内には様々な意見があることが国民に分かりました。自民党がそこからどれを選び取ったのかを明白にしていくことが大切です。
とりわけ来夏の参院選までに、何をどこまで実現したかを示すかが、自民党の大きな宿題になります。総裁選は多様な自民党を見せることができた一方、何が自民党なのかが分からなくなってもいるのも事実なので、それをどうまとめて示すかも岸田政権の必要な仕事だと思います。
二大政党制を疑うということが、今回の議論の大きなテーマになったと思いますが、忘れてはならないのは、与党も野党も結局、国会議員が政党のヘッドを決めているということです。そこに市民が関わるにはどうすればいいか。国民の声が直接的であれ間接的であれ反映されたリーダーを選べる道筋を示すことも、政党やメディアのつとめではないかと思っています。
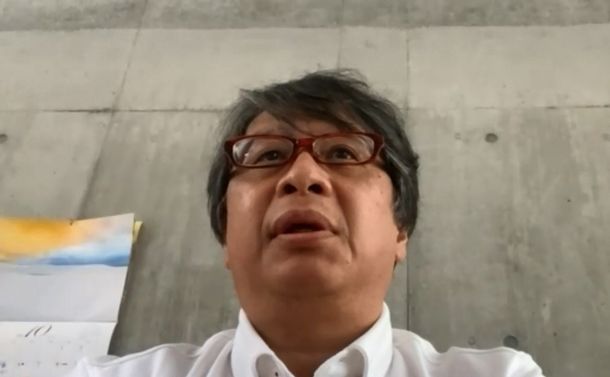 曽我豪さん
曽我豪さん
曽我 今回の衆院選では、メディアが独自に勝敗ラインを設定するしかないと思っています。個人的には、ラインは与党で「安定多数」をとれるかどうかだと考えています。
立法府が法案を審議して、修正していくときの基準は過半数ではなく、安定多数です。安定多数を失うと、衆院予算委員会の主導権が野党に移るので、補正ひとつ簡単には通らない。政局的にいうと、森友・加計・桜のすべてに喚問要求が出て、何も進まなくなる。安定多数を割り込めば、自民党は日本維新の会や国民民主党との、少なくとも「国会連合」というのも考えざるを得ないと思いますね。
そこで気になるのは、都議選でみられた「バッファー投票」です。基本的に自民党政権を望んではいるが、自民党が強大になり過ぎることに抵抗を覚え、牽制的に投票することですが、今回の衆院選でもこの「バッファー投票」が起きるかどうかが、ひとつのポイントだと思いますね。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください