大物の落選、立憲の惨敗、維新の躍進は想定外の事態だったのか……
2021年11月10日
今年の秋はいつになく短い思いがします。日本政治の選択と審判の季節が、慌ただしく過ぎ去りました。
総裁選でリーダーの顔を変えた自民党は、衆院選で与党による絶対安定多数を確保し、岸田文雄首相は「新しい資本主義」の旗を掲げて実績づくりに踏み出しました。政権交代という目標はおろか議席の維持さえ叶(かな)わなかった立憲民主党は、“創業者”の枝野幸男代表に代わる新たな顔選びを急ぎ、勢力を伸ばした日本維新の会は国民民主党とともに、「第3極」の確立をうかがいます。
こうした新たな状況を、どう見るべきなのでしょうか? 自民党内での「疑似」政権交代論が、立憲民主党の政権交代論を凌駕したのか。第3極の存在感の高まりは、二大政党制そのものへの挑戦なのか。「大物」が小選挙区で次々と敗れた世代交代の潮流は、各政党の新陳代謝を加速させるのか。そして、来年夏の参院選の「勝者」の条件は何か――。
世代も性別も様々な研究者や記者で政治を議論する「政治衆論2021」。第3回は、自民党総裁選、衆院選を経て立ち現れた政治の現状と課題、来夏の参院選とその後の展望について語り合います。(司会・構成 論座編集部・吉田貴文)
御厨貴(みくりや・たかし) 東京大学名誉教授
1951年生まれ。東京大学法学部卒業。東京都立大教授、政策研究大学院大学教授、東京大学先端科学技術研究センター教授、放送大学教授、青山学院大特任教授を経て現職。政治史学。著書に『政策の統合と権力』『馬場恒吾の面目』『権力の館を歩く』など。
松本朋子(まつもと・ともこ) 東京理科大講師
1985年生まれ。東京大学法学部卒業。2016年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程修了。名古屋大学特任講師、ニューヨーク大学客員研究教授を経て18年から現職。専攻は実証政治学・実験政治学・政治行動論・政治史。研究成果を海外学術雑誌に掲載。
曽我豪(そが・たけし) 朝日新聞編集委員(政治担当)
1962年生まれ。東京大学法学部卒業。朝日新聞社に入り、熊本支局、西部本社社会部を経て89年に政治部。首相官邸、自民党、野党、文部省など担当。週刊朝日編集部、月刊誌「論座」副編集長、政治部長、東大客員教授などを歴任。2014年から現職。
吉川真布(よしかわ・まほ) 朝日新聞政治部記者
1991年生まれ。2015年に朝日新聞社に入り、神戸、岐阜総局を経て2019年に政治部。安倍晋三首相番を担当した後、2020年から立憲民主党など野党を担当。立憲や国民民主党の合流などを取材した。現在は主に立憲の枝野幸男代表を担当している。
野平悠一(のびら・ゆういち) 朝日新聞政治部記者
1993年生まれ。2015年に朝日新聞社に入り、山口、神戸両総局を経て政治部。安倍晋三首相番や自民党の平成研究会(竹下派)、参議院自民党などを担当。菅義偉政権の発足時から、二階俊博前幹事長が率いる志師会(二階派)を主に取材している。
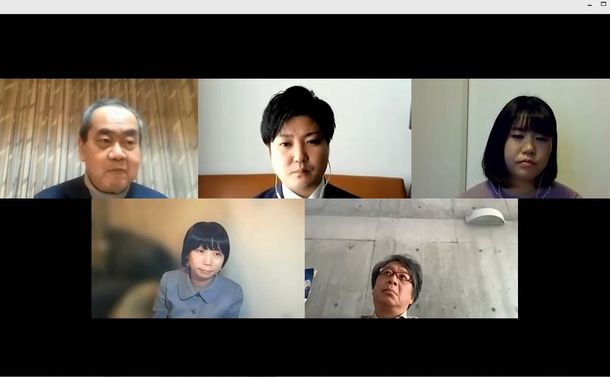 議論する5人。左上から反時計回りに、御厨貴さん、松本朋子さん、曽我豪さん、吉川真布さん、野平悠一さん(Zoomの画面から)
議論する5人。左上から反時計回りに、御厨貴さん、松本朋子さん、曽我豪さん、吉川真布さん、野平悠一さん(Zoomの画面から)――「政治衆論2021」の第3回です。10月31日投開票の衆院選では、自民党が公示前より15議席を減らしたものの、261議席と国会運営を安定的にできる絶対安定多数を獲得しました。発足から1カ月の岸田文雄政権はひとまず信任された形です。これに対し、野党第一党の立憲民主党は事前の予測と裏腹に議席を減らし、100議席を切る96議席の惨敗。枝野幸男代表は辞任を表明しました。一方、日本維新の会は公示前の4倍近くに達する41議席を得る躍進、国民民主党も11議席まで議席を伸ばしました。まず、今回の総選挙の結果について御厨貴さんから「問題提起」をしていただき、議論を始めたいと思います。
◇御厨貴さんの問題提起◇
今回の衆院選を一言で言えば、立憲民主党が沈み、自民党はほぼそのまま、維新が浮かんだということでしょう。
もともと、野党は菅義偉首相の自民党と戦うつもりでした。選挙区で統一候補を出せば、支持が低下する菅さんが相手に「勝てる」。コロナ禍の悪化や政府のコロナ対策への批判もあり、与党に「お灸を据える」以上の投票行動を有権者がとるとの期待がふくらみ、野党が勝つというムードが高まりました。
首相が岸田文雄さんになり、野党はいったん落胆したのですが、内閣支持率が思ったほど上がらず、負けないだろうという空気が続きました。ただ、コロナ感染者が急減したこともあり、有権者の「お灸を据える」気持ちが薄れていたことを、野党は見ようとしなかった。それどころか、メディアが持ち出した「政権選択選挙」という底上げの対立構図に、政権担当の準備もないままのった。これが失敗でした。
各地で激戦となった選挙は、自民党が危機感をバネに終盤で粘って競り勝ちました。自民党の若手議員にはいい経験になったと思います。これまで安倍晋三さんに頼って勝っていたのですが、今回は「安倍風」がないなかで危機感をもって戦ったことで、選挙のリアルを知ったはずです。自民党にとっては、そんなに悪い選挙ではなかった気がします。
注目したいのは、日本維新の会の躍進と、国民民主党が議席を増やしたことです。
日本の政党史を振り返ると、いわゆる「中道」はずっと弱かった。そもそも自民党は、左派社会党と右派社会党が統一して社会党になったのを受け、中道の改進党系が社会党に引き寄せられたら困るということで、自由党と民主党がその改進党系を巻き込んで合同してできた。その結果、55年体制の当初、中道的な政党はありませんでした。
1960年に社会党から割れて発足した民社党は、自社の真ん中に位置する中道政党と言えますが、大きくなることはなく、1990年代に政党再編が進むなかで解党しました。実は民社党と改進党には共通点があります。ほとんどの政策で自民党と大差ないが、防衛など国家的な問題になると自民党より「右」の主張をするという点です。
4年前の衆院選の際し、民進党の前原誠司さんが東京都知事の小池百合子さんとつくろうとしたのは、そういう立ち位置、防衛では「右」だが、それ以外の政策では中間に立つという政党です。それが、小池さんの不手際もあり、失敗した。その過程で、「左」に寄って旗揚げしたのが立憲民主党。ぽっかり空いた「中道」に立つのが国民民主党です。その意味で、国民が今回、比例で票を伸ばし、11議席を得たことには興味を引かれます。
では、維新の立ち位置はどこになるのか。国民の玉木雄一郎代表の国会での連携の呼びかけに腰が定まっていないのは、維新自身が自らをどこに位置づけたらいいか、決めきれていないからでしょう。一方、自民党は、これまで自公連立の枠組みでやってきたが今後、台頭した維新をどう位置づけ、関係性を築くか定まっていません。
いずれにせよ、今回の衆院選は、日本の政党地図の変容が見えた選挙でもあったと思います。
――御厨さんの問題提起を政党の現場から見るとどうですか。自民党担当の野平さん。いかがでしょうか。
野平 今回の衆院選は、投票日直近の情勢調査でも与野党がギリギリ競り合っている選挙区が多かった。そこで勝ち切れたことで、自民党は絶対安定多数を獲得できましたが、選挙中に自民党に不利に働くような問題が発生していたら、違う結果になっていたかもしれません。公示前から議席を減らしてもおり、「自民党が勝利した」というのはどうかなと思っています。
印象的だったのは、自民党幹部が応援演説で「今回は政権選択選挙にとどまらず、体制選択選挙である」と強調したことです。共闘した野党が勝てば、共産党が政権の中に入ってくる危機があると、声高に叫んでいました。野党共闘への危機感の裏返しだとも思いますが、「体制選択」という意識は国民にもあったのではないか。それが「第3極」の維新の議席増につながったと見ています。
 野平悠一さん
野平悠一さん――立憲民主党の敗北について担当の吉川さんはどう見ていますか。
吉川 ある種の「楽観論」が立憲民主党にあることは感じていました。メディアの情勢調査も、朝日新聞は厳しかったですが、それ以外は「議席を増やす公算が大きい」としたメディアが多く、ある党幹部は終盤でも「140議席はとれる」と言い、比例も「50議席は固い」と言う声がありました。実際は39だったですが……。
野党統一候補が政権への批判票の受け皿になっているという手応えを、党幹部は感じているようでしたが、結果は福山哲郎幹事長が「夢にも思っていなかった」という現有議席割れ。自民党が危機感をもち終盤でテコ入れをしたのに対し、野党には小選挙区で負けても比例で復活当選できるという「緩み」があったように感じました。
――メディアの情勢調査を見ると、朝日新聞は与党が絶対安定多数を超えると予想していましたが、他社の調査だと自民党が単独過半数とれるかどうかという予想が多かった。立憲も議席の上積みは確実と予想していたので、立憲幹部が楽観的になったのも致し方ない気もします。松本さんは今回の衆院選をどう見ますか。
松本 やはり自民党が接戦を制したのが大きかったと思います。競り勝った経験は議員の自信を強めることになるのか、逆に選挙が厳しかったことで、いっそう自民党に頼ることになるのか。現場はどう見ているのでしょうか。
野党共闘についてですが、共闘するために政策の軸を微妙にずらしたことが、「中道」の維新や国民の議席の伸びにつながったと思います。ただ、小選挙区で野党が過半数の議席をとるためには、共闘が必要なのも事実。立憲はこの矛盾をどう解決するのでしょうか。
もうひとつは世論調査です。今回は情勢調査も出口調査も各社で結果が割れました。アメリカでは選挙予測が難しくなっていますが、日本でも選挙の予測調査が難しくなってきているのでしょうか。
 松本朋子さん
松本朋子さん――私は世論調査の経験が長いので、松本さんの最後の疑問についてお答えします。今回は各社とも新しい方法で情勢調査を実施しました。なかでも朝日新聞は、小選挙区をネットのパネルで調査する画期的な手法で行いました。幸い朝日はほぼ的中させましたが、過去のデータが乏しいなか、厳しい調査でした。今後、新しい方式で国政選挙の調査を続け、データが集まれば、安定性も増すと思います。
それはさておき、自民党が接戦で勝利したことについて議員はどう感じているのでしょうか。
曽我 選挙後に会った関東圏の小選挙区で競り勝った自民党議員が口にしたのは、「このままでは来年夏の参院選は危ない」という危機感でした。今回は全国で自民党の大物議員が幾人も落選していますが、「先生を落としてはいけない」というコアな支持者をどこまで動員できたかが勝負を分けたと、実感を込めて語ってもいました。
興味深いのは、彼も含めて激戦を戦った若い議員がみな、自治労や日教組といった官公労の動きが極めて鈍かったと感じていることです。戦後の労働運動で共産党と対立してきたのは、「右」ではなく「左」の自治労などの官公労。立憲が伸びきらなかった理由のひとつに、官公労の動きの鈍さがあったという指摘はおもしろいと思いました。
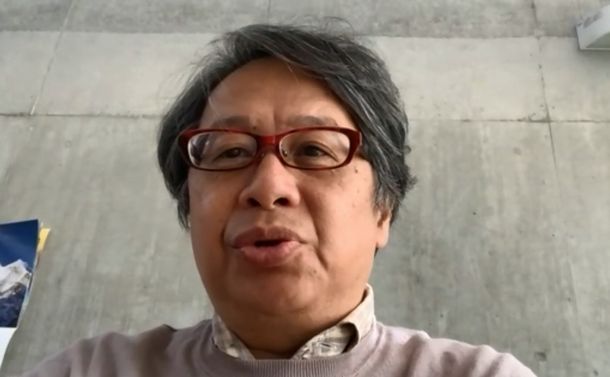 曽我豪さん
曽我豪さん野平 私も激戦区で競り勝ったことで自信を持つというより、むしろ危機感を強めている議員のほうが多いと思います。ある議員は「自民党も(立憲)民主党も飽きられている。有権者は新しいものを求めている」と言い、自民党も変わらないとまずいことになるという危機感を抱いていました。逆に言えば、立憲が今回、民主党の匂いを消すような代表選をしなければ、自民の脅威にはならないということも言っていました。
――野党共闘のあり方についてはどうでしょうか。
曽我 野党共闘に関連して思うのは、これまで野党が「国会連合」を真面目に考えてこなかった点です。本来、国会連合の延長線上に選挙での共闘があり、選挙で勝てば連立や閣外協力に進むというのが筋のはずです。でも、立憲がこの4年間に、他の野党と連合して、修正協議、議員立法など肯定的な仕事をしたかというと、やっていないと思うんです。政権へのアンチテーゼばかりでした。
立憲が「シャドーキャビネット」をつくらなかったのが致命的だったと思います。これがあれば、影の首相や大臣が主導して、野党との国会連合や政権構想に向けて動けたかもしれない。国会連合やシャドーキャビネットの取り組みをさぼったツケが、衆院選の最後で回ってきた気がします。
今後、与野党の間に位置する維新や国民を、国会で自民と立憲が引っ張り合うことになりますが、今のままだと立憲に引っ張る力はない。シャドーキャビネットをどうするか。国会連合をどう進めるか、早急に議論しないと、立憲はかなり厳しいと思います。
吉川 立憲と共産が国会で建設的な取り組みをしてこなかった「弱さ」は、私も感じていました。立憲と共産が党首会談で、立憲が衆院選で政権をとった場合、「限定的な閣外からの協力」を目ざすことで一致したのは投票の1カ月前の9月30日。有権者からすれば、「いきなり何だ?」となって当然です。国会で立憲と共産がもっと協働していれば、有権者も理解しやすかったのではないでしょうか。
枝野代表の姿勢は「できないことは言わない」です。シャドーキャビネットについても、「その通りにならない」という理由でつくりませんでした。全体的に、敵失狙いというか、政権の具体像を示さなくても、自民党に人気がなければ、野党第一党に票が来るという甘い見通しが、衆院選の敗北に繫がったのではと思っています。
 吉川真布さん
吉川真布さん野平 今回の選挙で印象的だったのは、対立型で与党を追及する野党議員が多数落ちたということでした。一方、国民の玉木代表は「対立ではなく解決だ」として、野党の国対の枠組みから外れ、野党の国会内ヒアリングもやらないとしています。これからは、独自の政策や対案を出して、国会連合で進めていく野党がより一層求められるのかもしれません。
――現場の見方について、御厨さん、松本さんいかがでしょうか。
御厨 「できないことは言わない」という「枝野論」もありましたが、枝野さんは弁は立つが、汗をかいて何かやるタイプの人ではないから、いかにもと思いました。シャドーキャビネットがそのまま実際の内閣に移行しないというのもおっしゃる通りなんですが、専門家を養成する意味はあるんです。
それぞれの分野の専門家を育てながら、政権に近づいていく。そうした日々の営みが大事なんだけど、立憲の“創業者”である枝野さんのこの4年間のやり方は、自分が会社の第一人者ということに頼り、地道な努力が足りなかった気がします。
立憲は新しい代表のもとでどう立て直すかですね。野平さんが自民党議員の言葉として紹介した「自民党も(立憲)民主党も飽きられている」「立憲が民主党の匂いを消すような代表選をしなければ脅威にはならない」という点がポイントだという感じがします。
 御厨貴さん
御厨貴さん松本 結局、野党にとっては政権担当能力をどう示すかが最大の課題ということですね。そして、自民に対抗するため、何らかの協力をしなければいけない以上、政権批判だけでなく、自党が進めたい政策を示すことが重要だとも思いました。であれば、自党の政策を追求するために国会連合を進めたり、シャドーキャビネットの大臣ポストを求めたりすることも可能になるからです。
曽我 朝日新聞の政治編集委員だった国正武重さんが最後に執筆した土井たか子さんについての著書に、次のようなことが書かれています。土井さんは社会党委員長として1989年参院選で社会党を大勝に導き、「山が動いた」という名台詞を残したことで知られています。その後、社会党が退潮し、委員長を下ろされた直後、国正さんに「自分が一番やばいと思ったのは、参院選で勝ったときだ」と言っているんですね。どういうことか。
ひとつは、これから自民党は本気で、あくどい手を使ってでも勝とうとするだろうと心配した時、社会党内には「なにを深刻ぶっているのか。勝ったんじゃないか」とまったく危機感がなかったこと。もうひとつは、自民党はいざとなると本物がでてくるが、社会党はいざとなると誰も出てこない。自民党のちっぽけなあくどいやり方にもおたおたして、気が付いたら負けているということです。
今回、絶対安定多数をとったのに、自民党は来年の参院選をにらみ危機感をもっています。枝野代表の辞任で危機に瀕している立憲はどうか。まずは、おたおたしない代表選ができるかどうか、本物がでてくるかどうかを、注視したいと思います。
――前半はこのあたりにして、後半に入ります。松本さん。問題提起をお願いします。
◇松本朋子さんの問題提起◇
幾つか論点をあげます。まずコロナについてです。
衆院選はコロナの感染が急速に落ち着く中で投票日を迎えましたが、コロナは選挙にどんな影響を与えたのでしょうか。ここで注目したいのは維新です。自民に不信を抱く、立憲にも入れたくないと人々の受け皿になったのはその通りだと思いますが、それにも増して興味深いのは、大阪府民の維新支持の急拡大です。
コロナ禍の特色のひとつは、政治リーダーのよしあしを有権者に意識させることになった点だと思います。政府のコロナ対応が批判されるなか、吉村洋文大阪府知事や松井一郎大阪市長は厚労省の非公開文書を公開したり、大阪の専門家会議の議事録を出したり、中央への批判を辞さずに情報の公開・発信を心がけました。そうした取り組みがコロナで頑張ったという評価につながり、維新票を増やしたのは間違いありません。
もちろん、政府批判は他の野党もしましたが、維新は自党の首長がいる自治体で実践できる点で優位にありました。口先だけだという批判に反論できるからです。政権担当能力への懸念を、自治体運営で払拭できる可能性を示した点は大きかったと思います。
次に投票率です。今回の55.93%は前回衆院選より2.25ポイントしか上がらず、戦後3番目の低い水準です。10代の投票率も前回の衆院選よりはマシになったとはいえ、各世代の投票率のなかで突出して伸びたというわけではありません。なぜでしょうか。
コロナの影響はひどかったですが、感染拡大が一息つき、そもそも欧米ほど被害が大きくなかったということはあるかもしれません。しかしそれ以上に、有権者が積極的に政策を選択できる状況になく、消極的な投票しかできなかったのがポイントではないかと思っています。
現状に問題を感じながら、有権者が積極的な選択ができなかった例のひとつにジェンダー問題が挙げられます。今回の衆院選での最高裁判事国民審査では、対象となった11人のうち、6月の最高裁判決で夫婦同姓を合憲とした人が不人気だったのは明らかでした。罷免率が低かった判事と高かった判事の差は、戦後2番目の大きさになったといいます。
しかし、夫婦別姓は最高裁判事審査の争点にはなっても、政党を選ぶ争点にはなりませんでした。ここで考えなくてはいけないのは、ジェンダーの平等を訴え、リベラルな姿勢を打ち出してきた立憲の女性候補者の割合が18.3%と前回より減っている点です。政党への公約に現実味のなさという議論もからみ、なおざりにしてはいけないと思います。
「分配」もまた、今回の衆院選のキーワードでありながら、有権者がどう選択していいか分からない争点だったと思います。与野党ともに「分配」を公約に挙げるけれど、財源はどうするのか、何をどう支えるのか、衆院選の議論からは見えてきませんでした。
所得再分配は、政府の介入権限を拡大する政策なので、政府への高い信頼が求められます。実効性のない不透明な分配政策が並べられても、有権者は選択のしようがありません。そもそも政治家は公約を守ろうと努力していないと考えている有権者に、どうやって信じられる公約を提供するかは、与野党を問わず政党の大きな使命だと思います。
最後に、衆院選の大きな反省として、欧米の幾つかの国で議論が始まっている論点について、議論されなかったということがあります。その一つはコロナ後の「出口戦略」です。大幅な財政出動を平時に戻すのは至難の業です。早めに議論を始めることが大切ですが、衆院選の主要な争点にはなりませんでした。
コロナ後の社会を考えた時、コロナ前への回帰でいいかのような空気が漂っているのも気がかりです。今の日本は、企業の生産性は低く、国際競争力は低下しています。非正規雇用の問題、子育てと仕事の両立が困難な労働環境、少子高齢化といったコロナ以前からの課題も加え、コロナ後を見据えた議論が、衆院選ではなかったのも大きな反省点です。
コロナ前よりいい社会をつくる、明確で堅実な改革のビジョンが、国民の政党への信頼を取り戻すうえでも、日本をガラパゴス化しないうえでも必要です。これも後半で議論できればと思います。
――維新の躍進とコロナとは関係あるでしょうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください