コロナ対策徹底批判【第三部】~上昌広・医療ガバナンス研究所理事長インタビュー⑧
2021年12月06日
昨年2月、日本だけでなく世界中の耳目を横浜港に集めたダイヤモンド・プリンセス号の問題は、日本国内で十分に検証・解明されたのだろうか。
少なくとも政府・自民党による検証はほとんど行われていない。ジャーナリズムによる検証も、政府や医療者側に取材したものはあるが、乗船客や乗員を対象に集中的にインタビューを重ねたものはないように見受けられる。
このため、ダイヤモンド・プリンセス号の問題を振り返る際にはコロナウイルスの国内侵入を防ぐ公衆衛生面だけが重視され、実際に船に乗っていた乗船客や乗員という生身の人間の医療面については、それほど深くは顧みられていないようだ。
だが、今後の感染症対策を考えるうえで、公衆衛生の側面だけが重視される考察ではたして十分なのだろうか。
臨床医でありながらコロナウイルスに関する世界最先端の医学・科学論文を渉猟する医療ガバナンス研究所理事長・上昌広氏への連続ロングインタビュー企画「コロナ対策徹底批判」第3部は、ダイヤモンド・プリンセス号の問題から見える日本のウイルス対策の基本的な失敗の構造に光をあてる。
 新型コロナウイルスの患者が出た大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号から乗客たちが下船。移送するために大型バスが停車している=2020年2月20日、横浜市の大黒ふ頭、朝日新聞社ヘリから、
新型コロナウイルスの患者が出た大型クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号から乗客たちが下船。移送するために大型バスが停車している=2020年2月20日、横浜市の大黒ふ頭、朝日新聞社ヘリから、上氏が最も強く指摘するのは、感染症患者を乗せたクルーズ船が停泊していたのは横浜港であって、首相官邸のある東京・永田町や厚生労働省のある霞が関ではないという事実だ。別の言い方をすれば、医師ではない安倍晋三首相や加藤勝信厚労大臣(いずれも当時)、あるいは医師免許を持ってはいてもクルーズ船内部の状況を知らない厚労省・医系技官たちが、ダイヤモンド・プリンセス号の乗船客や乗員の問題に判断を下すこと自体が間違っていたということである。
厚労省・医系技官たちや首相、厚労大臣は、国内にコロナウイルスを入れない、つまり「公衆衛生」の観点だけに基いて判断を下した。しかし、ダイヤモンド・プリンセス号には乗船客、乗員合わせて3713人もの世界中の人間が乗り合わせていた。乗船客たちは生身の体と心を持ち、コロナウイルス感染者を含めて、それぞれに様々な疾患を抱えていた。切実に「医療」を必要としていたのだ。
ダイヤモンド・プリンセス号内部の事情を知らない厚労省・医系技官や首相、厚労大臣が、具体的な乗船客に対面する「医療」ではなく、抽象的な「公衆衛生」の観点から結論を導き出した結果、大多数の乗船客は2週間以上、最大ほぼ1カ月間、クルーズ船内に閉じ込められた。
「感染させるために培養用シャーレに入れたようなもの」。昨年2月19日付のウォールストリート・ジャーナル日本版は、乗船していた米国人医師のこんな言葉を記事中で紹介した。
クルーズ船ダイヤモンド・プリンセス号は2020年1月20日に横浜港を出港。同25日に香港で下船した80代の男性がコロナウイルスの陽性者であることが、2月1日に確認された。連絡を受けた厚労省は同3日に横浜港で検疫を実施。その結果、31人中10人からコロナウイルスが検出された。
ダイヤモンド・プリンセス号には世界57カ国から乗船客2645人、乗員1068人の合計3713人が乗り合わせていた。
厚労省は、船内パーティなどでの接触飛沫感染で乗船客のほとんどが濃厚接触者に当たると判断。そのまま船内での2週間の隔離・検疫を実行した。2週間の隔離・検疫期間が終了した乗船客・乗員は順番に下船、3月1日に全員の下船が完了した。
国立感染症研究所の報告によると、下船完了後4月15日までにコロナウイルス感染の確定症例は712例あり、その他にも検疫官や船会社医師ら外部から入った9人の感染が確認された。死亡は少なくとも14人に上った。
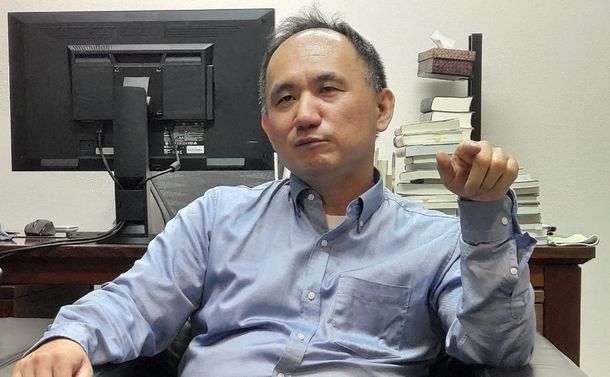 インタビューにこたえる上昌広・医療ガバナンス研究所理事長
インタビューにこたえる上昌広・医療ガバナンス研究所理事長
――今回から昨年、世界中から批判的な視線を浴びて大きな問題になったダイヤモンド・プリンセス号に対する政府の対応についてお聞きしたいと思います。
上さんはダイヤモンド・プリンセス号が横浜港に停留されていた昨年2月9日に公開されたForbes JAPANで「ただ閉じ込めればいいのか。新型コロナウイルスの合理的な感染防止方法とは」というタイトルの論考を発表しています(参照)。そこでまず指摘されたのは、クルーズ船に多くの高齢者が乗船している問題でした。高齢者は基礎疾患を持っている例が多く、室内に閉じ込めることで疾患を悪化させる可能性が高いと心配されています。
この論考にも書かれていますが、東日本大震災の後、福島県の浜通りで診療を続けていた上さんの医療チームが2011年5月21日と22日に飯舘村の住民を対象に健康診断したところ、前年の健診と比べられる564人の体重、血圧、血糖値、中性脂肪濃度が有意に上昇していた。この人たちの多くは被曝を恐れて、ほぼ2カ月間自宅に閉じこもっていたということでした。同じことがダイヤモンド・プリンセス号でも起こっていて、持病の悪化がコロナウイルス感染の増悪要因になると指摘しています。
ダイヤモンド・プリンセス号問題の後、大きな批判を浴びたPCR検査の不足問題から現在の問題に至るまで、厚生労働省・医系技官の失敗の構造は一貫しています。すなわち、医系技官の人たちが目の前の患者さんや国民のことを真っ先に考えるのではなく、国家のこと、イコール官僚の体面をまず気にすることに起因しています。
ところが、ダイヤモンド・プリンセス号には外国人客がたくさん乗っていて、外国人客はツイッターやフェイスブックなどで、どんどん母国に連絡したんです。それでニューヨークタイムズなど世界中のメディアが取材をしました。
ニューヨークタイムズなどは日本政府の対応の仕方を袋叩きにしました。各国政府にとっては自国民の健康が最優先なんです。日本政府が気にしていたような、自国に入れるとか入れないとかそんなことはどうでもいいことなんです。そもそも事実としてもう入っていると思っているわけです。
臨床医の立場から申しますと、臨床医というのは目の前の患者さんを最優先するわけです。その患者さんの状況に応じて臨機応変に対応すれば、そんなに間違わないんです。不幸にして救命できないケースも少なくはありませんが、失敗ではないんです。
 上昌広・医療ガバナンス研究所理事長
上昌広・医療ガバナンス研究所理事長
――臨床の経験上、どうしても救命できないケースはあるけれども、目の前の患者の様子を観察しながら臨機応変の対応を打っていけば失敗はない、ということですね。
目の前の患者さんに対して臨機応変に対応すれば、こちらが変わらざるをえない。それは、合理的に変わることを意味します。
当時、ダイヤモンド・プリンセス号に神戸大学の岩田健太郎教授が入って、「レッドゾーン」「グリーンゾーン」といったゾーニングのことを言いましたよね。当時はそのやり方が感染症予防の常識で、今になってそれを責めることはできませんが、今では感染の主要ルートは「空気感染」であることがわかっているので、ほとんど何の意味もないことだったんですね。
これを悪いと言うつもりはありません。当時は仕方なかったと思います。だけど、問題は、こうした対応は感染症学のこれまでのエビデンスを押し付けただけで、たぶん患者さんの実態を反映していなかったという点にあります。
具合がいいとか悪いとかは、患者さんを直接みればわかります。なのに、会うこともせずに、会議室で議論ばかりしている人がいる。「むしろ公衆衛生は患者をみないのがいいんだ」みたいなことを公言している人間すらいた。「我々は患者を直接みないから大局に立って判断できるんだ」と平気で言うんです。
――それだと机上の空論になりませんか。
そうです。実はそのころには日本国内には陽性者が相当入っているはずなんです。たとえばタイ人夫婦の問題もありました。
ダイヤモンド・プリンセス号問題が起きる直前の昨年1月下旬、日本を旅行していたタイ人夫婦の妻が体調を崩し、タイに帰国した2月4日に二人とも新型コロナウイルス感染が確認された。
つまり、ダイヤモンド・プリンセス号問題が起きる前に、すでに日本には感染者が入っていた蓋然(がいぜん)性が高い。ダイヤモンド・プリンセス号の乗船客を国内に入れる入れないなどという議論は、意味のない話だったんです。
必要なのは、乗船していた目の前の患者さんの状況に合わせて、融通の効く対応に変えていくことでしたが、そうはならなかった。官僚がいったん決めた机上の空論を押し付け続ける。太平洋戦争の時から現在のコロナ対応まで続く、日本の政治の基本的な問題だと私は思いますね。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください