2021年12月16日
2021年10月、1970年代にさかのぼる1190万件の記録や文書が含まれた、全部で2.94テラバイトのデータをもつ、いわゆる「パンドラ文書」を、国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)が分析した結果が公表された。トニー・ブレア元英首相やヨルダンのアブドラ国王ら世界の現旧首脳35人が、タックスヘイブン(租税回避地)に設立した法人を使った不動産取引などにかかわっていたことが判明したのである。
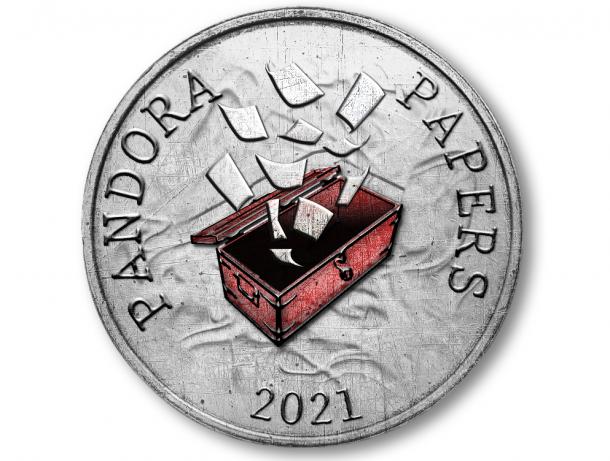 「パンドラ文書」のロゴ=国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)提供
「パンドラ文書」のロゴ=国際調査報道ジャーナリスト連合(ICIJ)提供ICIJは同じくリークされた資料である「パナマ文書」(2016年)や「パラダイス文書」(2017年)についても調査報道をしてきた。今回のパンドラ文書は、ICIJが手がけた秘密ファイルのなかでも最大規模で117カ国の600人のジャーナリストが分析や取材に従事したという。
筆者は、2015年6月に上梓(じょうし)した拙著『ウクライナ2.0』(社会評論社)の付論として、「タックスヘイブンをめぐる嘘(うそ)」という論文を公表したことがある。地球上の過剰資金の動きを分析することが、世界の覇権争奪を考察するうえできわめて重要であるとの観点から、もう10年以上、タックスヘイブンにも関心を寄せてきた。
この論文では、タックスヘイブン規制が十分でないことに加えて、そもそも「租税競争」(tax competition)を徹底しないまま、「租税協調」(tax cooperation)ないし「租税調和」(tax harmonization)に向かおうとしている国家の嘘を暴いている。わかりやすく言えば、国家は自らの租税のあり方を通じて、国家間の競争をするのではなく、国家でまとまって強制的に租税を徴収する体制の強化にあたっているにすぎず、それが不十分なタックスヘイブン潰しに向かっているだけだということを解説したものだ。
ここでは、まず〈上〉として、近年、国家が行ってきた横暴の歴史的経緯について説明し、そこに法的価値体系の対立があることを指摘したい。そのあとで、〈下〉として、「パンドラ文書」でも明らかにしきれていない、世界の「ダーティマネー」について論じてみたい。
通常の理解では、「パンドラ文書」などによって、政治家や有名人が脱税・節税にタックスヘイブンを利用している実態が明らかになったことで、こうした抜け道を塞ぐためにタックスヘイブンの利用をできなくしたり、難しくしたりするメカニズムの構築が必要であるということになる。
実は、そのための努力は後述するように、国家間の協調というかたちをとって何十年も行われてきた。これが租税協調だ。国家間での徴税をめぐっては、租税上の競争は否定されるべきではないが、タックスヘイブンの存在は「有害な租税競争」を誘発するから、国家間が協力してタックスヘイブンを阻止・抑制しようというのがこれまでの国家間の共通認識であった。
この延長線上で、国家を超えて各国で利益をあげながら、タックスヘイブンや移転価格(企業グループ内の取引価格)などを活用して、節税・脱税を行っている超国家企業ないし多国籍業に対して世界中の国家が協調して対処する動きも広がっている。
おりしも、2021年10月、経済協力開発機構(OECD)は、136カ国・地域は企業が負担する法人税の最低税率を15%とすることや、多国籍企業への課税権を自国から、たとえ現地に拠点がなくても多額の利益を得ている国に移すことに合意した。同月30日には、ローマで開催されたG20において、すべての首脳が、法人税の最低水準をめぐる競争に終止符を打つ「グローバル・ミニマム・タックス」を含む、新しい国際的な課税ルールに関する合意を支持した。
問題なのは、こうした国際的な取り組みに「大きな嘘」が潜んでいることだ。国家にもいろいろあって、「クレプトクラート」と呼ばれる「泥棒政治家」が国家のトップに君臨し、密(ひそ)かに国家の資金を外国に送金し、蓄財に励んでいるといった例がたくさん存在する点にある(拙稿「『クレプトクラート=泥棒政治家』と安倍首相」を参照)。国際的に国家同士が取り決めても、国家のなかには、国内法よりもクレプトクラートが上位に位置し、法を無視して振る舞うことが可能なケースが複数ある。クレプトクラートによる国富の略奪とその資金の洗浄(ロンダリング)こそ、「クレプトクラシー」であり、これに対処するには、租税協調という国家間の「なれ合い」だけではうまくゆかないのである。法の上に立ったクレプトクラートによる国家の横暴という現実に目を向ける必要がある。
まずはタックスヘイブンの歴史について知る必要があるだろう。タックスヘイブンの典型的タイプとして、①低い税ないし税ゼロ、②秘密厳守、③会社設立の容易さ・柔軟性――という三つの特徴があることが知られている(Palan, Ronen, Murphy, Richard & Chavagneux, Christian, Tax Havens: How Globalization Really Works, Cornell University Press, 2010)。別の本では、①秘密の提供と②低い税ないし税ゼロの二つの特徴を、タックスヘイブンを定義する基準としている(Shaxson, Nicholas, Treasure Islands: Uncovering the Damage of Offshore Banking and Tax Havens, Palgrave Macmillan, 2011)。前述した拙稿では、この二つの定義を参考にしながら、タックスヘイブンを「秘密の厳守を前提に、税金を節税・脱税する目的で行われる取引を容易に可能にする法令を備える法域」と定義しておいた。
なお、「オフショア」という言葉もこのタックスヘイブンの概念に含めて考えることができる。ただし、オフショアは本来、「非居住者である企業のための特別な税制を持つ領域」のことで、それ自体は何の問題もない。便宜上の船籍地として、パナマ、リベリア、マーシャル諸島などが利用されているのがこの例だ。それ以外に、節税や脱税のために資金を「沖に置く」場所としてオフショアが利用されている。あるいは、国内の制度自体が不安定で怖かったり信用できなかったりするために資金を「沖合に置く」必要に迫られているケースもある。
タックスヘイブンへの理解を深めるために、その4グループについて説明したい。第1グループは欧州大陸のタックスヘイブンである。具体的には、スイス、ルクセンブルク、リヒテンシュタイン、オランダ、オーストリア、ベルギーだ。連邦制をとるスイスは、米国の州におけるタックスヘイブンを見習ったと言われている。直接税は州、間接税は連邦の所管とされ、各州間で課税をめぐる競争が行われていた。これが金属・機械工業の盛んなツーク州における企業への優遇課税につながり、1944年、同州はタックスヘイブンとして機能するための税法を導入するに至った。皮肉なことに、州間の税制をめぐる競争が一部の州のタックスヘイブン化を促したのである。一方、ジュネーブを中心に隆盛した銀行家は18世紀から欧州の資産家のカネを秘密裏に預かってきたが、銀行の取得した機密保持を銀行に義務づける法律が1934年に施行されたことで、顧客情報の秘匿を前提とするタックスブンが生まれた。オランダはアジアへのオランダ企業の進出を後押しする目的で、1893年、持ち株会社について、海外子会社によって取得された所得すべてを免税とすることを決めた。その後も、資産がほとんどなく事業活動もない名義のみのペーパーカンパニー(shell company)の設立を認めるなど、タックスヘイブンの役割を果たしている。
第2グループはロンドン・シティおよび元大英帝国傘下の地域である。このグループのタックスヘイブンはロンドン・シティを中心にして3層のネットワークからなっている。もっともシティに近い内環はジャージー島、ガーンジー島、マン島という三つの英領で、中間の環は14の海外領土のうち、ケイマン諸島、バミューダ諸島、英領ヴァージン諸島、タークス・カイコス諸島、ジブラルタルである。外環は、英国が直接支配しているわけではない 香港やバハマ諸島である。
 英領バミューダの首都、ハミルトンの桟橋に並ぶヨット。バミューダは観光地とともに、「タックスヘイブン」の顔も持つ
英領バミューダの首都、ハミルトンの桟橋に並ぶヨット。バミューダは観光地とともに、「タックスヘイブン」の顔も持つ第3グループは米国内の州および米国の支配下にある地域である。連邦制をとる米国では、企業の本社を誘致し州の発展をはかる競争が激化し、それが州をタックスヘイブン化させることになった。ここでも租税競争がタックスヘイブンの創出につながったことになる。ただ、各州における企業への課税は相対的に低かったため、こうした税率の引き下げ競争よりむしろ企業設立の簡素化や、企業の買収などを許可したり、親会社と子会社間の取引を認め、移転価格を利用した節税を認めたりすることで企業誘致をはかる州が出てきた。具体的には、1875、1896、1899年にこうした企業関連法を相次いで制定したのがニュージャージー州であった。これを見習ってデラウェア州も1898年に法律を制定し、企業が独自に統治ルールを定めることを認めた。
 パナマ市の景観
Daniel Lange/shutterstock.com
パナマ市の景観
Daniel Lange/shutterstock.com第4グループはその他のタックスヘイブンで、ソマリアやウルグアイなどである。
注目すべきは、タックスヘイブンがいわゆるアングロサクソン的と呼ばれる英米法体系のもとで隆盛をみた点である。英米法体系は、ゲルマン法に由来する中世的慣習法として成立した判例法である「コモン・ロー」がイングランド法の基礎として発展したことを出発点としている。これに対して、市民の代表たる議員が議会で制定する公法たる制定法を立脚点とする「シビル・ロー」という大陸法体系はヨーロッパ大陸の法体系を特徴づけている。
英米法体系下では、制定法がない場合でも必要なことを私的に行うことができ、問題が生じた場合、訴訟によって裁判所に判断してもらうことで法的秩序が維持できるとみなす。これに対して、公法に力点を置く大陸法体系下では、法律制定に時間がかかり、法律に書いていない行為を率先して実行に移しにくいという特徴がある。あくまで制定法を重視するからだ。
英米法と大陸法の差は、〈法の上に人をおく〉英米法と〈人の上に法をおく〉大陸法の差になって現れている。
コモン・ローに立脚する英米法体系では、トマス・ホッブズ的立場が優先されてきた。すなわち、一人の人間ないし少数の人間だけが自分の属する国家だけを前提に、その国家の主権保持を錦の御旗として、自国内での民主主義の手続きを経て、自国内の一部の人間集団の利害を代表する政策があたかも国民全体の総意であるかのようにふるまう結果、国民全体の代表者としてふるまう人物が正義からかけ離れた行為を行いうる事態が起きるのだ。ここでは、法律があっても、法律を無視して個人が勝手な行動をとりうる。〈法の上に人をおく〉という事態が起きる。
ここでの「社会契約」は主権者たる国家に統治権を譲渡する、垂直的な「統治契約」となっている。いわば、市民という名で個々人の独善的な利益だけを優先し、それを民主主義という手続きを盾にして国民の総意とするのである。ゆえに、民主主義を隠れ蓑(みの)にして、一人の人間が国民の総意のもとに法律を無視することも可能になる。まさに、〈法の上に人をおく〉のである。
これに対して、ヨーロッパ大陸では、〈人の上に法をおく〉という、ジャン=ジャック・ルソー的立場が優先されている。そこでは、一人ひとりの要望や欲求である「特殊意志」ではない、全国民の意志にかなった、全国民の利益を追求する「一般意志」を具体化する、集合的な単一の人格としての「公民」が構成員として想定され、それが自発的に参加する結社(アソシエーション)としての政治体が主権国家であり、その主権に具体的に参画するのが市民とされている。社会契約は「公民が公民となる」ための水平的な社会契約であり、市民は公民となることが前提とされている。ゆえに、フランスやドイツといった大陸諸国では、公民という立場に立つところに正義を考える必要が生まれる。この公民のもとに制定された法はもはや私的利害を優先する私人に侵されることはない。そこでは、私人よりも法が優先される。まさに、〈人の上に法をおく〉のだ。
問題は、実際の歴史の進展をみると、〈法の上に人をおく〉英国や米国の法思想が軍事的優位を背景に世界をリードしてきたことにある。いわば、英国や米国が覇権国家であった結果として、英米法体系が世界中に混乱を撒(ま)き散らしてきたと言えなくもない。
たとえば、タックスヘイブンがその一例である。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください