安全保障化の「正の側面」に引きずられ、「負の側面」を見失った2年間
2021年12月31日
新型コロナウイルスの世界的感染が始まって2年。感染力の強いオミクロン株が各国で広がり、コロナ禍は一体いつ終息するのか、確たる見通しは立っていません。命にかかわるリスクにさらされ続けるなか、政治や社会はどう変わったのか。これまで「論座」にコロナについての論考を幾度も寄せていただいている国政政治学者の三浦瑠麗さんと社会学者の西田亮介さんに、あらためて寄稿をお願いしました。お二人の対談動画と合わせて、ぜひお読みください。(論座編集部)
 Dilok Klaisataporn/shutterstock.com
Dilok Klaisataporn/shutterstock.com日本にはリスク許容性が低い人が多いですが、それはなぜなのでしょうかと尋ねてきた人がいました。政治がいけないのか、社会の風潮なのか、日本の長い歴史に根差したものなのか。福島第一原子力発電所に貯蔵されている処理水の放出をめぐる議論の中でです。
自然界にある放射線と違いはないのに、ゼロではないというだけで印象が左右されてしまう。いったいどのようにリスク・コミュニケーションをすれば分かってもらえるのだろうか――。
この発言を聞いた時、すぐに目下のコロナ現象を想起したことは言うまでもありません。
リスク許容性というのは、実はそれほど定まったものではありません。リスクは実感されないときには対処が遅れ、ひとたび意識に上ったとたんに人々の行動を大きく縛る要因となる。平時には過小評価され、いざことが起こったときには過大評価されがち。それがリスクというものなのです。
不確実性とリスクを混同する人も多いのですが、不確実性とは、極言すれば、いつどこで何がどのようにどれほどの確率で起こるかがわからない、というもの。リスクは、それがある程度定量的に計算可能になっている段階を言います。
人間は全知全能の神ではないので、不確実性がゼロになることは永遠にありません。つまり、リスクがそこにあるとか、まだまだ分からないことが多いというのは、安全保障の世界にいる人間にとっては、動かない/動けない理由にはならない。不確実性やリスクとともに生きていくことが大前提となります。
社会がリスクをどのように認識するかは常に主観的なものであり、その認識のしかたには、政治やマスコミュニケーションが大きな役割を果たします。コロナ禍に翻弄されたこの1年、もっと言えばコロナが世界的に感染拡大した2年間を通じ、この点において日本及び世界のマスメディアや政治は、全く及第点ではなかったというべきでしょう。
コロナ禍における社会の反応は、国際政治学からみれば「安全保障化=securitization」(オレ・ウィーバー)を地でいった事例と言えます。「安全保障化」とは、従来は安全保障上の問題ではないとみなされてきたものが、安全保障課題として捉えられるようになる現象を意味します。異常気象や災害をもたらす気候変動問題、テロ、パンデミックのようなものが例として挙げられます。このように、パンデミックが新たな安全保障問題となるだろうという指摘はこれまでも普通に存在していました。
安全保障化という概念の枠組みは、安全保障をより広くとらえ、政策当事者らの優先順位を変えさせるとして、しばしば肯定的に捉えられてきました。確かに、安全保障化によって、これまで軽視されてきた政策や対応の優先順位がぐっとあがるのは、良い側面といえるでしょう。
ただ、安全保障化に伴う“恐怖”は、当然のように副作用を生み出します。たとえば、権力行使の範囲を拡大したり、自由な経済社会活動を抑圧したり、市民の相互監視や人権侵害をもたらしたりしがちです。多数派の認識の前面に恐怖が躍り出ることによって、多数派でない人々の権利は軽く見られてしまう。こうした事態を利用しようとする政治家が出てくるのではないか、というのは、かねてから懸念されていたことでした。
そして、この2年間の経験が教えてくれたこととは、それが必ずしも政治家に限定された行為ではなく、おそらくは悪意に基づくものですらないということでした。善意に基づく正義を追求する一方で、それとは裏腹に、現実と奇妙に折り合いをつけて副作用を受忍してしまう。この組み合わせは、むしろ政治に対して無知な人々にこそ顕著でした。
いったん大きな流れが出来てしまえば、もはや何がどうであったかも顧みられることもない。一つの正義に即した新たな情報を、次から次へと追ってしまう。脅威認識を支える不確実性やリスクはあとからあとから湧いてきます。もはや安全保障上の最優先事項なのだから、その脅威に言及していれば形が付くという事態です。
その意味では、「やりすぎるくらいがいい」と表明した岸田文雄政権は、まさにこの波に乗っているさなかであると考えられます。対抗者が不在なまま、中心なき集団的選択として、コロナ対策がとられているということです。
 オミクロン株の水際対策などについて取材に応じる岸田文雄首相=2021年11月29日、首相官邸
オミクロン株の水際対策などについて取材に応じる岸田文雄首相=2021年11月29日、首相官邸安全保障問題になれば、政府が適切に対応できるだろうというのは、まさに素人の発想です。本当に重要なプロセスは、安全保障上の問題となってからなのです。
政府が強い施策をとることを想定する以上、そこには責任とコストが生じる。また、最低限、戦いで負けないようにするという“使命”が生じます。そのための戦況把握や動員するリソースの準備、ありとあらゆるシナリオの検討と、国民の士気や支持などの状態の把握ができていなければ、準備もせずに期間の定めのない戦争に突入するのと同等の無責任さが生じます。「まだ動かない」ことも、戦には必要なのです。
ウイルスは人間でも国家でもないのだから、われわれは戦うよりほかに道がないではないか、戦争とは目的から何から違うんだと考える人もいるでしょう。ですが、仮に脅威が過大に見積もられている場合、人々の主観が脅威を増幅したり、新たな被害を別のところに生み出したりします。ただ、これは裏を返せば、主観がどうやって作られたかを分析し、それに引きずられすぎないように配慮することで、総合的に被害を最小化することは可能になるということでもあります。
1986年に「リスク社会」論を提起した社会学者ウルリッヒ・ベックは、今後、政府の役割の多くがリスクマネジメントになるだろうと予言しています。その指摘には先見の明があったというべきでしょう。
ベックが著書で「リスク」を正面から取り上げたのは、チェルノブイリ原発事故の直後でした。原発事故のような災害は、イデオロギーを選ばず人々に降りかかってくる事象です。国家は共通する脅威に対して国際協力を進めるのではないか、という淡い期待も、当時の議論からは伺えます。
ところが、宇宙人が襲来した時、国家が互いに協力するのかが定かでないように、パンデミックが襲来したときに各国がどう行動するかはシナリオ通りにはいきません。パンデミックは局所的事態ではなく、皆が被害に晒されるからです。まさに今回のコロナパンデミックでは、ワクチンの配分を中心として国際協力が低下しました。
イスラエルは希望者に4回目の接種を行おうとしているようですが、多数の先進国が最も性能の良いワクチンの2回接種を終えたにもかかわらず、さらなるブースター接種で感染拡大を防ぐことを優先し、発展途上国の人命を救う努力をなおざりにしています。中国は国産のワクチンに拘泥し、ワクチン外交を展開することで政治利用を図りました。入国規制では、各国が同盟国同士も含めて互いに報復的ともいえるような規制をかけあっています。
パンデミックは長年のリベラルの夢も打ち砕きました。近代の主権国家を中心とした枠組みが修正され、非国家主体が各国と連携し、コスモポリタンな集団が台頭して、そこから新たな権利が生まれるという夢は消え去り、家族であっても国境を越えて行き来ができない、今まで当たり前に働いていた外国人労働者が一斉に帰国するといった現象が生じています。
イギリスで報じられた圧倒的な人手不足は、BREXITの影響もあるものの、大半はこうした背景に基づく外国人労働者不足です。日本でも留学生が入国を阻まれ、里帰り出産などをはじめとした理由で長期帰国中の外国人の家族が日本に帰ってこられないという問題が目立っています。
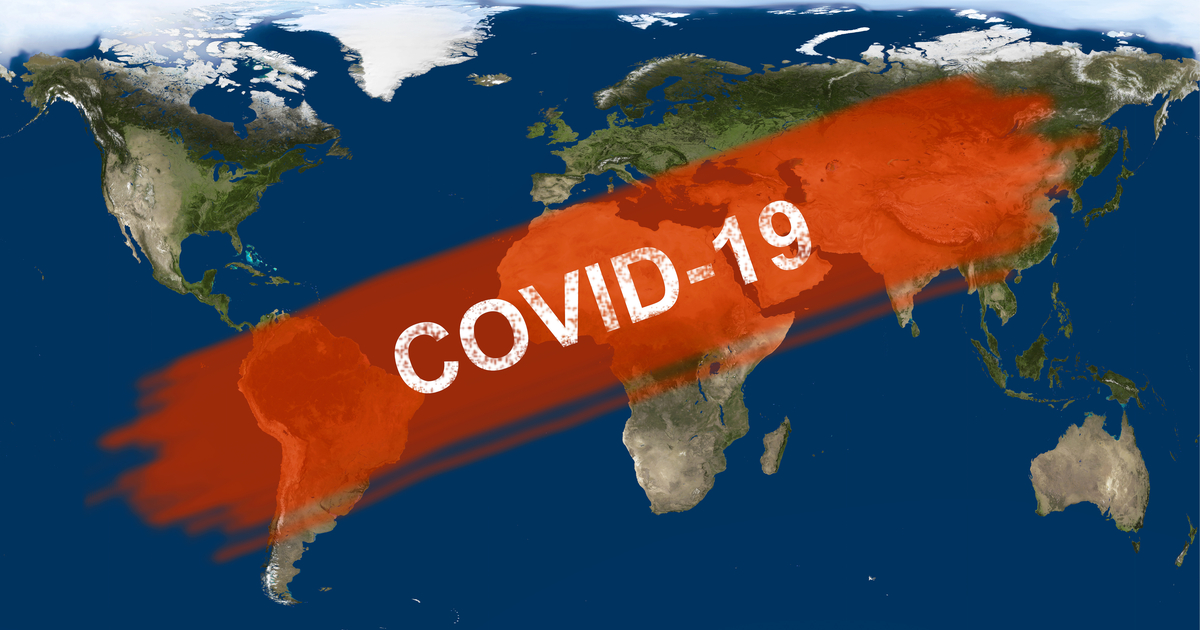 Viacheslav Lopatin/shutterstock.com
Viacheslav Lopatin/shutterstock.comコロナ禍に伴うこうした閉鎖的な風潮、国境管理の強化を指して、政治学者のイワン・クラステフは「うちにいようナショナリズム」という言葉を使いました。しかし、彼さえも、リベラルはこのような状況に鑑み、期間限定での私権制限に賛同すべきだとしています。例外的状況において人命を救うためなのだからと。これは陳腐に平たく言えば、私たちが私権制限に応じれば誰かの命を救うことができる、応じなければ誰かの命を侵害しているのと同じだ、という発想です。
こうした命の選択をさせてはいけないという議論をする人は、科学や人間の進歩によるコロナ封じ込めの可能性を信じがちです。安全保障にかかわる政府や人々の「認識」を広げれば、問題が解決に近づくかのような、過剰な合理性を読み込んでしまっているのではないかと思えてなりません。
これは、前述の安全保障化という現象の「正の側面」に引きずられすぎて、「負の側面」を見失ってしまっていることに他なりません。現に、そうした人々はコロナ以外の理由で亡くなる人や犠牲を負う人に関する算定をしません。疎外感から鬱を発症するなどして発作的に自殺で亡くなった人と、コロナで亡くなった人の失われた平均余命を天秤にかけることもしなければ、若者や子どもにとっての一年の価値と、私たち中年以上の人間にとっての一年の価値を比べることもしません。
現在、これまでもろもろ指摘されてきた安全保障化の理論的な弊害の分析や、リスクに対する過剰反応がもたらす害についての机上の分析は、さほど用いられなくなっています。それは、過去の指摘が間違っていたからではありません。論者の多くが今回のコロナ禍を研究対象としてではなく、大衆の一人として経験してしまったからでしょう。
思えば、3.11を論じた人々の多くも、津波に間近で接して九死に一生を得た人ではありませんでした。シビア・アクシデントや原発のリスクを盛んに論じた人たちも、原発の立地当事者に限られませんでした。翻ってパンデミックは、東日本大震災とは違って圧倒的に多くの人が「体験するもの」だったのです。自分自身が戦争やパンデミックを体験した時、それまで持っていた理論上の批判精神を現実に向けることができるかどうかは、一つの試練であると言えるでしょう。
日本のコロナ既感染者数は少ないとされていますが、実際には検査で炙り出された数のおよそ5倍から10倍いると言われます。その間をとれば、この2年間で人口のおよそ1割程度しか、無症状も含めて罹患していないことになります。
しかし、この間に生まれた閉塞感や恐怖感は、ほとんどの人に甚大な影響を与えている。パンデミックは罹患せずとも体験することが可能だからです。その結果、パンデミックがもたらす恐怖に巻き込まれてしまい、一市民として合理的な選択、具体的には、「皆と同じような言動」を行ってしまうということはないでしょうか。
各国では、ワクチンパスポートで日常の行動制限を行うだけでなく、医療アクセスも制限しようという議論さえ出てきているのが実情です。確かに、ワクチンは打つに越したことはありません。そもそも「保険をかける」という発想は、煙草をのむ人も、日々運動している人も、肥満に起因する病気に苦しむ人も、食生活に気を遣っている人も含めて広く加入させ、個人ごとのリスクに伴う保険料の違いはなるべく抑えて、負担を共有しようという概念に基づいています。
生まれや財産の多寡など自分ではどうしようもないことなら救うけれども、個人の選択の結果ならば救わないというのであれば、煙草もリスクを伴う職業につくことも個人の選択の結果でしょう。こういうと、いや、世の中は変わったんだ。これからは喫煙者も自費診療で、健康保険は使えないようにすべきだと言われそうな懸念も覚えます。こうした「過去に規定されない未来の構築」という発想自体が、近代からの移行の文脈の中でリスクを論じてきた人々の傾向でした。ここが、私が彼らの問題提起を重視しつつも、一番折り合えないところです。
しかし、すべての人間が強制と管理に応じるわけではない以上、「リスクに過敏な社会」はどこかに分断線を引かなければなりません。たとえば、混沌とした発展途上国と秩序だった先進国のあいだに、あるいはワクチン忌避者とワクチン推進者のあいだに……。
このように、リスクに過敏な社会は閉鎖的であり区別をつけます。極めて逆説的ですが、ワクチンを推進する米国の中にあって接種を忌避し続ける、国際色のかけらもない田舎の労働者こそが、米国の開放性を支えているのだという言い方すらできるのかもしれません。
 日本のワクチン接種証明書アプリの画面(見本)。2次元コードが表示される=2021年12月13日、東京都千代田区
日本のワクチン接種証明書アプリの画面(見本)。2次元コードが表示される=2021年12月13日、東京都千代田区同時代を生きる者として、もっとも顕著な変化であると思うのは、「命が一番大切」というイデオロギーが、「自由」や「民主主義」などにとってかわったことです。20世紀も19世紀も、血塗られた、命の犠牲の大きい世紀でした。けっして「命が一番大切」ではなかったからこそ、革命や独立戦争が起きてきたのです。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください