2022年01月14日
2021年11月、中国共産党の重要会議、第19期中央委員会第6回全体会議(6中全会)において、同党にとって3度目となる「歴史決議」が採択された。最初は1945年の毛沢東による「若干の歴史問題に関する決議」であり、ついで1981年、鄧小平の主導で「建国以来の党の若干の歴史問題に関する決議」が採択をみた。ここでは、中国の長い歴史からみた、その精神的基盤について考えてみたい。
おりしも、ロシアの有力紙「ヴェードモスチ電子版」(2021年8月3日付)に、「中国の危険性とは?:21世紀における中国の「ソフトパワー」の精神的基盤は何なのか」という興味深いタイトルの記事が公表された。考えてみると、中国と陸つづきのロシアでは、中国の脅威が現実のものと感じられた時代が長くつづいたから、ロシアにおける対中研究の蓄積は多いに違いない。そこで、ここではロシアの対中研究を紹介しながら、中国の「ソフトパワー」について考えてみたい。
「中国を眠らせておけ。中国が目覚めたとき、世界は震えるだろう」
こんな言葉を耳にしたことはないだろうか。あのナポレオンが発した言葉として有名らしいのだが、本当は後世の人がつくり出した警句のようだ(詳しく知りたい人は「「眠れる中国」とナポレオン」という記事を読むことをお勧めする)。
いずれにしても、何となく中国が大変な国であることはヨーロッパ人に意識されていた。最初に紹介したロシア語の記事では、つぎのように書かれている。
「「イエロー・ペリル」(黄禍)という言葉がドイツやフランスの新聞に登場するのは、19世紀に入ってからのことである。ロシアでは、1904年から1905年の日本との戦争に敗れた後に使われるようになり、主に日本人のことを指していた。現実の、あるいは認識されている危険性が中国に注目されるようになるまで、1世紀を要した。」
ただし、ロシアにおいては、1895年に「黄色い顔の実用主義者」という論文がドミトリー・メレジコフスキーによって書かれ、それを契機に中国への関心が高まっていた。
論文「黄色い顔の実用主義者」はインターネットで簡単に入手できる。そこで、この論文の内容を紹介し、19世紀末のロシア人が中国や中国人をどのようにみていたのかについて考えてみたい。といっても、その内容に入る前に、この論文自体の柱として引用されている、フランスの中国学の草分け的存在、ドゥアール・シャヴァンヌの1893年12月5日にコレージュ・ド・フランスで行われた講義である「中国文学の社会的役割」について書いておきたい。
シャヴァンヌは、「我々ヨーロッパ人はある種の形而上(けいじじょう)学的な概念をもっている」が、中国人はそうではないと喝破している。このあたりの問題を理解するためには、拙著『サイバー空間における覇権争奪』のつぎの記述が役に立つだろう(「終章 歴史的位相を問う」の注18, pp. 251-252)。
「古くからギリシャ人にとって「万物(タ・パンタ)」を意味してきた「自然」の外に、イデアという超自然的原理を設定し、それを参照しながら自然の存在を理解しようとする、プラトンの果たした決定的な思考様式の転回を、アリストテレスも受け継いでいると考えられる。この超自然的原理こそ、「イデア」、「純粋形相」、「神」、「精神」などと呼ばれるようになり、西洋文化形成の原動力となる。ところで、アリストテレスがプラトンのイデア論の批判的継承をやってみせた講義ノートが後世、『形而上学』[metaphysica]と呼ばれるようになったわけだが、ギリシャ語のmeta[…の後の]という前置詞に「…を超えて」という意味もあるため、「超自然学」という意味で受け取られるようになる。つまり、形而上学は現実の自然の外に何らかの超自然的原理を設定し、それに照準を合わせながらこの自然をみてゆこうとする思考様式を意味している。ゆえにプラトンの「イデア」もアリストテレスの「純粋形相」も、キリスト教神学の「人格神」も、形而上学的原理=超自然的原理の座を占めていたことになる。つぎにこの形而上学的原理=超自然的原理の座に人間理性がついたとき、近代世界が構築されることになる」
つまり、中国の思想の根底にあるのは、超自然的原理の忌避であるというのだ。そのうえで、シャヴァンヌは中国人の信条として親孝行の思想について解説している。この思想は、「息子と彼を生んだ者との間に存在する依存関係」にかかわっているが、「これと同じ関係が、同じ名前で呼ばれる、家族の生きているメンバーと、彼らの死んだ先祖の中で父系、父の血縁で結ばれているすべての人との間に存在し、国民とその父である君主との間に存在する」とまでみなされている点が肝要だ。この結果、もし身体の不調、疫病、飢饉(ききん)、洪水などがあれば、天が自然現象の最高の調整者とみなされているので、こうした現象は「親孝行が十分に行われていないことの確かな兆候」となる。あるいは、君主の「不徳」とみなされ、革命につながる。
別言すると、「親孝行とは、自然の力が規則正しく働くことを司(つかさど)る調和の法則」ということになり、「人間同士の良好な関係を司るもの」でもあることになる。自分を治めることができるようになれば、家を斉(ととの)えることが可能となり、家が斉えば国も治まるとみなすようにもなる(尾藤正英著『日本文化の歴史』)。それは、喪服の着方、挨拶の仕方といった礼儀作法の尊重といった行動様式を、世代を超えて守ることで維持される。
メレジコフスキーの「黄色い顔の実用主義者」では、この親孝行の思想が「自然の力の正しい作用と人間の間の正しい関係の両方が依存する法則」として、「歴代の人間が永遠に続く一本の鎖のようにつながっていく不思議な絆の象徴」となり、「中国の世界観の礎」となっていると主張している。
そこでは、徳を生み出す儀式や、徳のある礼儀作法への崇拝が広がり、中国古典文学への尊敬が硬直化する。それが、科挙において、受験者は古代の古典から選ばれたテキストの解説を作成し、同時に自分の文学的知識を示すというかたちで定着するというのである。
だが、これは、宋代に確立した四書五経(『大学』『中庸』『論語』『孟子』の四書と、『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』の五経)に精通した「実用的」な人が、人を治める能力が高いとみなす考え方を支配的にしただけだった。つまり、「文学、漢詩には、実用以外の目的はない」という状況に陥る。
この結果、「文字、形、肉、儀式、犠牲、利益、実用的な計算を崇拝し、不確かなもの、自由なもの、創造的なもの、動いているすべてのものを限りなく軽蔑し、自由な精神、永遠に反抗する精神の名のもとに化石化された形態を破壊する」中国人が支配的になった、とメレジコフスキーは主張している。これこそ、「黄色い顔の実用主義者」ということになる。
実用主義への傾斜は、明代以降に強まる。庶民層にも朱子学が浸透するようになった結果だろう。それは、社会状況の多様化・複雑化に伴って庶民層にも主体的に秩序を担わせる時代の必要性の反映でもあった。庶民にも修養を理解してもらい、実践しやすくするために生まれたのが陽明学だ(「松岡正剛の千夜千冊・王陽明「伝習録」」の説明が参考になる)。たとえば、読書や宇宙万物への観察を通じて、あらゆる物事に貫通しているとみなされる理を洞察し、その理を自己実現しようという「格物窮理」というテーゼは、自己に生まれつき備わっているとされる道徳性(良知)を発揮せよという「致良知」というテーゼに改変された。朱子学のうち日常道徳の実践部分に力点がおかれた結果、冠婚葬祭や日常生活の礼法が一般家庭に浸透するようになる。それが清代の「礼教」につながってゆく。
こうした19世紀末の中国人への分析をもとに、最初に紹介した「ヴェードモスチ」に公表された記事「「中国の危険性とは?」では、こうした儒教の考え方についてつぎのように指摘している。
「20世紀に入ってからは「敵対的な旋風」によって、残っていたものはすべて散ってしまったようだ。しかし、今世紀に入って、儒教は新たに人々の心をつかみつつある。最初は「影のイデオロギー」であった儒教が、時が経つにつれて日の目を浴びるようになってきた。」
まず、その魅力になっているのは、さまざまなかたちで良識を説くこと、正直さ、礼儀正しさ、相互の親しみやすさ、誠実さ、両親や、年齢ないし立場の異なるすべての年長者への敬意といった教えにあるとしている。そして、こうした考え方の根底には、「土地への愛着がある」という。こうした価値観は外国であっても受け入れられる余地が十分にあるから、それが中国の覇権を広げるための「ソフトパワー」となりうるかもしれないのだ。
記事では、「中国において儒教が公式にはまだ捨てられていない共産主義のイデアと共存している理由を理解できる」と記されている。「どちらのコンセプトも、人々が小さなことで立ち止まるのではなく、「より大きな幸福に向かって」導いてくれる完璧な社会をめざしている」と指摘している。
どうやら、イデアという形而上学的な概念をあまり気にかけない儒教思想は共産主義思想に寛容らしい。あるいは、中国共産党自体が儒教を攻撃しなくなっている。
ここで、1993年にフーブラー夫妻(Thomas & Dorothy Hoobler)によって書かれたConfucianismの日本語訳(『儒教』)をみると、毛沢東は反儒教キャンペーンを展開し、「妻を夫に隷属させ、家族を虐待する両親の権威を認めた孔子の倫理は、「奴隷根性」といわれた」のだという。だが、毛沢東には、「自分自身を儒教の理想的な支配者に見立て、皇帝のように振る舞うことが少なくなかった」と指摘している(「皇帝」については、下の「閑話休題」を参照)。そのうえで、『毛沢東語録』が「五経」にとって代わり、「毛沢東中国の官僚になろうとすれば、科挙の受験者が「五経」をそらんじたように毛沢東の著作をそらんじなければならなかった」とのべている。
1976年に毛沢東が亡くなると、儒教への攻撃は停止された。こうして、「歴史上の重要人物であり、偶像化もしなければ非難もしないというのが、共産党による孔子の新しい位置づけ」となったという。
ただ、習近平が中国の皇帝としてふるまいはじめていることに注意しなければならない。拙稿『サイバー空間における覇権争奪』では、つぎのように書いておいた。
「中国共産党中央宣伝部は2019年1月から「学習強国」というスマートフォン用アプリを配信しはじめた。習近平総書記(国家主席)の思想や政策を学ぶための情報サイトだが、「学習」には「習氏に学ぶ」という意味も込められている。党は大学や地方政府に呼びかけて同アプリの利用を推進している。これは思想統制を強化するねらいがあり、毛沢東が「毛沢東語録」を使って個人崇拝に利用したことを彷彿(ほうふつ)とさせる。すでに2019年4月現在、1億人以上がこのアプリのユーザー登録を終えている。
公務員や学生にはアプリへの登録が義務づけられている。アプリは習の経済政策に関するクイズにすべて正解すれば10ポイントがもらえるといったポイント制をとっており、アプリに頻繁にアクセスしなければポイントが増えず、その結果、点数の低い公務員や学生が自己批判を迫られるといった弊害がすでに起きている。」
2021年8月末のThe Economistによれば、「中国には現在、18の習思想研究センターがある」。多くは、政治・文化・科学・教育・宗教・外交・国家安全保障など、特定のテーマに焦点を当てるもので、7月には「習近平経済思想」を研究するための新しいセンターが設立された。こうした一連の動きは2017年に中国共産党第19回全国代表大会で導入された「新時代の中国的特徴を持つ社会主義に関する習近平思想」(习近平新时代中国特色社会主义思想)を、より有力な「習近平思想」に短縮することをねらっている。つまり、「毛沢東思想」にならぶ「習近平思想」を打ち立てることで、「皇帝=毛沢東」ならぬ「皇帝=習近平」をめざしているのだ。
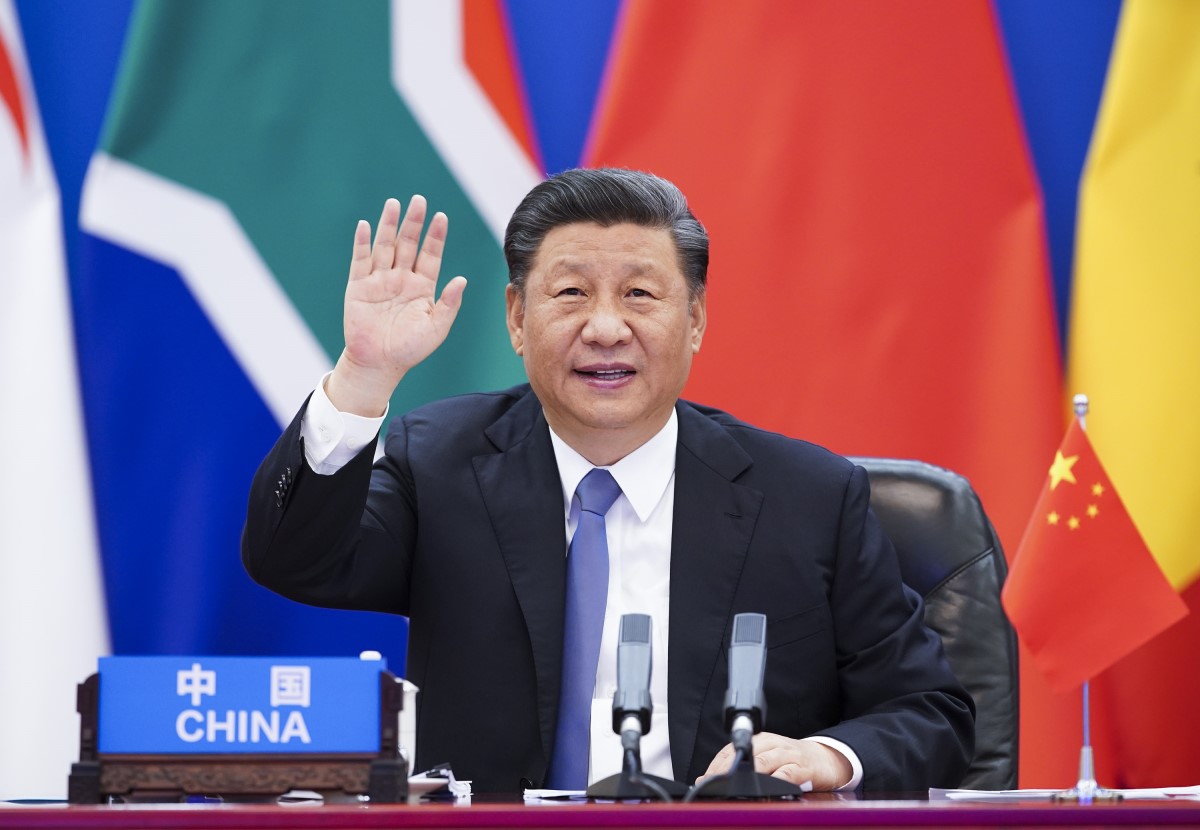 習近平・中国国家主席=新華社
習近平・中国国家主席=新華社閑話休題 「皇帝」って何」
ここで、中国の「皇帝」について考えてみたい(詳しくは拙著『官僚の世界史』を参照)。まず、秦帝国以後、「法」(法といっても、これは信賞必罰のことを意味している)を重んじるイデオロギーが広がったことが重要である。殷、周、春秋・戦国時代を経る過程で、「天」の意を占いによって読み解く者としての、天子による祭政一致の神権政治が払拭(ふっしょく)されたのである。
商の時代には、天上の空にいる(先祖の)神様を「帝」と呼び、それを周の時代に「天」と呼ぶようになったのだが、周代において、天空の支配者と人間界の支配者が明確に分離するようになり、祭政分離に向かったと考えられる。天にも中心があり、天命を受けて支配する皇帝は、真北を背にして立たなければならない。北極星を背景にして立ったとき、皇帝は天子と認められるのである。恒星が北極星を中心に回転しているように見える以上、北極星と天子の位置を重ねわせることが必要なのだ。
この祭政分離は、君主が絶対者たる「天」の委任によって人民のために人民を支配する存在としての「天子」であるとする孟子の考えを否定し、君主や王といった支配者こそ真っ先に法に従うべきだとする法家の思想の普及を意味している。この結果、官僚は皇帝という人格ではなく、法という非人格的超越的視点に従うことを促すことになる。だが、法家の過激な思想は秦の滅亡によって定着しなかった。その代わりに生まれたのが董仲舒によって再編された儒学であり、それが漢の武帝によって国教化されることになる。
皇帝は徳の高い人物として、徳のない人々を教化する。中国では宋代に入ると、天子が天子でいられるのは単に受命者の子孫だからではなく、自分自身がすぐれた人格者だからなのだという見方が有力になる。個々の皇帝たちがそれぞれに天の「理」に適(かな)っているからこそ、皇帝となったとみなすのである。そこには「神」という実体とかけ離れた天子が想定されているだけで、「神はいない」といってもいい。つまり、超自然的原理は中国では働いていない。
中国においても、天子としての皇帝は「聖なる権威」と「俗なる権力」を一元的に結びつける存在であるのだが、いわば政治家にすぎず、宇宙の原理をつかさどる究極の原因とはなりえないのだ。こうしたなかからは、自然をつくり出した神の計画を知るための科学が育たない。天子といえども、皇帝は必ず死ぬから、究極の原因への関心は薄くなる。この結果、中国は近代化が遅れ、現在、世界を支配している西欧的価値観からはかけ離れた状況におかれてしまう。
儒教が生き残った背後には、中国の周辺国に生きる華人(国籍を問わない民族としての中国人ないし居住している国の国籍を持つ中国系住民)たちが儒教を尊重してきたことがある(「華人」をめぐっては、拙稿「政治だけではない中国共産党の経済問題:東南アジアにおける華人支配」を参照)。
たとえば、台湾では孔子の誕生日(新暦の9月28日)を2016年まで「教師節」として祝祭日としてきた。「この国家的な祭日は、すべての教師がこの「万世の師」の偉大な伝統の伝達者として讃(たた)えられ、島内の多数の孔子廟で明代以来の踊りも含む特別の祭祀(さいし)が執り行われる」と、紹介したフーブラー夫妻著『儒教』に紹介されている。2017年以降、法定祝祭日ではなくなったが、「教師節」のお祝いはつづいている。
フーブラー夫妻は儒教の可能性をめぐって、「秩序ある社会、自然と人間の均衡、親切、慈愛、正直、誠実に身を処す方法」という点で、儒教は道徳的な力を秘めているという。
こうみてくると、儒教は儒教なりにソフトパワーとして影響力を行使できることになる。このソフトパワーを全世界に波及しようとしたのが、「孔子学院」であった。
2004年、中国政府は世界中の大学キャンパスにある孔子学院のスポンサーとなり、教師、教科書、運営資金を提供してきた。孔子学院は中国語・中国文化のセンターであり、世界各地の大学キャンパス内などに、一時期、1000以上の施設が設置されていた。最近まで、中国教育省の機関である「漢語」(ハンバン)が孔子学院を監督していたが、孔子学院への批判の広がりの後、中国政府は新しい組織、中国国際教育財団のもとに孔子学院を再組織化した。たとえば、米国務省は2020年8月中旬、孔子学院米国センター(CIUS)を中国政府の「在外公館」に指定し、「米国のキャンパスや幼稚園の教室で北京のグローバルなプロパガンダと悪意ある影響力キャンペーンを推進する団体」として同組織を非難していた(「ワシントン・ポスト電子版」を参照)。
米国では、ナショナル・アソシエーション・スカラーズの調査によると、一時、2017年に103校だった孔子学院数が2021年8月13日現在、38校にまで減少した(閉鎖が予定されている八つの施設も含まれている)。米国の大学内にある孔子学院の数は32校が確認されているという。
 中国アフリカ協力フォーラムの閉幕後、記者会見をする習近平国家主席(中央)=2018年9月
中国アフリカ協力フォーラムの閉幕後、記者会見をする習近平国家主席(中央)=2018年9月2021年7月14日付の「ワシントン・ポスト電子版」は、中国のアフリカ研修プログラムを研究している、ジョージア州立大学の政治学者、マリア・レプニコワへのインタビュー記事を掲載している。そのなかで、彼女は、「私が調べた資料では、中国共産党の統治が中国に適した唯一の統治システムであるとし、その民主的な特徴を強調している」としている。この研修では、政治的な側面以外にも、中国の経済的な成果を、圧倒的な数の統計データを使ったスライドで学び、高速鉄道や巨大都市、再開発された村など、経済発展を象徴するものも含めて、中国の魅力に触れることができるのだという。これらの研修には、中国のホスピタリティと寛大さを示す完璧なツアーが含まれており、豪華な宿泊施設や宴会料理で「中国のベスト」を体験することができ、「参加者は、近代化や都市化のレベルだけでなく、ホストの独特の労働倫理や組織力にも感銘を受け、もっとも印象深いツアーとなる傾向がある」としている。
このように、中国は、軍事力や経済力といったハードパワーへの対中警戒感の高まりのなかでも、儒教によって培われてきた中国文化というソフトパワーを何とか世界に広めようとしている。このとき、中国にとってのキーワードは「秩序」ではないか。
2010年末以降、チュニジアから始まった、欧米ジャーナリズムが勝手に「アラブの春」と名づけた一連の民主化運動は結局、中東での秩序を破壊した。民主主義を輸出しようとしても、受け入れる国に諸条件が整っていなければ、秩序が崩壊し、惨劇が起きるだけであることはこの「アラブの春」が教えてくれた(「中東の民主主義の不満点」というFTの記事を参照してほしい)。そう考えると、「秩序」を守ることは一概に否定できない。だからこそ、儒教的なソフトパワーが多くの権威主義的な既存権力に利用されてしまう。
ただし、そのためには、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください