主要国は軒並み不安定な情勢。岸田政権のオミクロン対策にかかっている
2022年01月16日
 岸田文雄首相=2021年12月23日、東京都港区、代表撮影
岸田文雄首相=2021年12月23日、東京都港区、代表撮影2021年、米日独と民主主義陣営の主要3か国で新政権が発足した。2022年、仏日米の3か国で選挙が行われる。政権交代も選挙も、結果次第では政治が不安定化する。実に、2021年、22年は、民主主義陣営にとり政権基盤が安定を欠く2年といえる。
 G20オンライン会合に出席した岸田文雄首相=2021年10月12日、内閣広報室提供
G20オンライン会合に出席した岸田文雄首相=2021年10月12日、内閣広報室提供国際政治の中、日本の参議院選挙はいかなる意味を持つか。
 閣議に臨む第2次岸田内閣の閣僚。中央は岸田文雄首相=2021年11月10日、首相官邸
閣議に臨む第2次岸田内閣の閣僚。中央は岸田文雄首相=2021年11月10日、首相官邸上記、民主主義陣営4か国のうち、米独の足元は盤石でない。
米国は、インフレが高騰し、国民の懐を直撃する。当初、一時的と見ていたFRBも、そうも言っていられなくなってきた。テーパリングの前倒しや金利引き上げでどこまでインフレを抑え込めるか、これからがまさに金融政策の正念場だ。
バイデン政権が華々しく打ち上げた大型法案の内、1兆ドル(約110兆円)のインフラ投資法は何とか成立したが、子育て支援や気候変動対策を含む1.75兆ドル(約200兆円)の歳出歳入法案は、未だ成立の見通しが立たない。議会で法案一つ通せないとあっては、バイデン政権の威信も揺らがざるを得ない。インフレの高進と法案成立の停滞でバイデン政権の人気は湿りがちだ。
加えて、ここに来てオミクロン株が猛威を振るう。一日当たり新規感染者数140万人超はにわかに信じがたい数字だ。11月の中間選挙までに、バイデン政権が、この「三重苦」を克服し支持率を回復させられるか、予断を許さない情勢が続く。
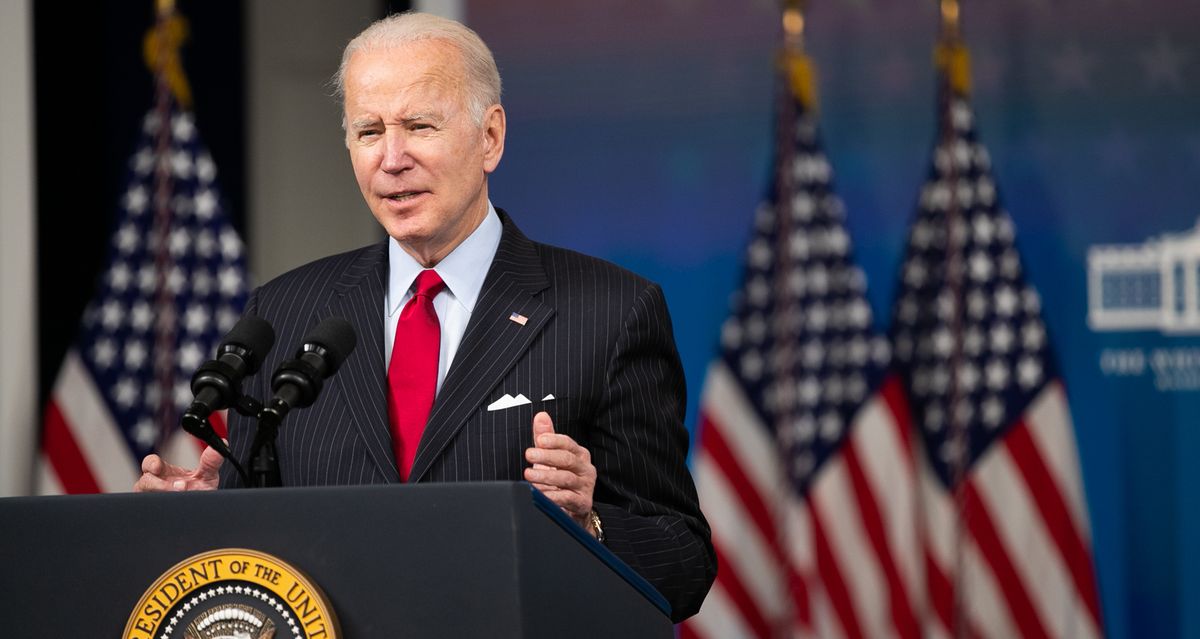 バイデン米大統領=2021年11月23日、ワシントン
バイデン米大統領=2021年11月23日、ワシントン民主党の敗北はすなわち共和党の勝利だ。その共和党は、依然トランプ氏の影が色濃く及ぶ。世界はここに来て「2024年トランプ氏復活」もあり得る、と考え始めた。それは権威主義体制側も含めてのことだ。
トランプ氏支持者の議会乱入事件以来、米国の民主主義は危機に瀕しているが、そのトランプ氏が戻ってくるのだろうか。2024年以降、米国は一層頼りにならない存在に堕す可能性がある。
 トランプ前大統領は退任後も全米各地で集会を続けている。「TRUMP2024」と書かれたTシャツを着て集会に参加する支持者=2021年6月26日、オハイオ州ウェリントン
トランプ前大統領は退任後も全米各地で集会を続けている。「TRUMP2024」と書かれたTシャツを着て集会に参加する支持者=2021年6月26日、オハイオ州ウェリントンドイツは、メルケル氏が抜けた穴は大きかった。メルケル氏に対しては「変革を回避し、専ら現状維持に終始した」との批判はあるが、その調整能力に異を挟む者はなく、メルケル氏のお陰でEUは結束しその存在感を高めることができたことは否定しがたい。そのメルケル氏が抜けた。
代わって誕生したショルツ新首相は複雑な3党連立の上に乗る。問題は、3党は連立に合意したものの同床異夢の面が少なくないことだ。環境やデジタルで積極財政を志向する緑の党に対し、自由民主党(FDP)は財政規律重視の立場であり、容易に財布のひもを緩めようとしない。自由民主党のクリスティアン・リントナー党首は財務相に就任、野放図な支出に目を光らせようと構える。
対露政策は、ウクライナ危機で、早くもショルツ首相の手腕が問われる事態になったが、同首相が属する社会民主党(SPD)はロシア・シンパが多く対露宥和的であるのに対し、外相に就任した緑の党のアンナレーナ・ベーアボック氏は基本的に対露強硬派だ。
 オラフ・ショルツ独首相=2021年12月16日(Alexandros Michailidis/shutterstock.com)
オラフ・ショルツ独首相=2021年12月16日(Alexandros Michailidis/shutterstock.com)
 岸田文雄首相と「チーム岸田」の総理秘書官ら=2022年1月6日、首相官邸
岸田文雄首相と「チーム岸田」の総理秘書官ら=2022年1月6日、首相官邸米独が今一つ安定に事欠く中、世界の注目は仏日両国に集まる。
フランスは4月に大統領選挙を控え、今のところマクロン大統領の優勢が伝えられるが、中道右派のペクレス氏が猛烈に追い上げており、情勢は予断を許さない。仮に、マクロン氏が勝利しても僅差だろうとされる。
 マクロン仏大統領=2021年10月22日
マクロン仏大統領=2021年10月22日岸田政権はこれまでのところ無難な船出となった。18歳以下への10万円給付、外国人の新規入国や3回目のワクチン接種、受験に際しての濃厚接触者の扱い等、政策が突然変更される例が相次ぎ、「方針がぶれる」との批判を受けたが、有権者は総じて好意的なようだ。支持率は上がっている。岸田総理がいう「聞く力」、つまり、国民の声に耳を傾ける姿勢が国民に好感されているのだろう。
 【左】衆院選で、岸田文雄首相は有権者の声を書き留めてきたという「岸田ノート」を手に各地で演説した=2021年10月22日、北海道旭川市【右】首相の街頭演説に集まった人々=2021年10月23日、福岡市
【左】衆院選で、岸田文雄首相は有権者の声を書き留めてきたという「岸田ノート」を手に各地で演説した=2021年10月22日、北海道旭川市【右】首相の街頭演説に集まった人々=2021年10月23日、福岡市尤も、菅政権の場合、最大の問題は別にあった。その強権体質が人事面に顔を出したことだ。強権体質自体は功罪両面あり、政策実行のためには強権も必要だ。しかし、学術会議人事にせよ検事長人事(菅氏は官房長官として関与)にせよ、強権が人事面に発揮されれば、何やら危うさを感じざるを得ない。暗黒政治まがいの強引さがこの政権にはあった。
これに対し岸田政権の場合、公家集団と揶揄されひ弱なイメージが付きまとうが、少なくとも暗黒政治を伺わせるような危うさは見受けられない。この安心感は大きい。「ぶれ」は大きくとも「危うさ」がない方がいいということだ。
 自民党の岸田文雄総裁が新首相に選出され、各党への退任あいさつのため衆議院の廊下を歩く菅義偉首相=2021年10月4日、国会
自民党の岸田文雄総裁が新首相に選出され、各党への退任あいさつのため衆議院の廊下を歩く菅義偉首相=2021年10月4日、国会岸田氏の場合、ひ弱さが拭えないのは事実としても、単なるひ弱といえない面もある。総裁選立候補の際、「二階氏に喧嘩を売った」ことで勝利の活路が開けた。権力奪取は時の権力者に挑戦状をたたきつけるのが正道だ。最強の権力者に挑戦し勝利を勝ち取った時、権力は挑戦者の手中に転がり込む。
これでコツをつかんだか、その後、外国人の入国禁止に際し「慎重すぎるとの批判は全て自分が負う」と一歩踏み込んだ。岸田氏の場合、この強さが必要だ。間違ったら後で直せばいいぐらいのつもりで思い切ってやれば、国民受けもしよう。もし、岸田氏が力強さを身につけていくようなら大化けの可能性もないではない。
 岸田文雄首相が大阪でのオミクロン株の市中感染について会見するニュースが流れる中、繁華街を行き来する人たち=2021年12月22日、大阪市北区
岸田文雄首相が大阪でのオミクロン株の市中感染について会見するニュースが流れる中、繁華街を行き来する人たち=2021年12月22日、大阪市北区これまでのところ岸田氏のパフォーマンスは悪くない。では、今夏までこの調子で行けるか。当面する最大の試練はオミクロン対策だろう。既に市中感染が広まり、国民はその急拡大に困惑を隠せない。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください