2022年01月28日
パンデミックは世界中の人々に人生について考えさせる契機をもたらしている。たとえば、「You only live once」(人生は一度きり)の略語であるYOLOという言葉が2021年4月21日付の「ニューヨーク・タイムズ電子版」に、「YOLOエコノミーへようこそ」という記事に登場するようになっている。YOLOだからこそ、いまの仕事を顧みて短い人生をやり直すことを問う動きが広がっているのだ。
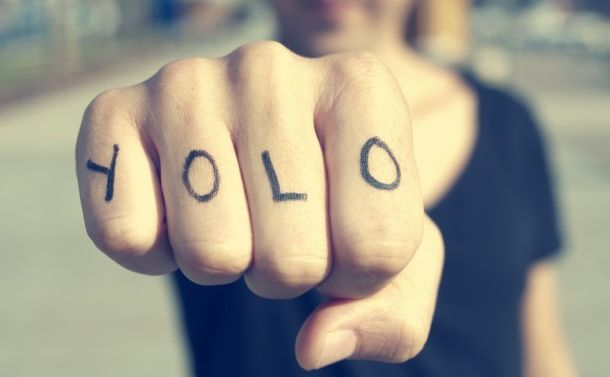 shutterstock.com
shutterstock.com日本でも、2021年7月4日付の「日本経済新聞電子版」の記事「雇用流動化、若者けん引 3年内離職率が10年で最高」において、「異業種から流入が多い業種はIT通信で、電機メーカーや金融などから人が集まる。リモートワークの拡大で住宅需要が堅調な建設・不動産は電機メーカーや外食、商社からの転職が多い」と指摘している。
そう言えば、2021年9月9日に開かれた経済同友会のオンラインセミナーで、サントリーホールディングスの新浪剛史社長が「45歳定年制」を提言したことが話題になった。45歳を定年であると「脅せば」、20代・30代の若者はもっと真剣に勉強するはずだというのが新浪社長の目論見(もくろみ)であったようだが、テクノロジーの急速な変化を前提とすれば、その変化に追いつけない人物はいらないと企業が考えてもおかしくない。あるいは、社員の側がテクノロジーの変化に鈍感な企業から逃げ出すのは至極当然だろう。
2020年10月にリリースされてヒットした、Adoの期間限定シングル「うっせぇわ」の歌詞も、いまの時代の気分を先取りしていたように思われる。「一切合切凡庸な あなたじゃ分からないかもね」という部分に、「あなた」という上司がたとえマヌケであっても、立てなければならない「不条理」に新入社員の行き場のない「怒り」を語っているようにみえる。
いわゆるデジタルエコノミーへの転換が急速に進むなかで、会社でも学校でも、こうしたテクノロジーの進化に追いつけない多くの「上司」がいると想像できる。にもかかわらず、こうした人々は偉そうにふんぞり返って、いろいろな初歩的な頼み事をしてくる。
本来であれば、こうしたデジタルスキルに劣った人々に対しては、教育を通じたスキルアップが必要なのだ。ところが、企業に余裕がなかったり、本人にやり気がなかったり、さまざまな理由から、こうした訓練の場が不足している。その結果、「うざい上司」が放置され、職場の雰囲気も停滞したままになる。とくに、日本の企業では、こうした閉塞(へいそく)感が広がっているのではないかと危惧される。
パンデミックはこうした「退廃した」職場から逃れる機会を多くの人々に提供した面がある。経済学者のポール・クルーグマンは、「昔の仕事を昔の条件でやりたくないと思う労働者たち」という記事を「ニューヨーク・タイムズ電子版」(2021年8月23日付)に掲載している。パンデミックはいわゆるテレワークを強いるなどの混乱を仕事にもたらしたが、そうした仕事の混乱が労働者にとっていい学習の機会になったというのだ。
具体的に言えば、「幸運にも自宅で仕事をすることができた人の多くは、通勤するのがいかに嫌だったかを実感し、レジャーやホスピタリティ関連の仕事をしていた人のなかには、数カ月間の強制的な失業期間中に、以前の仕事がいかに嫌だったかを実感した」はずだから、パンデミック後に従来の雇用がそのまま元に戻ることはない。ゆえに、「人手不足」という現象が一時的に広がることになる。
だが、クルーグマンは、「最近の「人手不足」の背景には、このような事情があるとすれば、それは問題ではなく良いことだ」と主張している。
これはあくまで米国での話だが、日本でも経営者がしっかりと労働者の心に寄り添わなければ、転職したり大学院で学んだりするかたちで多くの従業員が逃げ出しかねないのではないか。
 ビジネスセミナーに参加する企業人=Fractal Pictures/shutterstock.com
ビジネスセミナーに参加する企業人=Fractal Pictures/shutterstock.comこの二つについて論じる前に必要なのは、自らの愚かさに気づくことである、と指摘しておきたい。自分がバカであるからこそ、学び直さなければならないと痛切に感じ、それが新たな学びへの強いインセンティブになるはずだからである。
2021年6月に刊行された「OECD Skills Outlook 2021」によると、成人技能調査(PIAAC)でインタビューを受ける前の12カ月間に仕事に関連したフォーマルまたはノンフォーマルなトレーニングに参加した人の割合を国別にとってみると、平均して成人の5人に2人(40%)しか参加していない。「ギリシャ、イタリア、メキシコ、トルコでは成人学習に参加したことがあると回答した成人は25%未満であるのに対し、デンマーク、フィンランド、ニュージーランド、ノルウェー、スウェーデンでは55%を超えている」という。日本はOECD平均の約40%を下回っている。チリやスペイン並みにすぎない。
日本のこうした残念な結果の背景には、学びたい意欲はあっても、学びの場がないとか、学びへの理解が不足しているといった事情があるのかもしれない。そこで、「国別の研修への意欲と成人学習への参加を特徴づける学習者プロファイル」をみると、ノルウェーとオランダでは、25歳から65歳までの成人の39%と37%が成人学習に従事し、現在の参加レベルに満足している一方、ギリシャでは成人人口のわずか10%しかいない。
OECD諸国のなかで、成人学習に参加していないがトレーニングを受ける意思がある成人の割合が最も大きいのは韓国(18%)である。残念ながら、日本は韓国の半分にも達していない。つまり、自分の愚かさにも気づかないまま、のんべんだらりと生活するだけの成人が多いのだ。現に、成人学習に参加していないし、参加したくもないという割合は日本のほうが韓国を上回っている。こうした「バカ」どもが会社にのさばり、若い社員のストレスになっているのではないか。ゆえに、「うっせぇわ」と叫びたくなるわけである。
いまでも終身雇用にしがみつこうとする人が多いとは思えないが、実際には、年功序列や終身雇用の残滓(ざんし)があり、それが学習意欲の減退につながっているのかもしれない。ただ、このOECD報告では、「COVID-19(新型コロナウイルス感染症)の危機により、デジタル、リモート、スマートな働き方が広く採用されるようになったことで、個人がデジタルスキルを習得する必要性が生じた」と的確に指摘している。そうであるならば、ますます「学び直し」の必要性に気づかなければならない。
有名な世界経済フォーラムでは、2018年から3年連続で「リスキル革命」と銘打ったセッションを行ってきた。2020年のフォーラムでは、「2030年までに10億人の人々に新たな機会を提供する」ためのリスキル革命が議題となった。こうした問題意識には、人工知能(AI)の進化などによる「第四次産業革命」によって、雇用市場において、「1億3300万の新しい役割が創出される一方で、これらの新技術によって7500万の仕事が奪われる可能性がある」という、2018年の同フォーラムの予測がある。
リスキル革命はAI化などのテクノロジーの発展を前提としている。そうした再教育に際しては、「将来最も急速に成長する職業に焦点を当てることがとくに重要になる」ことから、世界経済フォーラムでは、「ケア、エンジニアリングとクラウドコンピューティング、セールスマーケティングとコンテンツ、データとAI、グリーンジョブ、人材と文化、専門的なプロジェクトマネージャー」という七つの専門分野で多くの雇用が増加するとみている。
この予測が当たるかどうかにかかわらず、著しいテクノロジーの発展によって、大きな変化が訪れることが確実な以上、少なくとも米国ではリスキリングを重視する動きが広がっている。
2018年7月19日、ドナルド・トランプ大統領(当時)は「米労働者のための国家評議会」を設立する大統領令に署名し、「米国労働者への誓い」を開始した。「我々の国はスキルの危機に直面している」という基本認識にたって、当時、「670万件以上の未充足の仕事」があるとの立場から、「生涯学習とスキルベースのトレーニングの環境を整え、需要に応じた労働力開発のアプローチを育成しなければならない」と、トランプは考えたのである。そのために、需要の高い産業で必要とされる労働者を訓練・再訓練するための国家戦略を策定するための機関を設置すると同時に、企業や団体にこうした機会をあたえることを誓約してもらい、労働者への訓練・再訓練を推進しようとしたのだ。
1年後の2019年7月25日、ホワイトハウスは「米国労働者への誓い」の1周年を祝った。その段階で、300以上の企業・団体が誓いに署名していた。署名企業は米国の学生や労働者に新たな機会を提供することを約束したことになるが、それはあくまで口約束にすぎず、法的な枠組みがあったわけではない。ゆえに、トランプが大統領選で敗北したことで、同評議会そのものが2020年9月23日を最後に開催されていない。
革新的なのはスウェーデンだ。2021年6月、スウェーデンのエヴァ・ノルドマルク労働大臣は、国会・政府に対し、スウェーデン労働法の改革案を提示した。この改革では、同じ会社で8年勤務した後に1年間教育・訓練に参加する権利が与えられる。このとき、給与の最大80%が支給されるという極めて画期的な内容となっている(ただし、教育訓練は本人の選択によるものではなく、雇用に貢献するものでなければならない)。同年11月には、ブルーカラー労働組合連合(LO)の指導部は労働法改正に関するスウェーデン企業同盟との協定に合意するよう、同組合の総評議会に勧告することを決定したという。
企業レベルでみると、マイクロソフトが2020年から世界中でGlobal Skills Initiativeを開始するなど、デジタルスキルの向上支援サービスの提供が広がりつつある。日本でも、同年12月からマイクロソフトのサービスがはじまった。①COVID-19 の影響で職を失った者、②新たにデジタルスキル取得をめざす者、③新卒学生――などを対象に、IT スキルに加えて、関連するコミュニケーションスキルなどの習得支援が実施されるようになっている。
 オンライン教育でスキルアップ=airdone/shutterstock.com
オンライン教育でスキルアップ=airdone/shutterstock.com2021年2月に公表された、リクルートワークス研究所の石原直子主幹研究員の「リスキリングとは」によると、日本国内では、たとえば、日立製作所は国内グループ企業の全社員約16万人を対象に、DX基礎教育を実施するというかたちで、リスキリングに取り組む(DXについては、拙稿「デジタル・トランスフォーメーション(DX)は世界の潮流」を参照)。富士通もDX化に呼応した企業内部の変革のためにリスキリングを重視する。
2021年12月21日に公表された「ヤフー、全社8000人を先端IT人材に 再教育で転換」という記事によれば、2023年度までに全社員約8000人を再教育し、業務で人工知能(AI)を活用できるようにするという。
すでに、日本にもトレノケートホールディングスというIT人材育成の専門企業もある。
とはいえ、会社が独自に社員教育の一環として、本格的なリスキリングに取り組むケースは決して多いとは言えない。そうなると、最初に紹介した第二の方法、すなわち、会社を辞め、学校で学び直すという選択肢が気にかかる。いわゆる「リカレント教育」は、一生涯にわたって教育と就労のサイクルを繰り返す学習制度のことであり、自分の人生をより柔軟に過ごす方法として十分に考慮に値する。
ところが、日本の場合、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください