2022年フランス大統領選はこう見ると面白い【1】日本のソフトパワーの視点から
2022年02月09日
4月の選挙に向けて、選挙ムードが高まってきたフランスの大統領選について、日本に与える影響という視点から考える連載「2022年フランス大統領選はこう見ると面白い」。前回の「防衛・安全保障」(「不安定で緊張高まるインド太平洋 関係を強化すべき欧州の国は?~仏大統領選を読む」)に続いて、今回は「日本のソフトパワー」の視点から大統領選をとらえてみたい。
古くから日本文化のよき理解者として、これを世界に発信してきたフランス。その国のトップであり、世界的にも強い影響力を持つ大統領が、親日派、あるいは知日派なのか、その逆なのかは、日本人にとって気になるところだ。これにより、世界における日本のイメージが大きく左右される可能性があるからだ。
本稿では、9人の有力候補者中、誰が日本との関係が深いのかも含めてお伝えするが、その前に前回同様、冒頭に選挙戦の現況をお伝えしてから本題に入る。
 andriano.cz/shutterstock.com
andriano.cz/shutterstock.com選挙戦の状況(2022年2月1日現在)
1月27日現在、45人(男32・女13)が出馬を表明し候補者条件である500人以上の議員推薦の獲得に動いている(リベラシオン紙)。
この45人のプロフィールは実に多様だ。国務大臣経験者やトランスジェンダーの女性市長も含む国・地方・EUの政治家はもとより、ジャーナリスト、農業生態学者兼大工、中学の数学教師、動物主義党の共同代表兼弁護士、ムスリム系政治団体の主宰者、21歳の学生、23歳の女性環境活動家、警察官、空軍大将、コンピュータエンジニア、起業家、哲学者、鉄道員でツイッター帝王、Youtubeで歌いながら出馬を表明した元教師、元フォード工場労働者等が顔をそろえている。
正式な候補者リストは、3月7日に公表予定だ。従って、それまでは新規の出馬表明者(マクロン現大統領含め)や辞退者も予想され流動的だが、最近の複数の世論調査や専門家の分析から現時点で有力候補とされるのは次の9人となる。
エマニュエル・マクロン(中道・共和国前進)、マリンヌ・ルペン(極右・国民連合)、ヴァレリー・ぺクレス(中道右派・共和党)、エリック・ゼムール(極右・再征服)、ジャン‐リュック・メランション(急進左派・不服従のフランス)、ヤニック・ジャド(中道左派・ヨーロッパ・エコロジー=緑の党)、クリスチャーヌ・トビラ (左派・無所属)、アンヌ・イダルコ(中道左派・社会党)、ファビアン・ルセル(フランス共産党・急進左派)
今から150年以上前、1867年(慶応3年)3月7日にパリに着いた渋沢栄一は、パリ市内の諸施設やパリ万国博覧会の視察を皮切りに、西洋近代経済社会の修学の旅をスタートした。
時を同じくしてフランスでは、逆に日本を理解し学ぼうとする文化的潮流が生まれていた。「日本趣味」と訳されるジャポニズムだ。モネ、セザンヌ、ゴッホ、ゴーギャンをはじめとする多くの画家が、浮世絵や陶器の絵柄など日本の美術品に感化され、それを自らの作品に取り入れた。
では、ジャポニズムの実践者たる彼らは、極東から運ばれてきた日本の芸術を、どのような目線や態度で捉えていたのだろうか?
米国の文学研究者エドワード・W・サイードは、1978年の著書『オリエンタリズム』で、18世紀以降に使われたオリエンタリズムは、一方的、傲慢で差別的なものであるとしている。植民地主義や帝国主義を背景に、西洋(支配者、特に欧州)の立場から、東洋(被支配者、特にアラブ世界)を上から目線で捉えたものであるという。
確かに、アカデミアの世界では、ジャポニズムで注目された日本の芸術作品も、サイード的な見方をされていたとの指摘もある(ノックリン1987)。ただ筆者は、一部の市民はそうだったかもしれないが、多くはこうした見方をしていなかったであろうと思う。少なくともジャポニズムの実践者たる芸術家や収集家たちは、上から目線ではなく、むしろ、一定の敬意をもって日本文化を捉えたのではないだろうか。
だからこそ、19世紀後半の日本趣味は一過性で終わることなく、20世紀に入ってからも、パリから日本文化が欧州各地、そして世界に発信されたのだと思う。
例えば、日本帝国は1900年のパリ万国博覧会に合わせて美術史の集大成 “Histoire de l'art du Japon”を編集した。これにより、主に飛鳥、白鳳、天平の仏教美術が世界に発信された。また1929年5月には、世界から学生や研究者が集まるパリ国際大学都市に、日本館(Maison du Japon、正式名称「パリ国際大学都市日本館ー薩摩財団」)が建設され、当時のガストン・ドゥメルグ大統領臨席のもと竣工式が行われた。これは、駐日フランス大使だった詩人・劇作家のポール・クローデルの提唱で、実業家の薩摩治郎八氏が私財を投じて実現したプロジェクトであった。
その後、先の大戦をはさんで戦後も、パリは日本文化を世界に発信し続けてた。、だが、90年代前半までは、限定的で線も細かった。日本文化に関心のある人は、旅行や在住で日本を知る人、日本関連のビジネス経験者、一部の学者、文化人、柔道関係者など限られていた。多くの一般市民の眼に映る日本は、70年までは発展途上国、80~90年前半は新興国、であった。
特に90年前後のバブル期には、日本企業が大挙して進出した。ジャパンマネーが、フランスの文化や産業を象徴するようなシャトー等の不動産、企業、美術品などに投資された。日本人観光客が、団体で大挙して押し寄せ、免税店や高級ブランド店で商品を買いあさる。それとともに、「KAROSHI」など過酷な労働環境で働く企業戦士を伝える報道も目立っていた。
当時の多くのフランス人にとって、新興国・日本は、経済を軸にした三つの顔を持つ国であった。「経済的に取り込んでおきたい金づる」、「新興の成金族」、そして「自分達とは不均衡な労働条件で、しかも安く質の良い製品でもって経済戦争をしかけてくる脅威国」の顔だ。
こうした日本の姿はフランス国内に経済的脅威論も惹起し、政界からも日本に対する批判の声が上がった。ミッテラン政権下で1991~92年に同国初の女性首相となったエディット・クレソン氏の発言は、その代表例だ。
同氏は、日本人について、狭いアパートに住み、2時間の通勤時間をかけ、あくせく働くとして、ヨーロッパとは不釣り合いな労働生活を送る「黄色いアリ」にたとえる発言をした。しかも、タイムズ誌(1989年)、ABCニュース(1991年)など国際メディアを通じてのものだった。従って、世界的なインパクトも大きく、瞬く間に日本にも伝えられ、日本人から大反発をくらった。
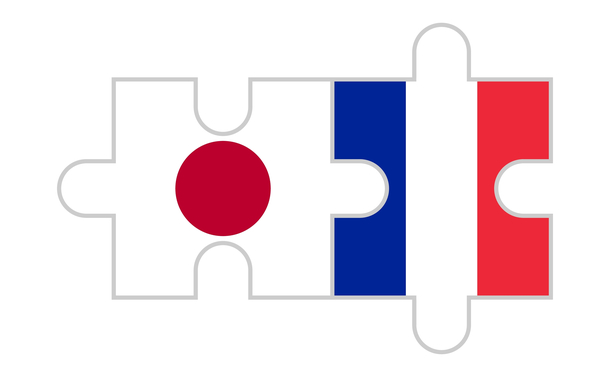 Sakchai.K/shutterstock.com
Sakchai.K/shutterstock.com筆者は、バブル崩壊後の1996年にフランスに移住した。それから25年になるが、この土地は個人的に住み心地がいい。複数の理由があるが、そのひとつに、肌感覚ではあるが、日本(人)に好意的な人たちが多いというのがある。日本の文化に一目置いて憧憬の念を抱く人も増えている感がある。
その背景には、90年代後半あたりから、一般市民が、日本の文化に触れる機会が増えことがある。特に、2000年代に入り、伝統文化からポップカルチャーまで日本文化の民主化が加速する。それまでは限られた人たちに限られていた日本趣味が、一般のフランス人に浸透し始めたのだ。
食(和食、和風フレンチ、器、日本酒、日本包丁等)、ファッション、建築・インテリア、ポップカルチャー(漫画、アニメ、ゲーム、音楽等)、道(柔道だけでなく、剣道、空手道、合気道、弓道、華道、香道、書道など)など幅は広い。また最近は、日本古来のサステナブルな思想や生き方などへの関心が高まり、様々なイベントやメディア、口コミを通じ、フランスから世界に発信されている。
皮肉なことに、日本では、バブル崩壊から今日までを、「失われた30年」と称し、「日本後退論」が拡がっている。一方、フランスではむしろ逆で、日本を新興国から先進国に昇格した国と見るようになった30年であったと筆者の眼には映る。その大きな理由は、文化の理解を通じ、日本人の生き方や精神性など、非物質的な豊かさを認め始めたからだろう。
 JeanLucIchard/shutterstock.com
JeanLucIchard/shutterstock.comフランスが、こうした日本文化の“アンバサダー”的な役割を3世紀にわたって果たしてきた背景には、大きく次の五つのインフラがある。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください