みなさまのお知恵、お貸しください
2022年02月18日
朝日新聞社の「論座」(当初はWEBRONZA)が言論サイトとして誕生して12年弱。公開している寄稿やインタビューの総数が2月18日、2万本に達しました。
日々、生産され消費され、目の前を通り過ぎていく情報と、「論」は性格が異なります。時を経ても色あせないものが数多くある。2万の論のいずれも、いまもお読みいただけることが、論が集う場所、「論座」の特徴です。ぜひご入会のうえ、多様な論をお読みください。
とまあ、宣伝はこれくらいにして、きょうは論座の悩みを打ち明けながら、これからとりくもうと思っていることをご説明し、みなさまにお願いごとをしたいと思います。
とりくむことを先に申し上げれば、公開の議論を通じて、論座の「進化」や「深化」や「シン化(?)」の方法を探る。そんな試みを始めようと思っています。名付けて「論座シンカ計画」です。
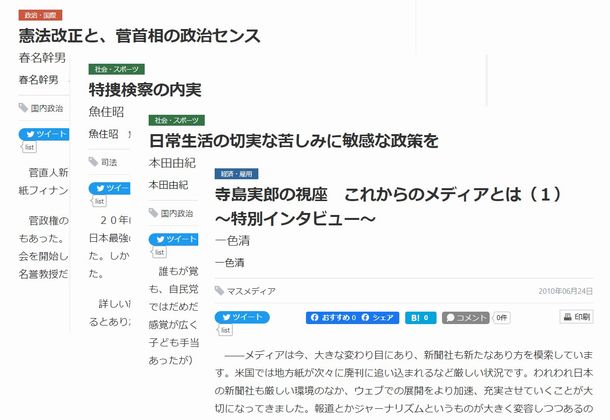 2010年、WEBRONZAスタートの日に公開した論考やインタビューの例
2010年、WEBRONZAスタートの日に公開した論考やインタビューの例私たちは悩んでいます。
いろいろありますが、私自身のいちばんの悩みは、言論やジャーナリズムを担う媒体としての役割を果たすこと。そして多くの方にお読みいただき、持続可能な媒体になること。このふたつの課題を、どうすれば両立できるかです。
一昨年の秋、論座の編集長に就きました。それ以来、様々な社会課題に直面している当事者や、課題解決にとりくんでいる人たちの論をご紹介したい。社会課題の解決に資するメディアになりたい、と編集部の会議などで言ってきました。
たとえばコロナ禍のもとでの介護職や保育士。孤立し、孤独を味わわされている若者。その大半は論を書く余裕などないにせよ、これだけ多くの方が課題に直面しているのだから、現実がもつ重みや迫力、複雑さを伝えられる方がきっといらっしゃるに違いない。そういった方にご寄稿いただければ、伝わりにくい声を伝え、見逃されがちな課題に光をあてることができるんじゃないか。そんなふうに考えたのです。
従来の新聞は、紙面の面積という制約があり、そういった方々の論をたっぷりとお伝えするのは難しかった。また、記者が取材し、執筆することがほとんどなので、その記者の力量にも左右され、課題の複雑さや現実の生々しさを伝えきれない側面もありました。けれども、ウェブの媒体である論座には、面積の制約はないし、寄稿が主体なので、ご自身でお書きいただくことができます。
新聞が直面してきた壁を、論座なら突破できるんじゃないか……。
その思いは、いまも変わっていません。引き続き、とりくんでいきます。
ただし、現実は思うようには進まないということも、日々、痛感しています。
そのひとつが、大切な課題だから、良質な論だから多くの読者にお読みいただけるとは限らない。そして「課題を社会に共有したい」と思ってご寄稿いただいても、読まれなければ共有はかなわない。そんな現実です。
数百万の読者のお宅に毎日届けられてきた新聞とは違い、ウェブの記事は、検索でひっかかる、巨大プラットフォームでめだつかたちで紹介される、SNSで拡散されるといったことがなければ、膨大な情報の海にのまれ、埋もれていきがちです。
埋もれないよう、かわいいネコのように人の感情を刺激する動画を載せるとか、「炎上商法」的な手法をとるといったやり方もしばしば使われます。ただ、私たちがそうしたやり方に頼った場合、一歩間違うと言論の場としての価値を毀損することになりかねません。
だからこそ、当事者ならではのリアルな迫力を武器に、読まれるようにできないかと考えたのですが、言うはやすく、行うはかたし。「書ける」当事者を探そうとしても、結局はインタビューすることになったり、寄稿の編集に手間暇がかかったりします。所帯の小さな編集部の力で、一本一本の論にそれだけの手間暇をかけるのは、やはり限界があります。
その手間暇をかける余裕を生み出すためにも、体力をつけなければならない。いっそう読まれるサイトになり、会員数を伸ばし、一定の収入を得て、志と技術をもつ人手を確保しないといけない。
体力がなければ、ジャーナリズムを担う媒体として、役割を果たすことはなかなか難しい。そう実感しています。
役割を果たしながら、読まれるサイトになるために、考えなければならないことはやまほどあります。
たとえば、せっかくの論がウェブの情報の海にのみこまれ、埋もれてしまわないようにする方法を、もっと考えなければなりません。
冒頭、論座で公開している論が2万になったとお伝えしました。ただ、2万の論があるといっても、読者が必要とする論にたどりつけなければ、宝の持ち腐れになります。時を経ても色あせない論を埋もれさせるのは、もったいない限りです。
とりあえずは、いま改めてお読みいただきたい論を、SNSや論座のサイトを通じて、ご紹介していきます。さらに、埋没防止の方法を探っていきたいと思います。
ウェブの特徴は双方向のやりとりができることです。その特徴を生かし、建設的な議論の場をどうつくるかも、悩ましい課題です。
論座はコメント欄を設けています。ですがそこには、目を覆いたくなるような差別や誹謗中傷の類いが書き込まれたり、読者同士のののしりあいになったりすることがしばしばあります。
いったいどうすればいいのか。すでに何人かの筆者にご寄稿いただき、公開の議論を始めています。それらを通じて、「ののしりあい」ではなく「議論」の場をつくるための方策を探り、実行に移していきたいと思っています。
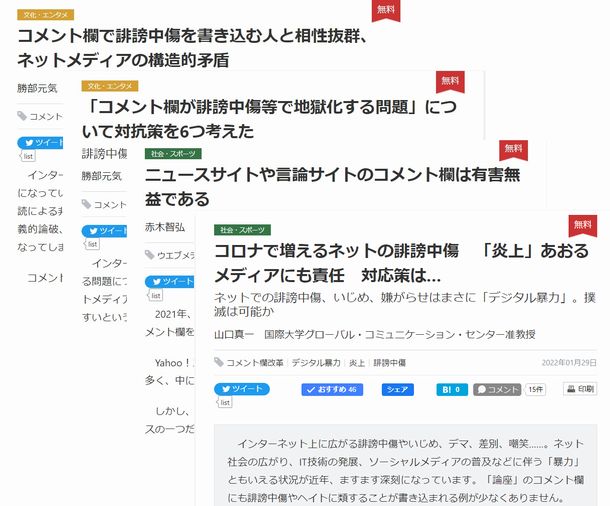 ネット上の誹謗中傷や、コメント欄のあり方などについて論じた寄稿やインタビュー
ネット上の誹謗中傷や、コメント欄のあり方などについて論じた寄稿やインタビュー「論座のシンカの方法」なんて、編集部内で議論すべきことなのかもしれません。ただ、新聞製作に慣れ親しんできた私のような者が、ない知恵を絞ろうとしても、なかなか前に進めません。そこで、こうして悩みを打ち明けながら、多様な筆者にご寄稿いただいたり、読者のみなさまのご意見を募ったりしていこうと思い至りました。
新しい論座づくりに、みなさまにご参加いただく。そんなイメージです。
「ご意見をください」というだけでは心に響かない。期限を設け、いついつまでに論座を改革すると宣言せよ……。編集部内には、そんな声もあります。
正直にいえば、そんな宣言ができるほどの自信は、私にはありません。簡単に解決策がみつかるくらいなら、こんなに悩むこともありませんから。
ただ、いつまでもグジグジしているわけにもいきません。この半年くらいの間に集中的にとりくみ、具体策を定めたいと考えています。
ぜひ、ご協力ください。とりあえずは本稿をふくめ、関連する論考やインタビューのコメント欄や、 info-ronza@asahi.com にいただければ幸いです。いずれ、このテーマでイベントを開くなど、ご意見をいただく場をつくることも考えていきたいと思います。
みなさまのご協力、伏してお願い申し上げます。

有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください