「熊が来る」が起きた背景を探る
2022年02月26日
2022年2月24日、ウラジーミル・プーチン大統領はテレビ演説し、そのなかで、「国際連合憲章第7編第51条に従い、ロシア連邦評議会の認可を得て、本年2月22日に連邦議会が批准したドネツク人民共和国(DNR)およびルガンスク人民共和国(LNR)との友好および相互援助に関する条約に基づき、特別軍事作戦を実施する決定を下した」と語った。
さらに、「その目的は、8年間キエフ政権によって虐待や大量虐殺にさらされてきた人々を保護することだ。そしてこの目的のために、我々はウクライナの非軍事化と非ナチ化をめざし、ロシア連邦の市民を含む一般市民に対して数々の血生臭い犯罪者たちを裁きにかけるつもりだ」と語ったのである。
 ロシア国民にウクライナでの軍事作戦の開始を告げるプーチン大統領(ロシア大統領府公式ページより、2022年2月24日)
ロシア国民にウクライナでの軍事作戦の開始を告げるプーチン大統領(ロシア大統領府公式ページより、2022年2月24日)この発言のなかで、「非軍事化」と「非ナチ化」は意味深長なものである。「非軍事化」は単に武装解除するというものではない。北大西洋条約機構(NATO)を1ミリでも東方に拡大させないために、ロシア軍の力でウクライナのいまの軍事力を圧殺するということらしい。そのためには、ウクライナ軍とその軍備を撤廃し、ウクライナは明らかに、ロシアと西側の間の非武装緩衝地帯のようなものにしなければならないという決意が込められている。いまの政権を、NATO加盟を永久に放棄する政権に交代させなければならないということでもあろう。ただ、「領土を占領することは考えていない」とした。
もう一つの「非ナチ化」という概念はわかりにくい。Entnazifizierungというドイツ語をロシア語化したもので、戦後のドイツとオーストリアの社会、文化、報道、経済、教育、法学、政治からナチスの影響を排除することを目的とした一連の措置を指す。なぜプーチンがそんなことを言い出したかは後述するが、彼自身の言葉で言えば、「NATOの主要国は、自分たちの目的を達成するために、ウクライナの極端なナショナリストやネオナチを支援している」という。そのナショナリストやネオナチをつかまえて裁こうというのである。
 キエフへの攻撃(2022年2月24日)=Giovanni Cancemi/shutterstock.com
キエフへの攻撃(2022年2月24日)=Giovanni Cancemi/shutterstock.comそして、いま現実にロシアに全面侵攻が行われ、ウクライナによる抵抗がつづいている。
筆者は、法律に知悉(ちしつ)しているプーチンが全面的侵攻に出るとは考えてこなかった。24日の演説を聞いても、その思いは変わらなかった。だが、そうではなかった。「熊が来る」という米国政府の予測が現実になったことになる。筆者の不明を恥じなければならない。それだけでなく、読者にも謝罪しておきたい。
ただ、「ロシア悪し」という世界中に広まりつつある声に対して、むしろ冷静になることを求めたい。彼の暴力は非難に値するが、それだけでは問題は解決しない。どこで世界は「道を間違えたのか」を探ることでしか、この問題を本質的なところから理解することはできないと思う。
「非ナチ化」というプーチンのとらわれている想いを理解するためには、「ユダヤ人問題」を知らなければならない。そこで、最近、名前を聞く機会が増えているリヴィウという都市の話からはじめたい。
ウクライナの首都キエフから大使館機能をここに移す動きが広がり、日本の報道機関もこの地からウクライナ情勢を伝える機会が増えている(2022年2月18日付の「ワシントン・ポスト」を参照)。だが、リヴィウそのものへの説明がないために、この地を理解すれば、ウクライナ問題の本質に近づけることを多くの日本国民は知らない。
筆者は2014年に上梓(じょうし)した『ウクライナ・ゲート』の序章の冒頭部分でつぎのように書いておいた。
「ウクライナという国家は本書の前扉に示したように、東はロシア、西はポーランド、ルーマニアなど、北はベラルーシ、南は黒海に挟まれた地域である。
ウクライナの歴史を理解するには、三つの言語ごとに若干異なる名前をもった場所に注目するとわかりやすいかもしれない。それは、ウクライナ語でリヴィウ(Львів)、ロシア語では、リヴォフ(Львов)、ポーランド語ではルヴォフ(Lwów)と発音される。つまり、それぞれの国家がこの場所を支配下に置いたことがあり、わが領土として自国語で呼び習わしてきたことになる。この場所はカルパチア山脈の西側にある。その意味で、リヴィウはその東側の地域と宗教も習俗も大きく異なっていた。」
にもかかわらず、1945年2月のヤルタ会談で、リヴィウのウクライナへの帰属が決められる。当時のリヴィウの人口構成比からみると、この地はポーランド領となっていたほうが自然であったように思われる。だが、国際連合創設を最優先に考えていたフランクリン・ルーズベルト米大統領はソ連のスターリンに安易に妥協し(なお、このとき、ソ連のスパイによってルーズベルトの考えはスターンに知られていた)、それがリヴィウに住む多くの人々に西側から見捨てられたという心情をかきたてたのだ。何しろ、リヴィウから西に100kmもクルマを走らせれば、ポーランドのプシェムィシルに着くのであり、リヴィウの人々を焚きつけて親ロシア政権の打倒を画策することは簡単なことだったのである(下図参照)。
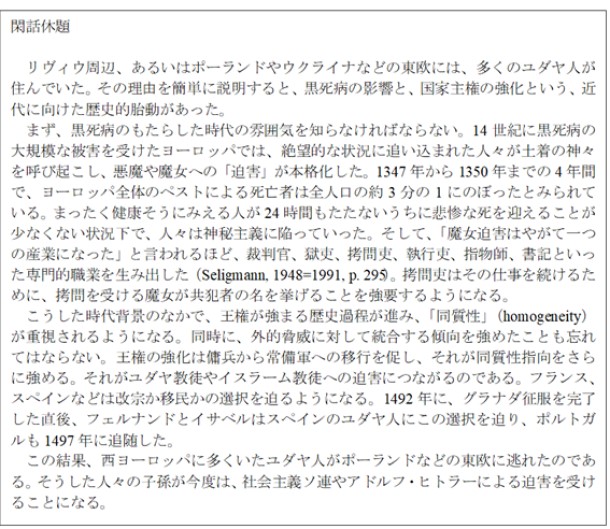
問題はそれだけではない。「閑話休題」に書いたように、この地にはユダヤ人が多く住んでおり、彼らのなかには、ソ連の社会主義から、ナチスの迫害から身を守るために、米国などへの移住を余儀なくされた人々が多くいたのである。そうした米国移住者の子孫から、ヴィクトリア・ヌーランド国務省次官など、いわゆる「ネオコン」としていまの国際政治を揺るがす政策を意図的にとっている者が生まれることになるのだ。
同時に、ユダヤ人を迫害・殺害したナチスから彼らを解放するため、ソ連軍の数百万人もの血が流されたことも指摘しておかなければならない。
さだまさしの「風に立つライオン」に「やはり僕たちの国は残念だけれど 何か大切な処で道を間違えたようですね」という歌詞が出てくる。たぶん、このヤルタこそ、「何か大切な処で道を間違えたようですね」という場所にあたるようにみえる。それは奇(く)しくもクリミア半島に位置している。
ヤルタ会談でウクライナに加えられたリヴィウ以西はウクライナのなかでも貧しい地域として放置されてきた(詳しくは拙稿『ウクライナ2.0』)。そうしたなかで、親欧米反ロシアの感情が芽吹き、それを刺激したのが米国のネオコン(新保守主義者)であった。そうしたナショナリズムの扇動を主導したのがヴィクトリア・ヌーランド国務省次官補(当時)である。拙稿『ウクライナ・ゲート』において、つぎのように記述しておいた。
「それでは、2014年2月以降、何が起きたのかをもう少し詳しく考察してみよう。それを示したのが巻末表である。時系列的にみると、1月から武力衝突が繰り返されていたことがわかる。おそらく「マイダン自衛」が徐々に武力を整えていった時期と重なる。英国のフィナンシャル・タイムズと提携関係にある、比較的信頼できるロシア語の新聞「ヴェードモスチ」が2月20日付で伝えたところによると、ウクライナ西部のリヴォフ市長は、三つの地区警察署の武器保管庫が襲われ、約1500もの銃火器が持ち出されたことを明らかにした。リヴィウ(リヴォフ)の南東にあるイヴァノ・フランキーウスクでは、武器が自衛組織との共同管に移行したという。この時点で、行政庁舎が自衛組織によって占拠されていたのは、ル-ツィク、リウネといった北西部の都市、イヴァノ・フランキーウシクである。リヴィウの場合、行政庁舎のほか一部の警察署も占領されていた(図1参照)。」図1 反政府勢力の動向=(出所)「ヴェードモスチ」,2014年2月20日
 政党「自由」の党首オレグ・チャグニボク(インターネット上で入手できる画像を筆者がダウンロードした)
政党「自由」の党首オレグ・チャグニボク(インターネット上で入手できる画像を筆者がダウンロードした)こうしたナショナリストたちは、ナチスを思わせる暴力集団と化し、彼らが民主的な選挙で選ばれて大統領となったヴィクトル・ヤヌコヴィッチを武力で追い出したのである。当時の雰囲気を知ってもらうために以前、紹介したのが以下のBBCの番組であった。
実際に暫定政権ができると、「自由」のメンバーが入閣した。当初、アレクサンドル・スィチ副首相、イーゴリ・シュヴァイカ農業政策・食糧相、アンドレイ・モフニク環境・天然資源相、イーゴリ・チェニューフ国防相の4人が閣僚に任命されたのだ。このとき、首相になったアルセニー・ヤツェニュークは駐ウクライナ大使やヌーランドの指示を受けていたことは間違いない。
こうした事情から、プーチンはウクライナでナショナリストやネオナチによるクーデターが引き起こされたとみなしている。もちろん、これはプーチンの思い込みではない。たしかに、2013年から2014年当時、こうしたナショナリストが「大活躍」していたことは事実だ。にもかかわらず、欧米諸国は彼らの横暴を赦(ゆる)し、プーチンのクリミア併合だけを批判した。その後、どうなったかというと、ナショナリストらが軍に吸収されただけでなく、民兵や義勇兵として残存し、ウクライナ国内で隠然たる勢力となってしまったのである。そのため、2015年のいわゆる「ミンスク合意」を履行しようとしても、彼らの強い反発が予想されることから、実際には何もできない状態が7年間もつづいてしまったのである。
しかも、こうしたウクライナの政情を米独仏も放置していた。米国に至っては、バイデン政権になっても駐ウクライナ大使さえ任命しないまま、ウクライナに関心を示そうとはしなかった。
つぎに、プーチンが持ち出した国際連合憲章第7編第51条について知る必要がある。ここに、もう一つの「大切な処で道を間違えた」という事実が関係しているからである。
この条文には、つぎのように書かれている。
「この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が行われた場合には、安全保障理事会が国際の平和および安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的または集団的自衛の固有の権利を損なわないものとする。この自衛権の行使において加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告されなければならないが、この憲章に基づく安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとる権限および責任に何ら影響を与えるものではない。」
1999年3月、北大西洋条約機構(NATO)はセルビア人によるコソボ・アルバニア人の「民族浄化」を食い止めるため、ユーゴスラビア共和国への空爆作戦を開始した。このとき、NATOが持ち出したのがこの第51条であった。といっても、これは、国連加盟国への武力攻撃に対する自衛権の行使を認めたものであり、コソボに適用することには疑義があった。
国連安保理は1998年3月に第7編を発動し、武器禁輸を課してコソボ情勢に対処していた。武力行使に至る過程で、NATOのソラナ事務総長は、「コソボにおける人道的災害の危険性」を理由に、想定される介入が正当化されることを明言する。
1998年10月に行われたソラナとNATO常設代表との会合に基づき、ソラナは「人道的惨事が続いていること」「コソボに関して明確な強制措置を含む別の国連事務局決議が当面の間期待できないこと」「コソボの状況の悪化とその規模は地域の平和と安全に対する深刻な脅威を構成すること」を指摘する。そして、NATO安全保障総局は、「同盟国は、コソボにおける現在の危機に関する特定の状況には、同盟国が威嚇し、必要であれば武力を行使するための正当な根拠があると考える」と結論づけたのである。
当時、ロシアはこうしたNATOの独断的結論に猛反対した。にもかかわらず、NATOは空爆を断行した。これを強く主張したのは、マデレーン・オルブライト国務長官である。彼女こそ、伝統的な地政学の考え方を米ソ冷戦時代に適合させて、「ユーラシアの征服」という野望をいだきつづけてきたズビグニュー・ブレジンスキーの文字通りの弟子だ。ユダヤ系の彼女もネオコンと言えよう。
このNATO空爆こそ、もう一つの「大切な処で道を間違えた」事件と言えまいか。だからこそプーチンは、24日の演説でつぎのようにのべている。
「まず、国連安全保障理事会の承認なしに、ヨーロッパの中心で航空機とミサイルを使ってベオグラードに対する流血の軍事作戦が実施された。数週間にわたり、都市や生命維持に必要なインフラを継続的に爆撃した。」
国連憲章で自衛権を規定した第51条については、その後、米英軍などによるイラク侵攻の際にもこの第51条との関連が問題になる。プーチン演説では、「その後、イラク、リビア、シリアという順だ」とされている。もちろん、在外国民を保護するという概念を第51 条の枠内に収めるのは無理がある。にもかかわらず、そうした論理を駆使して、空爆や侵攻を繰り返してきたのは欧米諸国だとプーチンは考えているのだ。
ゆえに、プーチンに言わせれば、同じ論理に基づいて、今度はロシアが「第51条に従い」「本年2月22日に連邦議会が批准したドネツク人民共和国(DNR)およびルガンスク人民共和国(LNR)との友好および相互援助に関する条約に基づき、特別軍事作戦を実施する決定を下した」ということなる。
実は、2月19日、筆者の尊敬するジャーナリストでこのサイトにおける考察にも多大な影響をあたえている、ユーリヤ・ラティニナは毎週放送しているラジオ番組の冒頭、「正直なところ、プーチンが攻撃を決断するとはずっと思っていませんでした。昨日の夜から、私は完全にショックを受けている。尊敬する聴衆に謝らなければならない。これは非常に重大なことです」と語った。筆者も彼女と同じ言葉を繰り返したい。
彼女の発言にしたがっていれば、もう少し早く方向転換できたかもしれない。それでも、事態を見守ることでしか対応できなかった。まだどこかにプーチンの抑制力に期待していたからだろう。
筆者自身にとって、「大切な処で道を間違えた」と言わざるをえないのはどこだったのか。2008年8月にグルジア(現ジョージア)で起きた「五日間戦争」に惑わされたせいかもしれない。いまでは、ロシアがジョージアに開戦したという誤報が真実のように日本のマスメディアに飛び交っているが、彼らは事実を何も知らない。
当時、米国務省でグルジア担当だったマシュー・ブライザ(Matthew Bryza)は当時のミヘイル・サーカシュヴィリ大統領に何度もロシアの挑発に応じないように求めていた。しかし、サーカシヴィリはNATOからの支援を信じて、大砲を撃ちこみはじめたのだった。
今回の場合、「ロシアのウクライナ侵攻計画」なるものをリークしたことで、むしろ米国がロシアを挑発しているように感じられた。なぜなら何度も書いてきたように、ヴィクトリア・ヌーランド国務省次官がそのリークの背後にいると思われたからである。この見立てが間違っていたのかもしれない。最初からプーチンは断固たる決意であったのだろう。
そんな筆者だが、何も知らずに一知半解な虚言を吐くのではなく、徹底した考察から世界の変化を精緻に分析しつづけていきたい。それは、ラティニナの反省と出直しに呼応するものでもある。
今回の考察がそうした姿勢を貫くための最初の一歩になりえていることを願っている。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください