日本の政治家に力量はあるか/言葉の力を知らずして国民と国際社会は束ねられない
2022年03月29日
 ウクライナのゼレンスキー大統領=2022年3月3日(Photographer RM/Shutterstock.com)
ウクライナのゼレンスキー大統領=2022年3月3日(Photographer RM/Shutterstock.com)日本でもすっかりお馴染みになったウクライナのゼレンスキー大統領。大統領の姿を目にする時、大統領はいつも決まって何かを訴えている。危機に当たり、指導者に求められる資質は何か。いくつかある中で、言葉の持つ力を知り、その力を使いこなせることであるのは間違いない。国民をまとめ上げ、国際社会に支援を訴えかけるのは言葉を通して以外にないからだ。
 欧州議会の特別セッションにオンラインで演説したウクライナのゼレンスキー大統領。議員は総立ちで拍手を送った=2022年3月1日(Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)
欧州議会の特別セッションにオンラインで演説したウクライナのゼレンスキー大統領。議員は総立ちで拍手を送った=2022年3月1日(Alexandros Michailidis/Shutterstock.com)国土が戦火に燃えさかる中の23日、ゼレンスキー大統領が日本国民に必死の訴えを行った。ウクライナの惨状は、日々、報道を通し我々の目に焼き付いて離れない。最高指揮官の生の声は我々に強い印象を与えた。日本も可能な限りの支援を惜しむものではない。今の国際情勢にあって、いつ立場が入れ替わるか分からない。我々は、同じ運命共同体にいるのだ。
 ウクライナ南東部マリウポリ市で3月14日にドローンで撮影された住宅地。ソーシャルメディアの画像から。市当局の情報では、ロシア軍に包囲され水や電気、食料の供給が途絶えたまま市民は地下室などに避難している
ウクライナ南東部マリウポリ市で3月14日にドローンで撮影された住宅地。ソーシャルメディアの画像から。市当局の情報では、ロシア軍に包囲され水や電気、食料の供給が途絶えたまま市民は地下室などに避難している
 ロシアのプーチン大統領(Rokas Tenys/Shutterstock.com)
ロシアのプーチン大統領(Rokas Tenys/Shutterstock.com)しかし、今、国民は、国の存亡をかけ必死に戦っている。ここで白旗を掲げれば、ウクライナという国は事実上地図の上から消えるかもしれないし、ロシアの圧政の下のウクライナは、最早、国民が知るウクライナではない。そう思うからこそ、国民は今日も武器を手にロシア軍の猛攻に耐えている。
 戦闘での犠牲者に祈りを捧げるウクライナ兵=2022年3月(Bumble Dee/Shutterstock.com)
戦闘での犠牲者に祈りを捧げるウクライナ兵=2022年3月(Bumble Dee/Shutterstock.com) ウクライナでの民間人の軍事演習=2022年2月(Drop of Light/Shutterstock.com)
ウクライナでの民間人の軍事演習=2022年2月(Drop of Light/Shutterstock.com)その国民の拠り所となり、団結の礎となっているのがゼレンスキー大統領だ。大統領自身、幾度か暗殺の危険に見舞われたし、ロシア軍は大統領を標的にしているともいう。大統領の身の安全のため、ひとまず、キエフから離れもう少し安全が確保できるところに避難したらどうかとの勧めもある。しかし大統領はそういう声に耳を傾けようとせず、キエフから毎日、国民にメッセージを送り続けている。
今や、ゼレンスキー大統領を一介のコメディアン上りとあしらう者はいない。政治経験の欠如や就任後の実績不足も何のその、大統領の支持は大きく上昇した。今や、大統領こそが、抵抗のなくてはならない支柱になっている。
 ロシアの侵攻から1カ月を経た3月24日に投稿したビデオメッセージで演説するゼレンスキー・ウクライナ大統領=ゼレンスキー氏のSNSから
ロシアの侵攻から1カ月を経た3月24日に投稿したビデオメッセージで演説するゼレンスキー・ウクライナ大統領=ゼレンスキー氏のSNSからそういう大統領にとり、唯一、武器ともいえるのが「言葉」だ。大統領の発する言葉こそがウクライナ国民を一つにし、彼らを祖国防衛に駆り立て、国際社会の支援を確かなものにしている。
そして、過日、その言葉が日本国民にも届けられた。既に、米国、英国、ドイツ、カナダ等、大統領は多くの国で演説した。日本の演説も大統領が強く希望した。ウクライナ側は生中継を求めたという。それはそうだ。ビデオメッセージで伝わるものは限られている。生の迫力こそが聞く者の心を動かす。
 米連邦議会で、ゼレンスキー大統領のオンライン演説を聴き拍手を送る議員ら=2022年3月16日、ワシントン
米連邦議会で、ゼレンスキー大統領のオンライン演説を聴き拍手を送る議員ら=2022年3月16日、ワシントン ウクライナの首都キエフからドイツ議会に向けて演説するゼレンスキー大統領=2022年3月17日、大統領府提供
ウクライナの首都キエフからドイツ議会に向けて演説するゼレンスキー大統領=2022年3月17日、大統領府提供23日夕刻、大統領は日本国民に感謝の意を伝えると共に、チェルノブイリの「原発」、「サリン」による化学兵器使用の可能性、「復興」の望み等に触れつつ、日本が引き続き支援を継続してくれることを強く求めた。大統領は、何を言えば日本国民の琴線に触れ、また、何を言わないことが、その支援を得る上で重要かを知っていた。
国内政治であろうと国際場裏であろうと、言葉こそが人を動かし人をまとめる。言葉こそが万感の思いを伝える。そのことは改めて言うまでもない。古今東西、危機に当たって、指導者はその言葉の力をもって国難を乗り越えてきた。それは、日本も同じだ。
 ウクライナのゼレンスキー大統領のリモート演説を聞く日本の国会議員ら。ウクライナと国会内会議室をオンラインでつなぎ同時通訳された=2022年3月23日
ウクライナのゼレンスキー大統領のリモート演説を聞く日本の国会議員ら。ウクライナと国会内会議室をオンラインでつなぎ同時通訳された=2022年3月23日しかし、もし、日本がウクライナの立場に置かれたとして、その指導者は同盟国の国会で演説し支援を求めようとするだろうか。仮にするとして、同盟諸国を結束させ、同盟国の国民を揺り動かし支援の輪を広げることができるだろうか。そのためには、聞く者に強く訴える力がいる。聞く者を揺り動かす力がいる。少なくとも、下を向き、用意した紙を読んでいてはその力は出てこない。
 ゼレンスキー大統領のオンラインでの国会演説後、取材に応じる岸田文雄首相=2022年3月23日、首相公邸
ゼレンスキー大統領のオンラインでの国会演説後、取材に応じる岸田文雄首相=2022年3月23日、首相公邸もう一つ、日本の場合、会社や地方の集まり等、国の中に小さな共同体ともいえる存在があり、政治の役割は、その相互の調整に向けられがちとの事情もある。指導者が国民に何かを訴えこれを糾合していくことは、どちらかと言えばそれほど重視されない嫌いがある。
 衆院選の応援演説をする小泉純一郎首相。群衆が殺到し負傷者も出た=2005年9月3日、北九州市
衆院選の応援演説をする小泉純一郎首相。群衆が殺到し負傷者も出た=2005年9月3日、北九州市しかし、危機に直面した時、日本のような国でも、国民に直接訴えかけその支持を得ることは不可欠だ。国民の団結なしに危機など乗り切れるものでない。
 緊急事態宣言について会見する菅義偉首相の映像が街頭の大型ビジョンに映し出された=2021年6月17日、東京都新宿区
緊急事態宣言について会見する菅義偉首相の映像が街頭の大型ビジョンに映し出された=2021年6月17日、東京都新宿区ただ、政府の訴えがどれだけ国民に届いたかは定かでない。
今回の危機で顕著なのは、力の侵略に対し経済制裁で対抗するとしたことだ。力で対抗せず経済制裁に止める時、それが効果を上げるには世論の喚起が不可欠だ。世論が大きく動いたからこそ、ドイツは戦後長く続けた外交防衛方針を180度転換したし、ビジネス、スポーツ、文化等、世界の幅広い分野でも制裁に同調する動きが広がった。制裁を実効性あるものにするには世論の喚起こそが重要だ。
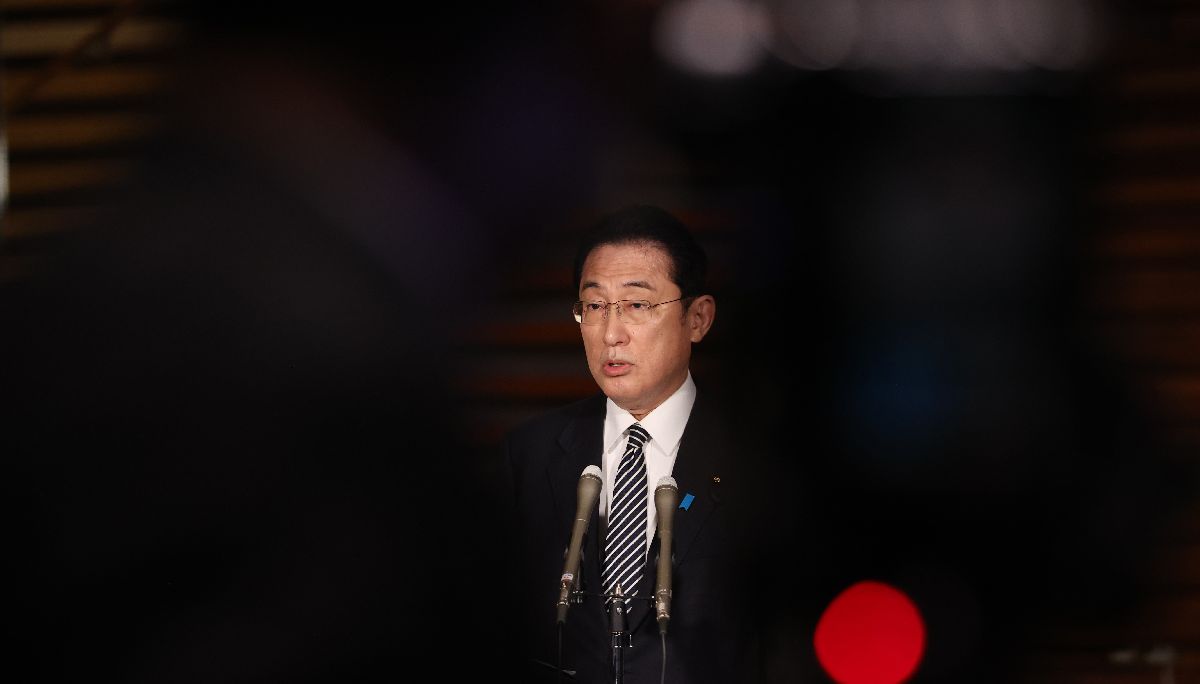 ロシアのプーチン大統領との電話会談後、取材に応じる岸田文雄首相=2022年2月17日
ロシアのプーチン大統領との電話会談後、取材に応じる岸田文雄首相=2022年2月17日今回、ウクライナ危機が我々に問いかけているのは、危機克服のため国民を団結させ国際社会に訴える必要があるとして、果たして、日本に「言葉」の力を駆使できる指導者がどれだけいるか、ということだ。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください