無料の公設民営塾を開設、バス代・下宿代補助、野球部充実、海外の無料ホームステイも
2022年06月21日
年々、地方の集落が地図から消えていく中で、過疎化を食い止めるべく、地元の公立高校に通う高校生を対象に無料の公設民営塾を運営する自治体がある。その一つが北海道足寄町だ。自治体との随意契約でBirth47という企業が指定管理者となり、町の予算で塾を運営している。
自治体が塾を開設することが、どうして過疎化を食い止めることになるのか? 本稿ではその“相関関係”を見ていきたい。
地方の過疎化が深刻さを増している。29歳以下の若年者が都市部に流出し続けて65歳以上の高齢者が多い過疎地域は、2019年4月時点の総務省調査で6万3237集落にのぼった。若年者が減るということは、地域の生産力が乏しくなり、税収入を確保できない自治体が財政難に陥り、住民の日常生活に支障が出るということだ。
高齢者が地域住民の半数を超える「限界集落」では、老朽化した住宅や空き家の増大、耕作を放棄された田畑や獣害・病虫害の放置、スーパーや商店の閉鎖、公共交通機関の廃線などが進んでいる。そんな限界集落が、2019年4月時点で過疎地域の32.2%を占めた。数でいうと2万372集落だ。そのうち、「いずれ」または「10年以内」に無居住化の恐れがあると、自治体が答えた集落は全国で3197もある。
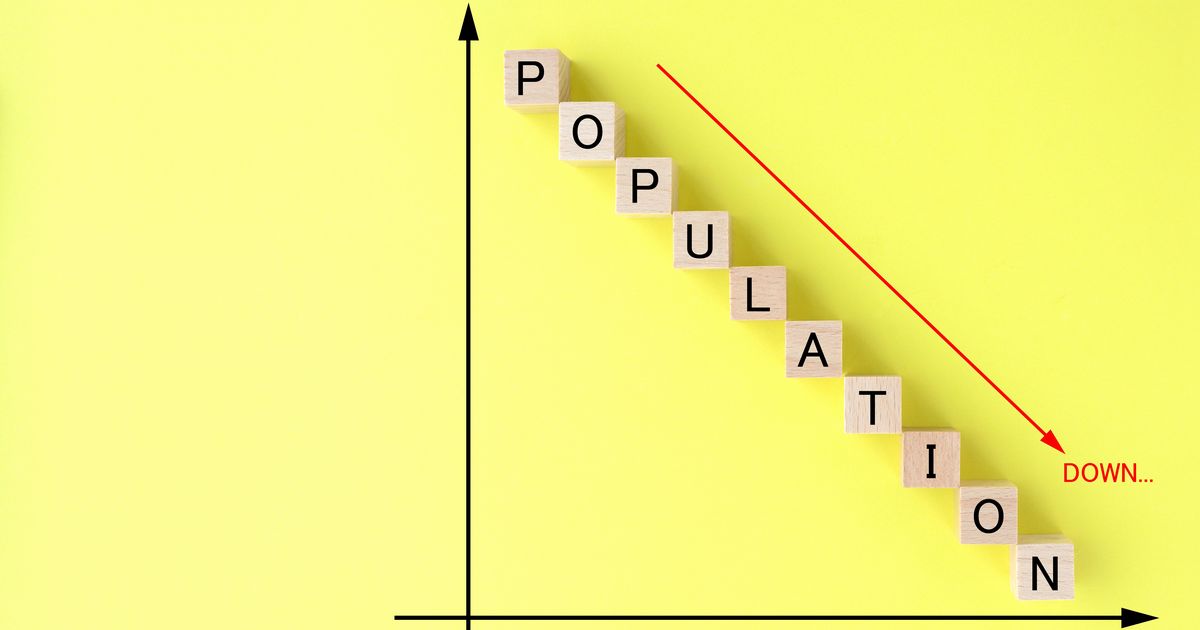 takasu/shutterstock.com
takasu/shutterstock.com2020年度、大学進学率は過去最高の54.4%を記録した。大学に短期大学、専門学校、高等専門学校も合わせた高等教育進学率だと83.5%に達する。高校進学率はほぼ100%だ。
このように、高等教育進学率が戦後、おおむね増加傾向を続けているなか、地方の自治体が若年層の流出をおさえるための一つのカギは、子育て世帯をいかに定住させるかにある。
子育て世帯が地元を離れるのはどのようなときか。それは、子供の進学のタイミングというケースが少なくない。とりわけ、義務教育を終えた子供を「もっといい」高校、ひいては大学に通わせたいと考える親が、一家で都市部に引っ越す場合が多い。
2019年に放送されたNHKの朝の連続ドラマ『なつぞら』の舞台となった十勝地方。その東北部に足寄町は位置する。1960年に人口2万人弱となったのをピークに、1995年には1万人を割り、2015年には7000人を切った。町の主産業である農業、畜産業、林業が低迷するにつれて、高齢化と後継者不足で離農者が増え、進学のタイミングや仕事がないなどの理由で若年者が町を離れていった。典型的な過疎化のパターンだ。
足寄町では、過疎化で生徒数が減少し、地元唯一の公立高校である北海道立足寄高等学校の定員割れが常態化している。これもいま全国の過疎地で共通して起きていることだ。
いわゆる「高校全入」時代になると、足寄高校に入学する生徒の学力のばらつきが大きくなり、十勝地方の進学校の優秀者と遜色ない学力を持つ生徒と、入試の点数がほぼ0点の生徒が一緒に授業を受けるようになった。
その結果、学力の高い地元の生徒が他地域の高校に進学するようになっていく。足寄高校は入学者を最低41名確保できないと、北海道教育委員会の方針で1学年2学級を維持できなくなる。1クラスに減らされると、同じく教育委員会の方針で高校再編計画の検討対象となる。
歌手の松山千春、国会議員の鈴木宗男などが卒業した足寄高校が統廃合でなくなれば、地元の子供たちは公共交通機関を使って他地域の高校に通学することになる。しかし、過疎地域で鉄道が廃止された足寄町では、バスしか通学手段がないため、バスで通えない高校に進学する子供は、親元を離れて下宿生活をするか、世帯ごと地元から離れることになるだろう。
つまり、足寄高校の1学年2学級を維持できないと、高校が廃校になり、子育て世帯の足寄町流出が進み、過疎化に拍車がかかる未来が待っているのだ。
 足寄高校=北海道足寄郡足寄町(みんなの高校情報北海道HPから)
足寄高校=北海道足寄郡足寄町(みんなの高校情報北海道HPから)2011年度に初めて、足寄高校の入学者は38人、つまり2学級を編成できない40人以下に落ち込む。当時の安久津勝彦町長は「これは大変なことになる」と思った。近隣の中札内村や同じ十勝地方の浦幌町の公立高校は、すでに募集停止となっている。明日は我が身だ。
その年の足寄中学の卒業生は62人いたにもかかわらず、足寄高校の入学者数が41人を切ったのは、帯広地方の進学校である道立帯広柏葉高等学校に進学した8人をはじめ、他地域の「もっといい」高校や高専に進んだ生徒が多かったからだ。
足寄町が最初にとった対策は、足寄高校に進学した生徒全員に入学一時金7万円を支給することだった。見学旅行の補助金3万円も支給し、高校も夏休みの合宿などを実施して生徒の学力向上に取り組んだ。しかし、2014年度に高校入学者は再び41人を切る。
高校進学を考える中学生の家庭を対象にアンケートを実施したところ、足寄高校への要望として圧倒的に多かったのが「学力向上」だった。しかし、高校でできることはすでにやった上での現状である。何か特効薬はないのか……。
2011年3月11日の東日本大震災。全国で学習塾やスポーツクラブを経営するBirth47の高橋宏幸社長が関東で震災に直面して頭に浮かんだのは、東北の復興のために全国の市町村の地方交付税交付金が減らされる、という予想図だった。高橋社長は、自身が生まれ育ち、公務員の両親がいまも住む足寄町の交付金が減らされたら、限界集落に転落するのではないかと危惧する。
高橋社長は早速、ふるさと納税制度を活用して足寄町に50万円を寄付。翌12年にも150万円を寄付した。安久津町長にとって、足寄町役場の職員だった高橋社長の父親は大先輩にあたり、高橋社長自身も子供の頃から知っていた。安久津町長は、2014年4月の東京出張の折、「ふるさと納税のお礼を直接言いたい」と高橋社長に面会を申し込む。
だが、夕食の席を囲んで、安久津町長が高橋社長に切り出したのは、足寄町に塾を開設してほしいという要請だった。足寄高校が再び1学級になったこと危機感を募らせた町長は必死だった。「足寄高校の存続が厳しい。高橋さん、助けてよ」
高橋社長は、それなりに生徒数のいる自治体でないと塾経営が成り立たないと説明したが、安久津町長から「でも、いいの? あしこう(足寄高校の愛称)、つぶれて」と迫られ、とっさに塾の運営費を町が全額負担してくれたら可能だと答える。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください