「宮本路線」成功の鍵は
2022年07月14日
政党の存在感がわれわれの日常世界から失われて久しい。政党がたんなる政治家の集まりではなく、無数に張り巡らされた利益集団を包括する政治マシーンとして、あるいは政治的理念にもとづいて結束する社会集団として、政治のみならず社会、経済、文化領域にまで浸透していた時代を知る者はもはや現役世代にはいない。
ただ束の間とはいえ、近年政党が一般大衆に存在を意識されたのはおそらく2009年の民主党政権交代であろう。その民主党政権の崩壊とともに、国政選挙の投票率は史上最低の5割程度で推移し、政党の社会的存在の希薄化は極まりつつある。
戦後政治において、政党の存在低下の決定的な節目は1990年代初頭であった。1993年の細川連立政権樹立から社会党の消滅に至る政界再編により、1950年代以来つづいた保革対立の枠組みが崩壊し、激しい政党の離合集散が生じたことで多くの有権者が政党との安定的なつながりを失い、投票率が低下していったからだ。
ただこうした離合集散の荒波を超え、党名を変えることなく有権者との安定的なつながりをある程度維持してきた政党もある。このうち特定宗教団体が支持基盤である公明党は脇に置くとして、多様な階層の個人、団体を組織し、政治的堡塁を築いてきた結社は自由民主党と日本共産党だけである。事実こんにちにおいても――もちろん悪名も含めて――広く有権者に党名を知られているのがこの両党であることはいうまでもない。
 田村智子副委員長(右から2人目)が当選確実となり、花をつける共産党の志位和夫委員長(左)。右は小池晃書記局長=2022年7月11日、東京都渋谷区
田村智子副委員長(右から2人目)が当選確実となり、花をつける共産党の志位和夫委員長(左)。右は小池晃書記局長=2022年7月11日、東京都渋谷区ただし両党には決定的な違いがある。自由民主党は野合としかいいようがない1955年の結党以来、政権政党であることだけが結束軸の政党である。構成されているメンバーのイデオロギーは相当に多様であり、時代によって変化する支配様式に適応しながら支配政党として存続してきた。したがって自由民主党の歴史はそのまま政治支配の歴史として描かれてきた。
それに対して日本共産党は科学的社会主義の理論を結束軸とした、単一のイデオロギーにもとづく政党である。構成されているメンバーは理念と実践の一致が求められ、時代によって変化する支配システムに一貫して対抗する政党として存続してきた。したがって日本共産党の歴史は統治権力に対抗する反システム政党の歴史として描かれてきた。
統治権力に対抗する反システム政党である日本共産党の歴史は、支配的な政治過程を描く「政治史」よりも、支配に対抗する「運動史」のカテゴリーで扱われてきた。膨大にある日本共産党関係の書籍、論文、ルポルタージュが結党当初から1970年代までの社会運動叙述に集中しているのも、議会政党としてよりも反システム運動として歴史に刻まれてきたからである。現代史において自由民主党は「政治」を、日本共産党は「運動」を代表してきたともいえる。
ところが最近になり、このような分類が崩れる状況が生まれている。
2015年、安保法制反対運動が数十年ぶりの大規模な集会動員を果たした直後、日本共産党は「国民連合政府」構想を発表し、国政選挙で初の選挙協力に乗り出した。いわゆる「野党共闘」路線は国会内での共闘から地域レベルでの野党支持者間の協力にまで深化し、日本共産党は政権をめざす連合勢力の一角を占めるまでになった。著者である中北浩爾氏が日本共産党を「否応なく意識せざるを得なくなった」のもこの野党共闘が契機である(注1)。
 市民連合との共通政策に合意し、握手する(前列左から)SEALDsの諏訪原健さん、社民・又市征治幹事長、民進・岡田克也代表、共産・志位和夫委員長、生活・小沢一郎代表、安保関連法に反対するママの会の西郷南海子さん=2016年6月7日、東京・永田町の参院議員会館
市民連合との共通政策に合意し、握手する(前列左から)SEALDsの諏訪原健さん、社民・又市征治幹事長、民進・岡田克也代表、共産・志位和夫委員長、生活・小沢一郎代表、安保関連法に反対するママの会の西郷南海子さん=2016年6月7日、東京・永田町の参院議員会館私の実感からも、他党の政治家、マスコミ、学者、社会運動家の日本共産党への関心は3.11後の反原発運動の高揚あたりから強まっていた。反原発運動や反安保法制の運動は「運動共闘」であったが、そこで生まれた運動の熱量を2015年に「政治共闘」に転化させたことで、日本共産党は一気に「政治史」のなかに位置付けられることになった。
日本共産党の政治学的な分析の必要性が高まるなかで、その役割を引き受け、100年にわたる歴史に社会科学のメスを入れたのが、本書である。
政治学として日本共産党を分析するにはいくつかの条件がある。日本の左翼100有余年の歴史は、アナキズム、社会民主主義から新左翼まで広がる対立と分裂の歴史であり、強烈な体験とイデオロギーが歴史叙述のなかに刻まれている。日本共産党はこの対立と分裂の歴史のど真ん中を歩んできた。だからこの左翼全体の歴史についての相当な知識と俯瞰的な視点がなければ、日本共産党を分析することはできない。
著者は『自民党―「一強」の実像―』(2017年)、『自公政権とは何か』(2019年)を上梓していることからも、保守政治の専門家と近年はみられがちである。ただ著者は元鉄鋼労連書記長であり、社会党、総評に大きな影響を与えた清水慎三信州大学名誉教授と、その弟子にあたる高木郁郎日本大学名誉教授に師事し、『経済復興と戦後政治―日本社会党 1945-1951年―』(1998年)、『日本労働政治の国際関係史 1945-1964―社会民主主義という選択肢―』(2008年)を上梓している。
であるから著者は、政治学のなかの「労働政治学」の系譜にあり、日本共産党の「運動史」を分析するうえで不可欠な、日本の社会民主主義と労働運動についての知識と業績を豊富に備えている。
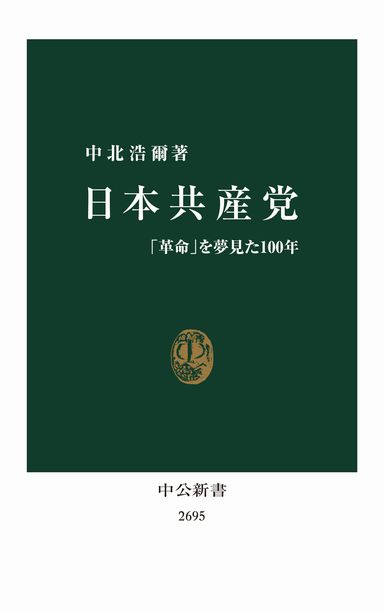 中北浩爾著『日本共産党』(中公新書)の書影
中北浩爾著『日本共産党』(中公新書)の書影本書の第一の意義は、日本共産党の100年の歴史を描いたことそのものにある。
実は日本共産党の公式の党史以外に、戦前から戦後の高度成長期以後をカバーした通史はない。公式の党史も、「日本共産党の80年」(2002年)が最後である。そして本書を通じて100年史を俯瞰してみると、日本共産党が各々の時代の歴史的条件に揺さぶられつつも徐々に路線を確立し、高度経済成長期を経て、こんにち知られる党のかたちがつくられたことがわかる。日本共産党は日本の政党のなかでもっとも長年の伝統を有しているわけだが、本書を通読するとその伝統は原初から一貫したものではなく、それが戦後政治の確立過程で「創られたもの」であることがわかる。
本書のもうひとつの意義は、日本共産党の100年の歴史を「政治史」として整理したことにある。
それゆえ本書の100年史は、1922年に日本共産党が世界共産党であるコミンテルンの日本支部として結成されたにもかかわらず、国際環境の変化と党内闘争を経て、「宮本路線」を確立し、議会政党として「政治史」に登場するという筋道で描かれている。欧州共産党の先進国革命型でもなく、毛沢東主義的な後進国革命型でもなく、独自の日本型共産党の路線を確立したのが宮本顕治であり、以後その路線の微修正を繰り返しながら今日に至っているというのだ。
この「宮本路線」を著者はこう定義している。「1955年の六全協の後、最高実力者になった宮本顕治のリーダーシップのもとで成立した日本共産党の路線であり、第一に民族民主革命を平和的な手段によって実現することを目指す1961年綱領を中核とし、第二に国際共産主義運動の内部で自主独立の立場をとり、第三に大衆的な党組織の建設とそれに基づく国会等の議席の拡大を図る政治路線」である(注2)。
 日本共産党の第8回党大会で、綱領草案の説明をする宮本顕治共産党書記長=1961年7月25日
日本共産党の第8回党大会で、綱領草案の説明をする宮本顕治共産党書記長=1961年7月25日日本共産党の「民族民主平和革命」「自主独立」「大衆的党組織の建設」は三位一体である。海外からの活動資金に依存しないためには大衆的な党組織が必要であり、大衆的な党組織を建設するためには多様な階層の組織化を可能にする革命路線を採る必要がある。
著者が指摘するように、日本共産党は「民族民主革命路線のもと、労働者よりも国民や民族を重視」した(注3)。これは日本の政治情勢を「社会主義前夜」とみなし、労働者階級を一元的な基盤とした当時の日本社会党の路線とは好対照をなしていた。社会党は高度経済成長のもと、労働者が増大しているにもかかわらず党勢が停滞したが、それに対して日本共産党は宮本路線のもと党勢を大幅に増大させたのである。
このように三位一体路線による劇的な党勢拡大の成功こそが宮本路線を正統化せしめ、その成功体験の強烈さゆえにこの路線がこんにちも日本共産党のアイデンティティに確固として据えられている。したがって政治史における日本共産党を論じるうえでは、この宮本路線の確立過程の分析と評価が焦点となるだろう。
では、本書の宮本路線の確立過程をめぐる叙述は果たして十分なものだろうか。社会主義革命の課題を彼方に置き、「民族民主」を当面の課題にすえた宮本路線の実践的根拠を探るためには、あらためて「運動史」の次元に降りた検討
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください