コロナ対策徹底批判【第六部】~上昌広・医療ガバナンス研究所理事長インタビュー㉒
2022年08月25日
臨床医でありながら世界最先端のコロナウイルス対策を渉猟する医療ガバナンス研究所理事長、上昌広氏に対するロング・インタビューは最終の第6部を迎えた。6部では「空気感染」の問題を中心に、日本の感染症対策を決める「感染症ムラ」の構造的な問題を見ていく。
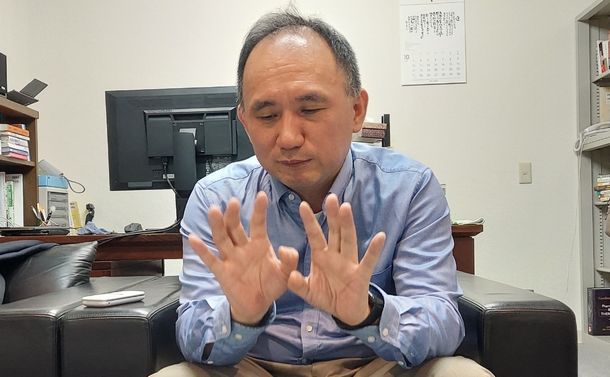 上昌弘・医療ガバナンス研究所理事長
上昌弘・医療ガバナンス研究所理事長――ロング・インタビューを締めくくるこの第6部では、厚生労働省・医系技官のコロナウイルス対策の中で最大の失敗の一つである「空気感染」の問題について、まずお聞きしたいと思います。よくご存じだと思いますが、2022年2月1日に、感染症や物理学などの日本の専門家8人が国立感染症研究所に対して質問状を送りました。
上昌広 連名で抗議しましたね。
――そうですね。抗議の意味合いを含む質問状を送ったんです。というのは、22年1月13日に感染研が公表したオミクロン株に関する第6報にこんなことが書いてあったんです。
「現段階でエアロゾル感染を疑う事例の頻度の明らかな増加は確認されず、従来通り感染経路は主に飛沫感染と接触感染と考えられた」
感染経路については、空気感染(=エアロゾル感染)がメインであることが世界の医学界、科学界で常識になっている時に、大変驚くべきことを報告しているんです。
上 もう宗教ですね。
世界中の医学者・科学者は、2020年2月から3月にかけて横浜港で展開されたダイヤモンド・プリンセス号の問題を注視する中で「空気感染」の可能性に気が付いた。感染者とは別の船室にいる人がエアコンのダクトを通じてコロナに感染した事実が判明したからだ。これを米国最先端の科学者グループから知らされた東京大学・シカゴ大学名誉教授の中村祐輔氏が上昌広氏に連絡。日本の一部でも知られることになった。
WHO(世界保健機関)は当初、「空気感染は一般的ではない」としていたが、2021年4月末に「一般的な感染経路の一つ」と認めた。米国の世界的科学誌『サイエンス』は同年8月27日号で「呼吸器系ウイルスの空気感染」という総説論文を掲載し、「コロナウイルスの主要な感染経路は空気感染」という理解が世界の医学界、科学界に定着した。
しかし、厚労省・医系技官はこの事実をなかなか認めず、日本のコロナウイルス対策の大半は世界の医学界とは方向が異なるものとなった。
――これを報じた毎日新聞に対して、質問状を出した専門家代表の本堂毅・東北大学准教授はこうコメントしています。
「世界では接触感染が起きるのはまれと考えられているのに、感染研は主な感染経路として、いまだに飛沫感染と接触感染を挙げている。国内のコロナ対策は感染研の見解を基に展開されており、このままでは無用な感染拡大を起こしかねない」(2022年2月1日付毎日新聞)
上 その通りですね。
――これに対して、感染研の脇田隆字所長から2022年2月7日に返答がありましたが、これがまた驚くべき内容です。
「ご質問の内容につきましては、研究者の間で議論の途上にあるところと認識しており、学術界において科学的な知見を基に合意形成がなされていくべきものと考えております。国立感染症研究所といたしましては、今回お問い合わせのあったご意見も参考にしながら、今後とも最新の科学的な知見に基づき感染症対策に資する情報発信を適切に行っていく所存です」
上 まあ役人が書いたものでしょう。
 国立感染症研究所=東京都新宿区
国立感染症研究所=東京都新宿区――空気感染について、「研究者の間で議論の途上にあるところと認識しており」というのは、驚くべき回答ではありませんか。
上 もちろん研究の途上であることは認めますが、空気感染のウェイトが高いのであれば、現実の対策としてその対応を取らなければなりません。空気感染するのであれば、飛沫感染対策はほとんど意味をなさない。「三密」をコントロールするだけでは意味がないんですね。
なによりも一番重要なことは、コロナは屋内感染が大半で、屋外ではほとんど感染していないという事実です。この一例からしても、空気感染のウェイトが極めて高いことが予想されます。飛沫感染や接触感染であれば、屋外でも感染しますからね。このことは2020年3月から言われていました。
これまでの日本の対策を考えてください。国民はよく覚えていると思いますが、飲食店を非常に厳しく規制してきました。しかし、これにはもう妥当性がないんですよ。飛沫感染などももちろんゼロではないですよ。でも空気感染のウェイトが極めて大きいのであれば、飲食店にだけ営業制限をかける合理的理由はもうないんです。
一方で、飲食店などが入っているビルの換気は、コロナウイルスの感染拡大に非常に大きく影響します。だから、そういうところには二酸化炭素モニターを使って合理的な対応を取ることが重要です。
満員通勤電車の問題もあります。ここでの換気の問題などは、まさに感染研が研究すべきものです。でも、感染研はJRや営団などとのハレーションを恐れてやらないのではないでしょうか。こういう問題は大学に研究費を補助して研究させた方がいいんですね。
――感染研はそもそもやる気がないんじゃないですか。
上 はっきり言って、学者じゃないんです。科学誌『サイエンス』は総説論文で明確に「空気感染」を打ち出しています。Airborne transmission、あるいはairborne infectionとはっきり書いている。文字通り「空気感染」という意味です。分科会の「専門家」が、「空気感染とエアロゾル感染は別だ」などと些末(さまつ)な議論をしていましたが、全然お話になりません。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください