いつの間にか、全原発再稼働が前提、FITの変質、自由化後退……
2015年02月16日
「日本は長い間原発なしで過ごしているんだから、もうあまり要らないのでは?」。こういう声をよく聞くが、現実は甘くない。国の政策はその逆、原発回帰へ向かっている。注意すべきは、あまり議論もないまま、さまざまな分野で小さな決定が積み重ねられ、それが外堀を埋める形になって議論の方向を縛りつつあることだ。「全原発の再稼働を前提」「FIT(固定価格買い取り制度=Feed in Tariff)の実質改悪」「電力自由化の先送り」などなど。原発回帰への道は周到に敷かれつつある。
長期のエネルギー政策を考える審議会「長期エネルギー需給見通し小委員会」(委員長、坂根正弘コマツ相談役)が1月末にスタートした。ここで今後のエネルギー政策、とりわけ原発の扱いが決まる。単に重要というだけでなく、原発事故後4年間の日本社会の議論の到達点が問われる。
最初の会合で坂根氏は「まずはすべての議論の出発点は省エネと再エネ(自然エネ)がどこまでできるのか、ここを出発点にしてはどうか」と述べた。多くの人が賛同する考えだが、現実に自然エネの可能量を「どんな方法で計算するのか」がカギだ。その点で心配な状況が広がっている。
昨年の九州電力・川内原発に続いて、2月に関西電力・高浜原発の2基も新規制基準に適合と判断され、再稼働に近づいた。日本には48基の原発がある。今のところ「適合」は4基だが、多くの人の関心は「いくつ再稼働するのか」だ。
4年前の福島原発事故が日本のエネルギー政策に突きつけたのは、A「原発を減らす」、B「自然エネを増やす」、C「電力制度の自由化を進める」の三つに要約できる。この三つは互いに関連していて、すべてを着実に進めなければ、どれも前に進まない関係にある。
3点について、福島事故後、かなりまじめな議論が展開された。原発については民主党政権が「2030年代に脱原発をめざす」という方針を立てたが、自民党政権はそれを否定した。ただ、「原発の寿命を原則的に40年とする」という方針は今も残り、原子力規制委員会も40年を超える運転延長には厳しい姿勢で臨むとしている。「寿命40年」が厳密に守られれば、短期間で原発数は急激に減っていく。
自然エネについては、欧州で成功しているFITが導入された。電力自由化の議論も続いている。
この流れが変わりつつある。まず自然エネルギー。FIT開始から2年経った昨年9月、電力会社は、「太陽光発電の計画が多すぎる」として送電線への接続を中断し、FITの制度が止まった。結局、電力7社が「これくらいしか導入できない」という少なめの接続可能量を発表し、政府が認め、小さな数字が「実質的な上限値」になってしまった。さらに「接続しても電気を引き取らない条件」も緩められ、太陽光だけでなく、自然エネ全般で導入の熱気は失せてしまった。FITは「全量を固定価格で買い取る制度」だが、変質してしまった。
 FITによる自然エネの買い取り中断、ルールの変更について九州電力の説明を聞く事業者たち。九州では影響を受けたり、建設を断念せざるをえない発電計画が極めて多く、事業者の不満が大きい。2015年2月4日、大分市内で。撮影・朝日新聞
FITによる自然エネの買い取り中断、ルールの変更について九州電力の説明を聞く事業者たち。九州では影響を受けたり、建設を断念せざるをえない発電計画が極めて多く、事業者の不満が大きい。2015年2月4日、大分市内で。撮影・朝日新聞この接続可能量の議論は「系統ワーキンググループ」という審議会で行われたが、そこで原発のとんでもない優遇があきらかになった。電力需要を埋めるためには、まず原発を優先して使い、あまったスペースで自然エネを考えるのだが、そのとき「今ある原発はすべて再稼働する」と考えるのである。稼働率は「福島事故前の30年間の平均」。つまり、48基すべてが昔の高稼働率で動くのが前提になる。
「寿命40年」は考えない。さらに、廃炉予定の原発も、加えて大間原発や島根原発3号機など建設中のものも含めて計算する。リアルさが全くない原発優遇である。それだけの原発を机上で動かしたうえで自然エネを考えるので、自然エネの入り込む枠は小さくなってしまった。
この計算方法が大問題なのだが、審議会では、資料の中で分かりにくい表現で書かれているだけで、きちんとした議論はなかった。極めて重要な考えが、こっそり決まってしまった。
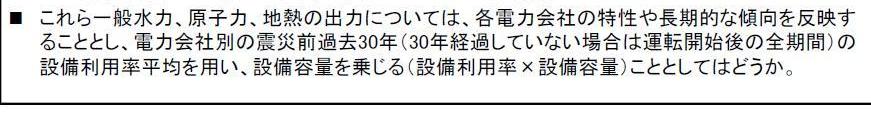 審議会の資料の表現。これが「全原発の再稼働、かつ高稼働率での運転」を意味することになった。最初は分かりにくい。
審議会の資料の表現。これが「全原発の再稼働、かつ高稼働率での運転」を意味することになった。最初は分かりにくい。もう一つは、各電力会社間を結ぶ連系線の扱いだ。陸上の風力資源の4割は北海道にあるように、自然エネ資源は偏在する。風力がつくる電気を連系線を使って関東、関西の大消費地に送れば多くの自然エネ設備が導入できる。しかし、これも連系線による全国融通はほとんどしないという条件で、自然エネの接続可能量を計算した。
欧州各国ではFITが自然エネを増やす強い武器になった。うまくいった背景には、欧州ではすでに電力自由化が進み、発送電分離が行われ、送電部門が公的な機関で運営されていたことがあげられる。日本は地域の巨大電力会社が送電線を所有し、自然エネ事業者は電力会社のライバルという関係にあるので、どうしても自然エネの受け入れを嫌がる。「発送電分離なきFIT」の悲しさともいえる。
電力自由化の議論もおかしくなっている。電力自由化では、A「15年をめどに、広域的運営推進機関をつくって連系線の利用を拡大する」、B「16年をめどに電力の小売りを全面自由化」、C「18~20年をめどに発送電分離(送電線の法的分離)をする」の3方針が決まっており、これらを盛り込んだ電気事業法の改正案が今年の国会で成立する見込みだ。
この分野もじわじわと後退している。「広域的運営推進機関」は連系線を積極的に使うための組織だが、本当にそうなるのかどうか。もともとの組織名(仮称)は「広域系統運用機関」だったが、いつの間にか「広域的運営推進機関」に変わったのである。
「広域系統運用」は送電線を全国規模で使って電気を融通するという明確な意味がある。しかし、「広域的運営」では「何を広域的に運営」するのかはっきりしない。定款の目的を示す条文を見ても、停電など非常時に融通をするように読める。通常時はどうなのか?
そもそもこれまでESCJ(電力系統利用協議会)という組織があったのだが広域融通に機能せず、そこで新組織ができることになった。それなのに、できる前からこうでは先が心配だ。「ESCJパート2」になる心配がある。
また発送電分離では、「18~20年をめど」としていたが、2月、経産省は「20年」にする方針をかためた。さらに電力業界は「安定供給確保などの準備が整わなければ延期する」という条件をいれることを求めている。安定供給の準備とは、十分な数の原発の再稼働などだ。ここでも原発が前提になっている。
要するに、「原発を優先」し、「自然エネを後回し」にし、「電力自由化は先送り」するような仕組みができつつ
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください