産学連携でも起業支援でもブレない政策が成果をあげている
2018年03月21日
ドイツの科学技術政策にあって日本の政策にないもの。それは息の長さではないだろうか。同じ政策、制度が長年続くことによって確実に成果を出しているドイツと、数年で終わるプログラムを取っ替え引っ替え出していく日本との差はあまりに大きい。若手研究者支援、産学連携支援、起業支援という3つの面からみてみよう。
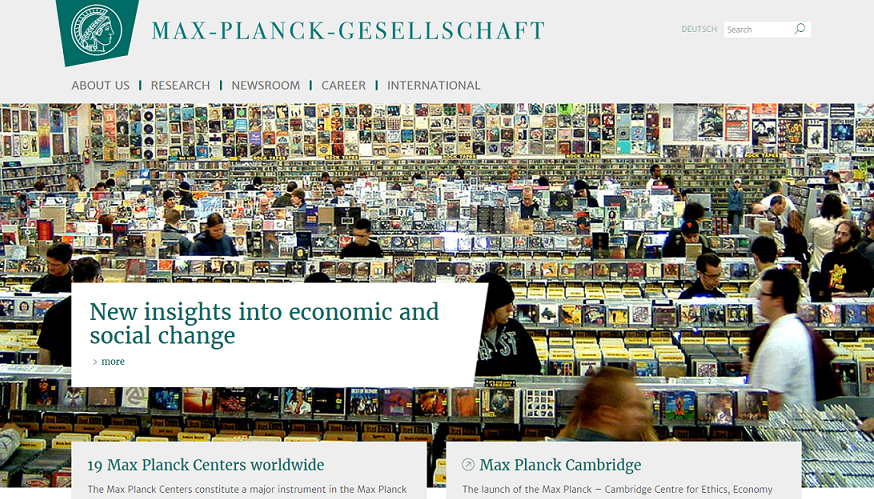 マックス・プランク学術振興協会のホームページ(英語版)
マックス・プランク学術振興協会のホームページ(英語版)大学にいる研究者を支援するドイツ研究振興協会は1999年、若手研究者の早期独立を支援するため、博士号取得後2~4年以内の若手研究者を年間支援額16万ユーロ(約2,200万円)で5年間支援するエミー・ネーター・プログラム(エミ―・ネーターは20世紀初めに活躍したドイツの女性数学者)を創設したが、これはマックス・プランク協会の研究グループリーダー制度を参考にしたといわれている。
 ドイツの女性数学者エミー・ネーター=ウィキペディアコモンズ
ドイツの女性数学者エミー・ネーター=ウィキペディアコモンズ欧州連合(EU)も2007年より、それまでの産業競争力強化のための研究開発を行うグループへの支援だけを行っていた研究開発支援の考え方を転換し、欧州の頭脳ともいうべき研究者個人をも支援することに舵を切った。ここでも若手研究者支援に力が入れられ、博士号取得後2年以上7年以下の若手には、5年間で150万ユーロ(約2億1千万円)、7年を超え12年以下の研究者には5年間で200万ユーロ(約2億8千万円)が支援されている。2016年度では前者で325人、後者で314人が採択された。
この若手研究者支援策はドイツのシステムと似ている。それもそのはずで、エミー・ネーター・プログラムを創設した当時のドイツ研究振興協会のヴィナカー会長が、その後、欧州連合におけるグラント創設時の事務局長に就任していたからである。よいシステムであれば、国を越えてでも伝搬し、長く続いていくことが当然と考えられているのである。
 ミュンヘン郊外マルティンスリート地区の起業支援会社バイオ・エム社の入るビル=2014年8月29日、筆者撮影
ミュンヘン郊外マルティンスリート地区の起業支援会社バイオ・エム社の入るビル=2014年8月29日、筆者撮影地域の産学連携の促進という観点から連邦政府が始めたクラスター支援政策の最初のものは、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください