人工林拡大の中で進んだ開放地と大径木の消失が、大型猛禽類の減少を招いた
2018年05月08日
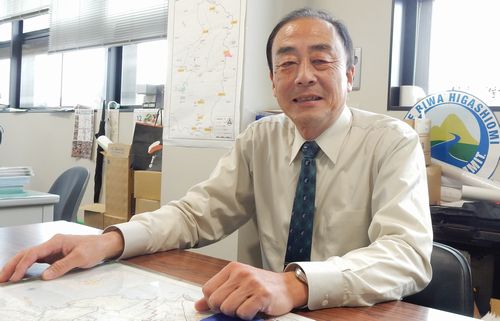 山崎亨さん
山崎亨さん◇ ◇
――日本のイヌワシの生息環境は、世界的に見て特殊だと聞く。
 森を飛ぶイヌワシ。こんな環境にすむのは日本だけとされる=井上剛彦さん提供
森を飛ぶイヌワシ。こんな環境にすむのは日本だけとされる=井上剛彦さん提供 ――行動がどう変わったのか?
つがいでの狩りの頻度が高い。1羽が木のない所へ獲物を追い出し、もう1羽が狩るという戦法を採ることが多い。だから1年中つがいで行動し、どちらかが死ぬまで2羽のつがい関係が続く。これは世界的に見ると、すごく珍しい。巣は主に断崖の岩棚に造られ、雌は2卵を産む。ところが2卵目のひなの孵化は1卵目より3日ほど遅れ、孵化直後から1卵目のひなによる攻撃を受ける。この『兄弟殺し』『兄弟間闘争』と呼ばれる行動が日本では極めて激しく、ひなが2羽ともに巣立つ確率は1%にも満たない。獲物の量が限られる森林地帯で、確実に1羽が育つように適応した結果だと考えられている。
――森林にすんでいるイヌワシだが、周辺にある開放地が貴重な狩り場となってきたわけだ。
かつて森林は焼き畑として利用されたり、薪や炭を得るために伐採されたりして、山間部にも開けた場所が点々とあった。茅場や採草地などと呼ばれる草原も各地に広がっていた。そうした人工的な開放地がなかったら、イヌワシは獲物を捕れず、日本で個体群を維持できなかったのではないか。少なくとも人間が森を利用するようになってから、日本のイヌワシは人の暮らしと共存してきたと言える。
――イヌワシの繁殖成功率は1980年代から低下するようになったと言われる。その頃から森に変化が起こったのか?
私が調査のフィールドとしていた鈴鹿山脈で、初めてイヌワシを見つけたのは1976年だった。当時は伐採地がいっぱいあり、植林から数年の場所もたくさんあった。イヌワシが狩りをしやすい環境が広がっていた。しかし、戦後の拡大造林で植えられたスギやヒノキがどんどん成長し、かたや燃料革命で石油やガスが普及したため、薪炭林が定期的に伐られることはなくなった。草原も放置されるようになった。このため4~5年も経つと灌木が伸びたり草が大きくなったりして、イヌワシは狩りをしにくくなっていった。日本イヌワシ研究会は、1981年から毎年、繁殖状況を調べているが、当初
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください