「日本は将来のエネルギーについて決定すべき時」 アミン前IRENA事務局長
2019年06月03日
日本で開かれる主要20カ国・地域(G20)エネルギー・環境関係閣僚会議や首脳会議を前に、政府は地球温暖化対策に関する「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略(仮称)」をまとめる。長期戦略は、パリ協定で2020年までに提出することを求められており、主要7カ国(G7)では、日本とイタリアだけが未提出だった。G20議長国として、メンツを守ることが主な目的なので、これまでの政策の焼き直しになりそうだ。
 国内有数規模の風力発電所「宗谷岬ウインドファーム」。風車57基が並んでいる=北海道稚内市
国内有数規模の風力発電所「宗谷岬ウインドファーム」。風車57基が並んでいる=北海道稚内市 世界に目を向ければ、再生エネはとっくに主力電源になっている。REN21(21世紀のための自然エネルギー政策ネットワーク)の「自然エネルギー世界白書2018」によれば、2017年に新規導入された再生エネ発電設備は178GW(1億7800万kW)で、全体の発電設備の増加分の70%を占めた。投資額の約75%は、中国、欧州、米国に向けられた。
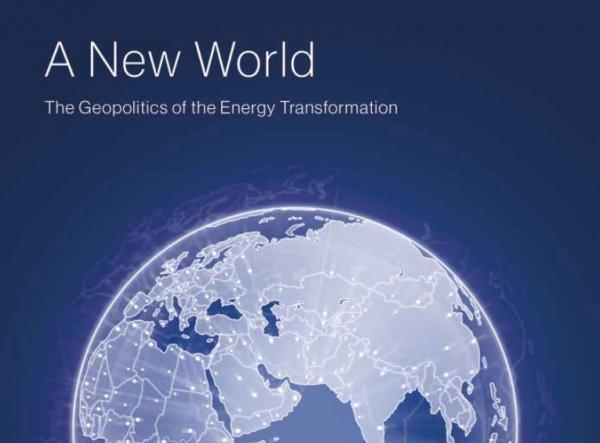 IRENA報告書「新たな世界:エネルギー変容の地政学(A New World: The Geopolitics of Energy Transformation)」
IRENA報告書「新たな世界:エネルギー変容の地政学(A New World: The Geopolitics of Energy Transformation)」報告書は、今年4月に8年間の任期を終えた前事務局長のアドナン・アミン氏が中心となってまとめられた。退任前に日本への提言を含めて聞いた。
――今回の報告書の目的は何か。
アミン ここ10年間に世界のエネルギーに起きた大きな変化を、理解するためだ。エネルギー全体で、最も伸びが著しかったのは再生エネだ。過去6年間、毎年、最も発電設備量を伸ばしたのは再生エネだ。コストも下がり、ほかのどのエネルギーと比べても競争力を持つようになった。
これまでのエネルギー資源は、一部の国々が保有していたので、それらの資源国は、エネルギーを戦略的、政策的に活用することができた。だが、再生エネでは、すべての国々がある程度は自分たちのエネルギーを国内でまかなえる。エネルギー自給や自立もある程度は可能だ。これは国家間の力関係にも大きな意味を持つ。
 アドナン・アミン前国際再生可能エネルギー機関事務局長
アドナン・アミン前国際再生可能エネルギー機関事務局長――それはどういうことか。
アミン 再生エネの導入拡大によって、電化やシステムの安定性が進む。化石燃料時代は、エネルギーの確保が力の源泉だった。だが、これからは再生エネへの投資や技術革新が力を生む時代になる。化石燃料の資源を持っているかどうかは、もはや問題ではない。
これまでの過去50年間に支配的だった国家間の力関係は、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください