世界ではとっくに同様の制度あり、何より継続が大事
2019年12月24日
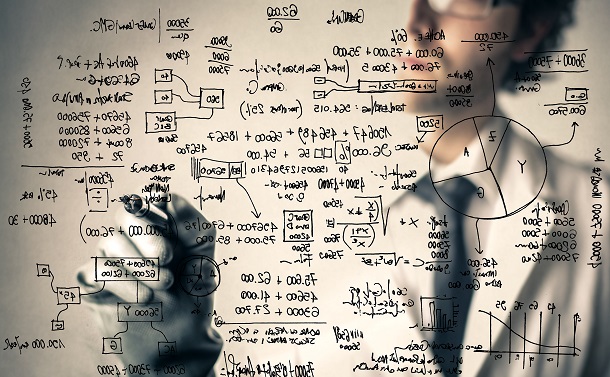 shutterstock.com
shutterstock.comまず、今回の案について調べると、これは令和元年度の補正予算による経済対策の一環としての事業として考えられているもので、そもそもの発端は平成31年4月の経団連の提言にあることがわかった。そこには「政府研究開発投資の方向性として、Society5.0の実現を目標とした『戦略的研究』と、特定の課題や短期目標を設定せず、多様性と融合によって破壊的イノベーションの創出を目指す『創発的研究』の2つに注力すべきである」とある。この後者を実現する具体的な政策が今回の若手支援策ということになる。
では、欧州の若手研究者支援はどのような状況にあるのだろうか。
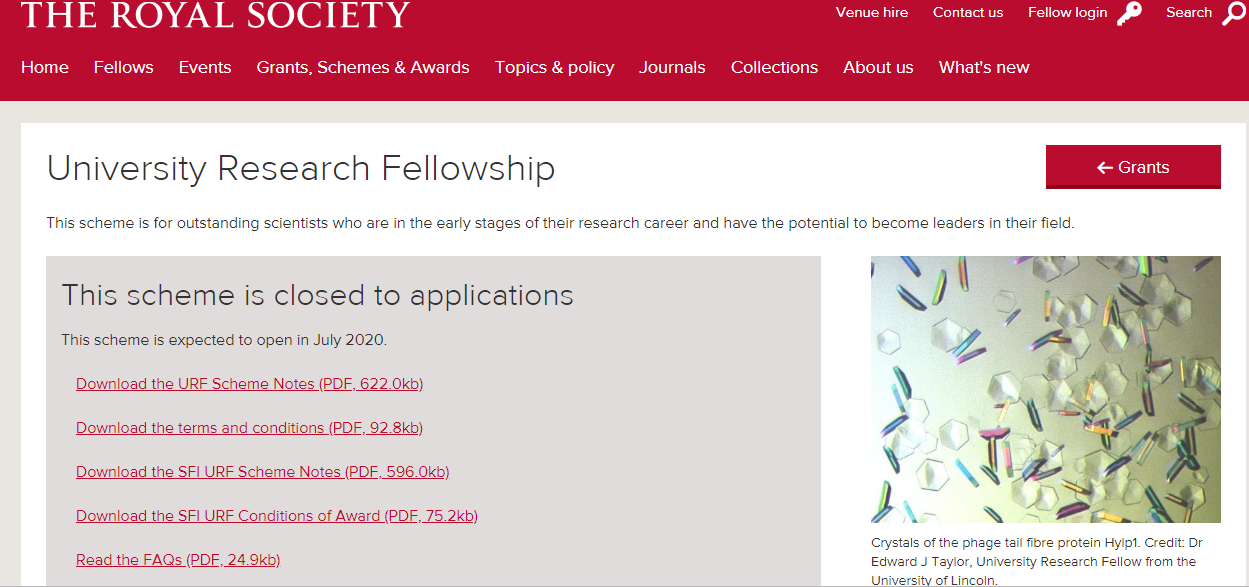 英国王立協会のユニバーシティー・リサーチ・フェローシップのHP
英国王立協会のユニバーシティー・リサーチ・フェローシップのHPドイツでは基礎研究を行うマックス・プランク研究協会のグループリーダー制度が知られている。1969年に創設され現在まで50年も続くこの制度では、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください