地域のありのままを可視化する『相馬INDEX』の挑戦とは
2020年03月19日
2月1日から2日にかけて、福島県を訪れた。NPO法人ETIC.が主催する「福島の食の復興応援ツアー」に参加し、福島県各地の「食」にかかわる現場を訪ね、そこで働く人たちの声を聞いてきた。
相馬市では、最後の仮設商店街にある食堂で地元食材に舌鼓を打った。漁業はまだ試験操業ではあるものの、「常磐もの」と呼ばれる新鮮な魚介類の卸売りをする若社長からその魅力を聞いた。
福島市では、完熟モモを瞬間冷凍したスイーツの商品化に成功した女性社長の話を聞き、ビールや餃子の商品開発に取り組む農業法人を訪ねた。会津若松市の農園ではネギの収穫を体験し、別の農園でトマトのジュースを試飲した。
筆者は2011年3月の東京電力福島第一原子力発電所の事故以来、何度も福島県を訪れ、「食」にかかわるプロフェッショナルたちに話を聞いてきた。今回聞くことのできた話は、事故から数年の時期とは大きく異なり、新しい事業の開始などポジティブな話題が多かったように思う。
 福島の現状を解説する復興支援センターMIRAIの押田一秀所長
福島の現状を解説する復興支援センターMIRAIの押田一秀所長主に収録されているのはもちろん相馬市のデータなのだが、比較のために福島県全体や他の市町村のものもあり、県全体の状況も理解できる。筆者は興味深くそれを読みながら押田の話を聞いていたのだが、そのときには、数週間後にデータが切実なほど重要となる事態−−新型コロナウイルスのアウトブレイク−−が、震災以来、再び訪れるとは思ってもみなかった。
このデータブック『相馬INDEX』の誕生には背景がある。2005年8月、アメリカ南東部の都市ニューオリンズを襲ったハリケーン・カトリーナだ。死者・行方不明者は2541人、アメリカ史上最悪の自然災害になった。
ところが……。災害後の数年でニューオリンズは全米で有数の「起業しやすいまち」に変貌した、という評判が日本に伝わってきた。たしかに「起業した個人」の数を見ると、カトリーナ以降で激増しており、アメリカの他の主要都市をはるかに上回る。
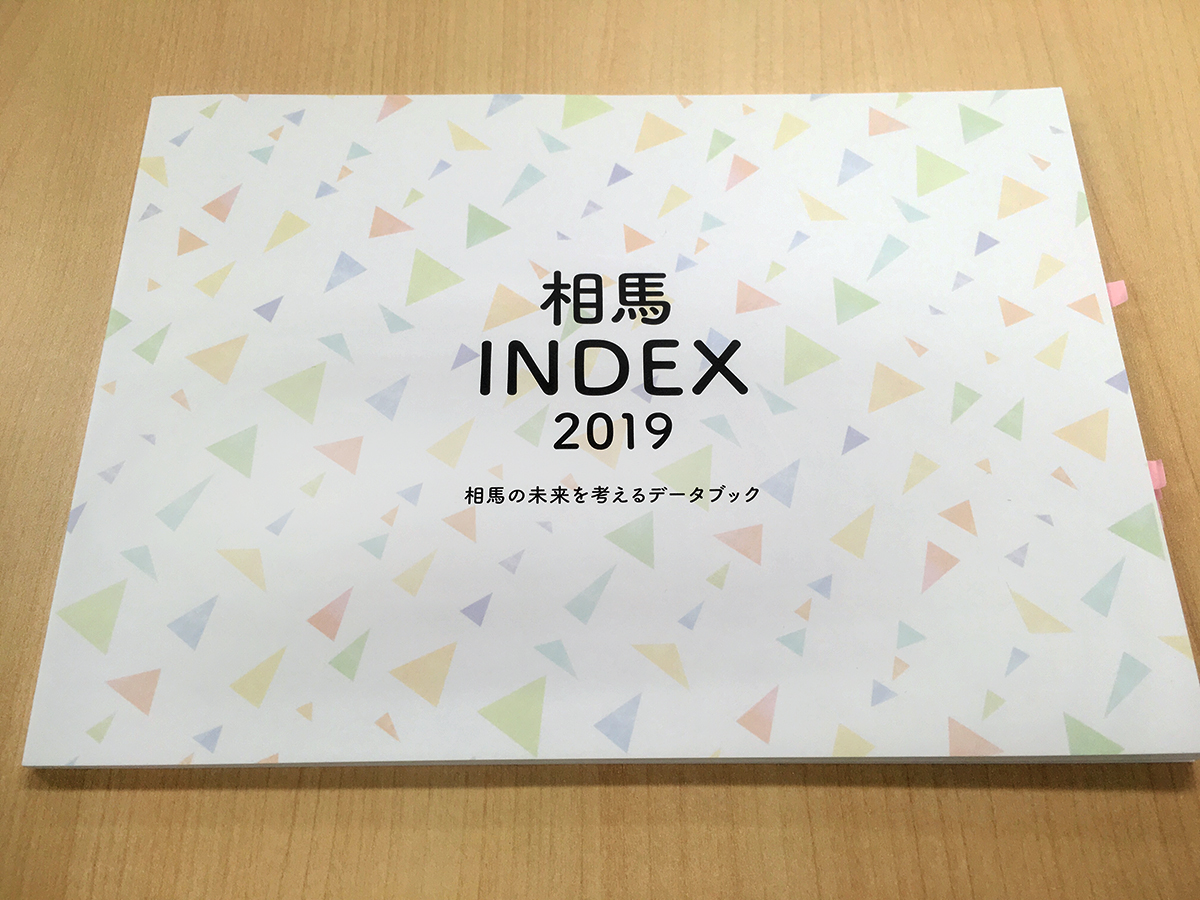 地域の環境や社会、経済の豊富なデータを収録するデータブック
地域の環境や社会、経済の豊富なデータを収録するデータブック有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください