新型コロナウイルスの画像を無神経に使いまわすな
2020年05月07日
在宅勤務をするとテレビを視聴する機会が増えがちだ。しかし、ワイドショー(一部の報道番組も含む)のコロナウイルスの取り扱いに不愉快にさせられる事が多い。見るほうが悪いと言われればそれまでだが、情報を知るためにテレビを全く見ないわけにもいかない。私の感じる不愉快さは、番組制作者がいつもどおりの決められた手順を繰り返すだけで、自分の頭で考えている様子が全くないためのようだ。
 不愉快とはいえ、テレビを全く見ない生活は難しい
不愉快とはいえ、テレビを全く見ない生活は難しい残念なことに、テレビ局の姿勢を自ら常に点検し必要に応じて修正しようとする動きは見られない。私も過去3回の記事(3月4日、4月2日、4月5日)でこの問題を提起してきた。それらと一部重複するものの、あえてワイドショー(及び一部の報道番組)が是正すべきと考えるいくつかの問題点を指摘させて頂きたい。関係者がこれを読むかどうかはわからないが、我々がこの危機を乗り越える上で支えとなるような番組を制作してくれることを切に望む。
コロナの話題となると、必ずウイルスの拡大画像が画面一杯に映し出されるのがお約束だ。オレンジ色と白黒の二種類、といえば誰でも目に浮かぶであろう。ネットニュースや新聞の電子版記事のアイコンとしても多用されている。しかしなぜそのようなどぎつい画像を用いる意味があるのか。私が最も気になるのはこの画像である。些細なことだと思う人もいるかもしれないが、制作者が自分でものを考えず、無意識にインパクトのある画像を示すことが当然だと思いこんでいる端的な例だと思うのだ。制作側のオリジナリティーの欠如を笑ってすませられるだけではない。毎日不安な話題ばかりに接している視聴者が、幾度となくあの画像を見せられたらどうなるだろう。
阪神淡路大震災、地下鉄サリン事件、東日本大震災の際、繰り返される報道画像のためにPTSD(心的外傷後ストレス障害)となった方がいたことが問題となった。今では、東日本大震災の津波の画像を映す際には、テロップや口頭で予め注意することになっている。過去の例から学ばないにも程がある。実際私は、画面いっぱいに映るウイルス画像に続き、それをご丁寧にも4分割、16分割、と次々に同じ画像を細かく増殖させた連続映像を見せつけられ、すっかり気持ち悪くなったことがある。過去の例から学び、自分たちの番組が視聴者に過剰な不安感を植え付けてしまう可能性を十分認識してほしい。
民放のワイドショー(含むワイドショー的報道番組)はほぼ2時間枠のようだ。在京4局(テレビ東京はワイドショーを制作していないようだ。一つの見識だろう)が、午前・午後・夕方の3回ほぼ似たような内容を別番組で繰り返している。その半分以上の時間はコロナ関係に費やされている。ニュース的な価値のある本質的な情報量はせいぜい20分程度だろう。それ以外は、意図的にインパクトを与えるような画像、単なる憶測や雑談、必ずしも科学的とは思えない説明をくどくど付け加えてコマーシャルにつなぐことで、なんとか2時間視聴者をひきとめようとしているように思える。
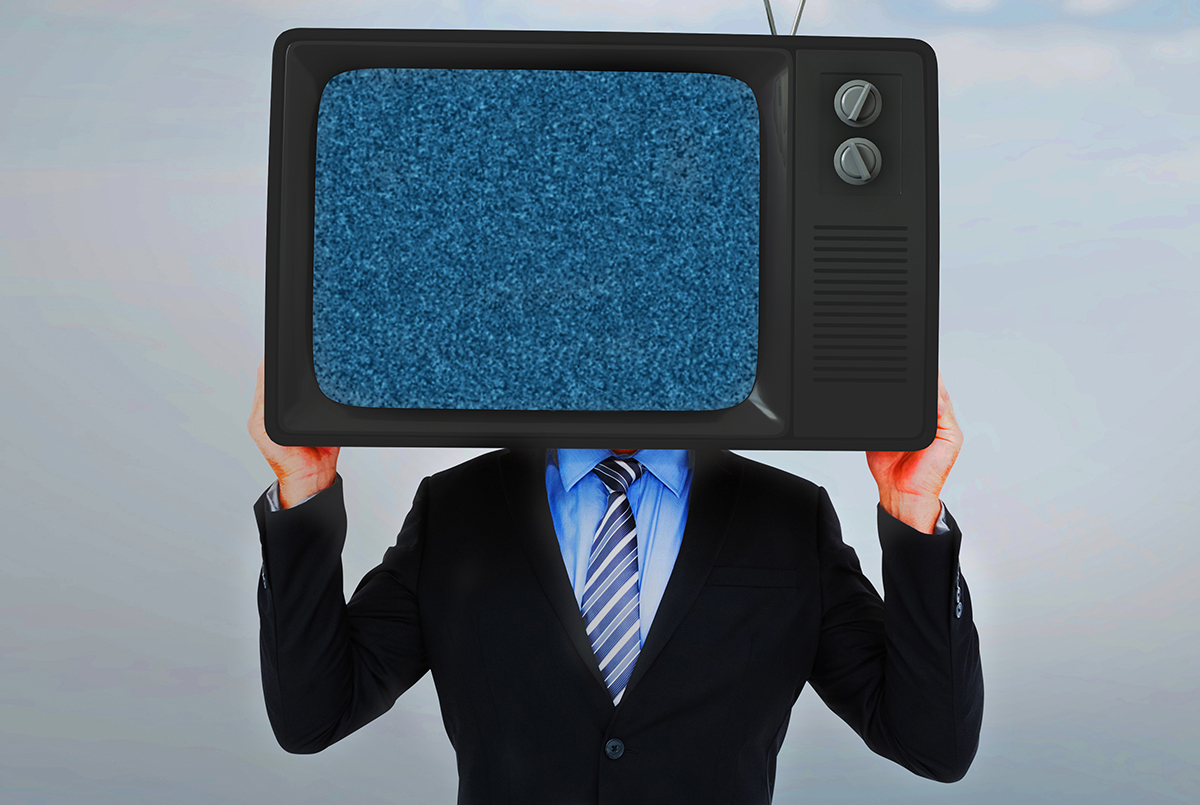 高齢者にはとりわけ、テレビは大切な情報源だが
高齢者にはとりわけ、テレビは大切な情報源だがテレビ局が互いに調整してそれらの順番をずらせておけば、視聴者はどれかのチャンネルで自分がみたい内容を選ぶことができる(事情は異なるが、大学のオンライン講義化は同時に講義のオンデマンド化に直結するので、学生にとっては選択の自由度が格段に増える)。あまり意味のないレギュラー出演者に出演料を払うのではなく、音楽・文化活動(笑顔を与えてくれる芸人も含む)ができず困っている人たちに正式に仕事を提供できる良い機会ではないだろうか。
テレビを見ない若者には関係ないだろうが、インターネットにふれることが難しい高齢者にとってやはりテレビは大切だ。このような状況だからこそ、テレビ的にインパクトのある映像を刹那的に見せ視聴率をあげる利益至上主義から脱却してほしい。
専門家「集団」が時間をかけて完成させた科学的知見は信頼できるものの、その途上での専門家の個人的解釈はおうおうにして間違っていることが多い。だからこそ、異なる意見をもつ専門家同士が互いに議論して、その真偽を検討することが不可欠だ。決して、テレビで解説してくれる専門家を信じるなと言っているのではない。科学とはそのような過程を経てやっと信頼できるレベルに到達できる性格のものなのである。その意味で、まだ検証されていない「最新」の仮説をあたかも真実であるかのように伝えたり、特定の専門家の意見だけを取り上げたりするのは危険である。
 特定の専門家の意見だけ取り上げるのは危険だ
特定の専門家の意見だけ取り上げるのは危険だテレビ出演を承諾してくれる専門家は限られている。治療薬やワクチン開発の最前線で活躍している研究者にはそんな時間はない。また、混乱を避けるためには個人ではなく学界として統一的な見解を公表すべきだと考える専門家も多かろう。当然、学界の公式見解が発表されるには時間がかかるし、慎重な結論に傾きがちだ。その結果、日々テレビで紹介されるある特定の専門家の意見が「専門家集団」を代表する見解であるかのように誤解させてしまっているとしたら、大問題である。
その専門家にすべて丸投げするのでなく、提供する情報の信頼性は、自分たちが責任をもって独立に取材し確認しておくべきだ。後で検証し、場合によっては明確に訂正することこそ放送人が守るべき倫理である。特に今回のように、未知のウイルスに関する情報の場合はなおさらだ。
この時期にわざわざ人出が多いところを探し出して、街頭インタビューする意義が私には理解できない。渋谷の若者、巣鴨のお年寄り、パチンコ店に行列する人々、スーパーで買物する家族。これらの人々に、マイクを向けて直接喋ってもらうことで何を伝えたいのか。自粛すべきなのにそうしていない人たちがいると世間に訴えているのか、逆に、このような人たちに自粛を強いることが間違っていることを知らせたいのか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください