同時多発テロ後を描くドキュメンタリー・フィクション映画「ザ・レポート」を見る
2020年05月25日
新型コロナウィルス感染症の拡大により、「ステイホーム」を余儀なくされたが、映画好きの私にとっては、不幸中の幸いで映画の「見ダメ」ができる貴重な期間となった。その中で、最も強烈な印象を与えたのが、米映画「ザ・レポート」であった。
原題は “The (Torture) Report”として、丸カッコのなかの「Torture(拷問)」の部分が黒塗りになっているのだが、その理由は本編を見ていただければと思う。この映画を見て、今の日本の国会や政治状況を見ると、いかに日本の民主主義が浅くて脆いものか。そう痛感せざるを得なかった。この映画を通して、コロナ対応に揺れる日本を振り返ってみたい。
この映画は、2001年9月11日の米国同時多発テロ後の米国を描いた実話に基づく、ドキュメンタリー・フィクション映画だ。9.11直後の米国は、「テロとの戦い」を背景に、全国で愛国的雰囲気が漂い、当時のブッシュ大統領は高い支持率を得て、米国愛国者法の成立(2001年)、国土安全保障省の設立(2002年)など、次々とテロ対策を強化していた。こういった高揚感が少しずつ薄れてきていた時期(2009)に、この映画の主人公である上院議会スタッフのダニエル・ジョーンズ(「スター・ウォーズ」シリーズのアダム・ドライバーが好演)は、CIAが実施した犯罪人に対する「拘留・尋問」に関する調査チームのリーダーに任命される。
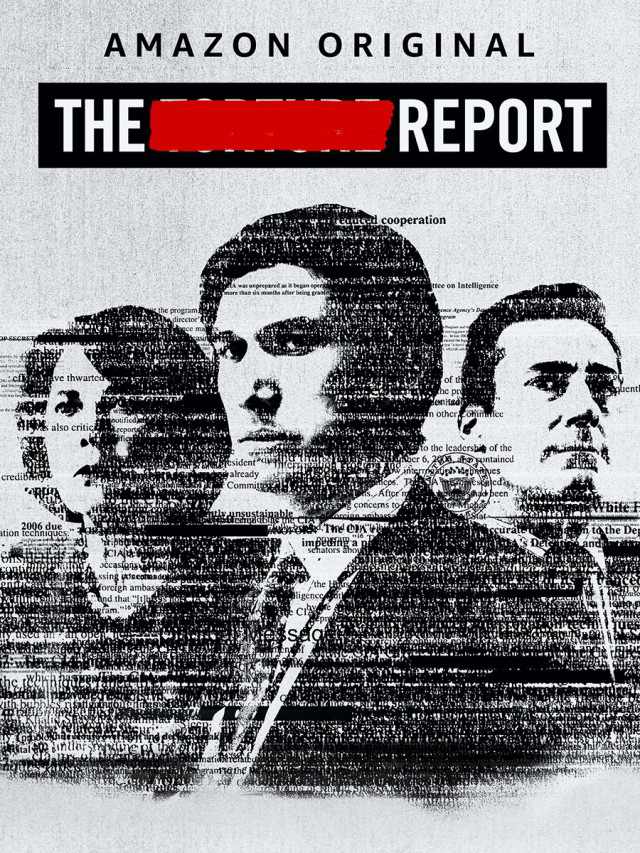 「ザ・レポート」(Amazon Prime Videoで配信中)から
「ザ・レポート」(Amazon Prime Videoで配信中)からCIAの内部でも疑問視されながら、尋問を任されたチームは「情報をとるには他に選択肢がない」との口実をつけて拷問を継続し、そのうち拷問自体が目的化していく恐ろしい過程、事実を隠蔽しようとする政権中枢部、その圧力を感じつつ長期にわたる調査に疲れ果てて辞任していく調査メンバー、上司でもある上院議員からも妥協を迫られる主人公……。まさに、米国政治のダークサイドを、これでもか、というばかりに暴露していく過程は、「アメリカでさえこうなのか」と救われない気分になっていく。
そしてジョーンズ氏が命を懸けて作った6700ページにわたる報告書は、闇に葬られそうになるのだが……。結末はぜひ映画を見ていただいて、この作品のメッセージをぜひ自ら考えていただきたい。残念ながら日本では未公開であり、現在はAmazon Primeで配信中である。
9.11を描いた映画としては、他にもおすすめの映画が目白押しである。ウサーマ・ビン・ラディン殺害までの過程を描き、CIAによる拷問シーンが出てきて問題となった「ゼロ・ダークサーティ」(2012)、テロを防げなかったCIAとFBIの対立を描いたNetflixオリジナルテレビシリーズの「倒壊する巨塔」(2018)、米国をイラク戦争へと導いたチェイニー副大統領を描いた「バイス」(2018)、イラク戦争の真実を追求した米地方紙記者の戦いを描く「記者たち~衝撃と畏怖の真実」(2019)などだ。
 「ザ・レポート」(Amazon Prime Videoで配信中)から
「ザ・レポート」(Amazon Prime Videoで配信中)から有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください