ファイザー、モデルナが挑む世界初の「mRNAワクチン」に立ちはだかる難題
2020年12月02日
最近、米国からのCOVID-19ワクチンの第3相臨床試験に関する2つの朗報が相次いで世界を駆け巡った。ひとつ目は、米ファイザー社と独ビオンテック社が共同で開発して11月9日に発表された「BNT162b2」、もうひとつは米モデルナ社が11月16日に発表した「mRNA-1237」だ。共に極めて良好な有効性が示された。
 世界的な製薬メーカー「ファイザー」が、新型コロナのワクチン開発に挑んでいる(写真はイメージ)
世界的な製薬メーカー「ファイザー」が、新型コロナのワクチン開発に挑んでいる(写真はイメージ)だがそもそも臨床試験の中間評価とは、「強い副反応が出た」または「薬効が著明なのでプラセボ投与の継続が倫理的に問題である」という際に、第三者委員会が試験を継続する是非を判断するためのものだ。継続するのであればその暫定結果を「中間報告」すべきではない。検者・被検者が印象操作されることによって、その後の治験の盲検性が失われる可能性があるからである。
「中間報告」の先陣を切ったのはファイザー社である。「ワクチン群とプラセボ群を合わせて94例の感染が確認され、ワクチン接種の有効率は90%以上であった」という内容だ。インフルエンザワクチンの有効率が年によっては30%程度であることを考えると、極めて高い数字であることには間違いない。だが、その医学的根拠については全く触れておらず、世界中に多くの混乱を招いた。
 バイオテクノロジー企業「モデルナ」もワクチン開発を進めている(写真はイメージ)
バイオテクノロジー企業「モデルナ」もワクチン開発を進めている(写真はイメージ)このファイザーの報告に対しては、多くの人が「ワクチンを接種した90%以上の人が新型コロナウイルス感染症を発症しなかった」と理解しているかもしれないが、これは誤りである。ワクチンの有効率とは「プラセボ対照群と比べてどれくらい発症を減らしたか」を見た数字である。すなわち、ワクチン接種群とプラセボ接種群を比較して、それぞれの群における発症数(発症率)を比較して出すのがルールである。
そこで、ファイザー社の「発症94例、有効率90%以上」だけの情報から考察すると、ワクチン群での発症は8例以下、プラセボ群は86例以上ということになる。本来なら86例が発症するところだったのを8例に抑えたとすると、86−8=78例の発症に減ったので、有効率は78/86 = 90.7%となる。もし、ワクチン群9例とプラセボ群85例の発症だとすると、(85−9)/85 = 89.4%となって90%を割ってしまうので、おそらく「有効率90%以上」とは、ワクチン群8例、プラセボ群86例だったのだろう。
一応、これを確認するためにファイザー社に問い合わせたのだが、「お問い合わせいただきました、『94例のワクチン群とプラセボ群の内訳』および『90%以上のワクチン有効性の具体的な算出方法』につきまして、現時点でご提供可能な情報はございません。この度は先生のご要望にお応えできず、誠に申し訳ございません」というご丁寧なお返事を文書で頂いた。ルールを無視してまで世界中に誤解を招くような曖昧なメディア発表をしておいて、もっとも重要な根拠の説明ができないとする理由な何なのか?
そう思っていたところ、9日後(11月18日)にファイザー社は「170例の感染者に達した最終分析」として、新たな発表をした。「ワクチン群8例とプラセボ群162例で、(162−8)/162 = 95.1%の有効率が示された。年齢層や人種を問わず有効で、重大な安全性の問題も生じていない」としている。11月20日に米食品医薬品局(FDA)に緊急使用許可(EUA)を申請するという。
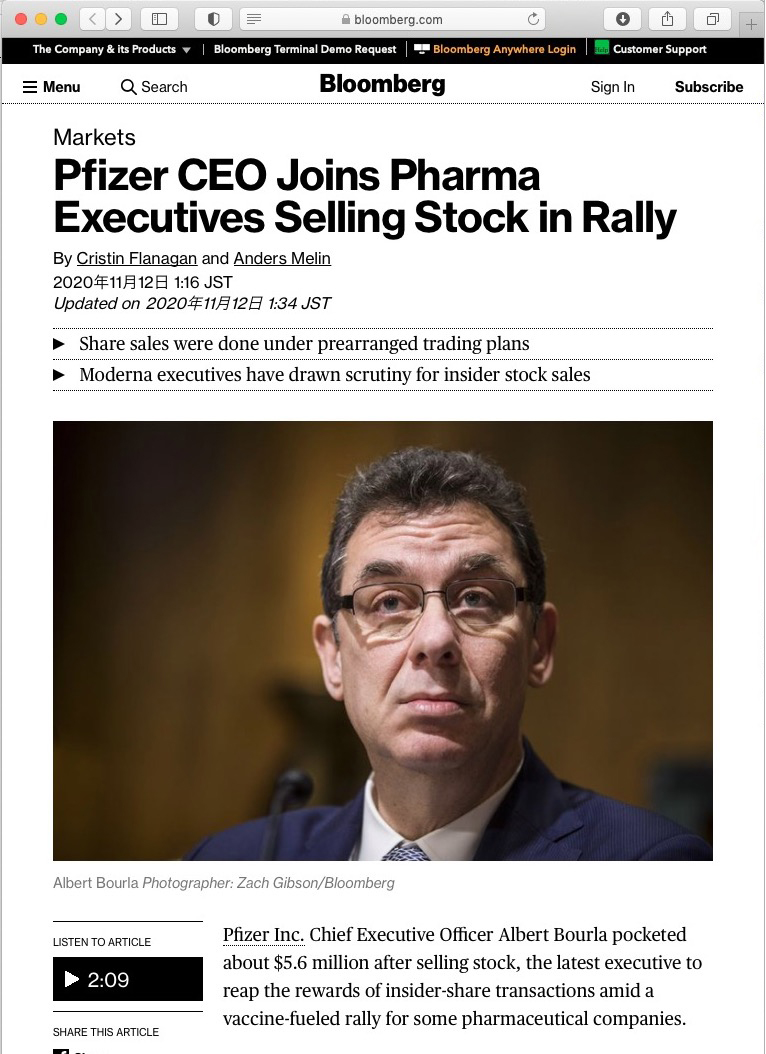 ファイザーのブーラCEOの株売却を報じるブルームバーグのサイト
ファイザーのブーラCEOの株売却を報じるブルームバーグのサイトこれを読んで「なんだ、自分の計算どおりで、そもそも隠すことではないんじゃないか」と思い、たった9日前に曖昧な「中間報告」をしたことへの疑惑がますます深まる。これはつまり、とにかくモデルナ社よりも先に発表することで、「世界に先駆けて」のインパクトが必要だったのではないか? そんな政治的・経済的な「オトナの事情」で医薬品開発を進めていいのか、と勘繰ってしまう。ちなみに、ファイザー社のブーラ最高経営責任者(CEO)は、「中間報告」発表当日の暴騰した株価で、持ち株の60%を売却して約560万ドル(約5億9000万円)の利益を得ているそうだ。これもまた見事なオトナの事情に見えてくる。
後塵を拝したモデルナ社は、ファイザー社から1週間遅れた11月16日に、「臨床試験に参加した約3万人のうち95人の感染が確認され、内訳はワクチン群5例、プラセボ群90例だった」と、腹を括ったように明瞭すぎる「中間報告」をしている。有効率は(90−5)/90 = 94.4%となる。その勢い(?)で、「感染例のうち、重症例11例のすべてがプラセボ群で、ワクチン群ではゼロであった」とも述べ、今後は数週間以内に米FDAにEUA申請を目指す予定だという。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください