多様性ある文理共同参画社会の実現へ
2021年03月15日
日本社会は、和をもって尊しとなす的価値観に支配されている。その結果、異なる意見を差し挟むことがあまり好まれない。しかし多様性を尊重しない社会は、変化に対して脆弱となり、適応できずに没落する。性別や年齢といった観点のみならず、文系と理系(このような区別自体がおかしいのだが)、さらには、大学院で学位を取得した専門性の高い人材に至るまで、意識的に多様性をとりいれバランスのとれた社会を実現することは、日本が国際的な存在意義を維持するために不可欠だ。
天文学分野に限らず、大学院で修士号・博士号を取得した学生の大半は、実は狭い意味のアカデミアではない職種に就職する。一方で、特に天文学専攻の大学院生の場合、在学中に学位取得後の多様なキャリアパスを知る機会に恵まれていないようだ。日本天文学会は日本学術会議天文学・宇宙物理学分科会と合同で2015年にキャリア支援委員会を立ち上げ、そのような学生のために活動している。
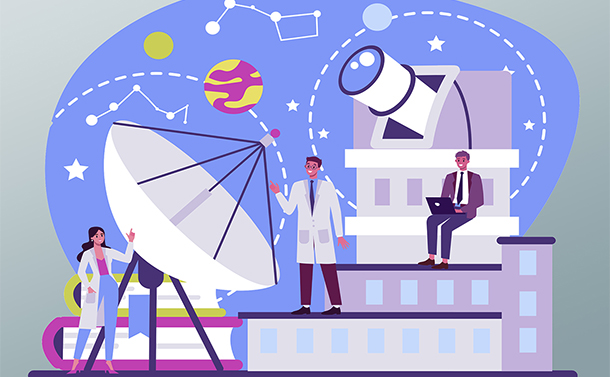 学位取得後のキャリアパスは多様か
学位取得後のキャリアパスは多様か今回お願いした8名は、5年から20年程度前に、国内の大学で天文学・宇宙物理学の修士号・博士号を取得した方々である。公立科学館、科学ジャーナリスト、文部科学省、衛星打ち上げ・運用、NHKで科学番組制作、天気予報など、研究の経験が活かせる多彩な職業で活躍されている皆さんの話は、大学という狭い社会での経験しかない私にとっても、とても刺激的であった。
会社づとめの傍らで社会人大学院生としてじっくりと学位取得を目指している方もいた。さらに、イタリアで博士研究員を経験した後、故郷の愛媛県でワイナリーを立ち上げたという極めてユニークな例を知ることもできた。大学院入学以来、あまり外のキャリアを知ることなく研究者となっている我々などよりも、はるかに高い問題意識をもち人生の選択をされている方々を目のあたりにし、参加した学生以上に、キャリア支援委員である我々自身の視野が広がったというのが実感だ。
私が博士号を取得したのは1986年。当時569名であった日本天文学会の正会員は、2020年には2172名(うち、学生が514名)に増加している(ただし、現在とは会員制度が異なっていた1986年には、かなりの学生は正会員ではなく準会員として所属していた可能性がある)。これは過去30年以上にわたる天文学の進歩を端的に示している。と同時に、ただでさえ少ない天文学関係の研究職ポスト数を考えると、天文学を学んだ大学院生が社会の多様な分野で広く活躍できる状況を整える重要性はますます高まっている。
第24期日本学術会議天文学・宇宙物理学分科会は、2018年と19年に、天文学博士号取得者に対するキャリアパス調査を実施した。その結果は、近日中に公開される予定であるが 、特に注目すべき点は以下に要約される。
科学雑誌Natureの2017年10月26日号に “A love-hurt relationship”という記事が掲載されている。これは世界中の広い分野の博士課程大学院生 5700人を対象として行ったサーベイ結果の紹介である。
強く不安に感じている問題はなにかとの質問(複数回答可)には、ワークバランス(55%)、キャリアパス(55%)、経済的問題(50%)、研究費(49%)、研究職の数(49%)、学位の価値に対する不安(32%)、複数回博士研究員を繰り返す人数の多さ(31%)、メンタルヘルス(28%)、との回答が続く。
 博士号取得者数が活躍する道は…
博士号取得者数が活躍する道は…一方で、約7割が大学院生活には満足だと回答していることからもわかるように、これらの悩みはいずれも将来のキャリアの不安定性からきているようだ。「好きだからこそ苦しむ関係」というタイトルは、研究は好きであるにもかかわらず自分の将来に強く不安を覚える学生の気持ちを表現したものなのだ。
将来就きたい職業の問いには、Academia(研究職)が52%、Industry(民間企業)が22%、Medical(医療関係)とGovernment(公務員)がいずれも9%、と回答されている。さらにpermanent job(任期なしの職という意味であるが、転職が当たり前の外国では、日本とは異なるニュアンスをもつのかもしれない)を得るまでに何年かかると予想するかとの問いには、6割近くが3年以内を選んでいる(約3割は4―6年、残りの1割がそれ以上を選択)。しかし、Academiaで任期のない終身研究職を得るには10年近くかかることが普通なので、現実はかなり厳しい。
日本の天文学・宇宙物理学の博士号所得者調査結果をみても、40歳近くまで任期付きの不安定な研究職を転々としている人は決して珍しくない。これは他の基礎科学分野においても、似たような状況だと思われる(ちなみに、誤解されているような気がするが、常勤研究職についたとしても給料はさほど高くない。最近話題となった内閣広報官の年収は東大総長とほぼ同額のようだ。そもそも東大総長が安すぎる気もするが、普通の教授はその半額程度でしかない。)。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください