日韓共同ワークショップに参加して
2021年07月14日
7月2日(金)、日本パグウォッシュ会議、アジア太平洋核軍縮・不拡散リーダーシップネットワーク(APLN)、世宗研究所の共催、明治学院大学国際平和研究所(PRIME)、長崎大学核兵器廃絶研究センター(RECNA)後援による、オンラインの国際共同セミナー「北東アジアにおける核のドミノの評価:北朝鮮の核の脅威と日本の対応」が開催された。北朝鮮や中国の核の脅威に対応すべく、韓国や日本が続いて核武装するシナリオを「核のドミノ」と呼び、そのような核の連鎖を防ぐための方策について、学界、メディア、NGOの専門家が意見交換を行うワークショップであった。
すでに第1回は5月にソウルで開催され、「韓国の対応」について意見交換が行われた。今回は2回目で、主に「日本の対応」についての意見交換であった。日本から11名、韓国から2名、米国から1名の合計14名が登壇した。なお、第3回は11月にソウルで、日韓の国会議員を招聘して開催される予定である。今回の会議の動画はウエブサイトで見ることができる。以下、今回の会議の要点をまとめてみた。
まず、ほとんどの参加者は、日本が独自に核武装する可能性は低いとの認識は共有できていた。一方で、共通した認識として、タイトルにある「北朝鮮の核の脅威」のみならず、中国からの脅威が高まっている、という認識も共有されていた。問題は、高まる隣国からの核の脅威への対応として、「核抑止力が不可欠であり、その強化が必要」との考え方が、政府や安全保障専門家の間で共有されている、という事実である。その延長線上にある「核武装論」は、もはやタブーではなくなってきている事実も確認された。
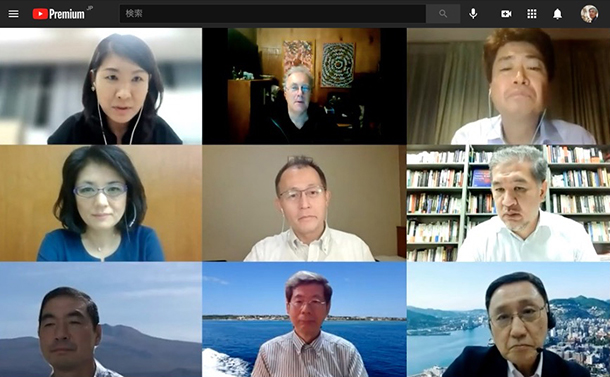 オンラインで開催した国際共同セミナー「北東アジアにおける核のドミノの評価:北朝鮮の核の脅威と日本の対応」
オンラインで開催した国際共同セミナー「北東アジアにおける核のドミノの評価:北朝鮮の核の脅威と日本の対応」これらの核武装論に共通しているのが、「核抑止」への強い信奉である。核の脅威に対応するには、「核抑止」が不可欠であり、その強化はもはや避けられない、という意見である。そこには通常兵器による軍事力(防衛力)強化も含まれているものの、「核兵器の抑止には核兵器しかない」という考え方が強く共有されている点が特徴である。しかし、核抑止論強化の議論には、核抑止が効かない可能性、効かなかった場合のリスク、核兵器が使われてしまった場合の影響などについては、ほとんど言及がない。もし核兵器が万が一この地域で使われたらどのような影響が出るか、そのような影響評価を地域で協力して検討すべき、との意見も聞かれた。
日本が核武装をしない理由として、①強い反核世論②核不拡散条約(NPT)原子力基本法といった国内外の法的制約③日米安全保障条約(核の傘の供与)の3つが挙げられたが、逆に言えば、これらの制約条件が弱まれば、核武装論を促進することにつながることになる。ワークショップでの議論を4つの観点から検討してみよう。
① 世代交代と平和教育の欠如
この問題で、衝撃的だったのは、柴崎秀子長岡技術科学大学名誉教授が発表した、科学技術系の学生への意識・知識・体験調査の結果であった。意識面での調査結果は下記の通り。
- 広島・長崎への原爆投下は正しい決定であった」賛成は日本人学生39%、米国人学生21%、留学生21%
- 「核兵器は必要である」賛成は日本30%、米国17%、留学生25%
- 「将来核兵器廃絶は可能だ」賛成は日本19%、米国66%、留学生39%
- 「核兵器は戦争抑止に有効だ」賛成は日本57%、米国41%、留学生48%
さらに、知識・体験面での結果も衝撃的である。
- 「原爆投下後の写真やビデオを見た」日本83.6%、米国93.3%、非アジア留学生95.6%、
- 「被爆者の体験を聞いた」日本23.8%、米国76.1%、非アジア留学生55.9%
- 「世界の核兵器の数」正解は日本39.2%、米国51.6%、非アジア留学生55.9%
- 「原爆死者数」正解は日本56.3%、米国68.1%、非アジア留学生72.1%
これらの調査結果を見る限り、科学者・技術者を目指す日本人学生の将来が心配になってくるが、これは学生の責任というよりも、教育の問題ではないか、と柴崎教授は指摘する。日本の歴史教育には、現代史が極めて少ない時間しか割けられておらず、しかも核兵器問題に関する教育は極めて少ない。
 北東アジアにおける「核の連鎖」の危機をどうすれば防げるか
北東アジアにおける「核の連鎖」の危機をどうすれば防げるか被爆者から直接体験を聞く機会も減少しており、いずれ被爆者や戦争体験者が存在しない時代がやってくる。また、平和教育も学習指導要領からは外れており、任意の教育プログラムとなっている。今後このような状況が続けば、「唯一の戦争被爆国」で育った若者たちの意識が大きく変わる恐れがある。
② 法的制約の緩和・崩壊
次に、法的制約についてもリスク要因がある。国内法でいえば、特に憲法9条と核兵器との関係が指摘された。1978年の福田首相、最近では2016年の安倍首相が、「憲法9条は防衛目的に核兵器保有を禁じていない」という趣旨の発言を行っている。しかし、過去の政府答弁では「相手国を攻撃するための兵器であるから、核兵器は自衛の範囲を超えている」という理由で、核兵器は憲法上持てない、とされていた。このように、憲法も解釈によって制約条件が取れていくことが懸念される。非核三原則がいまだに法制化されていない点も懸念の一つである。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください