エコなお家を横につなげるには何をすればいいのか? 取りあえずやってみた
2022年02月24日
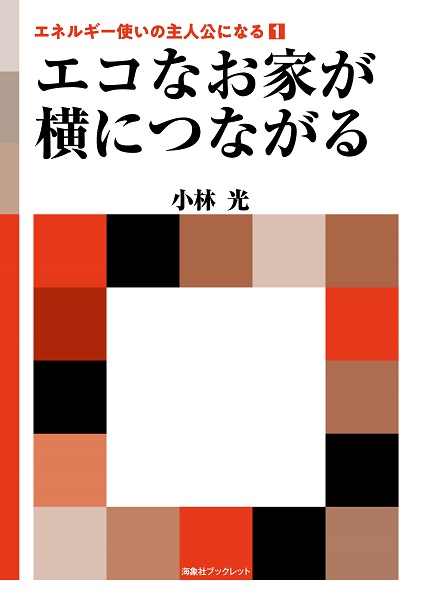 2021年6月に出版した「エコなお家が横につながる」(海象社ブックレット)
2021年6月に出版した「エコなお家が横につながる」(海象社ブックレット)この本でも紹介したが、実際、ドイツでエネルギーを中心とした地域公共サービスを担う公的な会社であるシュタットベルケのビジネスモデルでは、熱心に太陽光発電パネルの増設と、そこから送配電系統(グリッド)に電気を流す電力の逆潮流に取り組んでいた。地域のグリッドにつながる太陽光発電パネルからのカーボンフリーの電力は、FIT制度の下で国全体に配分されてしまい、地域で囲い込めない。にもかかわらず、シュタットベルケが取り組むのは、地域の配電網を地域の市民が管理経営していて、環境と共生できる地域の暮らしづくりに強い意思が働いているからに違いない。
 屋根置きの太陽光発電パネル=スマートソーラー社提供
屋根置きの太陽光発電パネル=スマートソーラー社提供また、ハワイ電力のケースでも、日本に比べて熱心に、配電網管理について再エネ電力を受け入れる観点からの運営が進められている。州政府の公的規制の下で地域独占をしている私企業のハワイ電力は、それゆえにハワイの島々と一蓮托生の運命共同体になっている。高価な化石燃料への依存が少ない島々の実現に向け、地域の経営に自分事として取り組んでいるのである。
例えば、ハワイでは、グリッドに逆潮流する個人の太陽光パネルは、蓄電池を備えた上で、日没後から夜明け前にそれを放電・逆潮流することが求められている。このことにより、グリッドには、夜間も、CO₂フリーの電力が豊かに流されることとなる。
家庭の蓄電池からの逆潮がほとんど認められない日本とは大きな違いである。こんな日本を、ではどうしたらよいだろう。
今でこそ、脱炭素は国是になったが、ちょっと前までは、脱炭素と聞けば産業界の人々は鼻で笑ったものである。環境対策はビジネスのお添え物、建前として飾って置けばよくて、環境に真面目に取り組むなどは青二才の所業だとでも言わんばかりであった。こうした中で、配電網を再エネ最優先で経営することはビジネスのテーマにはならなかった。風穴が開きだしたのは、環境動機によるものでなく、安全動機・防災動機によるものであった。
国内では「エコなお家が横につながる」において紹介した宮古島のケースや小田原のケースに加え、釧路の阿寒農協のケースや苫小牧のケースを見学させていただいた。釧路や苫小牧では、いずれも経済産業省系の補助金で支援されていて、主な狙いは、小さなグリッドが、系統被災時に、開閉器を閉じて、独立できて、そのグリッドの中にある太陽光パネルや蓄電池などを活用して自活できるようにすることが目的である。
もちろん、災害はない方がよいので、平時は、こうして増強された再エネ機器などが系統に、あるいは、グリッド参加者に利用されることとなる。環境目的であれ、防災目的であれ、やることはほぼ変わらない。ただ、見学してみると、グリッドにつながる需要家の防災・減災意識は高くとも、系統全体や配電を預かる一般電力企業は、そうしたマイクログリッド部分への特別の思い入れのないことが特に印象的であった。
配電事業者にどうやってローカルな利害への関心を持ってもらうのか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください