モンタニエ博士死去で思う生命科学の「スピード感」
2022年02月28日
欧米メディアの報道によると、フランスのウイルス学者でエイズウイルス(HIV)の発見者として知られるリュック・モンタニエ博士が2月、89歳で死去した。この業績で同僚のフランソワーズ・バレシヌシ博士とともに2008年のノーベル医学生理学賞を贈られた人だ。ただ、私のように1980~90年代に医学取材を経験した元科学記者には、HIV第一発見者の地位をめぐって米国の研究者との間で熾烈(しれつ)な争いを繰り広げた人という印象が強烈だ。それは、米国の大統領やフランスの首相を巻き込んだ知的財産権の争奪戦だった。
 東京・内幸町の日本記者クラブで会見するリュック・モンタニエ氏=2003年4月21日
東京・内幸町の日本記者クラブで会見するリュック・モンタニエ氏=2003年4月21日
 リュック・モンタニエ氏(左)=2011年撮影、フランソワーズ・バレシヌシ氏=2008年撮影
リュック・モンタニエ氏(左)=2011年撮影、フランソワーズ・バレシヌシ氏=2008年撮影
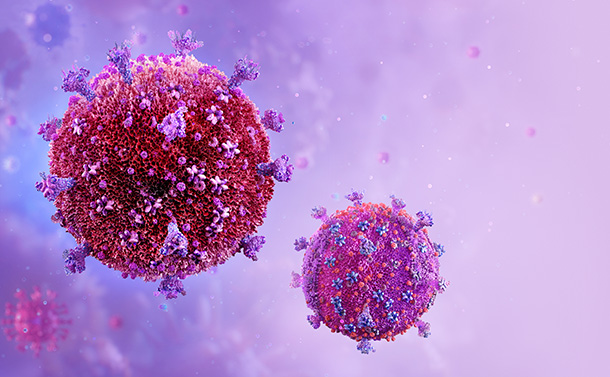 HIVのイメージ=shutterstock.com
HIVのイメージ=shutterstock.comしかもギャロ博士のグループは、見つかったウイルスに対する抗体測定法、即ちエイズ検査の手法も発表した。その特許が1985年、米国で認められる。これにフランス側は強く反発した。この対立に折り合いをつけたのが、1987年に訪米したシラク仏首相とレーガン米大統領の会談だ。このとき両国は、HIV発見ではギャロ、モンタニエ両グループが同等の貢献をしたとして、特許料を折半することで合意した。
だが、これでも一件落着とはいかなかった。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください