神経細胞の活動を光で操作 脳の働きや病気の解明にも貢献
2022年09月29日
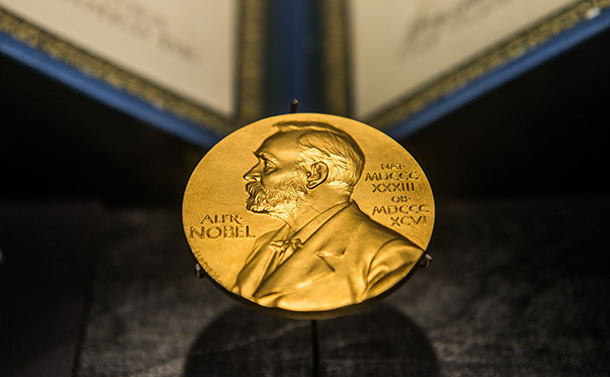 ノーベル賞のメダル=shutterstock.com
ノーベル賞のメダル=shutterstock.com論座で毎年恒例の大胆予想。ノーベル医学生理学賞の有力候補として、光遺伝学(オプトジェネティクス)に貢献した米スタンフォード大学教授のカール・ダイセロス氏と、独フンボルト大学ベルリン教授のペーター・ヘーゲマン氏を挙げたい。
「光遺伝学」と言っても耳慣れない言葉かもしれないが、2005年以降、神経科学を革命的に発展させた研究手法だ。どの神経の活動がどんな行動をもたらすかを精密に解明できるようになり、食欲、睡眠、運動などの脳の活動を理解するだけでなく、精神や神経の病気の治療に結びつく可能性も出てきている。この技術を患者に応用する臨床研究も始まっている。
 光遺伝学の研究を解説する朝日新聞の記事=2010年11月23日付朝刊科学面
光遺伝学の研究を解説する朝日新聞の記事=2010年11月23日付朝刊科学面従来から神経細胞を調べる方法として電気刺激がある。神経細胞に電気刺激を与えて変化を調べる。しかし、この方法には弱点があった。隣接して並んでいる神経細胞を区別することができないため、どの神経細胞への刺激が変化の原因なのか判別がつきにくい。
光遺伝学では光を当てることで神経細胞をオン・オフするスイッチが働くようにする。光に反応するたんぱく質を作る遺伝子を、特定の神経細胞に送り込んでおく。神経細胞に光を当てると、特定の神経細胞だけでスイッチがオンになり、隣接している別の神経細胞には影響を及ぼさない。これによって、調べたい神経細胞が引き起こす変化を明らかにできる。特定の神経細胞を操作し、その結果、どんな変化が起きるかという因果関係を調べることができる。
この画期的な技術はどのように実現したのだろうか。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください