学名はどうなった? アホウドリを2種に分けた研究者たちに聞いてみた
2023年01月21日
 アホウドリ=2008年2月、鳥島
アホウドリ=2008年2月、鳥島
動物考古学や考古鳥類学を専門とする江田真毅教授は、従来1種と考えられてきたアホウドリが、鳥島タイプの「アホウドリ」(伊豆諸島・鳥島を中心に繁殖する)と尖閣タイプの「センカクアホウドリ」(尖閣諸島で主に繁殖する)の2種に分かれるという研究へ、どのように取り組んだのだろうか。
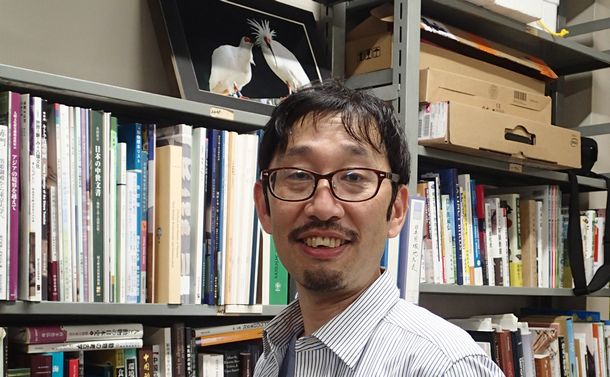 江田真毅・北大教授=筆者撮影
江田真毅・北大教授=筆者撮影
江田さん 1994年に大学へ入って参加し始めた北海道・礼文島での発掘調査がきっかけだ。もともと自分は考古学が専門で、中でも遺跡から出てくる動物の骨に関心があった。礼文島北部にある浜中2遺跡からは、たくさんのアホウドリ科の骨が出ていた。その骨には鳥を解体したときについた痕があり、生きた個体を狩猟で捕らえて肉を食べていたのだと考えられた。
――遺跡の発掘から、鳥の分類の新知見が生まれたとは興味深い。
江田さん 北太平洋にはアホウドリ、クロアシアホウドリ、コアホウドリと、アホウドリの仲間が3種いるとされていた。アホウドリは沿岸、コアホウドリは遠洋、クロアシアホウドリは前2種の中間的な海域を、それぞれ主な採餌場所にしている。3種の行動範囲が違うので、どの種の骨かが分かれば人の狩猟範囲の推定につながるだろうと考えた。
遺跡の1000年ほど前の層から出てくる骨をまず大きさで調べて、アホウドリの骨とそれより小さなクロアシアホウドリやコアホウドリの骨があると考えた。ところが骨に含まれたミトコンドリアDNAを分析してみると、クロアシアホウドリやコアホウドリと思った小さめな骨もみんなアホウドリらしいとなった。
ただ、よく調べると、中には塩基配列が1塩基だけ異なる骨があった。骨はどれもアホウドリのものだが、1塩基の差に従って二つのグループに分けてサイズを比較したら、グループ間に有意な差があるとわかった。こうした結果が得られたことから、二つの異なる集団のアホウドリが来ていたのだろうと考えた。
 礼文島の遺跡から見つかったアホウドリ科を含む鳥類の骨
礼文島の遺跡から見つかったアホウドリ科を含む鳥類の骨 アホウドリ科鳥類の骨を加工した針入れ=いずれも北海道大学総合博物館所蔵、江田真毅さん提供
アホウドリ科鳥類の骨を加工した針入れ=いずれも北海道大学総合博物館所蔵、江田真毅さん提供――当時、礼文島周辺にアホウドリがいたとは驚きだ。
江田さん 確かに今は見られないが、浜中2遺跡から出る鳥の骨の多くはアホウドリだ。当時の人々は島の近くにやってきた、これらの鳥を捕らえていたのだろう。日本海やオホーツク海沿岸の他の遺跡からもアホウドリの骨が見つかっている。
昔は北海道周辺にもたくさん来ていたのだろう。実際に各地の遺跡から出土した骨のミトコンドリアDNAを調べると、1塩基が異なる両方の骨が含まれていた。また浜中2遺跡の骨を、1塩基の差に基づく二つのグループに分けて窒素と炭素の安定同位体比を調べると、差があった。安定同位体比は食べ物の特徴を示すため、餌を採る海域の違いを示唆しているのかもしれない。浜中2遺跡からはどちらの骨も出ているので、それぞれの主な利用海域は別だが、ある程度の重なりはあったというイメージで捉えるのが良さそうだ。
ただ鳥島のような繁殖地で捕らえると、産卵した雌に特徴的な骨が見つかるのに、浜中2遺跡では見つからない。礼文島のあたりに繁殖地があったわけではなく、異なる場所で繁殖する2集団が非繁殖期に訪れていたのだろう。
――はじめは2集団と考えたのに、種のレベルで違うとなったのはなぜか。
江田さん 現在のアホウドリの主な繁殖地は鳥島と尖閣諸島。尖閣諸島での調査は難しいが、鳥島には尖閣生まれらしい個体が現れるようになっている。
鳥島生まれの個体には基本的にすべて足環(あしわ)が装着されているので、少数いる足環がない個体は尖閣生まれと推定できる。足環の有無の違いに基づいてDNAを調べ、長谷川博先生(東邦大学名誉教授)から提供を受けた尖閣諸島で得られた遺体などのDNAとも比較することで、二つの集団がそれぞれ鳥島と尖閣諸島に由来することがはっきりした。
2集団の分岐は約60万年前と推定され、
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください