寓意の未「完了」性――3・11後の世界の手触り
2017年03月09日
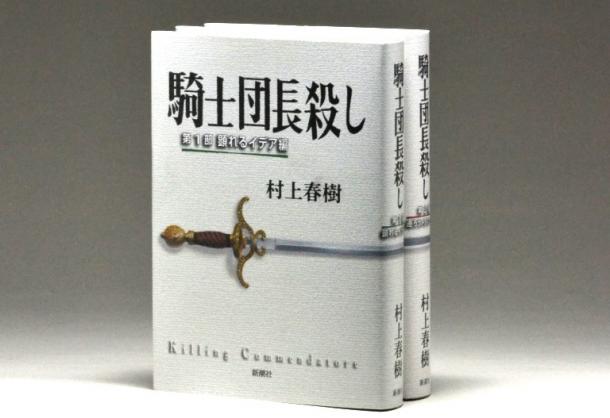 村上春樹『騎士団長殺し』(全2巻、新潮社)
村上春樹『騎士団長殺し』(全2巻、新潮社) 肖像画家の「私」が、「今から何年か前」の約9ヶ月間に起きた出来事の記憶を追いながら書いた文章、という体を持つこの小説の「あらすじ」を、まずは簡単にたどろう。
その約9ヶ月のあいだ、「私」は妻のユズとの「結婚生活をいったん解消しており」、この間の「私」は、「静かな海の真ん中を泳いでいる最中に、出し抜けに正体不明の大渦に巻き込まれた泳ぎ手のようなものだった」、と振り返られる。
三つ年下の妹・小径(こみち、コミ)を15歳のときに亡くした過去を持つ「私」は、36歳の3月、突然妻に別れを切り出され、二人で暮らす東京・広尾のマンションを出ることとなる。行く宛てもないまま車で東北の日本海側に向かってから北海道にわたり、さらに東北の太平洋岸をまわり、2ヶ月弱のあいだ車を走らせ続ける。
そのあと頼った美大時代の友人である雨田政彦(あまだまさひこ)が、父であり高名な日本画家である雨田具彦(ともひこ)の、空家になっている住まい兼アトリエを「私」に貸してくれることになる。具彦はいま認知症で高級養護施設に入っているという。
小田原市郊外の山中にあるそのアトリエで、留守番を兼ねて一人暮らしを始めた「私」は、免色渉(めんしきわたる)という変わった姓を持つ総白髪で50代半ばの男性の肖像画をなぜか描くことになる。また、アトリエの屋根裏に「隠匿」されていた『騎士団長殺し』という雨田具彦が描いた日本画をあるきっかけから発見し、強い衝撃を受ける。
『騎士団長殺し』という絵は、モーツァルトのオペラ『ドン・ジョバンニ』中の「騎士団長殺し」というシーンが、日本の飛鳥時代の情景に「翻案」された「暴力的な」絵だったが、そこには具彦自身が1938年にウィーンで体験した「痛切な」暗殺未遂事件が仮託されてもいた。
さらにある夜、聞き慣れない「鈴(のようなもの)」の音で目覚めた「私」は、その音が裏庭の雑木林にある祠裏の石塚から発せられていることを突きとめる。免色の助けを得て重機で石塚を除けると、下には石室があり、石室の底には奇妙な鈴が置かれていた。
やがて、「鈴(のようなもの)」を鳴らしていた存在が、「姿かたちをとったイデア」となって「私」の視界に姿を顕わす。それは、絵画『騎士団長殺し』から抜け出した「騎士団長の姿かたち」である。イデアとしての「騎士団長」が目に見え、会話することができるのは、この小説の中では「私」ともうひとり、「秋川まりえ」という13歳の少女だけだ。まりえは「私」の死んだ妹コミを彷彿とさせる少女で、「私」の肖像画のモデルとなり、免色の個人的な秘密にも関わっている。
その後まりえが謎の失踪を遂げ、「私」はまりえを救い出すために、「騎士団長」の姿をしたイデアをみずからの手で殺し、メタファーという異界――そこは生命を感じさせない「無」「空白」の世界だ――をくぐり抜けなければならなくなる……。
いま紹介した小説の筋とは別の地点に、小説の内側でみずから脈打つ物語がある。そしてその物語を動かしている源のようなものを、読者は読みとるはずである。それは、「あまりに強い思い/あまりに強烈な体験/あまりに生々しいもの」と言うしかないようなものだ。
まず、絵画『騎士団長殺し』に注ぎ込まれている「普通ではない種類の力」、あまりに強く、あまりに深い「魂」が、発端にある。絵画『騎士団長殺し』の背景には、雨田具彦のウィーンでの痛切な体験があり、痛切な体験の背後にはナチスドイツによるオーストリア併合や南京虐殺事件という歴史があった。
「私」がその絵に衝撃を受けるということは、絵から具彦の「あまりに強い思い」(と背後の歴史的事実)を受け取る、ということである。「私」が受け取ることにより、具彦の深くて純粋な「魂」が持つ招き寄せる力(それは同時に「危うい力」をも孕む)は、「私」を通して作動することとなる。
「私」の前にイデアが顕れたのも、その作動の力による。「私」が免色とともに石室を開き、その底から騎士団長の姿をしたイデアを解放させることと、「あまりに強い思い」の作動は、一見無関係に思えるかもしれない。しかし、無関係ではないどころか直接的に関係している。なぜか。それは、「あまりに強い思い」は寓意を通してしか表に出てくることができないからだ。その、一見無関係に思えること、脈絡のなさこそが、発端にある雨田具彦の思い・体験の強度を明かしている。次の騎士団長の言葉にある通りだ。
「雨田具彦の『騎士団長殺し』について、あたしが諸君に説いてあげられることはとても少ない。なぜならその本質は寓意にあり、比喩にあるからだ。寓意や比喩は言葉で説明されるべきものではない。呑み込まれるべきものだ」 (第1部451~452p)
具彦の「あまりに強い思い」は、屋根裏に住む「みみずく」に守られ、形を変えて蒸留され、イデア=騎士団長となって「私」に届いた。そうしてその後の「私」に一連の出来事を経験させ、「私」と免色、まりえ、ユズらとのあいだに新たな関係を形作らせる。つまり約9ヶ月にわたって「私」を巻き込んだ大渦の源となっているわけだ。
「あまりに強い思い/あまりに強烈な体験/あまりに生々しいもの」は、人の理性による統御を超えて存在して「しまう」。不可視だが時空を超えて実在するという意味で「イデア」となり得、かつ、騎士団長が言うように「招かれないところには行けない」。
かつまたいっぽうで、「あまりに強い思い/あまりに強烈な体験/あまりに生々しいもの」は、善悪や倫理、論理性を超えて実在しているという点で、「危うい力」や「ネガティブさ」を併せ持つ。
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください