名家の没落を劇的に描く
2019年02月28日
映画史上に巨大な異物のように屹立するオーソン・ウェルズ。この“呪われた天才”の監督作と出演作のうち14本が、東京・シネマヴェーラ渋谷で特集上映されている。ウェルズ映画と俳優ウェルズをスクリーンで堪能できる貴重なチャンスの到来だが、今回は監督ウェルズのフィルモグラフィーにおける最高作の1本、『偉大なるアンバーソン家の人々』(1942、モノクロ)を取り上げよう(本特集で上映される彼の自作自演作は、監督デビュー作『市民ケーン』、『恐怖への旅』、『上海から来た女』、『謎のストレンジャー』、『マクベス』、『オセロ』であるが、いずれも必見の傑作)。
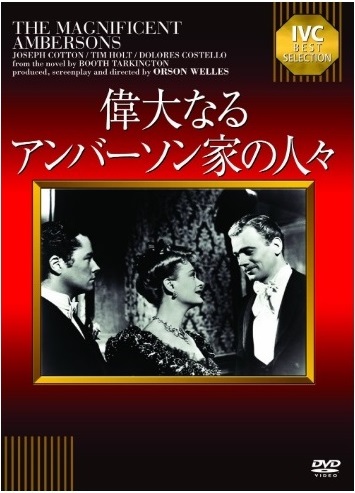 『偉大なるアンバーソン家の人々』(DVD、IVC BEST SELECTIONより)
『偉大なるアンバーソン家の人々』(DVD、IVC BEST SELECTIONより)このナレーションが予感させるように、描かれるのは、アメリカ中西部のスモールタウンに大邸宅を構えるアンバーソン一族の栄光と没落であるが、物語は人物間の葛藤や確執を中心に、ラブ・ロマンスを織り込みながら展開する。ただし『アンバーソン』の最大の魅力は、ウェルズの他の傑作と同様、物語と混然一体となった彼ならではの驚嘆すべきバロック的空間描写にあるが、それについては順を追って触れるとして、まずは本作のプロット・人物設定・主題について述べよう。
甘やかされて育ったアンバーソン家の嫡子、ジョージ(ティム・ホルト)は傲慢で尊大な性格であった。幼少期のジョージは「小さな暴君」と呼ばれたが、町の人々は彼がいつか“報い”を受ける日を見たいと願っていた(と語るウェルズのナレーションと並行して、フラッシュバック/回想シーンで、クラスメートと取っ組み合いの喧嘩をする気性の荒いジョージ少年の姿が映像化される。緻密なシナリオ構成にもとづく、ウェルズ好みの<伝記的話法>である)。
ジョージの傲慢な性格は成人してからも変わらなかった。そしてジョージは、美しく心優しい母親イザベル(ドロレス・コステロ)とかつて恋仲にあり、今も彼女に好意を寄せる温厚で聡明なエンジニア兼発明家、ユジーン・モーガン(ジョゼフ・コットン)に強く反発していた。父親のウィルバー(ドン・ディラウェイ)が亡くなり、ユジーンと母イザベルの愛が再燃すると、ジョージのユジーンに対する敵意はいや増す。
ところがジョージは、ユジーンの健気な一人娘ルーシー(アン・バクスター)に惹かれてゆく(こうした、傲岸不遜なジョージを中心にした主要人物らの<関係の力学>が、物語に強い求心力とアイロニーを加えている点も絶妙だが、それはつまり、ブース・ターキントンの同名小説をウェルズがみごとに脚色=脚本化したということでもある)。そして、アグネス・ムーアヘッド扮するジョージの叔母ファニーや、サイレント時代の名優リチャード・ベネット扮する、一族の家長アンバーソン少佐/ジョージの祖父がドラマを膨らませている。
ルーシー/アン・バクスターはといえば、ジョージと相愛の仲になるが、彼が無職であることに不安を抱き、定職に就くべきだと彼に忠告する。が、おごり高ぶったジョージはいっさい聞く耳を持たず、アンバーソン家の一員は労働などに手を汚すべきではない、財産を慈善団体に寄付して社会活動に参加する、人に指図される人生なんてごめんだ、皿を洗ったりイモを売ったり法廷に立つなんて、などと言い放ち、結局、二人の関係はぎくしゃくしてしまう。……やがて時代は20世紀に突入。町は工業都市に変貌しつつあり、急速に自動車産業が栄えていき、ユジーンは自動車開発で時代の寵児となる。
いっぽう、凋落の一途をたどるアンバーソン家の過去の栄光にしがみつくジョージは、母をユジーンから引き離すべく、ルーシーへの愛を断念する。そんななか、母が心臓発作で亡くなり、相次いで祖父アンバーソン少佐もこの世を去り、ジョージは一文無しになり、かくして一族の没落は決定的なものとなる。おまけに、ジョージは自動車事故で両足を骨折し、入院する――。
そして、アンバーソン家の末路についてのウェルズのナレーションが、
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください