高いところから教えを説くのではなく、低いところへ低いところへと自ら身を置く原点
2019年11月23日
若松英輔(批評家)
山本芳久(哲学者)
中島岳志(政治学者)教皇フランシスコの来日はいかなる意味があるのか――。教皇の発言を的確に理解するには、その思想の根源にあるものを把握しなければならない。教皇の論理に迫り、来日の意義に迫る決定的鼎談。
中島岳志(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授) カトリック教会の教皇フランシスコが、まもなく来日します。日本のメディアの注目は、主に広島・長崎の被爆地で教皇が何を語るのかといったことに集まっているようですが、今日はもう少し幅広い視点から、そもそも教皇フランシスコとはどんな存在なのか、そしてこの来日が私たちにとってどんな意味を持つのか、カトリックの信徒でもある若松さん、山本さんにお話をうかがいながら考えていきたいと思います。
まず、基本的なところなのですが、教皇フランシスコは、前教皇のベネディクト16世の後を継いで、2013年に第266代ローマ教皇となりました。歴代の教皇は「コンクラーヴェ」という制度によって選出されていますが、この制度について少しご説明いただけますか。
若松英輔(東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授) カトリック教会には、教皇を補佐する枢機卿という職位があります。世界には今、200人強の枢機卿がいますが、コンクラーヴェで選挙権、被選挙権が定められている枢機卿は120人弱です。立候補者がいるわけではなく、枢機卿がそれぞれ教皇にふさわしいと考える人に投票し、何度かそれを繰り返して3分の2以上の得票者が出るまで続けられます。
そう言ってしまうと、つまりは「選挙」でしょうということになるのですが、そうではなく、そこに神の働きが介在するというのが、コンクラーヴェと、いわゆる民主的な選挙とのもっとも大きな差異です。単なる人気投票や多数決ではなく、神に選ばれた人だけが教皇となる。
具体的にどのようなプロセスで決定されたのかも、外部には一切公表されないことになっています。それでも一部の情報が漏れてきてはいるのですが……。
中島 教皇に就任すると、その人は本名ではなく自身が選んだ「教皇名」で活動するようになります。現在の教皇の「フランシスコ」は、12世紀から13世紀にかけて活動した聖人のひとり、「アッシジのフランシスコ」から取られたそうですね。
山本芳久(東京大学大学院総合文化研究科准教授) アッシジのフランシスコ(1182-1226)は、もともと裕福な商家の出であったのが、その富を投げ捨てて信仰の道に入り、清貧と奉仕の生涯を送った人として知られています。教皇も、次期教皇に選出されることが決まったときに、親しい枢機卿から「貧しい人たちのことを忘れないでください」と声をかけられ、それでアッシジのフランシスコに思い至ったそうです。
アッシジのフランシスコは、フランシスコ会という修道会を立ち上げた「改革者」でした。
12世紀は、ヨーロッパで急速に都市社会が発展した時代です。農村社会なら、住民はほとんどが同じ土地に生まれ育っていて、考え方にもそれほどの差異はありません。その中に閉じこもって、祈りと労働の修道生活を送ることをよしとするのが、ベネディクト会に代表される従来の修道会の考え方でした。
ところが、都市部にはあちこちから、さまざまな人たちが集まってきます。考え方も多様で、中には従来のキリスト教からすれば「異端」的な考えの人もいる。フランシスコはその中に飛び込んでいって、彼らにも伝わるような形で神の教えを説こうとしたのです。
自分たちとさまざまな面で異なる人たちのただなかに積極的に出て行って教えを説いてまわる。それは、当時としては非常に「新しい」ことであると同時に、まさにイエス・キリストが弟子たちとともにやったことでもありました。ある種の原点回帰的な精神だと思うのですが、これは現教皇がやろうとしていることとも非常に重なる気がしますね。そのあたりも、後でお話しできればと思います。
ちなみに、アッシジのフランシスコが立ち上げたフランシスコ会は、当時の教皇に認められたことで影響力を増していくのですが、当初は「異端すれすれ」だとみなされていました。そして、実は今の教皇も、一部のカトリックの神学者や哲学者からは「異端的だ」と批判されています。改革者であるがゆえに、極度に保守的な人から見れば「異端」であるかのようにすら見えるという、その点も重なるといえるかもしれません。
若松 アッシジのフランシスコに象徴されるのは、「貧しさ」「平和」「被造物への愛」だといえると思います。
「被造物」という言葉は、あまり聞き慣れないかもしれませんが、キリスト教では世界は神によってつくられたと考えますから、万物が「被造物」であるわけです。フランシスコは、ことに自然との交わりを深めました。これらのことは、教皇フランシスコの言動にも強く表れています。
もう一点、アッシジのフランシスコが、教会内で、決して「えらい人」ではなかったということにも注目したいと思っています。先にも少しふれましたが、カトリック教会は、教皇を頂点に枢機卿、司教、司祭、助祭というヒエラルキーが存在します。フランシスコは聖職者の中でも一番下の位である助祭だった、と伝えられています。
そうした人物の名前を現教皇があえて選んだということは、司教や司祭よりもなお、一般の信徒に近いところで生きようとする、あるいは教会と信徒、そして民衆の間に入って活動していこうとする姿勢を明確に示しているようにも思います。
 ミサに集まった参加者に手を振って応える教皇フランシスコ=2019年5月、ブルガリア
ミサに集まった参加者に手を振って応える教皇フランシスコ=2019年5月、ブルガリア中島 また、教皇フランシスコの非常に大きな特徴として、非ヨーロッパ出身だということがありますね。生まれ育ったのは南米のアルゼンチンで、両親はイタリアからの移民。ですからご自身は移民2世として、スペイン語を母語に育っています。非ヨーロッパ出身の教皇というのは、カトリックの歴史の中でも非常に珍しいことだと聞きました。
教皇は、トランプ米大統領がメキシコとの国境に壁を建設しようとした計画を強く批判するなど、移民・難民の問題についても積極的にメッセージを発信されていますが、その背景にはやはりご自身のルーツもあるのではないでしょうか。
山本 著書などの中で教皇がしばしば使われる言葉に「周辺」「周縁」があります。生まれ育ったアルゼンチンという国が、ローマを中心とするキリスト教世界からすれば「周辺」であるという意識が、いわば「周辺」「周縁」に属する人々ともいえる移民、難民へのまなざしにつながっている気がしますね。
同時に、「周辺」や「周縁」を見つめるということはキリスト教にとって必然であるという意識も、教皇の中には強くあるように思います。もともとキリスト教とは「移住者の神学」であって、旧約聖書でも、神の促しを受けたアブラハムが故郷を捨てて新たな土地へと出立していく場面が物語の原点になっている。そのように、「周辺」へと出かけて新たな人々と出会って積極的に関わっていくことにこそ、キリストの教えの根があるんだと考えておられるのではないでしょうか。
若松 キリスト教は、すべての人間は、神を求め「旅する人」であると考えます。誰もが神を探す旅を生きているというのです。旅人は、移住者であることを宿命とします。事実、晩年のイエスも生地ナザレを出て、エルサレムまでの「旅」を生きていました。教皇は、こうした伝統を踏まえつつ、現代的問題としての移民・難民の問題に積極的に発言をしています。
右傾化が伝染病のように広がる今の世界では、移民・難民は「見捨てられた人」になりがちです。しかし、教皇は彼らに向かって、どんな人も見捨てられることがあってはならない、と訴えます。教皇の言動には、伝統的かつ時代的な意識が共存しているのです。
中島 キリスト教の、もっとも根っこの部分に戻りつつ、それによって現代の課題に向き合おうとしている、ということですね。
若松 『使徒的勧告 福音の喜び』で教皇は「出向いて行く教会」という印象的な表現を用いています。「使徒的勧告」という言葉は耳慣れないと思いますが、教皇が世界のすべての教会に書き送った書簡のような文章です。
どこへ「出向いて行く」のか、というと、それはさまざまな意味で、教会との関係を見失った人々のところ、ということなのです。この点においても、今までの多くの教皇との違いをはっきりと感じます。
これまでも多くの国を訪れたヨハネ・パウロ二世(第264代教皇)のような人物もいました。しかし、現教皇はその交わりをいっそう広く民衆に向かって開いています。彼はおそらく、「自分が教皇となど会えるはずがない」と思っている人にこそ会いに行かなくてはならないと考えている。来日にあたってもおそらく、そうした民衆との出会いを希求しているのだと思います。
教皇にはさまざまな「顔」があります。「ローマの司教」「イエス・キリストの代理者」あるいは「バチカン市国の元首」というものもある。そのなかに「神のしもべたちのしもべ」という「顔」があります。現教皇は、この点を従来の教皇などに比べても、いっそう強く体現していると思います。高いところから教えを説くのではなく、低いところへ低いところへと自ら身を置こうとする。
こうした態度は、彼がイエズス会の出身であることから来ているのかもしれません。もともとイエズス会は、創立者の一人であるフランシスコ・ザビエルが日本にやってきたことでも知られるように、世界各地への宣教に力を注いだ修道会でした。遠藤周作の小説『沈黙』で描かれている神父たちは皆、イエズス会士です。はるかヨーロッパから命がけで遠方の地にやってきて、民衆と同じ目線で語り、そのまま土地に骨を埋めた人も少なくなかった。そうした精神が、教皇の中にも受け継がれていると感じるのです。
 若松英輔・東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授
若松英輔・東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授山本 私は、若松さんがおっしゃった「伝統的かつ時代的」という教皇の在り方にも、イエズス会の精神が表れているように感じます。
ザビエルの後、東アジア全体への宣教を取り仕切ったヴァリニャーノ(1539-1606)というイエズス会士がいるのですが、彼の思想のキーワードは一言でいうと「適応」です。ラテン語でaccommodatio(アコモダチオ)という概念で、英語で言えばaccommodationという語になります。ヨーロッパで形成されてきたキリスト教の教えをそのまま説くのではなく、宣教地の文化や習慣、あるいはその地にもともとある宗教に適応させながら伝えていくという考え方です。
教皇がやろうとしているのは、各地の文化や習慣だけではなく、現代世界の根本的な問題──環境問題や平和の問題、構造的な貧困問題など──に「適応」させながらキリスト教のメッセージを語り直すということなのではないでしょうか。そこに「アコモダチオ」を重視するイエズス会の精神が表れていると思うのです。
中島 空間的な差異だけでなく時間的な差異にも「適応」させていく。それこそが「伝統」というもののあり方だという考え方ですね。最初に山本さんが触れられていた、アッシジのフランシスコの「原点回帰」の姿勢にも通じると思います。
若松 そもそも「カトリック」とは「普遍」という意味です。これまでは、それぞれの宗派が「違い」を表現することに懸命でした。しかし、教皇は、「普遍」とは何かをあらためて体現しようとしているように感じます。普遍的な部分を大事にしていてこそ、教会はいつの時代にも新しく生まれ変わることができる。そもそも今の教皇は「教会」をキリスト者以外の人にも開こうとしているわけです。
山本 戦前の日本のカトリックの指導者であった岩下壮一の遺著に『信仰の遺産』というタイトルの書物があります。「信仰の遺産」という概念は、岩下が編み出したものではなく、新約聖書にまで遡るカトリック神学の基本概念の一つです。
信仰とは、個人がただ何かを信じる、思い込むというものではなく、イエス・キリストとその直弟子たち(使徒たち)から受け継ぎ、受け渡されてきた「遺産」である。そして、その遺産は固定的なものではなく、新たな状況の中で常に解釈し直されていくのだ、というのが、「信仰の遺産」という概念の含意するものです。
本質が変わるのではなく、同じ「遺産」が、社会の変化に応じた解釈を得ることで新たな光を当てられるのだ、というのですね。
このあいだの10月に、19世紀イングランドの神学者であるジョン・ヘンリー・ニューマン(1801-1890)が、教皇フランシスコによって列聖されました。ニューマンの代表作の一つに『キリスト教教理発展論』という著作があるのですが、そのなかにも、非常によく似たことが書かれています。キリスト教の教理は時代とともに発展していくものだが、その「発展」とは変化することではなく、キリスト教の教えの中にもともと含まれてはいたが明示的に表現されてはいなかった事柄が、状況の変化に応じて新たに表現し直されることを指す、というのです。
たとえば、とても偏った仕方でキリスト教の教えを説明しようとするような人々が出てきた際には、「さすがにそれは違うでしょう」という仕方で、これまでは明示的に表現してはいなかった事柄をあらためて明示的に表現することによって、教えを新たに明確化する必要が生じる、それがキリスト教の教理の「発展」なのだ、とニューマンは説いたのです。
教皇フランシスコのやろうとしていることも、これと重なる部分があるのではないでしょうか。「伝統は動く」とか「前進している教義」というのも、教皇が、社会学者であるドミニック・ヴォルトンとの対談本の中で使っている言葉ですが、伝統、つまりは「信仰の遺産」を、大切に受け継ぎつつも現代世界の中で非常に斬新な仕方で解釈し直そうとしているのです。
 山本芳久・東京大学大学院総合文化研究科准教授
山本芳久・東京大学大学院総合文化研究科准教授若松 ニューマンのいう発展とは、いわば樹木の成長のようなものです。キリスト教という森の中でさまざまな樹木が発展し、次々にいろいろな花が咲いていく。咲いている花はそのときによって違うけれど、森のあり方そのものが変化することはなく、むしろより深まっていく。教会はそういうものでなくてはならないのだと思います。
このことを移民・難民の問題に即していうならば、その森に今、遠くの森から移民・難民という新しい種が運ばれてこようとしている。それに対して、これまで森にないものだからと排斥するのか、それとも異なるものが加わることによって豊かになっていくと考えるのか。私たちはどうするかを問われている。
ここでの「森」が、単なる風土的な土に根づくのではなく、「神」という土壌に根を張るものである、そこには自然を超えたはたらきがある、というのが教皇の確信です。
カトリックは長く、民族や宗教の異なる人たちに対して「異邦人」という言葉を使ってきました。注目するべきは、教皇は、その「異邦人」によってこそ、教会という森が完成されていくのだという意識を、とても強く持っているところです。
中島 伝統を守るためにこそ、新たな解釈をし直す、ある種の改革をしていく。そうした教皇の姿勢は、現代社会における非常に大きな問題の一つである「原理主義」を考えるときにも、重要な気付きを与えてくれると感じます。
原理主義は、キリスト教はもちろんイスラーム教やヒンドゥー教など多くの宗教に存在しますが、共通しているのは世界には「唯一の原理」というものが存在するとしていること、そしてそこに復古することこそが正しい教えへの近づきだと考えることです。伝統を大切にするためには改革が必要だという教皇の立場は、ちょうどその原理主義の思想の正反対にあると思います。
若松 本来、信仰というもの、信ずるという行為は、つねに動き、変化していくものであるはずです。それを変化しないもの、止まっているものとしてとらえたときに、強い暴力性が生まれる。それが原理主義の実態ではないでしょうか。原理主義者にはもう「謎」は存在しない、ともいえます。しかし、「謎」がないところに真の意味での超越もまた、存在しえないのです。
山本 原理主義は、伝統というものを、非常に単純化して定義できるものとしてとらえているように思います。実際には、伝統というのはもっと豊かなものであって、まだまだ解釈し尽くされていない部分が絶対にあるはずで、私たちもまたその豊かな伝統の中に生きている。それに対する尊重のような念が、原理主義には決定的に欠けていると感じます。
中島 おっしゃるとおりです。信仰というのは、人間は真理というものを完全には把握しきれないというところからスタートするもののはずです。原理主義のように、真理が「これだ」と指さして示せるものとして存在すると考えるならば、それは人間の能力への過信にほかならず、もはや信仰とはいえないのではないでしょうか。
しかし、そうした原理主義的な傾向が、宗教の違いを超えて世界的に広がっている。「伝統は動く」といい、改革を恐れない教皇のあり方そのものが、この状況への一つのアンチテーゼとなるように思います。

中島 教皇の考え方、思想が非常によく表れているのが、2015年に発表された回勅(教皇から全世界のカトリック司教、信徒へ宛てる形で出される公的なメッセージ)『ラウダート・シ』です。
またアッシジのフランシスコの話に戻るのですが、彼は死の直前に「被造物の讃歌」という歌を遺していますね、太陽、月、星、風、火など、あらゆる被造物を人間の「兄弟」として讃える内容で、これはアッシジのフランシスコの思想のかなりコアなところにある考え方だと思います。「小鳥に対して教えを説いた」という話も有名ですよね。
『ラウダート・シ』を読んでいて、教皇もまた、このアッシジのフランシスコの思想を非常に強く受け継ごうとしているのではないかという気がしました。これは環境問題に関する回勅だといわれていますが、そこにはいわゆる環境保護、単に「木を伐らないでおきましょう」といったことを超えた、ある世界観、宇宙観のようなものが描かれているように感じます。
山本 世の中に様々な社会問題があるうちの一つとしての環境問題、というふうに狭い意味でとらえてしまうと、教皇の意識とはかなりずれてきてしまう気がしますね。教皇が目指しているのは、人と人、人と自然、そして人と超越者のつながりといった、万物のつながり全体の調和を回復していくこと。環境問題は、今の社会においてもっとも「調和」が失われている側面であるがゆえに、その調和を取り戻すための突破口になるということなのだと思います。
中島 それは、いわゆる西洋世界が持っている環境問題に対するアプローチとは、かなり異なりますよね。私は自分は仏教徒だと思っていて、キリスト教世界にそれほどなじみがあるわけではないのですが、その私が読んでも非常に共感できる宇宙観だと思いました。
若松 ここで問題となるのは「自然」のとらえ方です。自然は、人間が利用するもの、消費するものなのか、私たちを生かしてくれているもの、そして私たちが守り、育むものなのか、という問題です。『ラウダート・シ』で教皇は、自然が人間によって支配されるべき対象であるかのように理解したのは誤りであったとはっきり述べています。
「自然との共生」という言葉がありますが、教皇の立場はそれよりもう一歩踏み込んでいる。私たちは自然なしには生きていくことができない。その、キリスト教的にいえば私たちを「生かしている」力の表れでもある自然を、これまで自由に利用し、徹底的に消費してきた。それ自体がどうなのかという問いかけなのだと思います。
中島 教皇とアッシジのフランシスコに共通する感覚の重要なポイントは、「私的所有」という概念に対するアンチテーゼだと思います。近代社会は、その概念を前提として発展してきたわけですが、そもそも万物を「所有する」ということは許されるのか。アッシジのフランシスコはそこを疑ったからこそ、富を捨て、豪華な住まいを捨てて清貧の生活を送りましたが、教皇も同じような感覚を抱いているのではないかと思います。
若松 空、空気、水などに象徴される自然は、私たちが「所有できないもの」です。むしろ、さまざまな文化は、自然を「分かち合う」なかで生まれてきた。しかし、近代は、いつの間にか自然を「所有」し、さらには独占できるようにさえした。ここに教皇は強く警鐘をならすのです。「神」のものを、あたかも自分のものであるかのように振る舞う人間たちの愚かさを指摘するのです。
中島 『ラウダート・シ』の中では、水道の民営化についても非常に厳しいことを書かれていますね。
水道民営化はよく、「貧しい人たちが水を手に入れられなくなるからよくない」という話に還元されがちです。それは間違いではないけれど、教皇が言っているのは、それを超えた「いのち」の問題、あるいはアッシジのフランシスコの「被造物の讃歌」のような問題。水というものを特定資本が所有して、売買の対象とするということ自体に対する根源的な問いなのだと思います。
山本 水の問題に関してはしばしば、教皇は「共通善」という言葉を使われますよね。これは私の専門である中世スコラ学に由来する言葉で、「私的善」の対立概念です。私有することのできない人類共通の善という次元を確保しようとする理論なのですが、それが教皇によって新たな文脈の中で生かし直されていると感じます。
若松 「所有」の問題を考えるときには、身体の次元、心の次元ではなく、「いのち」の次元で考えるということが重要だと思います。
たとえば、臓器売買は許されるのか。臓器は「私」のものなのか。教皇の考えからすると、もちろんそれはノーです。なぜなら、臓器は「いのち」とつながっているものであって、自由に売買できるものではない。あなたのものではなく、あなたに「預けられた」ものだからです。
あるいは土地、大地も、根本的な意味において、大いなる「いのち」とつながっている。それを区切って売買するというのが、そもそもとても不自然なのではないかというのが、教皇の問いかけなのだと思います。
原発の問題も、この感覚と非常につながっています。原発事故が起こって放射能が飛散することで、土地が使い物にならなくなってしまう。それは言い換えれば、土地が、放射能事故によって略奪され、形を変えた「所有」が始まるということです。つまり、それまで人々に平等に分け与えられていた土地が、よく分からない力によって所有され、奪われてしまう。だから原発は、あってはならないのです。
中島 福島第一原発事故の後、福島で農家の方が自殺するということがありました。ずっと耕してきた土地に放射能が降り注いで、もはや前のように作物を育てて生きてはいけないかもしれない。そのとき農家の方が抱いたのは、大地が汚染されたと同時に、自分のいのちもまた汚染されたという感覚だったのではないか。土地を耕すことが自分の生命の鼓動そのものでもあった、その営みが寸断されてしまったことに対する絶望だったと思うのです。
だから、一部でいうように「かわりに別の土地を確保すればいい」という問題ではない。所有物としての土地を失ったというだけの絶望ではないからです。アッシジのフランシスコが「被造物」として大地をも讃える、その感覚がそこにあるのだと思います。
もう一つ、教皇フランシスコが死刑に対して非常に強く反対していることも重要だと思います。これもやはり「いのち」の問題だと思うのです。他者の命を「合法的に」絶つことができる、つまりは人の命を所有することができるという観念自体に対する、強烈な懐疑。死刑は冤罪があるから駄目だといった法的な問題の前に、「いのちの所有」自体が許されない概念だという思いがあるのではないでしょうか。
 中島岳志・東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授
中島岳志・東京工業大学リベラルアーツ研究教育院教授山本 日本では、キリスト教はもともと死刑には反対だろうと考えている人も多いと思うのですが、実は伝統的には、ほとんどの神学者が死刑の存在を認めています。私が長らく研究してきたトマス・アクィナス(1225頃-1274)は、現代に至るまで、最も優れたカトリックの神学者とされていますが、彼もはっきりと死刑を肯定しています。そのことを背景に置くと、教皇がやろうとしていることのラディカルさが見えてきますね。彼は「カテキズム」という、現代のカトリックの教えを網羅した書物においても、死刑についての記述を書き換えたのですが、非常に思い切った行動です。
若松 私たちがそもそも「いのち」を裁けるのか、という問いかけですね。所有と裁きというのは、とても近しい関係にあると思います。
死刑の問題をめぐって、世田谷区長をつとめる保坂展人さんと話をしたことがあります(参照『保坂展人×若松英輔「いのちの政治学」』)。保坂さんはキリスト者ではありませんが、教皇フランシスコの世界観と著しく共振することをすでに実践しています。いじめや自殺をめぐって「いのち」のあり方を考え、原発に象徴される暴力的な科学技術のあり方に警鐘をならし、持続可能な社会を環境、教育、福祉の分野においても試みています。何よりも世田谷を誰も「見捨てない」街にしようとしていることに強く打たれるのです。今回の来日で、保坂さんと教皇の面会が実現しないのは本当に残念です。彼は教皇と「考え」を同じくするだけではありません。それをすでに実践しているのですから。
保坂さんは、現存する国会議員経験者のなかで、おそらく唯一、死刑囚と面会したことのある人物です。この事実にまず、大きく驚かされました。彼は国会議員として、超党派の仲間たちとともに死刑の廃止に向け真摯に活動をしました。しかし、そのことがなかなか実現しない。大きな犯罪をおかした人間の「いのち」を問題にしても共感する人は少ない、というのです。
「いのち」の次元で世界のありようを考える、「いのち」の尊厳とは何かを私たちは、もっと深めていかなくてはならないと思うのです。
このことで思いだされるのは『苦海浄土 わが水俣病』を書いた石牟礼道子さんです。存命だったら彼女も、ぜひ、教皇と言葉を交わしてもらいたかった一人です。彼女の本によって私たちが知った水俣病事件とは、公害という社会的現象ではなく、「いのち」とは何か、「いのち」の尊厳とは何か、という問題を突きつけているのだと思います。「いのち」をお金で買うことはできません。
中島 2011年に浄土真宗大谷派が親鸞聖人の七百五十回御遠忌(法要)を開いたとき、そのテーマとして掲げられたのが「今、いのちがあなたを生きている」でした。実は門徒の間では「何を言っているか分からない」と評判が悪かったそうなのですが(笑)、私はとてもいい言葉だと思いました。
「いのちが」あなたを生きているのであって、「私が」いのちを生きているのではない。いのちはどこかからやってきて、私という「器」でとどまっているものであり、いのち自体を所有することはできないという感覚を説いているのだと思うのですが、教皇の感覚はこれとも非常に近いと思います。
若松 「いのち」とは、他の何ものによっても代替することができない何ものかです。「いのち」は量的に認識されることを拒む。常に、ただ一つの、質的存在です。そのいのちとつながっている大地、空、森、そして水……世の中には絶対に代替できないものに満ちあふれている。この事実を、私たちが思い出せるかどうかが問われている。
今回の来日でも、教皇はさまざまな「いのち」に関するメッセージを発すると思うのですが、それを身体や心の話に置き換えず、そのままの形で受け取ることがとても大事だと思います。
中島 『ラウダート・シ』の中に「重荷を負わされ荒廃させられた地球は、見捨てられ虐げられたもっとも貧しい人々に連なっており…」という一節があります。その後ろには「わたしたちは自らが土の塵であることを忘れてしまっています」ともある。つまりは大地、そしてすべての自然と私たちの身体とのつながりを論じ、その地球の環境が破壊されることによって、貧しい人々が暴力にさらされているんだ、と述べているわけです。この世界観は非常に重要だと思いました。
若松 万物はつながりのなかにある。空はいわば、人類の屋根です。河は、人類の泉です。今、中国やインドは、大気汚染に苦しんでいます。その陰には無謀な経済成長による自然破壊がある。水や空気が汚染されればいずれは私たち自身が生きていけなくなる。中でも最初に厳しい目に遭うのが弱い人たちだ、ということです。
山本 これもまた、旧約聖書以来のキリスト教の発想とのつながりを感じますね。『創世記』で、アダムとイヴが神に禁じられた木の実を食べたことによって、土にはアザミといばらがはびこるようになり、人間は食べ物を得るために過酷な労働を強いられるようになる……。人間の罪と、自然の循環の「破れ」とが、密接につながっているという発想がそこにあるのだと思います。
中島 教皇は、人間が尊重しないといけないのは、自然の掟や地上の被造物間に存在する「繊細な均衡状態」だと言っています。その均衡状態を、自分たちの手で崩すことなく、微調整を重ねながらなんとか保っていくこと。それこそが人間の力の限界であり、私たちがやるべきことなのだと思います。
そして、その均衡状態が崩れたときに、最初にひずみが来る弱い人たちの視点から世界を見なくてはならない、その「弱い人たち」を生み出している原因でもある、世界のスタンダードになりつつあるグローバル資本主義を反転させていかなくてはならない。そういう感覚を、教皇は強く抱いているように思います。
若松 そのグローバル資本主義について、教皇は、先に見た『福音の喜び』で、「この経済は人を殺します」という言い方すらしています。これまでの教皇の回勅にも、経済問題に触れられているものはいくつかありましたが、ここまで言い切った人はいなかった。一歩踏み込んだ表現だと思います。
若松 「均衡」の感覚は、これからの時代を作っていく重要な要素になっていくと思います。この感覚を目覚まし、世界を再構築できるかどうかによって、それぞれの地域、社会、国家、そして世界のありようが変わってくると思うのです。
このことをいち早く提唱していたのが、深層心理学者の河合隼雄です。「均衡」という言葉の対極にあるのが、「統合」だと思います。マルクス主義でもキリスト教原理主義でも、さまざまな「イデオロギー」は世界を統合して、一色にすることを目指す。
いっぽう、「均衡」は、イデオロギーによって分断するのではなく、さまざまなものが、それぞれの役割と意味を表現しながら共存できる世界です。そこにあるのは「イデオロギー」ではなく「コスモロジー」なのです。
もちろん、キリスト教もある時期まで、「自分たちこそが正しい」という「統合」の方向に進んでいたことは否定できません。その中で、教皇は「均衡こそ大事だ」ということをここまで言ってくれたからこそ、支持を集めているのだと思います。
中島 全体のバランスが崩れるのを補正することが大事だ、という考え方は、東洋の哲学や仏教にも非常に近いですよね。そうした発想がカトリックのトップから出てくるのは非常に面白いなと思いました。
若松 真言宗の開祖である僧侶・空海は、水害を防ぐための治水事業にも力を注ぎましたね。そこにも、自然と人間のつながりが破壊されれば、最初に一番弱い人が苦しむという世界観があったように思います。
中島 仏教の教えを探求するがゆえに治水をする。それも、近代のように巨大ダムを造るといった形ではなく、自然とうまく付き合うための堤のつくり方を模索していく。それはやはり、「うまく付き合えなくなった」ときに誰が傷つくのかを考え、世界全体を俯瞰していたからだと思います。
もともと「東洋と西洋」というときの「東洋」というのは単なる空間的な概念ではなく、近代社会と対比される「何か」のことだったと思うのです。それが今、キリスト教社会とさまざまな面でつながろうとしている。これは非常に重要なことだと思います。
若松 宗教のあり方、信仰のあり方自体が、とても新しい形に入っていっているような気がします。かつて、アッシジのフランシスコの時代にはイタリア国内で数多くの戦争が繰り広げられていたけれど、今その戦争はなく、イタリアという国が生まれて、EUができてと、世界はどんどん大きく──ある意味では小さくなっている。その中で、かつては「宗教が同じ」ということがあるアイデンティティを形成していたのが、今はもう少し違うところにアイデンティティを感じる人が増えつつある。教皇は、それを体現している人ではないでしょうか。
山本 その観点からも重要なのは──実は私も最近気づいたのですが──『ラウダート・シ』という回勅には「宛先がない」ということです。
通常、教皇が出す回勅の最初には「すべての信徒のみなさまへ」といった「宛先」が書いてあります。内容によっては「すべての良心に基づいて生きている人々へ」など、キリスト教徒に限定されない場合もありますが、『ラウダート・シ』についてはまったく書かれていない。バチカンのウェブサイトで確認すると、日本語の翻訳で抜けてしまったとかいうことではなく、どの言語の版にもないんです。これはもう、意図的に宛先を限定せずに「すべての人」に届けようとする姿勢の表れとしか思えません。
若松 私が非常に大事にしている、カトリック信者でもあったフランスの哲学者ガブリエル・マルセルの言葉があって、「『われわれカトリックは』、と言うとき私たちは「普遍(カトリック)」の埒(らち)外にある」というんです。つまり、「われわれカトリック」と発言したとたん、自分たちのとなりに「カトリックならざる者」が生まれ、その行為は本当の意味での「普遍」からは遠ざかってしまう、というんですね。
同様に、回勅で「カトリックの皆さんへ」と言ったとたんに、そこに溝が生まれてしまう。教皇は、その溝を創造的に破壊しようとしているわけで、これは非常に革命的なことだと思います。だって、キリスト教を信じていない人のところへも「回勅」を届けようとしているわけですから。本当に今までなかったことだと思います。
中島 今回の教皇の来日も、そういう視点からとらえる必要がありますね。つまり、日本のカトリックの人たちに挨拶に来るのではない。むしろ、キリスト教徒ではない大半の日本人に対して、しかも宣教とはまた違った文脈で来られるというところが重要なのだろうと思います。しかも、滞在中には被爆者や東日本大震災の被災者との対話が予定されているなど、非常に困難なところへ追いやられた人たちのそばに行くということを非常に大事にされている。その意味を、私たちはもっと考えなくてはならない。
若松 自分も含めたカトリックの人たちに少し苦言を呈するなら、カトリックだから、この回勅をもっともよく理解できると思っていたら、それは大間違いだと思うのです。もちろん、カトリックだから知識もあって読み込める部分はあるでしょうが、逆にカトリックだからこそ理解できないところもある。狭い意味のカトリシズムでは読むことができない革新性がこの回勅にはある。カトリックである私たち自身も変わらないと読み解けない、『ラウダート・シ』はそういう回勅なのだと思うのです。
中島 同時に、キリスト教徒ではない私にとっても非常に読みやすい回勅でした。本の著者名を見なければ、キリスト教の指導者が書いたということも分からないのではないか、と感じる部分も多い。それが教皇の覚悟なのだろうし、キリスト教の本質に迫ろうとするからこそ、キリスト教の装いを捨てていくというやり方を志向されているのだろうと思います。
私が研究してきた、インドのガンディーもそれに近いところがあります。ヒンドゥー教徒として生きようとすればするほど、彼は「歩く」「食べない」「糸車を回す」といった、言語を超えた非常にシンプルな行動に回帰していこうとした。だからこそ彼の言動は宗教の違いを超えて、多くの人に届いたのだと思います。教皇もそれに似たところがあるのではないでしょうか。
山本 イエス自身が、まさにそういう人だったという記述が「新約聖書」にあります。イエスは学者のようにではなく、力ある言葉を語った、それが多くの人を驚かせた──というのです。
言葉の語り方だけではなく、教えの内容としても、イエスには、シンプルで力強い実践への回帰という側面が顕著に見出されます。
たとえば、新約聖書の「ルカ福音書」には、「善きサマリア人のたとえ」という有名な物語があります。「隣人をあなた自身のように愛しなさい』と説くイエスに対して、ユダヤ教の律法学者が、「わたしの隣人とは誰ですか」と尋ねます。この律法学者は、「隣人とは誰か」と定義を求めたわけですが、定義するとはつまり、枠をはめる、壁をつくるということでもある。「ここまでは隣人だが、この枠の外にいる人々は隣人ではない」というように。それに対して、イエスはあるたとえ話を通じて、「隣人となる」という定義を超えた実践を強調し、壁を破って橋を架けることの大切さを説くのです。
「隣人をあなた自身のように愛しなさい」というイエスの言葉はとても有名で、あたかもイエスが編み出した言葉であるかのように紹介されることがしばしばありますが、実はそうではありません。もともとは、旧約聖書の「レビ記」という書物に登場する言葉なのです。膨大で様々な教えを含んでいる旧約聖書の中から、そのエッセンスを「隣人愛」という仕方で抜き出すことによって、イエス自身が、旧約聖書以来の「信仰の遺産」をいわば再解釈し、自らの置かれた時代状況の中で生かし直そうとしているのです。
教皇フランシスコが試みている「橋を架ける」実践というのもまた、そのイエスの精神を、現代の時代状況に応じた新たな仕方で生かし直したものとして位置づけることができると思います。
旧約聖書以来の「信仰の遺産」を再解釈したイエスの教えを更に教皇フランシスコが再解釈するという仕方で、信仰というもの、伝統というものが、数千年に及ぶ歴史の中で帯びてきた厚みを保ちつつ、時代に即応した新たな生命を動的に獲得し続けているわけです。
 バンコクの空港に到着した教皇フランシスコ(中央)=2019年11月20日
バンコクの空港に到着した教皇フランシスコ(中央)=2019年11月20日中島 「隣人」という言葉が出ましたが、この「となり」という概念が、私は非常に大切だと思っています。
宮崎駿の『となりのトトロ』というアニメがありますが、宮崎がいう「となり」とは、単に物理的な意味ではなくて、トトロのような霊的な存在、あるいは死者のような目に見えない存在も含めて「そばにいる」「隣在している」ということですよね。現代を生きる私たちは、そうした「となり」の存在を失い、その姿を見ることができなくなっている。「トトロ」もそのことに対するアンチテーゼとして描かれた物語だと思います。教皇はそうした状況に対して、常に「となりにいること」の大切さを思い出させようとしている人だと感じるのです。
だから、教皇フランシスコという人は私にとって、とても偉大な人であると同時に、常に「となりにいる人」という感覚です。その両面が、矛盾することなく同居している。
若松 おっしゃるように、「となり」が見えないというのは、現代の私たちに突きつけられた非常に大きな困難の一つです。貧困や災害によって「となり」で苦しんでいる人がいるのに、それが「見えない」。そうした視座を失ったのです。
知識と情報を得て、現代人はほんとうに多くの「視点」を獲得しました。今、私たちは宇宙から地球を見ているような気持ちにさえなれます。しかし、その一方で、自分のとなりで苦しんでいる人の身になってみる、という「視座」を見失ったのです。
インターネットが普及し、世界は急速に拡張しました。その分、世界そのものの構造が非常に単層的になっている。平面的世界での幸せ、そこでの安住ということしか考えられなくなっている人が少なくない。
そうした考えだからこそ、さまざまなものを「所有」し、「独占」しようとするのだと思います。もし、それを分かち合うことができれば、人は、深いところでのつながりを見出すことができる。信頼は「広がる」前に「深まらねば」なりません。この順序を逆にすることはできない。
山本 「となり」は先ほどの「隣人」の話だけではなく、キリスト教、そして宗教における重要なキーワードですね。旧約聖書の『出エジプト記』には、「奴隷にされているヘブライ人たちをファラオのもとから連れ出せ」と神から命じられたモーセが「自分にそんなことできるわけがない」と思ってためらっていると、神が「私は必ずあなたとともにいる」と励ますシーンが出てきます。
さらに新約聖書でも、イエスの誕生が語られる場面で、旧約聖書の「イザヤ書」の一節が引用されます。それは「見よ、おとめが身ごもって男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる」という一節です。この「インマヌエル」はヘブライ語で、「神、われらとともにあり」という意味なのです。つまり、救い主として生まれてくるイエスは、最初から「われらとともにある神」を体現する存在としてあったわけです。まさに「となり」の重要性につながってくるエピソードだと思います。
若松 ここまで、教皇の言動や姿勢について、さまざまなことを語ってきましたが、それが教皇という人個人の思想だけによるものかといえば、決してそうではないと感じます。彼という人物一人が「えらい」という話ではなく、ここまで積み上げられてきたさまざまなものが、教皇を通じて開花したと考えるべきだと思うのです。さらにいえば、無数の語らざる者たちが、教皇に言葉を与えているようにすら感じます。
ここで詳しく語ることはできませんが、故郷であるアルゼンチンで、軍事政権による弾圧のなかでいのちを落とした仲間たちのことを、彼は一日たりとも忘れたことはないと思います。彼個人の特性と、彼がキリスト者としてさらには教皇として、過去の積み重ねから受け継いできたもの。その両面を見ていく必要があるのだと思います。
中島 教皇自身も、自分のオリジナルな思想だとはまったく思っていないのではないでしょうか。そうではなく、自分は「やってくるもの」を受け止める器に過ぎないというような感覚があるからこそ、キリスト教とは縁のなかった私のような人間にも、そのメッセージがダイレクトに届くのだと思います。
若松 私には「扉」としての教皇、という感覚がありますね。教皇という人を通じて私たちは、普通に暮らしているとその存在が見えてこないような弱い立場の人たちや、助けを必要としている人たちと出会うことができる。その扉の鍵を、教皇は開いてくれているんだと思います。
山本 先ほども少し御紹介した、フランスの社会学者との対談をまとめた『橋をつくるために』(戸口民也訳・新教出版社)という本があるのですが、この「橋をつくる」というのは、教皇フランシスコの魅力を象徴するキーワードですね。キリスト教の中も外も関係なく、これまで分断されていたようなところにも、すべてをつなぐための橋をかけていく。そういうことをやろうとしている方だと思います。
この本の中で教皇が自ら明かしていますが、この「橋をつくる」というコンセプトは、単に思いつきで語られているものではなく、実は「教皇」という言葉の語源とも深いつながりがあります。
教皇のことをラテン語でsummus pontifexというのですが、この語源をたどると、まさに「橋をつくる」という意味がある。summusとは「最高の」という意味で、pontifexとは「祭司」という意味なのですが、このpontifexという語の語源は、「pons(橋)をfacio(作る)」というように分析できるのです。
教皇というのは橋をつくる存在であり、さかのぼればイエス・キリスト自身もまた、神から人へ架けられた橋、そして人と人との間に新たに橋を架けようとした存在であった。教皇はそうした本質的なところから、自らの役割をとらえ直そうとしているのです。
 欧州歴訪で、ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇と会談した韓国の文在寅大統領=2018年10月18日、バチカン、韓国大統領府提供
欧州歴訪で、ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇と会談した韓国の文在寅大統領=2018年10月18日、バチカン、韓国大統領府提供 中島 その意味では、日本に来られるにあたって、いま日本が抱えている大きな問題の一つである、韓国との関係についても意識されているところはあるかもしれませんね。教皇は韓国にも以前訪問されたことがあり、カトリックである文在寅大統領とはすでに2回会われています。先ほど「となり」の話をしましたが、今日本では、韓国という国が「となり」にあること自体を拒絶しようとするような動きが先鋭化している。そこに「橋をかける」ような感覚も、どこかでお持ちかもしれないという気がします。
若松 内政干渉などの問題もありますし、教皇が来日中、外交問題に直接的にふれるような発言をする可能性は低いでしょう。しかし、それを高次に暗示する言葉は、必ず発すると思います。さらに、今回の来日を経て、その後に彼が何を言うのか。それも含めて持続的に注目していってほしいと思います。そこからこそ、私たちと教皇との対話がはじまると思うのです。
中島 今日はあまり触れられませんでしたが、日本の貧困や格差の問題についても、教皇は非常に強い関心をお持ちだと聞いています。そうしたさまざまな角度から教皇が発していくであろうメッセージを、私たちはどのように受け止め、繊細に読み解いていけるのか。それが問われていくことになると思います。
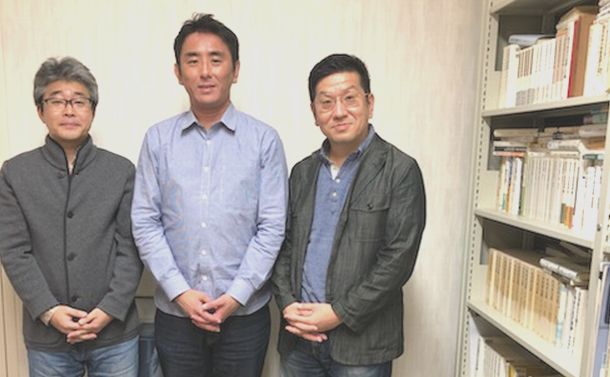
有料会員の方はログインページに進み、朝日新聞デジタルのIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞デジタルの言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください