オンラインスペシャル対談「業平の恋と和歌」
2020年11月17日
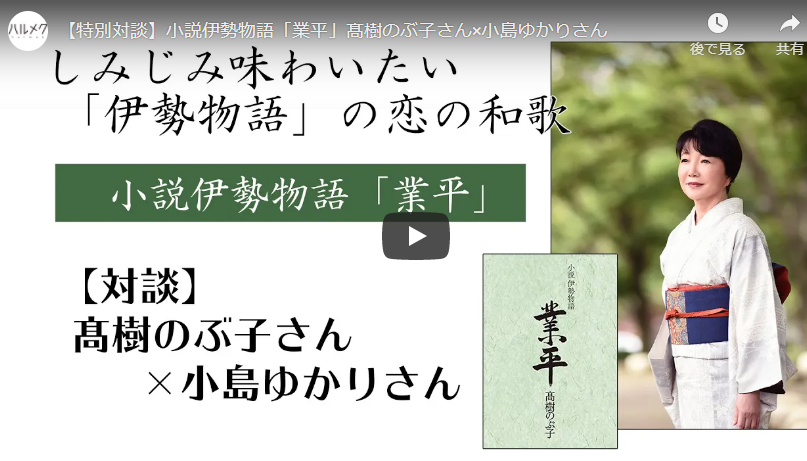 オンラインスペシャル対談『業平の恋と和歌」の動画から
オンラインスペシャル対談『業平の恋と和歌」の動画からコロナ禍で何もかもが停滞していた最中の5月に発売された髙樹のぶ子著『小説 伊勢物語 業平』(日本経済新聞出版)。たちまち重版がかかり、勢いが止まりません。
恋愛の指南書としてのみならず、生き方や人間関係を学べる教育書としての評価も高く、今年の夏には東京の開成中学でテキストに活用されました。また、もっと理解を深めたいというたくさんのオファーを受け、11月初旬には新書『伊勢物語 在原業平 恋と誠』(髙樹のぶ子著、日本経済新聞出版)も刊行されました。
そんな「伊勢物語ブーム」の到来ともいえる流れの中、髙樹のぶ子さんと歌人・小島ゆかりさんによるオンラインスペシャル対談『業平の恋と和歌」が開催されました(主催:朝日新聞社「論座」、雑誌「ハルメク」協力:日経BP 日本経済新聞出版本部)。その模様をダイジェストでお届けします。
オンラインスペシャル対談『業平の恋と和歌」の動画はハルメクのHPでご覧になれます。
 対談した髙樹のぶ子さん(右)と歌人・小島ゆかりさん(左)
対談した髙樹のぶ子さん(右)と歌人・小島ゆかりさん(左)髙樹のぶ子 たかぎ・のぶこ
1946年、山口県生まれ。80年『その細き道』で作家デビュー。84『光抱く友よ』で芥川賞、94年『蔦燃』で島清恋愛文学賞、95年『水脈』で女流文学賞、99年『透光の樹』で谷崎潤一郎賞、2006年『HOKKAI』で芸術選奨文部科学大臣賞、2010年『トモスイ』で川端康成文学賞受賞。芥川賞をはじめ多くの文学賞の選考にたずさわる。2017年、日本芸術院会員。2018年、文化功労者。ほかの著作に『マイマイ新子』『百年の預言』『甘苦上海』『ほとほと』『明日香さんの霊異記』など多数。09年に紫綬褒章受章。18年に文化功労者に選出。
小島ゆかり こじま・ゆかり
1956年、愛知県生まれ。早稲田大学在学中に「コスモス」入会。歌集に『希望』(若山牧水賞)『獅子座流星群』『エトピリカ』『憂春』(迢空賞)『純白光 短歌日記2012』(小野市詩歌文学賞、日本一行詩大賞)『泥と青葉』(斎藤茂吉短歌文学賞)ほか。17年に紫綬褒章受章。産経新聞などで歌壇の選者を務める。全国高校生短歌大会特別審査員。
小島 髙樹さんから連絡があって、「今度、伊勢物語を小説にするの」と伺った時、「わっ、それは大変だ」と思いました。
髙樹 うふふ。
小島 「伊勢物語」は125段で構成されているエピソード集です。短いものだと数行で終わっている。そして、「昔、男ありけり」の男とは、業平のことであろうと言われてはいますけれど、明らかに業平とは無関係な話も入ったりしています。それらをシャッフルし、捨てるべきものは捨てて再構成し、業平の一代記に仕上げるというのは気の遠くなるような作業。至難の技だと言わざるを得ません。
髙樹 蛮勇を振るいました(笑)。
小島 「源氏物語」はストーリーが壮大なので多くの人は歌を読み飛ばしてしまいますけれど、「伊勢物語」は純然たる歌物語ですので、歌を読み解かなければ読み進めることができません。歌詠みである私達でさえ手こずるのですが、小説家である髙樹さんがどのように読み解くのだろうかという点に私は非常に興味がありました。
拝読して大変に驚きました。学者とも歌詠みとも違う解釈です。業平は髙樹さんの読み解きを一番喜んでいるのではないかなと、そんな気がしました。
髙樹 ありがとうございます。
小島 文体にも驚きました。あのように雅(みやび)で、しかもエロチックで艶やかな文体がいかにして生まれたのか、大変に興味があります。もう一つ、本の分厚さにもビックリでした。「伊勢物語」の注釈書というのは薄いのですが、それを450ページにまで膨らませるというのは凄い。いかに高樹さんが妄想を膨らませてお書きになったかという証かなと(笑)。
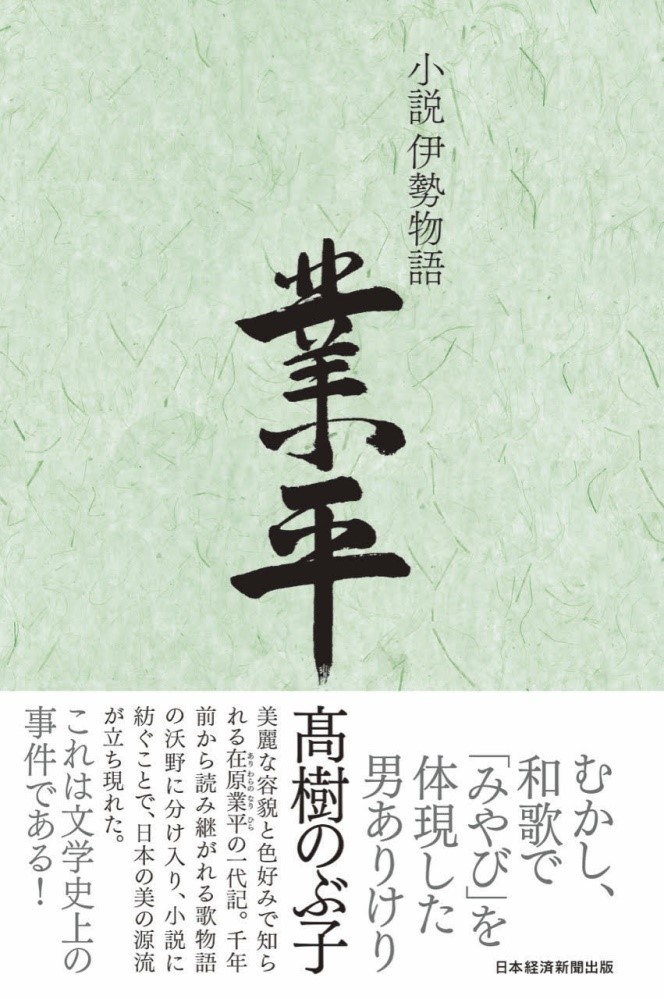 『小説 伊勢物語 業平』(日本経済新聞出版)
『小説 伊勢物語 業平』(日本経済新聞出版)髙樹 小説家である以上、現代語訳にはしたくなかった。それを第一の目標に掲げて古典にアプローチしようと考えました。
小説にするためには業平という主人公が必要。その主人公のものと思われる歌を「伊勢物語」の中から抽出し、なおかつ業平の人生の流れの中において、歌を入れ込んでいくという。しかも物語があって歌にたどり着き、歌によって物語が引き立つという相乗効果を狙いたいという試みで。私は大変なことに乗り出してしまったのだと、新聞連載を始めてから気づいたのです。
でもそうした構成より更に難しかったのが、今、小島さんがおっしゃった文体についてです。業平が生きた時代の雅な空気を平安から現代に蘇らせたい。さてどうするかと試行錯誤を重ねました。
小島 そうでしょうね。
髙樹 注釈がつくのは無粋であると。地の文として書き、注釈と同じようにちゃんと意味が伝わるようにするためにはどうしたらいいのかと考えた末に、白状してしまうと万葉の時代の長歌を参考にして書き始めることにしました。
5音と7音の2句を交互に数回繰り返し、最後を7音で止めて反歌に続くというリズムは、日本人の生理にフィットしているのでしょうし、調子がいいということで。実際には小説を5音と7音の繰り返しで書き進めることはできませんが、なるべく近づけたいと意識していたのです。すると体内リズムが確立され、「です、ます調」と「体言止め」のミックスが不調和でなくなってきて、この音律で歌の説明もイケると。そうして、ようやく「小説伊勢物語」を書くことができそうだと思うことができました。
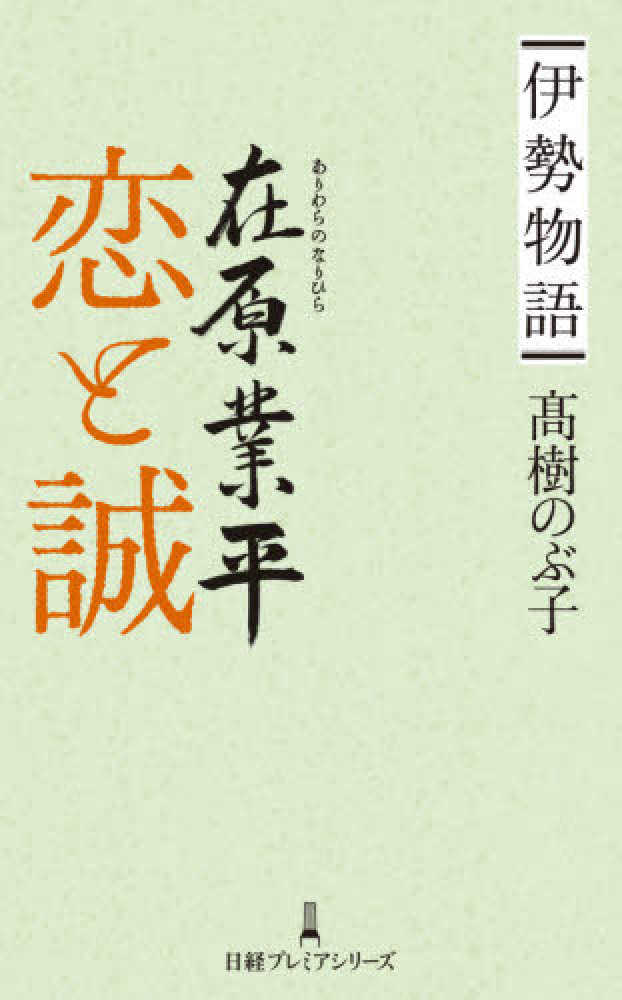 『伊勢物語 在原業平 恋と誠』(日経BPM)
『伊勢物語 在原業平 恋と誠』(日経BPM)
私は歌を作る時、口語も使いますけれど、基本的には文語調で旧かなで。それはなぜかというと、旧かなの文体のほうが時間の流れがゆったりだから。なぜか丁寧で雅な「です、ます調」のほうが、「で、ある調」より色っぽいんですね。奥行があって、羞恥心があって、突き詰めてゆくとエロチックな文体になるのです。長歌から文体のヒントを得たというお話、非常に納得がいきました。
髙樹 できれば一度ならず二度、三度と読み返していただける作品にしたいと思っていました。それだけの魅力をどうやって作るかと考えた時に思い浮かんだのが音楽性のある文体だったのです。
小島 歌をきちんと鑑賞するためには、最終的にはリズムが体の中に入らないと反応できません。ですから髙樹さんが体内リズムを確立してから小説を書き始めたとおっしゃるのを聞いて、本質的なところを掴んでおられるなと。
髙樹 そうなのですね。
小島 この直感は何でしょうかと不思議な気持ちがしました。
髙樹 業平が降りてきてこういう文体でやってくれと(笑)。
小島 そう。業平と髙樹さんは気が合うのでしょう。
髙樹 いい男だから嬉しいわ。
小島 アハハ。

髙樹 私は小島さんの感想を聞くのが一番怖かった。業平の一代記とはいえ、小島さんから「歌の解釈が的外れです」と指摘されたらアウトだと思って。でも褒めてくださったので嬉しかったです。
小島 多くの場合、注釈書を見た時に意味を読んでしまうのですよね。
髙樹 そうそう。
小島 でも意味ではなく、言葉に込められた心を思わなくてはいけません。それから言わないことの空白にある息づかいのようなものも感じ取らなければいけない。
ずいぶんと昔の話ですが、リービ・英雄さん(西洋出身者としてはじめての日本文学作家)が万葉集の英訳本を出版なさった時に、ご本人から伺った忘れられない話があります。たとえば有名な「田子の浦うち出でてみれば真白にぞ富士の高嶺に雪は降りつつ」という山部赤人の歌について。リービさんは「真白にぞ」をどう訳すかということに頭を悩ませたと。
意味だけを追うと「ひどく白かった」とかいうことになってしまいます。でも結果的にどうなったかというと、「White Pure White」。歌の中には「白」は一度しか出てきていないのに、二度重ねた。このことにより「なんという白さなのだろう」と感動した様子が伝わってくるわけで、私は本当に感心してしまいました。
髙樹 まさにその「言い重ね」が業平は得意中の得意で。超絶技巧的に周囲の人達から拍手をもらうということあるでしょうけれど、業平の場合は作為とか型を超えて言葉が溢れてしまう。溢れてしまう時にため息が次々と重なって出てくるような言葉の使い方をしている。溢れるパッションで詠んだ歌だから、業平の歌は現代人の心にも響くのではないかと私は思うのです。
小島 それこそが業平の天才性でしょうね。紀貫之が業平の歌を「その心余りて言葉足らず」と評していますが、これは否定的な評価ではなく、心が余る故に型をはみ出している状態を指し、いかようにも解釈のできる業平の歌やその天才ぶりをを高く評価しているのです。たとえば「見ずもあらず見もせぬ人の恋しくはあやなく今日やながめくらさむ」という歌は、「見なかったわけじゃないけど、見たわけでもない」って、一体どっちやねん! と思わず突っ込みたくなってしまいますよね。
髙樹 アハハ。
小島 でも業平は、同じ言葉を重ねたり、対立することを言ってみたりしながら、自問自答している。あるいは相手に問いかけている。そこが大きな特徴ですね。
髙樹 私が業平の歌の本質的なところを掴んでいるかどうか。今日は歌人である小島さんに分析していただけるということでワクワクドキドキしています。よろしくお願いします。
小島 お時間に限りがありますので、代表的な3首取り上げてみたいと思います。最初は
『小説伊勢物語』では「雨そほ降る」という章に出てくる一首です。「起きもせず寝もせで夜を明かしては春のものとてながめ暮らしつ」。この歌はさきほどの歌と同じで、起きてるわけでもなく、寝てるわけでもないと。
髙樹 どっちやねん! (笑)。
小島 普通に訳すと、起きているわけでもなく、寝ているわけでもなく夜を明かして。そして昼は昼で春の倣いである長雨を見つめてボンヤリとしているとなります。これだけ読むと恋の歌であるとはわからないのですが、古今和歌集では恋歌3の巻頭に入っています。
髙樹 恋歌1から5まであるのですね?
小島 そうです。恋1と恋2は、ちょっとお手紙のやり取りをしたりしている段階の「まだ見ぬ恋」。恋3になると初めての逢瀬の前後。恋4が熱愛状況から別離まで。そして恋5が失った恋の追憶となっています。
恋3の巻頭というのは、恋3の真ん中あたりに初めての逢瀬の歌がきますので、後朝の歌ではなく、まだその手前で悶々としているという感じだと思うのですが、それを「伊勢物語」では、ちゃっかりと後朝の歌にしています。とても素敵なところは「容姿はさほどでもないけれど、心映えが素敵な女性」だという点。そしてどうやら人妻らしい女性と一夜を共にした朝ということです。
高樹 そうそう。
小島 髙樹さんの解釈はこうです。昨夜、私はあなたの傍で、起きているのか寝ているのか判らぬまま朝を迎えてしまいました。そぼ降る雨のせいでしょうか、それともあなたが春の雨のようにわたしの中に入ってこられて、起きることも寝ることも叶わぬ甘い酔いで縛ってしまわれたのか。いまあなたから離れてもあの雨は、こうして空から、いえわたしの身内でも、降り続いております。春の雨とはこのように長く、いつまでも終わりのないものとは知ってはいましたが、切ないものですね。
髙樹 うふふ。
小島 本当にお見事だと思います。どういう風に想像を膨らませていかれたのでしょう?
髙樹 ここで私がテクニカルだなと思ったのは、起きてるか寝てるかわからなかった一夜というのは、男も女も共有している。業平はトロトロしているようなむつみ合い方をしたことを相手の女性に思い出してほしくて歌を詠む。すると女性は反応して余韻に浸る。これが恋上手な男の駆け引きというか……。単なる社交儀礼の歌を超えて、恋をより強く印象づけている。やはり業平は恋の達人だなと私は勝手に思って。
小島 それにしてもの想像力ですね。だって歌には「春のものとて」としかないのに髙樹さんは「あなたは昨夜、春の雨のように私の中に入ってこられて」と。これこそが余白を読むということだと思います。
髙樹 そうなら嬉しい。単に歌の解釈をするだけでなく、書かれていない情念へと自在に想像を広げていく。これは小説にしかできないことなのです。現代語訳でそこまでやってしまったらクレームがついてしまいますから。
小島 妄想作家である髙樹さんの本領発揮というところで、大変感銘を受けました。
髙樹 光栄です。

小島 これは名歌としてつとに有名。西行も藤原俊生もみんなが褒めちぎっています。これこそ「その心余りて言葉足らず」の典型のような歌です。
髙樹 「や」をどう受け止めるかというところで、さまざまな解釈が出て来たようですね。
小島 そうです。「や」を疑問と捉えるか、反語と捉えるか。疑問と捉えた場合には「月は昔の月ではないのか?」「春は昔の春ではないのか?」となり、反語と捉えた場合には「月は昔の月ではないのか? いや、昔の月のままだ」「春は昔の春ではないのか? いや、昔の春のままだ」となります。そして、いずれも「我が身ひとつはもとの身にして……」と続くのですが、「……」の中身が問題となるわけです。
「恋しいあなたを失った今、元のままであるはずの月も春も違ってみえるのだ」というのが「……」の中身。この歌は髙樹さんの小説の中では「忍ぶ草」という章に出てきます。そしてこう解釈しておられます。
ああ。この月はいつぞやの月とは違うのか。この春は去年の春ではないのか。何も変わらぬ月や春のはずなのに、わが身だけが元のままの御方を思い続けているせいで、月や春さえ、昔とは違ってしまったように思えてしまうのです。
つまり髙樹さんは反語的なニュアンスで受け取って、恋しい人がいないということは世界の見え方が変わってしまうということを伝えておられる。画期的だと思います。というのも学者や研究者の世界では、この歌の「や」は疑問であるというふうに、ほぼ定着しているので。
髙樹 そうなの?
小島 学問的には、その時代の用例を徹底的に調べて、「や」がどういう風に用いられたかを検証していきます。ただ、学者の中にも、そうはいっても人とは違う規格外のことをしてしまうのが業平だから絶対とは言えないという人がいるようです。もう一つ、業平は漢詩の教養を備えていたので、その辺りを探っていくと、この歌の「や」は反語的に使われていたと考えることもできるといわれています。
髙樹 あえて学者の方々のお考えを学ぶことなく、たとえ知ったとしても蹴散らして、あくまでも小説の流れの中の歌として、自由に解釈させていただきました。業平の恋のため息の中にとりこんじゃえというのは非学術的ではあるかもしれないけれど、私は業平の恋に向けられたパッションがこの歌を詠ませたという体で書き進めました。
小島 この歌は他にも論点がありまして。月と春が並列して歌われているのですが、考えてみるとおかしいのです。だって梅の花を眺めている場面なのですから。これも業平の特徴で、細かい描写から大きな描写へと飛躍するということがあるのですね。
もう一つ、「もとの身にして」というところ。これは古今和歌集のスタンダードな型として、自然と人事を対比的に捉えるというのがあります。となるとここは「心」であるはずなのに「身」という生々しいワードが出てくる。ここにも業平の個性が現れていると思います。
髙樹 身体ということを業平はものすごく意識していたようですね。
小島 梅の頃といえばまだ寒いのに、恋の回想をしながら板敷きの床の上に身を横たえている。中身の肉体からヒシヒシと心の辛さが伝わってくるという。
髙樹 季節感と身体感覚と心を言葉でつないでいるというのは凄いことですよね。業平の身体から飛び出した勢いが言葉に乗っているから、その言葉が千年後の現代まで、時間軸を超えて人の心を打つのではないでしょうか。

小島 業平は物の本質とか人の心の核心にあるものが直感的に視(み)えた人という気がします。歌は大雑把に分けると、恋文のような「贈答歌」、そして今で言うところのつぶやきにあたる「独詠歌」、そして「唱和歌」といって、たとえば「令和」のもとになった万葉集の「梅花の宴」(序文に「初春の令月にして気淑く風和らぎ、梅は鏡前の粉を披き、欄は珮後の香を薫らず」とあり)などがそうですが、みんなで花見をしながら順に歌を詠み唱和していくというもの。この唱和でも業平は圧倒的に優れています。業平はエンターテイナーですから。
髙樹 死に対する無常観というか、どんなに地位のある人であってもいつかはお迎えが来るということを偉い人の前で歌ったりして、周囲の人達をハラハラさせてみたり。
小島 死生観というところで、もう一首。小説では最終章「つひにゆく」に出てくる、しかも最後を締めくくる歌ですね。
「つひに行く道とはかねて聞きしかど昨日今日とは思はざりしを」
私は業平の生涯がどんなふうに締めくくられるのか、それを楽しみに小説を拝読していました。そして最後まで読み終え感動しました。
髙樹 終わらせ方も迷いどころでした。「伊勢物語」が今日まで形を変えつつも残っていることの意味のようなものを、いかにしてエンディングに持っていくかというところでずいぶんと苦しんだのですけれど、伊勢斎宮に取材に行った時に、専門家の方から「伊勢という名前の女性が業平の最後の妻として近くにいたのですよ」と訊いて心が決まりました。それ頂きました、という感じで(笑)。
小島 なぜ「伊勢物語」と呼ばれるのかについては諸説あります。
髙樹 ええ。伊勢の斎宮との不倫関係というエピソードがあってというのが、有力な説なのですが……。私は業平が歌を伊勢に託した。つまり伊勢という女のことが好きであると同時に、女を信じたという幸せな終わり方にしたかったのです。
小島 地位や名誉に追いすがることなく、溌剌とした女性が登場して爽やかに終わるというのは、歌や恋に生きた業平らしいなと思うのと共に、髙樹さんらしいなと思いました。
髙樹 嬉しいです。でも書いている最中は自分らしいかどうかなんて考える余裕もないほどに必死でした。さまざまなエピソードを切り貼りしながらも滑らかに展開することを心掛けていたのです。
小島 小説の底に流れる大テーマとして業平の人生哲学というものがあります。後に清和天皇の后となり藤原髙子との密通や、伊勢の斎宮との密通などの話が有名で、業平はプレイボーイとして広く知られていますが、決してそれだけの男ではない。業平は人間力に溢れた魅力的な男性であったことが、『小説伊勢物語』からはしっかりと伝わってきます。
髙樹 業平の魅力を一言でいえば雅な人物であること。では雅とは何かというと、言葉にするのは難しいのですが、問題が生じた時にオロオロとしたり、イライラとしたり、即座に解決しようと躍起になったりせず、ゆったりと構えている。ままならないことがこの世にはあるのだということを知っている。達観しているといった高い精神性を備えていること。耐えている姿の中に雅というものが生まれるのだと、私は思うのです。
 髙樹のぶ子さん(右)と歌人・小島ゆかりさん(左)
髙樹のぶ子さん(右)と歌人・小島ゆかりさん(左)
髙樹 コロナに対しても、慌てず騒がずで、これまでにもさまざまなことがあって、それでも人々は生きてきたのだから、これからも生きていくのだとドシンと構えて、コロナ禍の中でも楽しいことをみつけて行ける男性がいたら、頼もしいじゃありませんか。安心感があって、尊敬できて……。業平のような男性が増えるといいなという願いを込めて小説を書きました。
小島 在原業平は「源氏物語」の光源氏のモデルになった人物だと言われています。それだけに業平と架空の人物である光源氏は類似点が多いのです。
たとえば二人とも幼くして皇位継承権を失って傷ついた体験がある。屈折した悲しみなどを心に味わった。それゆえに人の心の苦しみがわかるといった優しさを備えていて、私は良い意味で業平や光源氏は中性的な感性を育んでいたために女心がわかる。だから女性にモテたのだと思うのです。
髙樹 『小説伊勢物語』は、今すぐに読み始めることができなくても、一家に一冊置いておいて欲しいと思います。別にセールスするわけではないのですが、大野俊明さんの美しい絵を眺めるだけでも癒されます。開けばメロディーが流れてきますので、その音に耳を澄ませてほしいと作者としては願っています。
小島 読むたびに新しい発見がありますので、一家に一冊といわず、一人一冊持っていただき、繰り返し読んでいただきたいと思います。業平は人間力の人だと言いましたが、『小説伊勢物語』を読めば、思いやりって何だろう、コミュニケーションって何だろう、孤独って何だろうという問いが湧いてきます。その答えを求めるのではなく、業平もこんな思いをしていたのかと共有する。老若男女を問わず、読めば必ず心が成長する一冊だと自信を持ってお勧めしたいと思います。
髙樹 ありがとうございます!
オンラインスペシャル対談『業平の恋と和歌」の動画はハルメクのHPでご覧になれます。
有料会員の方はログインページに進み、デジタル版のIDとパスワードでログインしてください
一部の記事は有料会員以外の方もログインせずに全文を閲覧できます。
ご利用方法はアーカイブトップでご確認ください
朝日新聞社の言論サイトRe:Ron(リロン)もご覧ください